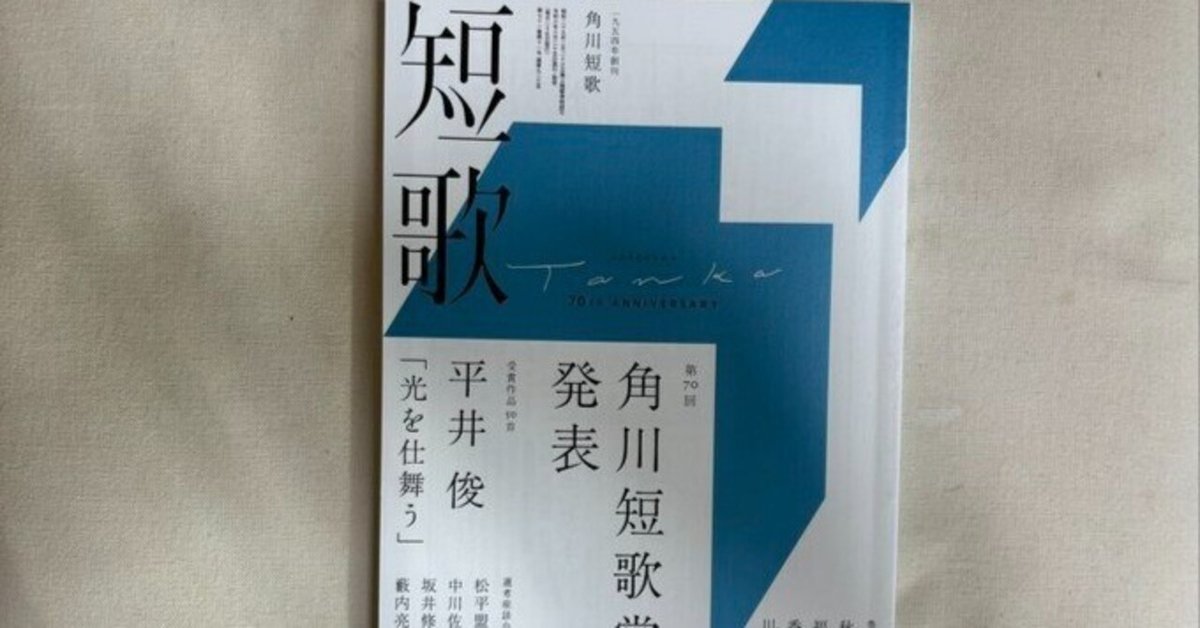
角川『短歌』2024年11月号
①村ごとに言語違ふとフィリピン人講師が英語で語りぬ今日は 香川ヒサ フィリピンの事情だろうか。他の村と接触の必要が無く、自分たちだけで生活が成立していた証だろう。しかし一旦外に出たら言葉が通じない。例えば英語で意思疎通を図るしか無いのかもしれない。
②すずかけの、鉛筆うすく引きて読むヒポクラテスの誓いの、みどり 藤島花 静謐な美しさのある歌。すずかけのみどり、を景として置き、その間に挟んで動作がある。主体が医療に関わる人かは措いて、誓いに感銘する心が鉛筆の線に表されている。「うすく」がいい。
③「『短歌』の裏方たち」
大井学〈伊藤一彦さんがおっしゃっていた(2020年代の若い人の歌は)現在しか歌ってないっていうのは、口語が時制を扱いづらいっていうことと一致している感じがします〉(…)
馬場あき子〈我々は「時間」というのを問題にしてたものね〉
馬場あき子の話を伊藤一彦と大井学が聞く、「オーラルヒストリー」の第六回。この口語が時制を扱いづらい、というところ、今の私自身の問題意識と重なっている。引き続き、こういう話題にアンテナを張り続けたい。
④肉体はむしろ邪魔なりほんとうに寄り添うという力仕事に なみの亜子 下句に惹かれた。「ほんとうに寄り添う」ということは「力仕事」なのだ。そしてそれには肉体は邪魔。精神と精神が寄り添うことにこそ「力」が要る。逆説的に響くが真実だと思った。
⑤「言霊の短歌史 戦国武将と言霊」
鎌田東二〈平安時代から貴族社会では歌を詠むことが社交上必須でしたし、コミュニケーション手段でもありました。将軍(武士)も貴族と関わるので必然的に歌を作り、家臣たちも作る、という連鎖が生まれました。〉(…)
笹公人〈合戦を前に武士同士が集まり、連歌を作ったりしてますが、それは予祝の意味があったのでしょうか。〉
鎌田東二〈和歌という文芸を通して、みんなの決意や覚悟を確認したり、政治的な意味での拘束力もあったと思います。〉(…)
笹〈この時代は芸能や文芸などを通して和歌を詠んでいます。末法の時代で、明日生きているかどうかわからない、武士に至っては殺されるかもしれないというなか、和歌を詠んでいます。〉
中世には、思想的言語的に大きな変化があった。それを短歌と絡めて知ることができ、興味深かった。
2024.11.26.~28. Twitterより編集再掲
