
【暦と暮らそう】5月(皐月)
佐藤家のニッチなカレンダーと
今月の七十二候の紹介です。
お出かけのきっかけや、創作のヒントになると幸いです。
どんどんご活用ください。
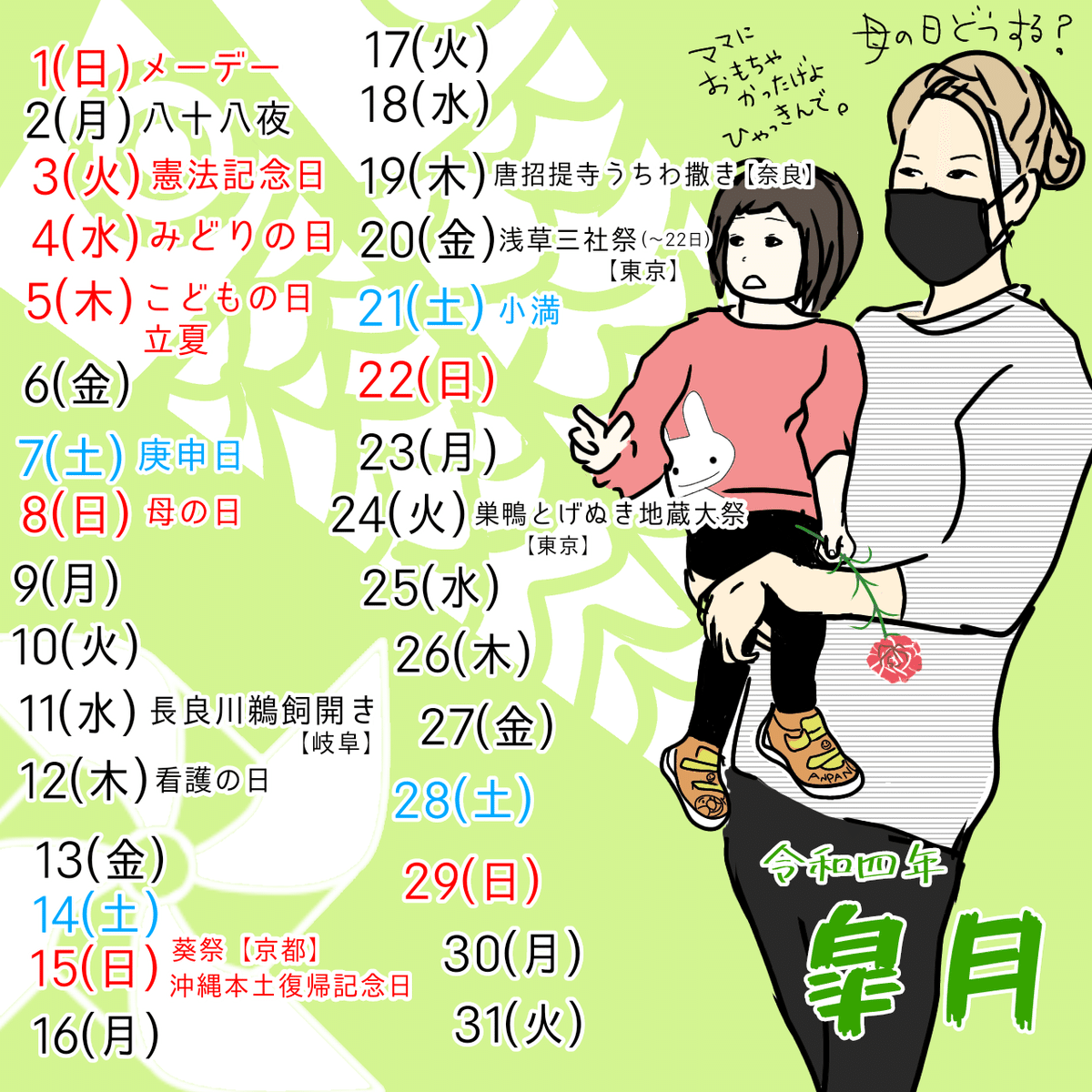
↑佐藤家のニッチなカレンダー
(※イベントなどは変更や中止になる事もあるので、お出かけ前はご確認ください。)
*****
二十四節気↓
5月は「立夏(りっか)」と「小満(しょうまん)」です。

【立夏】5月5日~5月20日

暦の上では夏がくる。
新緑、青葉の季節に気持ちいい風。
「五月晴れ(さつきばれ)」と言いたくなるが、
旧暦の5月は今の6月にあたり、実は五月晴れは、梅雨の晴れ間の事だそうな。
なにはともあれ、
この頃、夏の訪れを感じ始める。
【小満】5月21日~6月5日

小満とは、
生命が生き生きと、草木が生い茂るという時期。
もとは、秋に蒔いた麦の種が、冬を越して穂をつけた事にホッと一安心する“小満足”からきてるとも。
「小満」は、生物がぐんと成長する時期だ。
*****
七十二候↓
二十四節気(立夏・小満)を
それぞれ初候・次候・末候に分け、
その時季ごとの生き物や気候の様子が
感じられる名前がついている。
1年で72種類あり、だいたい5日に1回変わる。

*****
【立夏】
「蛙はじめて鳴く」5月5日~5月10日
蛙(かえる)は、ほとんどオスしか鳴かない。
メスへの愛のアピールや縄張り主張だからだ。
アマガエルでいえば、寿命は5年くらいらしく、
春に卵から孵(かえ)り→
夏にオタマジャクシに手が出てカエルになり→
冬11月頃~3月頃まで冬眠する→
春4月頃~繁殖期で、5月頃から鳴き出す(求愛)
というサイクルのもよう。
そっかー。この時期うるさいって思ってごめんね。
カエルさん、頑張って彼女ゲットしてね。
「みみず生ずる」5月11日~5月15日
ミミズは他の虫よりおくれてお目覚めのもよう。
七十二候になっているのは、農作業する人にとっては大切な生き物だからだと思われる。
ミミズがいる土は豊かだと言われる。
だって、腐葉土(枯れ葉などが腐って発酵したもの)を食べて、栄養たっぷりの糞をして、
土壌を「ええ土」にする。
そして、土のなかを這(は)いまわるから
結果、土も耕してくれる。
そりゃあ、
「お!そろそろ、みみず生ずる頃だ」ってなるわな。
「たけのこ生ず」5月16日~5月20日
たけのこが生える頃。という事なのだが、
我々がいつも食べてる筍は、3月や4月に見かける。
今?生えてくるころなの?と思う。
そう、昔から日本に生えていたのはそれとは別の「真竹(またけ)」。
これが生えてくる頃が5月だそうな。
他にも筍は色んな種類があり、
よく見るタケノコ(孟宗竹)が育ちにくい東北では、細長い「根曲がり竹」が主流。

【小満】
「蚕(かいこ)起きて桑(くわ)を食(は)む」5月21日~5月25日
シルク=絹。
これは蚕(かいこ)という虫さんが吐き出した糸なのだ。
白色のイモムシさんのような幼虫(カイコ)が、
モリモリと桑の葉を食べて、体のまわりに白い糸を吐き出して繭(まゆ)を作る。
それを絹糸にする。
かつては日本中で絹産業が盛んだったので、
蚕のエサになる桑畑がたくさんあったそうな。
そんな人々の生活にぴったり寄り添ってた七十二候。
時代と共に変わりゆく私たちの生活。
昔は昔の良さが、今は今の良さがあり
個人的にはノスタルジーになるけども、複雑だ。
たくさんの蚕が桑の葉を食べる時の音は、
「シャ~ サ~」と雨が降ってるようで、
「蚕時雨(こしぐれ)」といわれるそう。
きっと、身近でそんな音が聞こえてきたら、
「あぁ、“蚕おきて桑を食む”の季節だなぁ」と
感じるのかなぁ。
紅花(べにばな)栄(さか)う
5月26日~5月30日
紅花は、紅色の染料や口紅の元になる。
別名を「末摘花(すえつむはな)」という。
源氏物語でも出てくる「末摘花さん」は、鼻が赤く美人とは言えないキャラで、
光源氏が「鼻が赤い」と「花が赤い」をかけて、
末摘花と名付けたとか。失礼やな、、。
ともかく、そんな時代から暮らしに寄り添ってきた花だったもよう。
麦秋至(むぎのときいたる)
5月31日~6月5日
麦の収穫の頃。
秋に種をまき、初夏に収穫をする麦。
そのあとひいて小麦粉にしたり、
煎って麦茶にしたり。
ちなみに小麦は粘り気があり、パンに向く。
大麦は麦茶やビールになるそうな。
「秋」とは穀物の収穫の意味もあるようで、初夏だけど、「麦秋(ばくしゅう)」というのは
麦にとっては実りの秋だからなのである。
●おしまい●
諸説ありで、個人的な感想も入ってますが、
「こんな季節なのねー」と楽しんでもらえれば幸いです。
#つくってみた #ふるさとを語ろう
#七十二候 #二十四節気 #5月 #イラスト
#佐藤家カレンダー #暦 #創作カレンダー
