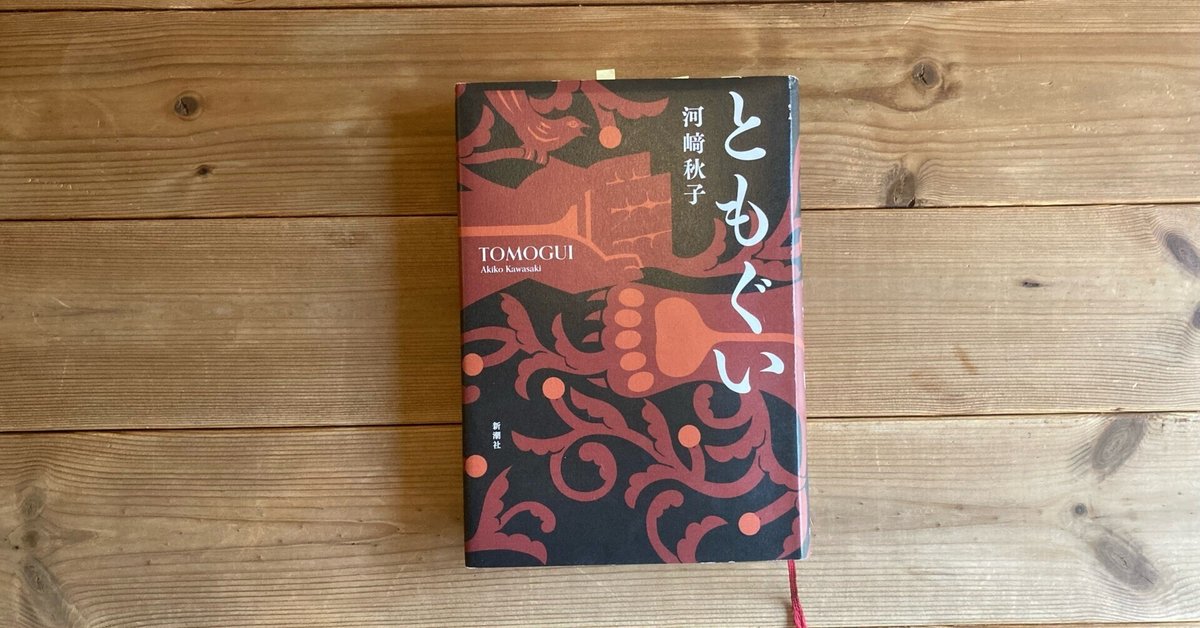
『ともぐい』河﨑秋子 著
カフェ店主おすすめの一冊と、個人的に気に入っているツボをご紹介いたします。
今回は、わたしにとって今年のベスト、『ともぐい』(河﨑秋子)です。
2024年直木賞受賞作とは知らずに、夫の本棚で見つけて読みました。
『羆嵐』(吉村昭)、『クマにあったらどうするか』(姉崎等・片山龍峯)、『羆撃ち』(久保俊治)など、もともとクマに関する本は好きですが、今回は冒頭から荒々しく生々しくも繊細な表現に惹き込まれ、目を離せなくなって一気に読了。
ところどころ、三島由紀夫を彷彿とさせる細やかで鮮やかな描写に惹きつけられます。
熊爪は蘇る肉のえぐみを舌に感じながら、今仕留めたばかりの鹿の腹を裂き始めた。朝の張り詰めた空気に温かく緩んだ蒸気が立つ。それがむわりと鼻の奥に粘りつく。少しだけ、人の股座の臭いに似ていると思う。命の匂いだ。立ち昇る湿気が瞬時に凍り付き、日の出間もない力強い陽光を受けて金色に輝いていた。
開かれた腹の中には、剥き出しの鹿の内臓がつやつやと横たわっている。裂け目に近い腹筋が、魂は消え去ったというのにひくひくと動いた。腸も、胃も、動きを止めて、汗で粘ついた白粉のような白さを晒している。その白さが、肝臓の鮮やかな赤紫色を引き立たせていた。
そして、猟師である主人公熊爪がクマと対峙する姿は、さきに挙げた3冊に通じるものがありつつも、小説という枠の中でその逞しく野性的な精神が見事にたっぷりと堪能できて、別格の味わいがあります。
さらにこの骨太な作品を生み出したのが、女性であることにも大変驚かされました。
さて、この一冊のわたしのツボですが、それは主人公熊爪の「勿体ねえ」という言葉。
「そんな、無茶苦茶なことすんのか。怒った熊ってのは」
八郎が上ずった声で話に入る。熊爪は乱暴に頷いた。
「もう、もともと山にいた熊も起きてくるべし。したら、殺し合いだ。食わねえのに殺し合いだ。勿体ねえ」
勿体ねえ、ともう一度呟いて、熊爪はつまんだ刺身を醤油で真っ黒にして口に放り込んだ。
人間に追い立てられ、自分の縄張りを越えて移動してきた「穴持たず」(冬眠せずに空腹を抱える凶暴な熊)への対応を話す場での、熊爪のセリフです。
さらに、クマ同士の闘いに巻き込まれて負傷した熊爪は、山中を彷徨いながら考えます。
山も森も木々も、腹立たしいぐらいにいつも通りだった。春の陽気に誘われて羽化した白い蝶が、水辺に遊んで花を探している。番となった四十雀が雛のためにその蝶を捕らえる。もし熊爪がここで力尽き、ただの肉と骨と脂の塊となったなら、獣と鳥がその身をたちまち自分らの糧とするだろう。
ひたすらに前を向きながら、熊爪は考えていた。死んだ果てにそうなるのなら、それでも良いのかもしれない。
ーーなにしろ無駄がねえ。
ふいに良輔の涼やかな横顔がよぎった。奴から聞いたところによると、町の人間は人が死んだら燃やして骨にしてしまうらしい。
「肉も燃えちまうのか。なんか勿体ねえ」
生きていくために、食べるために動物を殺し、捌き、保存し、山菜を採って季節に合わせて暮らす熊爪。
人間よりも獣に近い感覚で生きる彼にとって、「ある生き物の死=他の生き物にとっての糧」であり、「無駄がない」のです。
それが「勿体ねえ」という言葉に集約されていて、そしてさらに『ともぐい』というタイトル、物語のラストにも繋がっているように思います。
コスパだタイパだと効率重視で生きる現代人ですが、人間という生き物は、ずいぶん「無駄」で「勿体ない」サイクルの中にいるのかも、と思い至ります。
だからって、誰かが死んだら食べるということはできそうもないと思いつつ、映画『生きてこそ』とか、小説『ひかりごけ』とか、さまざまな作品が思い浮かんで悩ましい。
新しい話題作はあまり読むことがないのですが、久しぶりにぐいぐいと引き摺り込まれ、有名な受賞作はやはりすごいなあと思いました。
タイトルの『ともぐい』には、様々な意味が込められているように思えて、「生きること」と「食べること」、そして熊爪が度々漏らす「面倒くせえ」に象徴される他人との関わりについて、改めて考えさせられる読了後のひととき。
犬が、実にいい仕事をしているところも良かった。
森の秋も深まってまいりました。
人間はスタッドレスタイヤに履き替えて、クマはそろそろ冬眠前の腹ごしらえでウロウロする季節。
当店駐車場も横切ったりしております。
そんな秋の終わりに、「勿体ない」とはどういうことなのか、「ともぐい」とは何なのか、「面倒くさい」様々なしがらみなんかも考えながら、読んでみるのはいかがでしょうか。

