
脳内物質を使いこなして能力を上げていく
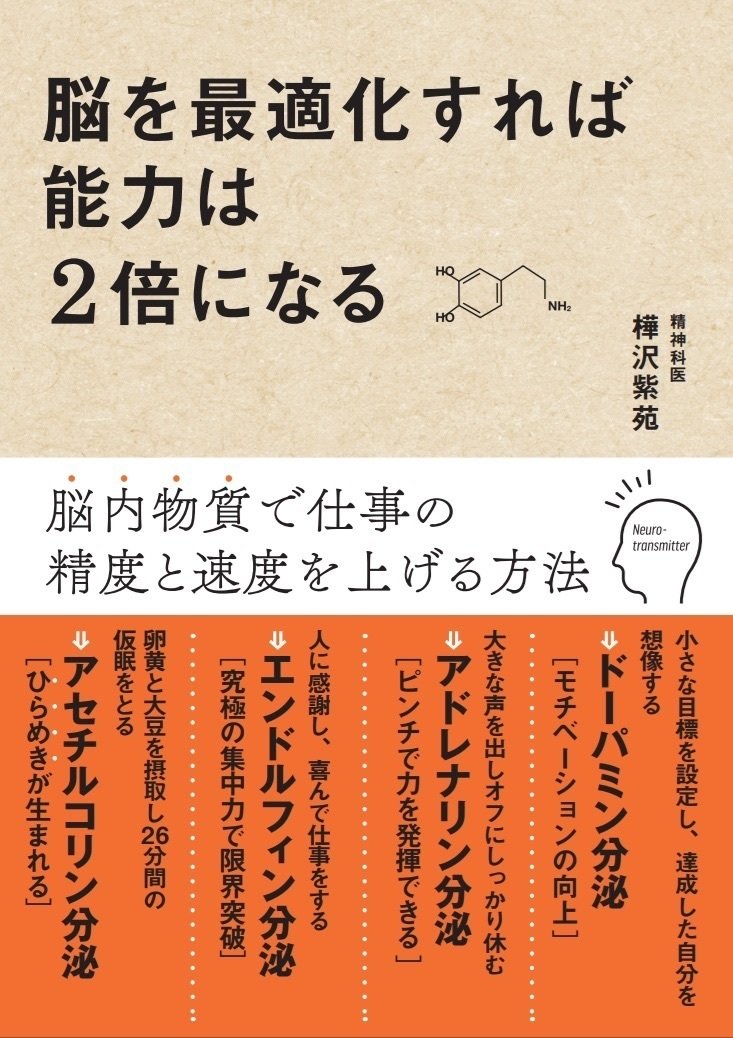
「脳を最適化すれば能力は2倍になる」
この本の序章の冒頭に、「脳の機能を十二分に引き出せばあなたの仕事は変わる」とあります。ただ、私は脳の機能を十二分に引き出しているという自信はなかったですし、意識的に脳内物質を使いこなしているとも思えませんでした。
この本に書かれてあるのは、7つの脳内物質を使いこなすことによって、やる気や集中力を上げ、ひいては仕事などのパフォーマンスを上げられることや、睡眠の質を上げられる、などといったことです。
自己成長は自分にとって大きなテーマなので、本書を手に取りました。自分が抱える課題の解決のヒントになりそうなアドバイスを、見ていこうと思います。
1.ドーパミンを味方につけて目標達成につなげる
目標の達成は、私にとって永遠の課題です。自分には、受験でうまくいかなかった過去があります。すべり止めの学校には受かりましたが、「自分が納得できる成果を出す」ことに強い苦手意識があります。他にも、資格試験で結果を出すのにとても時間がかかったりと、成長が遅いことにコンプレックスを感じてきました。
今、英語の勉強が取り組んでいることの1つです。仕事に関わっていて、中長期のビジョンという点でも自分にとって重要です。
ただ、今までのような成長スピードではまずい。成長スピードを速めたい。目標達成には、何が重要な要素か?整理してみました。
・行動量
・仕事や勉強のやり方
・時間術
・やる気
・目標設定
やる気は重要な要素の1つと思います。
やる気:
[名]みずから物事をなしとげようとする積極的な気持ち。
(明鏡国語辞典より引用)
積極的か、それとも消極的な気持ちで(嫌々)物事に取り組むかでは、おのずとパフォーマンスは違ってくると思います(後者は、ノルアドレナリンが分泌され中長期的に心身によくないと、本書で説明されています)。
樺沢先生によると、人間の脳にやる気を出させるには、報酬を与えることが大事なのだそうです。報酬によってドーパミンが働き、やる気が上がるとのこと。この報酬サイクルをどんどん回していくことが、目標達成によって重要なようです。また、目標を設定することでもドーパミンが出るようです。
樺沢先生は、ドーパミンを分泌させる報酬サイクルを「7つのステップ」として解説しています。
(1)明確な目標を設定する
(2)「目標を達成した自分」をイメージする
(3)目標を繰り返し確認する
(4)楽しみながら実行する
(5)目標を達成したら、自分にご褒美を与える
(6)すぐに「新しい高い目標」を設定する
(7)「目標達成のプロセス」をくり返す
(1)の目標設定は、最近私が特に気をつけていることです。
樺沢先生が強調しているのは、「短期間で実現可能な目標」です。
昔の自分は、過去の挫折もあって、「目標は高く設定して、頑張らなければ」という呪縛を自分にかけていた気がします。しかし、その考えが目標達成の妨げになっていたんだなと、最近ようやく気づけました。目標が高いと、なかなかそれに近づけないので、やる気が落ちてきてしまいます。短期の目標も立てていましたが、遠くの目標に意識がいきがちだった気がします。
樺沢先生著「集中力がすべてを解決する」で「30点目標仕事術」が紹介されていました。目標を低くして(30点)まずはやってみることが大切さだというアドバイス。「やってみて修正する」ことの大事さを実感できるようになっていたところだったので、樺沢先生の言う「手の届きそうな目標に設定する」というアドバイスが、スッと入ってきました。
目の前の1週間の短期目標、「ちょい難」の目標に集中するよう心がけたいと思います。
目標が達成できたら、自分を褒めてあげたいとも思えました。褒めることは、心理的に大きな報酬になるのだそうです。これは(5)のご褒美です。
他に気をつけたいことは、
(3)目標を繰り返し確認する
ことです。私は目標を書いたはいいけれど、手帳の途中のページで、すぐに見つけられない有様。
すぐに見れる場所に書くなどして、毎日意識づけをしていきます。目標を達成した自分を想像してワクワクすることで、ドーパミンが出るようです。
全然できていないと感じたのは、
(4)楽しみながら実行する
ことです。
「やらなきゃいけない」というべき思考が強いんだと思います。義務感が強いと、楽しむことは難しそうです。
元プロテニス選手の杉山愛さんが、「やることを楽しむのがモットー。自分がやることに、楽しみを見出す」ということを語っていました。結果を出している方は、こういう前向きな心の持ち方が、上手なんだなと感じます。
べき思考を少しでも手放して、少しでも物事を楽しめるよう試行錯誤をしていこうと思います。
・短期目標に集中
・報酬を忘れない
・目標の意識づけ
・楽しむ工夫をする
こういったことを新たに意識して、報酬サイクルを回しながら、目標達成につなげたいと思います。
2.やってみる大切さ ーまず行動してアセチルコリンを出す
さて、先ほどの「30点目標仕事術」ですが、行動を起こすことの大切さは、科学的にも説明がつくことなのだそうです。
作業を始めると、脳に刺激がいき、アセチルコリンが分泌され、やる気が上がってくるのだそうです。
昔の自分は行動する前にあれこれ考えてしまっていました。ただ、自己分析をしてみると、行動する前に考えたこと、心配事は杞憂に終わっていたと気づきました。無駄に考えるよりも「やってみてから考えることが大事」と思えるようになってきました。
自分自身の経験に加えて、体の仕組みを理解することで、よりいっそう「何事もまずはやってみよう」という思いを強くしました。
3.メラトニンとセロトニンで睡眠の質を上げて、生活にメリハリをつける
日中の活動を支えるのは、何と言っても睡眠です。
私は近年、睡眠障害があり、中途覚醒が何度かあります。だからこそ質の良い睡眠をとる大切さ、ありがたさがわかるようになりました。
メラトニンは眠りを誘うホルモン。そして、セロトニンがメラトニンの材料になるのだそうです。
セロトニンは、分泌されると集中力が高まり、気分が上がり、頭が冴えるとのこと。日中の活動で重要なセロトニンが、睡眠にとっても大事。ということで、メラトニンとセロトニンの両方を意識していきたい。
・日光を浴びる
・リズム運動
この2つはセロトニンを活性化する方法として紹介されていますが、朝に日光を浴びることは、メラトニンの生成にとっても重要だそうです。そう考えると、朝散歩は本当に効果が高いことなんだなと、納得します。樺沢先生が強調する理由もわかりました。日光浴と朝の運動、まずまず実行できていますが、もう少し増やしていきたいです。
睡眠1つとっても、「部屋を暗くする」など他にも実行しやすいアドバイスが本書には満載で、お金をかけずにできることもたくさんあります。ちょっとした行動の変化で日々の生活の質を上げることができるのだから、面倒くさがらずに少しずつ取り入れていきたいです。
この本で、自己成長のヒントをたくさんもらいました。しっかり休んで心身の調子を整えながら、日中は仕事や勉強、遊びに精を出す。脳内物質をうまく使いこなして、自己成長につなげていきたいと思います。
