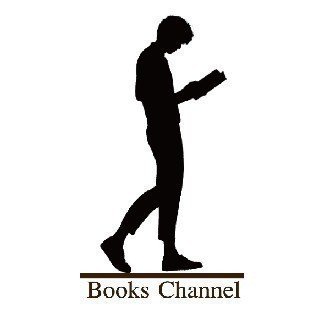幸福度ランキング1位なのになぜ自○率も高い?その何故?”を分析
Introduction
きっかけは「2024.7.6, 取調室にて〜SAYONARAシティボーイズ(文化放送)」BGMとしていた後半部分です。重いテーマであり、答え・正解など存在しないのでしょうが、何故?を分析したい衝動にかられましたもので、進めさせて頂きます。
何故世界第一位の幸福度の"Finland"が26位と日本と変わらぬ程の自○者が多いのか?
ちなみにフィンランドは人口、5,541,000人(2020年度)であり、議院内閣制をとる共和制かつ民主主義の国家となります。日本の人口は2024年1億2,488万5,175人であり、大いに懐疑的ですが、イギリス、スウェーデン、ノルウェーなどと同様に「立憲君主制」かつ「民主主義」国家です。比べるのにはやや無理があるのかも???しれません???を大前提にさせて頂きます。

幸福度1位なのになぜ?フィンランドで自殺率が高い意外な理由
「世界一幸せな国」としてたびたび注目されるフィンランド。国連の発表する「世界幸福度ランキング」で7年連続首位に選ばれた実績などから、多くの人が“理想の国”とイメージしているかもしれません。
ところが、そのフィンランドが意外にも日本と同程度の自殺率を抱えていることをご存じでしょうか? この記事では、
フィンランドが「幸福度1位」とされる根拠
それにもかかわらず自殺率が高いとされる要因
日本との共通点と相違点
に着目し、フィンランドの“幸福の裏側”を徹底解説していきます。
1. フィンランドが幸福度ランキング1位の理由
フィンランドが世界幸福度ランキングで常に上位に入るのは、「自由度」「社会的支援」「所得(GDP)」「健康寿命」「寛容度」「腐敗の少なさ」などの指標で総合的に高得点を獲得しているからです。加えて、無料かつ質の高い教育や医療、手厚い社会保障制度などが多くの人の生活を支え、“平均的な幸福感”を底上げしています。
■ 社会保障と医療の充実
高度な医療をほとんど自己負担なく受けられる仕組みや、学費無料で大学まで進学できる制度が多くの国民に選択肢を与えています。これにより、将来への不安を大幅に減らすことが可能です。■ 自然との共生と生活スタイル
広大な森や湖のある環境の中で過ごすことで、精神的な豊かさを感じやすい側面があります。またワークライフバランスを重視する企業文化も普及し、休暇の取得や家族・プライベートの時間を大切にするライフスタイルが整備されています。
2. それでも自殺率が高いとされる背景とは?
2-1. 日照不足と季節性うつ(SAD)
北欧諸国特有の問題として、冬の長大な夜があります。日照時間が極端に短いことで心身のリズムが乱れ、うつ状態を引き起こしやすいと言われています。反対に夏は白夜が続き、やはり生活リズムが崩れるケースも。
こうした気象条件は、いくら福祉制度が整っていても精神面に影響を与えやすく、深刻なうつ症状へ発展する人が一定数存在します。
2-2. プライバシーを重んじる文化がもたらす孤立
フィンランドでは「静けさを尊重し、他者に干渉し過ぎない」気質を美徳とする面もあり、悩みを周囲に打ち明けるハードルが高いことが指摘されています。人との距離感を大切にするがゆえに、深刻なメンタルヘルスの問題を抱えた人にサポートが行き届きにくい場合があります。
2-3. アルコール問題と社会的ストレス
北欧諸国全般に見られる歴史的なアルコール問題や、近年の社会変化に伴う過度のストレスも一因として挙げられます。失業率の変動や都市部への人口集中により、孤独感と経済的な不安が同時に高まることがあるため、そこからうつ状態に陥りやすくなる人もいるようです。
3. 日本との共通点と違い
フィンランドの自殺率と日本の自殺率は、人口10万人あたりでみるとほぼ同程度です。それでも背景にはそれぞれ異なる要素が混在しています。
■ 共通点:
メンタルヘルスへの偏見や相談のしにくさ
経済的・社会的プレッシャー(過労や学業・就業へのストレスなど)
■ 違い:
日照時間や厳しい気候が与える影響(フィンランド特有)
社会保障の充実度(日本よりもフィンランドのほうが制度は手厚いが、問題が起こる層をゼロにできない)
4. 「幸福度が高い=自殺率が低い」とは限らない理由
「幸福度」は、国全体での平均的な満足度や豊かさを示す指標です。一方、自殺に至る理由は個人のメンタルヘルスや切実な経済的困窮、人間関係の断絶など多岐にわたります。
社会が豊かで平均的に満ち足りていたとしても、少数ながら“幸福”から取り残された人の苦しみが見えにくく、相対的な孤独感が深まる現象が起こるのです。
5. フィンランドと日本から学ぶこと
フィンランドは国内外から注目されるほど社会制度が充実しており、多くの人が高い満足感を得ています。それでも自殺率をゼロにできていないという事実は、「どんな国でも社会の隙間からこぼれ落ちる人が出る可能性がある」ことを示唆しています。
日本も同様に、長時間労働や偏った人間関係などで精神的ストレスをためやすく、自殺率が高止まりしている面があります。
両国とも「声を上げられない人をいかに早期発見し、支援につなげるか」が今後の大きな課題と言えるでしょう。
まとめ
「世界一幸せな国」と称されるフィンランドでも、自殺率は決して低くはありません。これは決して“幸福度ランキングが嘘”というわけではなく、平均的な幸福感とメンタルヘルスの問題がいかに複雑に絡み合うかを示しています。
日本においても同様で、自殺率の高さが長年の社会課題になっています。この記事が、フィンランドと日本の事例から学び、「いかに孤立を避け、適切な支援を行き渡らせるか」を考える一助になれば幸いです。

感想
良き家族・良き友人は命に関わる宝物であることを思い知りました。


Related keywords= #1278日目
いいなと思ったら応援しよう!