
【読書メモ(その1)】「人間は進歩してきたのか―現代文明論〈上〉「西欧近代」再考」佐伯啓思(著)(PHP新書)
発行年度が古い新書ではあるが、現代文明の本質を捉えるため、最低限どのような展望をもっておく必要があるのかということに対して、西欧近代社会の思想的バックボーンを形作った思想家の考え方をわかりやすく俯瞰しているので、備忘録として残しておきます。
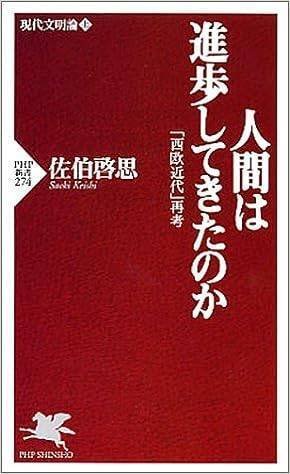
[ 内容 ]
「西欧近代とは何か?」
だれもが疑わなかった理想社会に齟齬が生じはじめた。
その現実を前に、再認識を余儀なくされている「近代」の意味。
自由、平等、民主主義、市場経済…アメリカが掲げる輝かしい「文明」は、同時に形式的な官僚主義、空虚なニヒリズムを生み出した。
信ずべき確かな価値を見失い、茫然自失する私たち。
人類が獲得した果実ははたして「進歩」だったのか。
ホッブズ、ルソー、ウェーバーなど、近代を決定づけた西欧思想を問いなおし、現代文明の本質と危うさに真っ向から迫る新しい文明史観。
[ 目次 ]
第1章 文明の捉え方―進歩の思想と文明の衝突
第2章 「確かなもの」の探求―西欧近代の成立
第3章 「近代国家」とは何か―ホッブズの発見
第4章 「人民主権」の真の意味―ホッブズからルソーへ
第5章 フランス革命とアメリカ独立革命―異質な近代革命
第6章 個人主義の起源―マックス・ウェーバーと西欧近代
第7章 不安な個人の誕生―合理主義の行方
第8章 西欧進歩主義の壁―ニヒリズムの時代へ
[ 発見(気づき) ]
本書は、京都大学での著者の講義「現代文明論」の前半部分をもとに書かれたもの。
はしがきでは、現代の混迷と混乱のもとにあるものは、自由と秩序の観念をめぐるものだと思われる。
これは、西欧の近代思想の挫折といってよい。
本書は、我々が自明のものとし、そのなかにすっかり浸かってきた西欧近代の思考を、まずは相対化することを目的とする。
現代文明の本質を捉えるために、最低限必要と思われる展望をメモしておく。
第1章の「文明の捉え方-進歩の思想と文明の衝突」では、1989年、フランシス・フクヤマが「歴史の終わり」という論文を書いたが、ここに示されている歴史観は、人びとはより自由で、平等で、経済的に豊かになっていく、すなわち近代の理想が現実化していくというものである。(「歴史の進歩」思想)
その背後には、すべての人間は自由、豊かさ、平等、衛生的で健康的な生活を求めるものだという普遍的人間観がある。
そして、それを実現しているのは西欧文明であり、他国は西欧を手本とすべし、ということになる。(西欧中心的な「近代主義」)
これは、その国や地域の文化と調和した多様な近代のあり方を認めず、つねに西欧的価値を基準にして論じるというアポリアをもたらす。
ちなみに、戦後日本も進歩史観の影響を受けて、西欧モデルを無批判に受け入れている。
しかし、それは、そもそも進歩なのか、非西欧の日本にも該当するのか。
それを確認するために、西欧の近代社会がどういうものなのかを俯瞰しておく。
第2章の「「確かなもの」の探求-西欧近代の成立」では、歴史の進歩説は、歴史は不連続に飛躍すると、観念すると説明している。
新しい時代は常に古い時代を破壊し、打ち破って登場したと考える。
本書は、この歴史観を否定する。
例えば、近代社会は、中世・封建社会を打ち倒したわけではない。
中世社会は、自壊したのであり、そこから生じた混沌の中から、例えば、デカルトが確かなものを探求した。
そのデカルトさえも、神を背景にしてコギトを発見する。
宗教改革も確かなものを求めての聖書への原点回帰であり、これが結果として近代的、世俗的な社会秩序を生み出した。
宗教改革は、ローマからの脱却、迫害による普及、俗語共同体の誕生、宗教戦争をもたらし、それらが1648年ウェストファリア条約での世俗的な主権国家の成立につながる。
これがヨーロッパ近代のメルクマールである。
第3章の「「近代国家」とは何か-ホッブズの発見」で、デカルトが精神の基礎を求めたのに対し、社会秩序の基礎を求めたのがホッブズであると述べている。
ホッブズは、人間がお互いに相争うなかで、唯一確かなものは生命だと考える。
そして、この生命の安全を確保する装置として国家を正当化する。
ホッブズの社会契約説によれば、市民社会を支えているのは国家である。
また、政治の基盤は宗教から分離される。
そして、武力を好まず、従順な市民像が描かれる。
神は国家の背後に存在する。(主権者)
しかし、具体的な宗教のかたちを決定するのは国家である。(中性国家、統治機構)
第4章の「「人民主権」の真の意味-ホッブズからルソーへ」では、ホッブズの議論の弱点は、主権者が市民を傷つける場合にはどうすればよいかという点である。
ロックは自然権(所有権)の絶対を説いて、これに反する主権者を否定する。
ルソーは、ホッブズと同じ前提に立ちつつも、すべての人が主権者であり、従属者になるような契約を行うことによって一般意思、ホッブズの矛盾を解決しようとする。
一般意思の具体的な形態としては、共同防衛(共同体に命を預ける)や立法が考えられる。
しかし、一般意思という考えは、独裁、全体主義をもたらす恐れがある。
根源的な民主主義を現実に徹底しようとすれば、それは、民主主義とはまったく逆のもの、すなわち、独裁や全体主義を導く。
第5章の「フランス革命とアメリカ独立革命-異質な近代革命」の中でルソーは、ホッブズの宗教的要素を払拭し、国家と市民社会の分離を回避しようとした。
そして、宗教的要素を取り除いたとき、政治権力を基礎付けるものとして共和主義(市民が積極的に公にかかわり、共同体の善きものを実現する。)という古典古代的な政治観を復活させようとした。
しかし、近代社会では、こうした市民を持ち込めず、代用として国民の意思(世論)を持ち出す。
これは、全体主義への転化をもたらす。
フランス革命とアメリカ独立革命は通常、封建社会を打ち壊し、自由と民主主義の原理、人権の観念を打ち立てたとされる。
しかし、フランス革命は失敗、アメリカ独立革命は成功であった。(アレント)
アメリカ革命は、無の空間での政治権力創出だったのに対し(それでも共和主義を参照した)、フランス革命は、貧困市民層の恨み、怒りに支えれた権力の破壊だった。
ルソーの民主主義論のうち、古典古代的な共和主義を再構成しようという面はアメリカに、根源的な人民主権という面はフランスに受け継がれたといえる。
バークは、フランス革命を、権力は、無から作り出すことはできないという面から批判する。(世襲の原理)
また、合理主義や人間の理性は頼りなく、それよりも、どうしてかよくはわからないものの、歴史のなかで続いてきた慣習やある程度の不平等などにこそ、うまくやっていく知恵が堆積されているはずだと述べる。(「偏見の擁護」)
このため、抽象的な人権を批判し、権利は特定の歴史や習慣とは切り離せないと説く。
第6章の「個人主義の起源-マックス・ウェーバーと西欧近代」の中でウェーバーは近代化とは合理化だと説いたとある。
そして、これが西欧で可能だった理由は、カルヴァン派の禁欲思想にあると言う。
予定説による絶対的な内面的孤独化(誰も自己を救うことはできない)が、個人主義と深くかかわる。
個人は、神を内面化することから生まれる。(「倫理的個人主義」)
同時に、その場合の自己は、命令する自己と命令される自己に分裂する傾向をもっている。
絶対的に孤独な個人は、契約によって共同体を作る。
ここに私と公の明瞭な区分が生まれると同時に、私(信仰生活)の結果が公(社会)で評価されるので、私が公へとつながっている。
重要なことは、個人はキリスト教的な背景と古典共和主義的背景をもって誕生したことである。
個人は、社会を解体して自然状態に戻せば自動的に出てくるものではない。
第7章の「不安な個人の誕生-合理主義の行方」では、ウェーバーは、近代の合理化が人間を機械化してしまう恐れにも触れていたとある。
特に、宗教的支えを失えば、近代市民社会の合理性は硬直化してゆき、むしろ非合理的なものに転化すると恐れていた。
神も失われ、自然の中に生きることもできず、しかし、社会の中で、自ら自己を制御するほかない。
ここに近代的な個人主義(世俗的個人)が生まれる。
世俗的個人は神の支えを失い、不確かで不安の状態にある。
道徳的自我(誠実さ)と、ほんとうの私が対立するようになる。(社会は神の代替とならないため、自分の中に確かな根拠を求める)
また、合理化は、監視されていると思い込ませる近代的権力を生む。(フーコー、パノプティコン、規律・訓練型権力)
個人は、システムの中に包摂されてしまう。(監視者の内面化=宗教的個人)
第8章の「西欧進歩主義の壁-ニヒリズムの時代へ」において、ここまでで、西欧近代の価値の普遍性という意識は、西欧の啓蒙主義思想によって生み出されたものだということが分かる。
西欧近代の価値観が世界化するかは分からない。
しかし、自由や平等といった抽象的価値の内容を決めるのは社会独特の文化や歴史や伝統的規範意識であるということは言える。
このことは、伝統的価値や規範から開放され、それを打破して近代が出現するという進歩主義の図式で事態を理解してはならないということである。
また、近代の企ては西欧でもうまくいってない。
自由や民主主義が実現した時代は、非常に退屈でつまらない時代であり、ニヒリズムをもたらしたからである。
リベラリズムの基礎づけがうまくいってないのもこれが原因である。
確実性の探求を目指した西洋近代は、進展すればするほど、生や世界観の確かさを失わせていく。
ニーチェの予言したとおり、現在、我々はニヒリズムの時代にあると言えるかもしれない。
【参考記事】
哲学者ニーチェが「道徳を最も嫌った」論理的理由 自分自身を誠実に打ち出すことこそが望ましい
https://toyokeizai.net/articles/-/461925
本書の主旨をひとことで言えば、西欧近代の行き着いた先である現在はニヒリズムだ、ということになる。
何ともやりきれない結論だ。
著者の議論を読むと、あの有名なギリシア悲劇「オイディプス王」を思い出す。
国が不幸に見舞われている原因を突き止めようとしたら、もっと大きな悲劇を知ったという話だ。
本書も、振り返りになるが、なぜ冷戦後の世界は混迷しているのかという問題を解きほぐしたら、ニヒリズムという巨大な問題につきあたったという内容である。
本書は、夏目漱石の講演録「現代日本の開化」に通じるものがある。
夏目漱石は、著者が西欧進歩主義に疑問を呈したように、当時の開化が必ずしも人間の心理的苦痛を減じないと論じ、これを開化のパラドクスと呼んだ。
具体的には、かつては、生きるか死ぬかで悩んでいたのが、今日は、いかに生きるかで悩むようになり、開化によっても悩みは無くなっていないというのだ。
これは、本書でいう不確定性、ニヒリズムの問題である。
夏目漱石の「現代日本の開化」もそうだったが、本書で評価すべきは、進歩主義や文明化というものの限界を的確に指摘し、警鐘をならしている点だ。
リベラリズム陣営に顕著であるが、冷戦後の混迷の世界で、さらに西欧進歩主義を推し進めようとする動きが見られた。
自由や民主主義の無理な適用がその好例である。
しかし、そのような自由や民主主義の表層的拡大は成功しないし、そもそも自由や民主主義自体がニヒリズムを生むと著者は指摘する。
自由や平等といった抽象的価値の内容を決めるのは、社会独特の文化や歴史や伝統的規範意識であるからであり、それにもかかわらず自由や平等は、歴史や伝統を掘り崩してしまうからである。
これは形は異なるが、夏目漱石の開化のパラドクスと似ている。
【関連記事】
以下に↓つづく。
