
愛しすぎる女たち
「愛しすぎる女たち」ロビン・ノーウッド(著)落合恵子(訳)
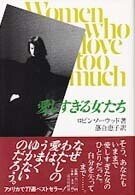
カウンセラーである著者が、クライアントへの精緻なインタビューを通じ、自分を失ってまで、対等ではない恋愛を自ら選択してしまう女性の心理を見事に分析しています。
「愛しすぎる」とは、どんな状態のことを指すのか、著者はこう著述しています。
「「愛しすぎる」ということは、愛する男性の数や恋愛の回数が多すぎることを言うのではない。
愛の深さを示すものでも、むろんない。
それは、一人の男性に強く執着し、執着を愛だと思いこみ、自分の人生や健康、幸福にとってもマイナスになると承知しながら、その執着を断ち切れないでいる状態をいう。
それはまた、喜びではなく、苦悩と苦痛の深さによって愛情の深度を測ろうとすることでもある。」(本書「愛を返してくれない彼」より)
これって、全ての人に当てはまるのではないでしょうか?
恋愛に限らず、愛情が伴うもの、家族関係、親子、友達、ご近所づきあいなど、あてはまることがいっぱいでした。
人間は本来独善的なもので、「自分がこんなにあなたの事を思っているのになぜ判らないの?」という怒りみたいなものは誰しも持っているんじゃないかと思います。
大切なのはその表し方なんだって思います。
また、この本を通じて、人間の”こころ”について考えてみると、いろいろな人がいて、いろいろな事情を抱えて生活している社会においては、それ以上踏み込まないという、最低限の礼儀が重要になってくるんじゃないかと思います。
でもね、過去に一度や二度、すべてを投げ出して、「真実」に向かって言葉を掘りたくなったことってありませんか?
「自分は他者とは違う」という孤立。
絶対的な孤立を抱えた生を、どう理解すればいいのか?
実のところ、他者のこころなんて、わかり得ることではないのかもしれないんじゃないのかって。
家族や友人や、比較的身近にいる人たちでさえ、年を重ねるにつれ、いろいろな生活の背景から、疎遠になることも多々あります。
でも、ほんの少し、ほんの一瞬、「ああ、こころが通じたな」と思う、宝物のような瞬間。
そのような刹那を大切にしないといけない。
たとえ幻想だとしても、いや、それが真実かもしれないから、それを頼りに、自分を生きるしかないのだと、誰しも、心の奥底では、自らに言い聞かせているのかなって感じます。
他者に多くを望まないこと、自分と他人は違うのだとわかること、その上で自分を生きていかなくてはいけないことをね。
それが大人になることだって、頭で理解はしているのですが・・・・・・
まだまだ、本当のところはどうなのか?
理解には、至っていません。
ひとを理解し、ひとから理解されることを望むのは、甘えではないだろうか?と。
そんな気持ちが過ぎることもあります。
なんか、暗くなってしまいましたが、人間が他者に対し、未熟な理解力しか持ち得ないものであるならば。
まずは、その理解の助けとなる手段や場の共有が大切であり、そのための間接的な表現、つまり、言葉の意味を大切にしていくことで、なされ得ると信じたいと思います。
家族、仕事、恋愛、人間関係。
美味しい人生味わうために!
現実に傷つきながらも、考えることをやめないみなさんに!
きっと、幸せが舞い降りてくると思います。
