
【哲学は何の役に立つのか】時代が悪いと言うのなら

[テキスト]
「絶望を生きる哲学 池田晶子の言葉」池田晶子(著)NPO法人わたくし、つまりNobody(編)

池田晶子さんをご存知でしょうか?
特に、若い人たちに向けて、自分で、
「考える」
ことの大切さ、面白さを語りつづけた池田さん。
その著作は、2007年に、世を去ったあとも、息長く読まれ続けています。
目まぐるしく変化する時代のなかで、物事を正しく考え、よりよく生きるために、
「時代が悪い」
「環境が悪い」
と、ついそう言いたくなるけど・・・
「時代とは何か。
ひとりひとりの人間の生きているそこ以外のどこかに、時代という漠とした何かが別にあるわけではない。
時代が悪いと言うのなら、あなたが悪いのだ。
何もかもすぐにそうして時代のせいにしようとするあなたのそういう考え方が、時代の諸悪のモトなのだ。
なぜ自分の孤独を見つめようとしないのか。
なぜよそ見ばかりをしているのか。
不安に甘えたくて不安に甘えているくせに、なお誰に不安を訴えようとしているのか。」(『睥睨するヘーゲル』より)
そうであれば、生きることの愉しさとは、どこにあるのでしょうか?
ニーチェはかつて、
「人間は重要なことについては、つねに原因と結果を取り違える」
と道破しました。
ご賢察の通り、ある種の問いに答えが出ないのは、しばしば、私たちが原因と結果を取り違えているせいです。
だから、天才は、解答不能な難問に立ち向かうときに、とりあえず、話を逆にしてみるという技術を、駆使しました。
大切なのは、
「結果」
じゃなくて、その
「道のり」
を、どんなふうに歩いているか、ということ。
例えば、歩くことを楽しんでいれば、どんな結果でも、
「結果オーライ」
になる。
笑顔で歩いている人は、どこに辿りついても、結果、笑顔になる。
だから、
・近道をさがすよりも
・早く歩くことばかりを考えるよりも
歩いている今、ここを楽しめる人であることが重要です。
結果は、一つの点にすぎないけれど、そこに至る日々は、ながいながい一本の線であり、無数の分岐点が存在しています。
人生のほとんどの時間は、道のりなんですよね。
では、
「生きることの意味は何か?」
という問いに答えるのが難しいのは、答えが無数にあって、収拾がつかないからです。
このことについて、内田樹さんは、
「街場の現代思想」(文春文庫 )内田樹(著)

本書の「生きることの愉しさについて」の中で、以下のように述べていました。
「人間は死ねるから幸福なのだ」
「人間は限られた時間、限られた空間のうちに封じ込められ、一度壊れたら二度と旧に復することがなく、一同失ったら二度と出会えないものに囲まれている。
人間をめぐる事象のすべては不可逆的に失われる。
しかし、『すべては消滅し、私たちは必ず死ぬ』という事実そのものが実は人間の幸福を基礎づけているのである」
「今目の前にある『うつろいやすいもの』の美や儚さは、それらの器物そのもののうちに内在するのではない。
そうではなくて、『それが失われた瞬間に立ち会っている私』という先取りされた視座が作り出した『想像の効果』なのである。
私たちが『価値あり』と思っているものの『価値』は、それらのここに事物に内在するのではなく、それが失われたとき私たちが経験するであろう未来の喪失感によって担保されているのである」
「私たちが物語を楽しむことができるのは、仮想的に想定された『物語を読み終えた私』が未来において、現在の読書の愉悦を担保してくれるからである」
「人間は前未来形で自分の過去を回想する」ジャック・ラカン
「私たちが、いま自分のみに起きているある出来事(人間関係であれ、恋愛事件であれ、仕事であれ)が、『何を意味するのか』ということは、今の時点で言うことができない。
それらの事件が『何を意味するのか』は100%文脈依存的だからである」
「その出来事が終わった時点にまで、想像上の時計の針を進めなければならない」
「今生きつつある人間関係がどれほど複雑で、どれほどものごとの現われが錯綜していても、起きつつある事件がどれほど不可解でも、『死んだ後の私』を想定しうる私にとって、それは生きる経験の愉悦を増すこそすれ、それを減殺するものではない。
むしろ話が複雑になり、混乱が深まるほどに、『私という物語』を読み終えたときに立っている視座から一望俯瞰される風景の広大さに対する期待が私たちの中では高まる」
「今の若い人たちに欠けているのは、『生きる意欲』ではなく、実は『死への覚悟』なのである。
『生きることの意味』が身にしみないのは、『死ぬことの意味』について考える習慣を失ってしまったからである」
未来から今を見る視座。
死から生を見つめる視点。
この視点こそが、
「今」
を、より生き生きと、意欲に満ちたものにさせてくれる。
日々、
失われ・・・
壊れ・・・
儚く・・・
過ぎ去るものに、囲まれている私たち。
だからこそ、
「今」
に価値を見出すのでしょうね。
モノ、そのものに価値があるわけではない。
それが、やがて、失われるからこそ、価値があるのだとしたら・・・
そして、今の私たちに、足りないものがあるとすれば・・・
それは、
「生きる意欲」
ではなく、実は、
「死への覚悟」
なのだと思います。
「生きることの意味」
が身に沁みてこないのは、
「死ぬことの意味」
について、考える習慣を、失ってしまったからなんだと、そう考えられませんか。
今一度、私たちが、自分の人生に対して、生きることの愉しさを感じるためにも、
・自分がどういうふうに老い
・どういうふうに病み衰え
・どんな場所で
・どんな死にざまを示すことができるのか
を、繰り返し、繰り返し、想像することであり、困難な想像ではあるけれど、今、この場での自分の
「今」
の人生を輝かすのは、尽きるところ、その想像力で得られた現実なのだと思います。
であれば、人生の愉しみとは、可能な限り、深く味わうことに、帰着してきます。
なるようになるし、ならないようにはならないんですね。
さあ、この先どうなるか。
基本的には、各自が、自分に善いことだけをする、自分さえ善ければいいという構えを崩さなければ、何があっても大丈夫だと、池田晶子さんは言っています。
他人や、社会を、気にしない、惑わされないということです。
おそらく、多くの人々は、
「人生の価値」
を、
「生活の安定」
に求めているのかもしれません。
「先が見えない不安」
とは、人々の
「口癖」
でもあります。
そんなのは、今に始まったことではないんですよね。
人は、生まれた限り、死ぬものであり、その間にいろんな目に遭う。
それが人生というものです。
そうでしょう?
であれば、なんで在るんだかわからないこの奇跡的な存在。
つまり、人生を、可能な限り深く味わってみたいという気持ちを持ってればいいと思いませんか?
これをまた裏返すと、そんなに気張らなくてもいいのかなとも言えるわけですが、べつにいいんでしょうねぇ、なんでも。
そう、なんでも、同じじゃないか・・・
まあ、面白いですね、
「人生がある」
ということは。
と言うことで、そんな想像を膨らませるために、ちょっと、哲学は何の役に立つのか、考えてみたりして、みませんか?(^^)
■哲学は何の役に立つのか
「哲学は何の役に立つのか」(新書y)西研/佐藤幹夫(著)

[ 内容 ]
思春期はなぜ苦しいのだろうか。
親も社会もなぜ「うざい」のだろうか。
学校へ行け?
高学歴?
働いて早く一人前になれ?
やってられねえ!
…しかしそのとき、じつは「哲学すること」の入り口に立っている。
世界とはなにか。
自分はなぜ生まれてきたのか。
なぜ生きるのか。
なぜ人に好かれないのか。
誰もが問うこの問いこそ、人がひとりでは生きられないことによっている。
人は何を足場としどこへ進もうとするのか。
それを考える技術こそが哲学である。
西洋近代哲学は、その問いをギリギリまで押し進めた。
「問い‐答え」という対話を通じて「哲学すること」の意味を問う入門書の決定版。
[ 目次 ]
序章 哲学の難しさに負けないために
第1章 ニーチェ 「自分」をどこから考え始めるか
第2章 ソクラテス‐プラトン 「考える」ことについて考えてみる
第3章 カント 「人間」とは何だろうか―近代という枠組みを考えてみる
第4章 ヘーゲル 教育と働くことをめぐって
第5章 フッサール・橋爪大三郎 「私」から社会へどうつなげるか―「われわれ」の語り方
第6章 カント・ヘーゲル 9・11以降、「正義」についてどう考えるか
終章 東浩紀・フーコー 哲学はなぜ必要か―再び「考える」ことの足元を見つめて
[ 問題提起 ]
頭で考えたことは、実は現実世界では、役に立たないのではないか。
そんな問題意識から手に取ってみたのが、この対談集である。
結論は、当たり前だが、
「頭で考えたことは役に立つ」
である。
理論は、もちろん万能ではない。
現実にかみ合わない部分は出てくるだろう。
だが、そもそも、現実社会の問題意識から理論的モデルは構築されるのであって、プラクティカルに現実問題に理論を適用し、解決していく努力をすることはできるはずである。
現代的問題意識と哲学的命題を絡めながら理解していく。
そうすることで、やっぱり、
「頭で考えたことはこうして役に立つ」
と考えられないか。
ある学者は、理論と現実は、弁証法的連関によって、止揚されるというようなことを言っていた気がするが、まさしくその通りなのであって、この止揚に失敗すれば、机上の空論となって、
「学者のお遊び」
と揶揄されるのである。
生命倫理が結構そうなっているように感じられるのは、そのためかもしれない。
駿台のある講師が言っていたことだが、臓器移植に反対する知識人が多くいるなかでも
「現実に人は死んでいく」
のだと。
だからといって、生命倫理は無力なのか。
多分そうではないだろう。
「行き過ぎた」
部分は、止揚に失敗したと見るべきであって、本来、弁証法的連関に取り込まれれば、実用的なのではないか。
むしろ、その連関に取り込む努力をしていくべきでは。
いずれにせよ本対談は、大御所哲学家の理論を現代に当てはめていく、そういう試みである。
[ 結論 ]
個人的に印象に残っている部分を、少しだけ説明しておく。
まず、最初に、ニーチェの話が来ている。
超人やルサンチマン、永遠愛。
高校では倫理で学習するタームである。
ただし、高校倫理では、やはり試験のための学習という感は否めなく、内容には、あまり立ち入らないことが多い。
ニーチェの思想は、何も、キリスト教にだけ通用するというものではなく、現代社会と関連させれば、こうなる。
全ての運命を引き受けるのが
「超人」
である。
これまで、色々と大変だったけど(神は死んだけど)、過去はもう変えられないのだから、それらを全て運命として背負って(運命愛)、頑張って生きていこうじゃないか。
ニヒリズム(虚無主義)を超えていこうじゃないか、と。
その形而上学は、すさんだ現代社会の人々の心をとらえるのかもしれない。
次に、ソクラテスやプラトン。
大昔の人。
けれど、哲学するということは、長い歴史のうち、古代ギリシアから始まった。
これは、人間のライフサイクルの中での思春期ということと、パラレルに考えることができる。
哲学は、理想が壊れた時から始まる。
理想が壊れるとは、安定した世界が揺らぐことと、同値である。
古代の世界では、異文化接触から自己の相対化が必要になる。
そのための手段として、考えること、ロゴス、つまり、論理が出てくるわけである。
そして、たまたまギリシアは、民主的で共和制で、対話ができる環境だった、と。
これらの条件が重なって、哲学は、公共圏における思考のゲームになったということだ。
さらに、ソクラテス・プラトンは、関心の転換期でもある。
それまでは、自然に関心が行ってた(タレスなど)けど、彼らからは、人間の方に行く。
これらを、人が、思春期に自分の
「哲学」
を得るプロセスに、そのまま当てはめられるというわけである。
個人的な例で言うと、だいたい中学の生頃だったと記憶している。
まず、理想の崩壊とは、挫折そのもの。
それまで
「やればできる」
と思ってた、ある種の全能感が、崩れるわけである。
どうしようもないという感触を味わう。
「理想というブロンズ像がガラガラと音を立てて崩れていく」
といった感覚である。
そして、世界観が揺らぐと、考えなければならないわけである。
ひたすら頭で。
アイデンティティが確立できずに、危機が訪れる。
本対談では、教育(中等教育かな)のことが色々と関連して出てきているのが面白い。
青春時代に袋小路になること、エネルギーだけあって、観念が、肥大化してシンドイということ、自己の承認や、社会や、他者の必要性があること、それが、無理だと自分の世界に引きこもること、などが書かれてある。
こうして、思春期に自己を、再び、得ていく。
思春期に、少数ではあるが、教育に漠然と問題意識を抱き、エネルギーの矛先が、教育に行っていた方も、いらっしゃるのではないだろうか。
プラトン・ソクラテスと思春期に話を戻すと、本当の意味での対話ができるのは、
「(例えば男の子の場合の)バカを言い合える」
友人関係なのだということ。
それから、関心が、自然→人間に行くというのも、共通している気がする。
純粋な哲学から敷衍して、人の心の中に入っていく現象学や批評の話。
それと
「対話」
ということが、やはりキーワードとなってくる。
「哲学は対話する プラトン、フッサールの〈共通了解をつくる方法〉」(筑摩選書)西研(著)

本対談での、在日(この表現の是非は置いておいて)の人との
「対話」
という例が印象に残っている。
もちろん、在日の人と普通の(?)日本人の人との経験は、異なるわけである。
その異なる経験を、お互いに伝え合い、コミュニケートしていくのが対話。
で、そのためには、自分の経験を探っていって、相手に分かる形で、一般化する批評の方法が、必要になってくる。
つまり、相手に分かる言葉で、何とか伝えていく。
それは、相手も同じ。
それで、お互いの
「感触」
を探っていく。
その積み重ねが対話であり、そうやっていって、一つずつ偏見を取り除いていく作業が、感動的である、と。
で、そういうことは、多分、今、一番、世界で、かなり必要とされている。
それが、可能なのか、不可能なのか。
それを、東浩紀・フーコーとの関連で、主に、西氏が語っていく。
フーコーの見解では、自分の経験を掘り下げていって、他人に分かる形で一般化すること(「本質抽出」という)は、それ自体が、権力によって歪められているので、禁じ手とされているらしい。
そうなると、本源的に、対話は、無理だということになってしまう。
それが、正しいのか、どうなのか。
西氏は、この考え方を、
「フーコーの悪しき遺産」
と言っているのだが。
フーコーを受け継ぐ、東氏に関しての
「動物化」
も言及しているのだが、個人的には、対話の不可能性につなげる方が、面白かった。
[ コメント ]
ここまで見てきて、結局、哲学は、
「役にたつのか」
「現実を分析しきれるのか」
という問題はどうだろう。
「「哲学は日常と乖離していなければならない」という主張は、入不二基義「哲学の誤読ーー入試現代文で哲学する!」によっています。」
「哲学の誤読 入試現代文で哲学する!」(ちくま新書)入不二基義(著)

野矢茂樹の論文を引けあいに出しながら、こう書いている。
哲学的な疑いは、日常のものとは違う。
日常の表現としての
「他者の痛みは本当のところは分からない」
と、哲学的な疑いの表現としての
「他人の痛みは本当のところは分からない」
は、似て非なるものである。
対して、哲学者の池田晶子は、
「事象そのものへ![新装復刊]」池田晶子(著)

で、
「哲学は、研究室や図書館に在るのではなく、日常の中に在る」
と述べている。
まず、哲学と日常との距離を定義することから、議論を始めなければならないということである。
「哲学と日常との距離」
とは、モデルと現実の乖離ということ。
いやしくも学問(=紙の上の情報)なら、モデルに限界がある。
けれども、モデルというのは、やはり、日常に適用するために、作るものなのだ。
ニーチェ・モデルにしても、ソクラテス/プラトン・モデルにしても、東浩紀/フーコー・モデルにしても。
他にも、カントやヘーゲル、フッサールなどの話が出てくる。
「他者の痛みは本当のところは分からない」
と、日常で思って、壁を感じたときにこそ、哲学的な思考を要請するわけです。
そういう意味では、やはり、哲学と日常は連続している、のだと考えられる。
だから、結論はこうなる。
「頭で考えたことは役に立つ。」
と。
「評伝 島成郎」佐藤幹夫(著)

■哲学は人生の役に立つのか
「哲学は人生の役に立つのか」(PHP新書)木田元(著)

[ 内容 ]
江田島の海軍兵学校で終戦を迎え、あてもなく焼け跡の東京へ。
テキ屋の手先や闇屋をしながら、何があっても食べていける術は身につけた。
しかし、いかに生きるべきかという悩みは深まるばかりの青年期。
ドストエフスキー、キルケゴール、やがてハイデガーの『存在と時間』に難問解決の糸口を見出す。
それから半世紀以上を経て、はたして答えは見つかったのだろうか──。
八十歳を迎えた哲学者が、波瀾の運命をふり返りながら、幸福、学問、恋愛、死生観までを縦横に語る。
著者は哲学の勉強をはじめるまで、農林専門学校に通うなど、さんざんまわり道をしてきた。
そしてハイデガー思想を理解したいために、カントやヘーゲル、フッサール、メルロ=ポンティという具合に何十年もまわり道をした、と言う。
しかし、まわり道をしたからこそ、新しい道が開けてきたのだと思う、と回想する。
思いきり悩み、迷いながらも、力強く生きることの大切さを教えてくれる好著である。
[ 目次 ]
序章 「幸福」なんて求めない
第1章 混乱の時代を生き抜いてきた
第2章 思いきり悩み、迷えばいい
第3章 頭より体力が基本だ!
第4章 哲学者だって女性に惑った
第5章 人生ずっと、まわり道
第6章 遊びも一所懸命
第7章 好きなことをして生きる道
終章 死ぬための生き方
[ 問題提起 ]
「なにもかも小林秀雄に教わった」(文春新書)木田元(著)

と本書の二冊は、
「敗戦直後の混乱期」
に猛烈な勢いで本を読み、
「文学と哲学のはざまで」
精神形成をしてきた著者が、かたや哲学の側から、かたや文学の側から、読書体験と重ねつつ自らの生の軌跡をたどったものである。
この二冊には、異色の哲学者木田元の迫力に満ちた姿がまざまざと描出されており、圧倒される。
[ 結論 ]
著者木田元は、満州(現中国東北部)の新京(現長春)で育ち、中学卒業後、家族と離れて日本に渡り、江田島の海軍兵学校に入学するが、四か月余りで終戦となる。
まだ十代前半の身で、終戦直後の大混乱の渦中に放り出された著者は、上野駅での野宿、テキ屋の手伝いを経て、ようやく、山形の親類を捜しあて身を寄せる。
まもなく、母と三人の姉弟が引き揚げて来るが、満州国官僚だった父がシベリアに抑留されていたため、小学校の代用教員をしながら、東京まで闇米を運ぶなど、獅子奮迅の働きぶりで、一家の暮らしを支えてゆく。
このとき、著者は、三十キロを背負い、両手に十五キロずつと、合計六十キロの闇米をもって、他の闇屋になぐられながら、満員の汽車に乗り込んだという。
まさに、体力勝負だ。
首尾よく汽車に乗り込んだ後は、『芭蕉七部集』や芥川龍之介などを読んでいたというから、驚くほかない。
このように、手段を尽くして、多種多様の本を入手し、寸暇を惜しんで、濫読にふける著者の姿からは、一種の
「知的飢餓感」
が感じとれる。
戦後まもない飢餓の時代に、生きあわせた著者にとって、生きるために、自分および家族の空腹を満たさねばならないことと、知的空白を埋めようとする渇望とは、切っても切れない関係にあり、生きることと、読むこと、知ることが、渾然一体となっていたかに見える。
また、著者ほど、江戸文学、ロシア文学、漢詩から小林秀雄等々にいたるまで、多岐にわたる大量の文学書を読破した哲学者はいないと思われるが、その知的好奇心は、後年には、純文学のみならず、外国および日本のミステリ等々、エンターテインメントの分野にも及ぶなど、とどまることを知らない。
混乱の巷で育まれたこの限りない知的飢餓感と、恐るべき知的好奇心による一種の
「雑食性」
を、著者は、けっして失うことなく、今に至るまで、保ちつづけている。
これは、
「象牙の塔」
で
「純粋培養」
された、ひよわな学者には及びもつかない芸当であり、まさにダイナミックな
「知の巨人」
というほかない。
この二冊には、そんな著者の
「猛禽」
のような彷徨と探究の跡が如実に記されており、胸躍る面白さがある。
さて、著者は、ひょんなことから大金を手に入れ、ともあれ学校に行きたいと、新設された山形県立農林専門学校に入学する。
一年たらずで資金切れとなり、身のふりかたを考えねばならなくなったころ、幸いにも父が帰国、家族を養わねばならない重荷から、ようやく解放される。
かくして、心おきなくドストエフスキーに夢中になったりするうち、専門学校の先生から、ハイデガーの話を聞き、自分の抱える底なしの絶望感と呼応するものを直感して、どうしても
「存在と時間」マルティン・ハイデガー(著)高田珠樹(訳)

を読みたいと、東北大学を受験する決意を固め、猛勉強のあげく合格する。
以後、東北大学の哲学科に在籍すること十年、ハイデガーのみならず、カント、ヘーゲル、フッサール等々の原書を、次々に読破してゆく。
受験勉強のさい、著者は、朝から晩までぶっとおし、凄まじい集中力で、短期間に英語をマスターしたが、大学入学後も、哲学書を読むのに必要なラテン語、ドイツ語、フランス語など、種々の語学を、同様の方法で、次々にマスターした。
この壮絶な集中力に、いかなるときも本を手放さない、あの
「知的飢餓感」
と共通したものがあるのはいうまでもない。
やがて、著者は、中央大学に就職、東京に移住し、メルロ・ポンティのほとんどの著作を翻訳する一方、
「現象学」(岩波新書)木田元(著)

などの著作をあらわすなど、旺盛な執筆活動を続行する。
著者自身の言によれば、こうして
「まわり道」
をしたあげく、哲学に足を踏み入れる契機になったハイデガーを、本格的にとりあげた著書を完成するに至る。
「ハイデガー」(20世紀思想家文庫 4)木田元(著)

ハイデガーを読みつづけること、三十三年の成果だった。
ただならぬ粘着力であり、持続力である。
まっしぐらに、短期間で目標を達成する集中力と、むしろ、好んでまわり道や寄り道をし、発想を豊かに膨らませながら、徐々に、目標へ到達する持続力。
変幻自在にして、柔軟な著者ならではの両面性だが、やはり、その根底には、精神形成期の
「知的飢餓感」
と
「雑食性」
がひそんでいるといえよう。
「ハイデガーの思想」(岩波新書)木田元(著)

「ハイデガー『存在と時間』の構築」(岩波現代文庫)木田元(著)

「ハイデガー拾い読み」(新潮文庫)木田元(著)

終戦後、劇的な体験をした著者は、けっして、単なる書斎の人、知の人ではなく、たくましい生活者の感覚と、強靱な身体性を合わせもった人である。
[ コメント ]
著者の知的世界や、その哲学は、タフな身体性に裏打ちされているともいえよう。
そんな稀有の哲学者が、著したこの二冊の本は、生半可な絶望を吹き飛ばす躍動感にあふれており、圧巻というほかない。
■哲学の謎
「哲学の謎」(講談社現代新書)野矢茂樹(著)

[ 内容 ]
時は流れているだろうか。
私が見ている木は本当にそこにあるか。
他者、意味、行為、自由など根本問題を問いなおす対話篇。
[ 目次 ]
1 意識・実在・他者
2 記憶と過去
3 時の流れ
4 私的体験
5 経験と知
6 規範の生成
7 意味の存りか
8 行為と意志
9 自由
[ 発見(気づき) ]
「哲学って、何の役に立つんだろうね?」
という言葉を、何度、聞いたことか。
そして、その言葉を聞きながら、私は、小声で
「役になんか立たないんじゃないの」
と、つぶやいたものだった。
こういう言葉のやり取りが、日常の中で、
「普通に」
交わされている事実を、どう考えたらいいのだろうか。
おそらく、哲学という学問が、単なる机上の空論をこね回しただけの学問か、あるいは、凡人にはなかなか理解し得ないような真髄をもった、とてつもなく深い学問かのどちらかなのだろう。
そして、たぶん、その答えは、後者であるはずである。
なぜそう考えるのかというと、
「哲学」
という学問の歴史に、その理由がある。
一般に、哲学は、古代ギリシャで始まったとされているが、そうだとすれば、数千年の歴史をもった学問ということになる。
論理は、飛躍するが、数千年の歴史に淘汰されずに残っていること自体が、哲学に、深い意義と、価値があることを、証明していると言えるのではないであろうか。
[ 教訓 ]
ところで、本書は、私のような
「哲学初学者」
向けに書かれている。
哲学について、何の知識がなくても、読み進めていくことができる。
文章構成にも工夫がされており、ある二人の男性の対話形式で、進められている。
これを読んでいる私たちは、二人の対話を読み進めながら、自然のうちに、哲学的な問いに向き合うことになる。
また、本書は、
「哲学初学者」
向けと書いたが、決して、優しい問題を、取り上げているわけではない。
目次を見ていただければわかるとおり、
「意識・実在・他者」
「記憶と過去」
「時の流れ」
ほか9つの項目から構成されている。
そして、どの項目をとっても、
「○○とは?」
と考えると、一筋縄ではいかない、問題ばかりだということに、気付くはずである。
事実、本書で取り上げられた問題の中で、
「答え」
にたどり着いたものは、一つもないのである!
すべてが、疑問を残して終わっている。
ある意味で、ここが、本書の面白さであり、同時に、
「哲学の深さ」
と言えるのではないであろうか。
[ 一言 ]
ところで、本書の第4章「私的体験」の中に、次のような記述がある。
『ある人たちは実際、こうした懐疑に捉えられて、どうしようもなく落ち着かなくなる。
(中略)
問題は、われわれがこうして他人の知覚についての懐疑に思い至ってしまうということなのだ。
実生活には無関係かもしれない。
しかし、こんな懐疑に辿り着いてしまうというのも、きわめて人間的な現象だ。
そして、この懐疑に「何か気持ち悪い」と反応するのもまた、きわめて人間的な現象にほかならない。
だから、その気持ち悪さから目をそらさずにこの懐疑をもっと見つめることで、われわれ自身を知ることができるかもしれない。
実際、ここには哲学が問題にすべき何かがある。
この懐疑そのものはきっかけにすぎないかもしれないが、これをバネにして何か開けてくるかもしれない。』
この記述にあるとおり、あなたは、この本を読むことによって、
「何か気持ち悪い」
という感覚を伴った、懐疑の気持ちが、わいてくるかもしれない。
「語りえぬものを語る」(講談社学術文庫)野矢茂樹(著)

もし、そうなったとしたら、その謎に、挑戦してみたらどうだろうか。
「はじめて考えるときのように 「わかる」ための哲学的道案内」野矢茂樹(文)植田真(絵)
著者である野矢茂樹氏は、読者のそうした挑戦を、受け止めてみたい気もあるそうである。
巻末に、連絡先も明記してあるので、東大助教授の野矢氏に、挑戦状を叩きつけてみてはどうだろうか。
もしかしたら、興味深い対話ができるかもしれないのだから。
「ウィトゲンシュタイン 『哲学探究』という戦い」野矢茂樹(著)

■子どものための哲学
「〈子ども〉のための哲学」(講談社現代新書)永井均(著)

[ 内容 ]
悪いことをしてなぜいけないか。
ぼくはなぜ存在するのか。
この超難問を考える。
[ 目次 ]
●なぜぼくは存在するのか
ロボットの疑惑
ぼくが存在しない2種類の状況
個別化された脱人格的自我
世界の複数性と唯一性
●なぜ悪いことをしてはいけないのか
好いと善い、嫌なと悪い
善いことをする動機の問題
人間はみんな利己主義者か
哲学に対する2つの態度
[ 問題提起 ]
本書は、
<子ども>
のための哲学入門書。
なぜ、
<子ども>
なのかといえば、ほんとうの哲学とは、ひとが、難なく理解している事柄に疑問を感じ、その意味を、自分なりのやりかたで、探っていく行為のことであり、それこそが、純粋に、知的な
<子ども>
の思考法だからである。
だから、哲学は、世間のひと(哲学者でないひと)を乗り越えるための試みではまったくなく、むしろ、ひとが、やすやすと、苦もなく到達している地点へと、必死に這い上がろうとする努力、にほかならない。
哲学にたいする以上の考えを前提として本書は、
「<ぼく>はなぜ存在するのか」
「なぜ悪いことをしてはいけないのか」
という2つの事柄について
<哲学する>
ことを、作者とともに体験できる仕組みになっている。
がしかし、当然のことながら、哲学する理由がなければしないでもよく、また、出来合いの哲学諸説を摂取することは、実は、哲学から、もっとも遠い行為であってみれば、結局、哲学するのかしないのか、また、どのようにするのかしないのかは、これも、当然ながら、読者自身が、自分で考えることだ。
「哲おじさんと学くん」永井均(著)

[ 結論 ]
タイトルに、
「子ども」
なんて語が使われているから、平易な本だろうと気楽に手に取ってみたら、あにはからんや、こんな難しい内容とは・・・と感じるので要注意。
著者が、
「自分の問題」
として、長年考え続けてきた、
「なぜぼくは存在するのか」
「なぜ悪いことをしてはいけないのか」
の二つの問いをめぐって哲学する本。
この問いについて、論理的に説明できる/したくなるひとが、哲学的なひとなのだろう、きっと。
私なら、面倒くさくなって、途中で放り出してしまう気がする。
内容について、あれこれ書く前に、著者の哲学観に触れておく。
「翔太と猫のインサイトの夏休み 哲学的諸問題へのいざない」(ちくま学芸文庫)永井均(著)

著者は、哲学とは、
「自分にとっての問い」
を、自分の頭で、考え続けることだ、という。
この
「自分の問い」
を、自分で考えずに、知識として、プラトンやデカルトやカントやハイデガーや・・・、そういった過去の哲学者たちの著作を読み耽る行為は、哲学するとはいえない。
それは、哲学とは、何の関係もない行為だ、という。
他人の哲学を理解することは、しばしば退屈な仕事である。
そして、どんなによく理解できたところで、しょせんは、何か、まとはずれな感じが残る。
ほんとうのことを言ってしまえば、他人の哲学なんて、たいていの場合、つまらないのが、あたりまえなのだ。
おもしろいと思うひとは、有名な哲学者の中に、たまたま、自分によく似たひとがいただけのことだ、と思ったほうがいい。
哲学は、向こう側にあるのではない。
哲学史の本の中に、
「哲学」
として登場してくるものは、もう、哲学ではない。
向こうにある哲学を学ぼうとすれば、哲学した人の残した思想を読んで理解し、共感を感じたり反感を感じたりできるだけだろう。
哲学は、こちら側にある。
自分自身の内奥から哲学をはじめるべきだ。
「哲学的洞察」永井均(著)

永井さんのいう
「子ども」
とは、ソクラテス的な
「無知の知」
をもっている存在のことだという。
子どもは、自分が、世界について、何も知らないことを知っている。
だから、不思議に思ったら、何でも、大人に質問する。
これに対して、大人とは、
「自分が世界について何も知らないということを忘れてしまっている」
存在であるという。
であれば、この本が、
「子供のための」
と謳っていても、それが、難解な内容になるのは、不思議なことではないだろう。
「子どもの問い」
といえば、ミラン・クンデラは、
「存在の耐えられない軽さ」(集英社文庫)ミラン・クンデラ(著)千野栄一(訳)

に、こんなことを書いていた。
「本当に重要な問いというものは、子供でも定式化できる問いだけである。
もっとも素朴な問いだけが本当に重要なのである。
問いにはそれに対する答えのない問いもある。
答えのない問いというものは柵であって、その柵の向こうへは進むことが不可能なのである。
別ないい方をすれば、まさに答えのない問いによって人間の可能性は制限されていて、人間存在の境界が描かれているのである。」
冒頭の二つの問いに、永井さんは、どう決着を着けたのか。
「なぜぼくは存在するのか」
という問いは、ウィトゲンシュタインの
「言語ゲーム」
「はじめての言語ゲーム」(講談社現代新書)橋爪大三郎(著)

「言語ゲームが世界を創る 人類学と科学」(SEKAISHISO SEMINAR)中川敏(著)

「言語はこうして生まれる 「即興する脳」とジェスチャーゲーム」モーテン・H・クリスチャンセン/ニック・チェイター(著)塩原通緒(訳)

の概念から解かれていくが、これがまあ入り組んでいて、途中で、幾度か欠伸してしまった。
これは、
「わたしの問い」
ではなかったらしい。
「なぜ悪いことをしてはいけないのか」
のほうの問いも、わたしはあまり関心がもてなかった・・・、論の進め方は、面白いと思ったけれど。
もし、わたしの中に
<子ども>
がいたとしたら、何を哲学しようとするだろう。
「時間ってなに?」
とは、思うかもしれない。
突き詰めて考えるかどうかは、別として。
「世界は時間でできている ベルクソン時間哲学入門」平井靖史(著)

[ コメント ]
読み終えた思ったこと。
結局哲学というものは(わたしはこの道に無知ですが)ひたすら問い、考え続ける行為なのだろう。
少なくとも、永井さんにいわせると、難解なものではありえないらしい(「哲学が難解なのは、それが他人の哲学だからだ」)。
安易に
「答え」
を求めることなく、
「自分自身の問い」
を生きること。
哲学というと、大仰なイメージを抱いてしまいがちな自分のような人間には、新鮮に感じられた。
「問いが世界をつくりだす メルロ゠ポンティ 曖昧な世界の存在論」田村正資(著)

「問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション」安斎勇樹/塩瀬隆之(著)

「問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する」安藤昭子(著)

■今を生きる思想
「フーコー入門」(ちくま新書)中山元(著)

[ 内容 ]
「真理」「ヒューマニズム」「セクシュアリティ」といった様々の知の「権力」の鎖を解きはなち、「別の仕方」で考えることの可能性を提起した哲学者、フーコー。
われわれの思考を規定する諸思想の枠組みを掘り起こす「考古学」においても、われわれという主体の根拠と条件を問う「系譜学」においても、フーコーが一貫して追求したのは「思考のエチカ」であった。
変容しつつ持続するその歩みを明快に描きだす、新鮮な人門書。
[ 目次 ]
序 現在の診断
第1章 人間学の「罠」
第2章 狂気の逆説
第3章 知の考古学の方法
第4章 真理への意志
第5章 生を与える権力
第6章 近代国家と司牧者権力
第7章 実存の美学
第8章 真理のゲーム
[ 問題提起 ]
フランスの哲学者ミッシェル・フーコーの展開した概念群を初期、
「狂気の歴史 古典主義時代における」ミシェル・フーコー(著)田村俶(訳)

からフーコー最後のプロジェクト、「統治性」
「フーコーの後で 統治性・セキュリティ・闘争」芹沢一也/高桑和巳(編)重田園江/土佐弘之/箱田徹/廣瀬純/酒井隆史/渋谷望(著)

「フーコーの闘争 〈統治する主体〉の誕生」箱田徹(著)

「ミシェル・フーコーの統治性と国家論 生政治/権力/真理と自己技術」(知の新書)山本哲士(著)

「フーコーの〈哲学〉 真理の政治史へ」市田良彦(著)

「フーコーの風向き 近代国家の系譜学」重田園江(著)

のプロジェクトまでを取り上げている。
本書の思考とは、フーコーの思考の軌跡を追い、フーコーという思想家の思想棚卸しを行うのではなく、
<現在>
に生きるわれわれが、自分たちの生き方を問い直し、社会を変革していく武器とするためである。
果たして、私は、武器を得ることが、出来たのだろうか。
『狂気の歴史』では、
「狂気」
が
<神懸り>
であり、人間が理性で見えないものを、見る眼を、神に植えつけられた。
が、歴史とともに、狂気が病となるのだ。
狂気が病となり、
「精神医学」
と
「心理学」
が生まれる事となった。
精神病院が精神病患者を生み出し、狂気を批判の対象とした。
また、人間科学の誕生から人間は発明され、近いうちに、人間は終焉する。
学門は、当たり前に、あるものではない。
歴史の必要性が、学問を産んだ。
私たちが、当たり前に考えている知識や、教養も、学を考古学していけば、成立した背景を、紐解けるのだ。
[ 結論 ]
精神病院、福祉施設は、時代のモード(流行)により左右される。
人里はなれた山奥に、収容される患者。
数十年の社会的入院。
歴史が変われば、地域で暮らす高齢者。
痴呆から認知症から統合失調症。(精神分裂症から統合失調症)
外出の促進。
拘束から、尊厳のある介護へ。
主体である精神病患者、高齢者は変わらない。
歴史が、彼らを変えるのである。
『ニーチェ・系譜学・歴史』では真理。
「真理を語るものはだれか」
「真理とはそれなしにある種の生物が生きて生けないごみょう。」
「ニーチェの歴史思想」須藤訓任(著)
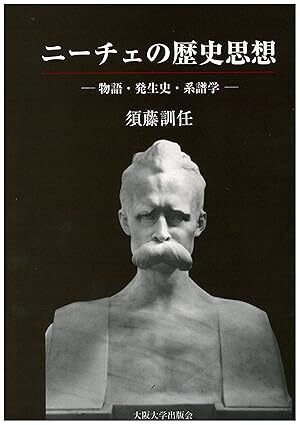
真理は、どうしても、信じざるをえないものとして存在し、現実の社会の権力的な関係において、戦略的な機能を発揮すると解明する。
スターリニズム、カンボジアの虐殺しかり。
真理を、舞台裏から眺める感。
が、これは難しい。
真理が、そこにあるなら、すでに、戦略的に、もう、どうしようもないよう、私が組み込まれているのだ。
だとすれば、後世の歴史で、過ちを語られても、私は、避けることができないではないか。
逆説的に真理だから。
真理とされるものを、舞台裏から覗けるよう、構造を知れ、ということか。
権力は、外部から抑圧されて、訪れるものではない。
人々が、他人との関係性のなかから、己の欲望を追求するなかで、発生する場のようなもの。
権力が上から、外部にあるのではなく、私たちがいる限り、場として生まれるなら、反権力は、愚かしいことなのか。
福祉社会は美しいが、福祉の名の下に、国家が国民を管理している社会保障を理由に、国民情報を、よりいっそう収集しているのではないか。
また、システムに属さないことを望んだものには、福祉が与えられないのだろうか。
「福祉国家の歴史社会学 19世紀ドイツにおける社会・連帯・補完性」坂井晃介(著)

「福祉国家の基礎理論 グローバル化時代の国家のゆくえ」田中拓道(著)

また、国家は、従順な体をつくる。
福祉国家における疾病、出生率、死亡率の管理は、一見、穏やかな権力に写るが、これは、経済コストの為労働力を効率的に確保する、国家の利益を守る権力である。
社会福祉に携わる人間が、声高に社会保障の冷徹さを叫び、ヒューマニズムを説いても、全くの平行線なわけである。
国家は、私たちから湧き上がった権力でしかないなら、支払うコストに効果が見合うものでなければ、システムとして不完全でしかないのだ。(「国家理性」国家は国家の力の維持そのものを自己目的としている。)
思想は、生活していく上で、役立つツールでなければならない。
とフーコーは、述べている。
上に上げたのは、私が、特に、気になったキーワードである。
私が、実際に、フーコーの思想概念群を理解したとは考えられない。
[ コメント ]
本書のヴォリュームでは、仕方ないのかもしれない。
本書、最後に、フーコーは、様々な支配を受けてういるわたしたちが、今の真理を暴露し、別の真理を、みいだしよい関係ができる可能性を探れれば、となんとも消極的に記されている。
私がツールとして得たのは、マスメディアから発信される違和感を感じた言葉が
「国家理性」
や権力としての人格で述べられてる事に気づかされたということだ。
私をはじめ、多くの個々人が、ミニマムに考えていれば、分からないはずである。
だが、国家はあるのだし、解体されることもないだろう。
支配を、善悪ではなく、あるものとして捉えれば、分からなかった関係から、他者として認められることまでは、出来そうだ。
生活していくのに役立つまではいかないが、括り付けられている見えない糸が、目に映るようになった程度か。
あらぬ方向へ、引っ張られるのに、もう、驚きはしない。
■主体の系譜学
「ミシェル・フーコー 主体の系譜学」(講談社現代新書)内田隆三(著)

[ 内容 ]
言葉を、狂気を、監獄を語る遠見の思想家フーコーの視線はどこに向けられたのか?
資料集成の奥、思考不能の空間へ。
多様な言説の分析を通し、遠望される非在の場。
主体のない饒舌と沈黙が交差する深部をフォーカシングして見せる「陽気なポジティヴィズム」に迫る。
[ 目次 ]
序章 知識人の肖像
第1章 フーコーの望遠鏡
第2章 変貌するエピステーメー(16世紀、ルネサンス;侍女たちのいる空間;「人間」の登場へ)
第3章 外の思考(私は構造主義者ではない;外の思考;これはパイプではない)
第4章 権力と主体の問題(言説の分析;主体化の装置;主体の問題)
[ 発見(気づき) ]
今も、フーコーの考えたことの1%も理解できているとは思わないが、定期的に、読みたくなる。
この本は、異能の哲学者ミシェル・フーコーの解説書。
原典や位置づけを知っている読者向けに書かれた再入門書の趣き。
フーコーについて、興味のあるところを、中心に書いてみる。
エピステメを、どう訳すかは、人によって異なるが、個人的に、しっくりくるのが
「視座」
という訳。
もしくは、
「思考の台座」
か。
昔の
「中国の百科事典」
には、こんな動物の分類があったそうだ。
動物の分類:
a.皇帝に属するもの
b.芳香を放つもの
c.飼いならされたもの
d.乳呑み豚
e.人魚
f.お話に出てくるもの
g.放し飼いの犬
h.この分類自体に含まれるもの
...(以下略)
今の私たちからすると、これは、分類とは思えないが、当時の編集者や読者は、この分類で、世界を見ていた。
重複や矛盾などは、メタレベルの混乱さえ、含んでいる。
西欧においても、17世紀頃までの自然を対象とした記述は、物事の類似や、印象、神話や昔話と結び付けられて語られた。
観察、記録、寓話の混沌とした記述。
それが、自然を語るタブロー(表)だった。
[ 教訓 ]
1657年のヨンストンスの「四足獣の博物誌」
は、違うやり方をした。
足が4本あるとか、夜行性だとか、30センチくらいだとか、草食だとか、動物の世界固有の要素に着目して、分類を行った。
18世紀、リンネが
「記録すべきものは、数、形、比率、位置である」
とし、動物の器官を構造と捉えた。
眼に見えるものばかりだが、色彩、匂い、触覚などその他のものは、排除される。
伝説に、どのように扱われるかは、関係がない。
4つの要素だけで、世界を文節化する灰色の分類。
博物学の始まり。
そして、18世紀末になると、動物の諸器官の構造が織り成す機能、眼に見えない本質が記述の中心となる。
表(タブロー)は、系列(セリー)に置き換えられて、博物学が、生物学へ進化した。
フーコーの言うエピステメは、それぞれの時代に生きる人々が、思考の外(フーコーの言葉では<外>の思考)にあるものとの関係性で、人間の思考が、規定されているということだと思う。
私たちは、
「中国の百科事典」
の分類を笑うが、今の私たちの分類が、数百年後、笑われないとも限らない。
フーコーは、<外>の問題を、言語や狂気、政治権力、セックスといった、多面的な視点から分析して行く。
一見、無関係そうに見える周辺的な、それらのテーマから、人間主体の本質、大きな哲学問題へと深く深く、切り込んでいくスリリングな語り。
私が、フーコーが好きな理由である。
<外>は、人間にとって見えず、思考不能で、永遠に到達できないものであるが、<外>と<内>が相互に影響しあう歴史の中で、エピステメという思考の台座を作り出す。
この本では、その変化を、
「分解とずれの累積による一種のカタストロフィーを通して、トポロジカルな形態の変化、切断、異動」
と説明している。
[ 一言 ]
フーコーというと、私は、一番に連想するのがパノプティコンである。
18世紀のジェレミー・ベンサムによって考案された
「理想的な監獄建築」
である。
実際には、これそのものは、建設されていないと思う。
ドーナツ状の建物と、ドーナツの輪の中心に、塔を配置する。
ドーナツ状の建物は、独房が分割配置されていて外周、内周どちらにも窓がある。
塔にも、監獄を監視するための窓がある。
光が、この構造物の外側から入ると、逆光によって、独房内の囚人のシルエットを、中央塔の監視者は見ることができる。
しかし、囚人は、監視者を見ることができないようになっている。
囚人は、個別化され、互いに、連絡できない。
常に、監視者から見られているのではないかと意識する。
フーコーは、パノプティコンのモデルを使って、権力が、いかに効率よく影響力を発揮しているか、を語る。
囚人たちは、見られているかもしれないという意識から、自分の精神の内面へ逃げ込む。
権力との関係から、個人の内面=主体が発生する。
パノプティコンを、インターネット(コミュニティ)と見ることは簡単であるし、現代の思想家も、試している。
監視社会とはいっても
「ビッグブラザー」
のように、明示的に、本当に監視する権力、余さず記録するモニタリング機構は必要ない。
そんなコストは、必要ないのだ。
見られているかもしれないという意識、内面にある監視の眼による自己監視の作用だけで、権力は、フルに機能する。
この本の訳では、フーコーのいう
「機械仕掛け」
のポイントを、3点にまとめている。
1.権力の行使が非常に経済的であること
2.権力が没個人化されていること
3.権力が自動的に作用すること
国家に限らず、権力のネットワーク監視は、進んでいる。
インターネットは、自由の象徴という時代も終わりつつあると、最近のニュースを見て感じる。
むしろ、権力にとって、インターネットは、パノプティコンとして、機能するのではないかと思うくらいだ。
ただ、パノプティコンの考え方は、幾つかのアイデアを加えれば、ネットワーク上でのモラルを維持する仕組み、コミュニティの浄化機能として、活用することもできるのかもしれない。
そんなことを考えた。
この本は、入門書ではなく、再入門書として、要所がまとめられており、数時間くらいで、フーコー思想の俯瞰をするのに良い本だなあと感じた。
■参考図書(新書)
「哲学の問い」(ちくま新書)青山拓央(著)

「哲学するってどんなこと?」(ちくまプリマー新書)金杉武司(著)

「〈私〉を取り戻す哲学」(講談社現代新書)岩内章太郎(著)

「アウグスティヌス――「心」の哲学者」(岩波新書)出村和彦(著)

「はじめての哲学的思考」(ちくまプリマー新書)苫野一徳(著)

「自分で考える勇気 カント哲学入門」(岩波ジュニア新書)御子柴善之(著)

「哲学マップ」(ちくま新書)貫成人(著)
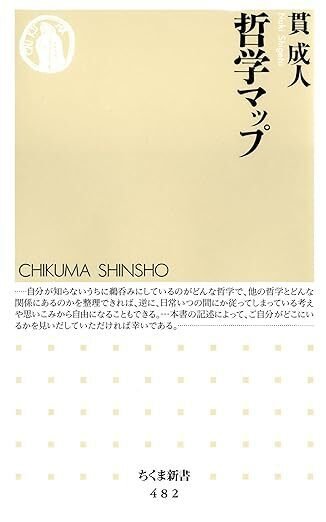
「言語哲学がはじまる」(岩波新書)野矢茂樹(著)

「西洋哲学史 古代から中世へ」(岩波新書)熊野純彦(著)

「世界哲学史1 ──古代I 知恵から愛知へ」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史2 ──古代II 世界哲学の成立と展開」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史3 ──中世I 超越と普遍に向けて」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史4 ──中世II 個人の覚醒」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史5 ──中世III バロックの哲学」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史6 ──近代I 啓蒙と人間感情論」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史7 ──近代II 自由と歴史的発展」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史8 ──現代 グローバル時代の知」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

「世界哲学史 別巻」(ちくま新書)伊藤邦武/山内志朗/中島隆博/納富信留(責任編集)

■参考図書(単行本)
「武器になる哲学 人生を生き抜くための哲学・思想のキーコンセプト50」(角川文庫)山口周(著)

「〈私〉の哲学を哲学する」永井均/入不二基義/上野修/青山拓央(著)

「「人間関係×哲学思考」頭のモヤモヤを、32人の哲学者が答えていく」ひぐち まり(著)

「存在と時間 哲学探究1」永井均(著)

「世界の独在論的存在構造 哲学探究2」永井均(著)

「独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか 哲学探究3」永井均(著)

