
【読書メモ(その2)】「人間は進歩してきたのか―現代文明論〈上〉「西欧近代」再考」佐伯啓思(著)(PHP新書)
【関連記事】
前の記事は↓を参照。
[ 発見(気づき) ]
私も自由や民主主義を考える際、文化や歴史、伝統を無視ないし軽視しがちな非文脈的アプローチには反対であり、著者のこの点に関する指摘には同感である。
それでは、どうすれば我々は、このニヒリズムの時代(ニヒリズムに囚われし心の解放等)から脱することができるのか。
この点に関して、オイディプス的な著者は、解決案を示してくれてはいない。
本書は、「あくまで、「現代文明」の本質を捉えるために、われわれは最低限どのような展望をもっておく必要があるか」(7頁)を論じることを意図しているに過ぎない。
ニヒリズムという本書が明らかにした問題に如何に対処するか。
これは、読者にも投げかけられた課題であるが、なかなか挑みがいのある問であり、且つ、世界史の勉強のし直しとしても、とても良い視点であると考える。
そこで、今、我々に必要な問いのひとつが「私たちはどこにいるのか?」ではないのかと感じた。
このニヒリズムを再考するのに、例えば、アガンベンは、「私たちはどこにいるのか?」と問い、自ら金銭教と呼ぶ今日の資本主義のもとにいる限り、私たちは、住んでいる場所を旅行者向けの遊園地へと変容させてしまい、住む能力を喪失したのではないかと指摘している。
私たちにとっての健康、法、デモクラシーとは何か?
そして、何よりも生きるとはいかなることか?
それらを根底から問い直すアガンベンの議論は、決して無視できないと思う。
過剰な消費社会とは対極的に、ニヒリズムを感じさせない、アガペン言うところの「いと高き貧しさ」等といった生の形式も考えられるのではないだろうか。
【参考図書】
「私たちはどこにいるのか?」ジョルジョ・アガンベン(著)高桑和巳(訳)

「いと高き貧しさ―修道院規則と生の形式」ジョルジョ・アガンベン(著)上村忠男/太田綾子(訳)
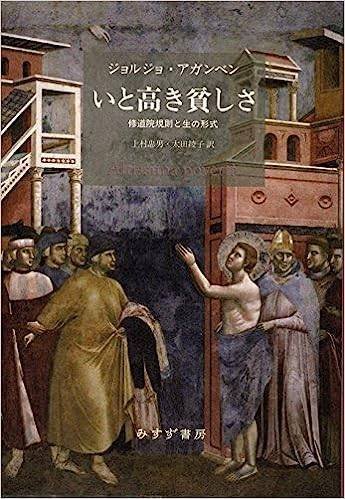
さて、中世から近代への移行には、ガリレオなどの科学革命、フランスなどの市民革命、イギリスなどの産業革命、そして、ヨーロッパを教皇の支配から解き放した宗教改革が要因と分かりやすい。
そして、宗教改革の中では、それまで権威的にラテン語かギリシャ語だった聖書を各国(地域)言語へ翻訳して、それが、グーテンベルクの活版印刷機で普及してベストセラーになった事が大きいと指摘している。
一つの機械だけでも科学技術は、世界史を変えているという実例だろう。
とすると、現代のネットの普及は、今後、100年にどのようなインパクトを与え、それを予見できる人たちが、また、支配層になってゆくのだろうか?
それはさておき、ハンチントンの「文明の衝突」とかフクヤマの「歴史の終わり」とか聞いた事のある現代思想家も引き合いに出して、イラク戦争や9.11の位置づけみたいなことも解説している。
西洋型近代国家が世界の枠組みの最終型でもないだろう事は想像できる。
これからは、イスラムや中国、インド、そしてロシア等の文化が西欧型文明と対立してゆく過程を経て、どこへ向かおうとしているのか、先が見えない状況下にある。
個人的には、石油ピークとか、地球温暖化とか、資源有限論などの科学的視点も話しに差し込んだら、もっと面白い世界史の解説書になる気もする。
高校の歴史の勉強は嫌いだったが、未来を想像するために過去を学ぶ(ホッブス、ロック、ルソーと続く系譜が登場する箇所など。)のは、やはり面白いと思う。
ホッブスは、自然状態で人間は、自分の生命・財産の安全を守るために闘争状態にあると。
それを回避するために、全員が主権者にある意味、権利を渡して、安全を担保してもらう。
この際、主権者が一人なら絶対君主になるだろうし、合議制ならある意味民主主義。
いずれにせよ、主権者は、傭兵でも雇って国民の安全を守り、私人は、その主従関係的な中に、個人的自由を得る。
したがって、個人は、国を守るとかの意識はほとんどない。
まさに、今の日本の状況と同じである様に感じる。
アメリカが主権者で従属した日本人を守り、日本人は私的自由と利益を謳歌する。
ルソーは、ホッブス流だと主権者と私人の対立が生じやすい。
自然状態から社会状態に移って安全は確保されたが、主従関係が新たに生じてしまった。
そこで、各人が契約により安全な社会状態をつくる。
一般意思を持った抽象的な主権者が出来る。
ここでは、古代共同体(ポリス)のように、各人が主権者的意識を持ち、共同体の安全を守る傾向が出てくる。
しかし、一般意思のような抽象的なものを介在させているので、それを持った主権者だと言う独裁者が現れたり、世論が一つの方向に向かうと、全体主義的傾向が必然的にでてくる。
[ 教訓 ]
本書は、政治学、経済学、社会学、心理学、哲学、あらゆる諸分野の知を統合して近代史を描き出す。
ここでは、西欧近代社会を導いたものとして、三つの革命(産業革命、市民革命、科学革命)よりも、宗教改革(宗教的世界から世俗的世界への転換)にスポットが当てられている。
西欧近代の標榜する自由、平等、進歩などの価値は、権威の解体へと向かう。
そのため、近代が進めば進むほど、歴史は切り捨てられ、生や世界観の確かさは失われ、個人の内面にあっても、超自我がうまく形成されなくなる。
これがニーチェの言うニヒリズムだ。
【参考記事】
哲学者ニーチェが「道徳を最も嫌った」論理的理由 自分自身を誠実に打ち出すことこそが望ましい
https://toyokeizai.net/articles/-/461925
データ的に見ても、英語人口、西欧での出生率の低下に対し、中国、インド、イスラム圏は躍進している。
西欧近代の普遍性に大きな懐疑がつきつけられる。
さて、このニヒリズムから生まれるものとして、冷笑主義(シニシズム)、快楽主義(ヘドニズム)、熱狂主義(ファナティシズム)、科学主義(サイエンティズム)の4つが挙げられる。
科学主義については、一見意外に思うが、論理実証主義による知識の断片化とその寄せ集め、そして価値判断の停止のことであり、そのため、世界観、人間観、歴史観は科学の場において居場所を失うとなると納得がいくだろう。
この4つ組は、面白いと思う。
血液型による性格判断よりも精度が高く応用が効きそうだ。
近年よく目にする瑣末な揚げ足取り、過剰なトンデモ叩きなどは、科学主義+冷笑主義だ。
今、われわれが抱えている問題、例えば、グローバル化した経済の中での生の不安、アメリカを中心とする世界の政治構造や新たな戦争など、これらは、突然、前触れもなく、突然に出てきたのではない。
これらの問題にはみな歴史的な背景があり、この部分を視野に入れた、視座から見なければ、この問題についての本質というものを捕まえることが出来ないと著者は言う。
これらの問題について、歴史的な展望を踏まえた視座を得るために、西洋における近代社会形成の歴史を振り返るということがこの本の目的である。
この本は、中世の宗教的世界から近代の世俗的社会にどう移行したのかを、宗教革命、デカルト、ホッブズ、ロック、ルソーの思想を解説しながら見ていき、さらにマックスウェーバーが言う、近代資本主義の精神は、プロテスタントの一派である、カルヴァン派から発生したと言うことについても言及する。
そして、近代資本主義の精神を生むもととなった、個人の心のうちにある、神の存在というものが見えなくなった現代において、ニヒリズムが蔓延し、混乱が起きている状況と言うのが、今現在であり、最初にあげた問題の根には、近代を生んだ精神の危機と、西洋民主主義の普遍化に抵抗する異文明(イスラム文明など)との文明の衝突の時代に入ったということがある、と結論して終わっている。
このように、要約してしまうと小難しいと思われるかもしれないが、本文は平明で、すごく分かりやすく、近代についての歴史が分かるようになっている。
この著者もまた、難しいことを誰にも分かるようにやさしく書くことができる人だ。
この本を、以前読んだ際に、初めて、近代民主主義の歴史が分かったような気がした。
公共哲学と、民主主義の違いが分からなかったが、民主主義の中で、ルソーが取り入れた、古代ギリシャに見られる、共同体を作ることで善をなしていくという考え方と、カルヴァン派の誠実、勤勉、社会奉仕を積極的に行うことで、死後の救済の確約を得ると言う二つの考え方が、公共哲学のルーツとなっていると言うことがわかった。
西洋民主主義の歴史や今、現代社会が新たに抱えている問題の根がどこから来ているのかがやさしくわかる本だと思う。
近代の入り口で大混乱に陥ったヨーロッパのなかで、その混乱をおさめるための理論装置を開発したのがホッブズだと著者は言っている。
善の実現をめざすために自らが積極的に政治の主人公になるギリシア・ローマの古典的市民像とは違って、ホッブズ的世界では、人々はひたすら自分たちの私的な利益を自由に追い求める。
武装も解除し、公のことには関心を寄せない。
全体の利益は、人々とは別の主権者が守ってくれるのである。
「古代の都市国家のように、何か共同体の「善」あるいは「善き生活」を実現するものが国家なのではなく、あくまで個人個人の生命や財産の安全を確保する公的権力機構が国家だということになります」(112頁)
「古典的世界では、政治を行うことは公共的なものにコミットするということでした。
防衛義務や政治参加は重要な公的活動です。
ところが、ホッブズの考える市民像はまったく違っていて公共的なことには関心をもたない。
彼の関心はもっぱら「私」の生命・財産、「私」の身のまわりの自由といったことになります。
そして、これこそが近代的市民とわれわれが考えるものなのです。
つまり、「公」よりも「私」を優先し、もっぱら「私」の利益を追及する者、それこそが近代的市民なのです」(113~114頁)
このホッブズを起点として、著書は、ロック、ルソーへと話をすすめ、アメリカ独立革命、フランス革命について論じている。
そしてウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で近代的な個人主義の誕生へと話を流し、核にあったキリスト教精神が失われたなかでは私的利益だけを追い求める個人の巣窟に社会がなってしまいかねないと批判している。
西欧においては、宗教改革により教会の権威が衰え、確かなものを再構築しなくてはならなくなった。
ホッブスは、人間一人一人が万人の万人に対する闘争という状態にあるのを回避するため、個々人は無制限の自由を放棄し、絶対的に確かなものとしての主権者と契約を結ぶことを考えたが、主権者と個人の間の関係が不明であり、個人は容易に主権者による強い抑圧の危険にさらされ、個人と主権者の統一は保証されなかった。
その問題を解決したのが、ルソーであり、個人は絶対的な主権者でもあることにより、個人と主権者の統一が図られた。
個人と絶対的な存在との同一視は、プロテスタントに見られる神の内在化と一致するが、宗教改革より時間が経つにつれ、その絶対的な存在は、虚無へと変化し、個人は再び確かなものを喪失しているというのが、現在の状況である。
著者は、この確かなものを喪失している状況が、西欧近代・現代文明の根本問題であると説くが、その虚無の存在自体をポジティブに取扱うことができないであろうか?
日本文化の普遍的意義を抽出する上でのかぎとなるのは、その点ではないだろうかと思う。
米国は、9.11同時多発テロを野蛮な原理主義による文明に対する攻撃と呼び、その後のイラク侵攻を、米国によるイラクを民主化し解放する戦いとして正当化した。
結局、米国が侵攻の論拠とした大量破壊兵器は存在しなかったし、テロの根絶という目的も果たせなかった。
正義と悪の戦いという米国が打ち出した構図の背景には、人間の求めるものはみな同じで、進歩は普遍であるとする西欧近代の進歩主義観がある。
【参考記事】
自分の「正義」を振りかざさないで
https://note.com/bax36410/n/n5a0beeda0488
【レポート】「正義」と「正しさ」
https://note.com/bax36410/n/n8074d724086f
この本は、その成立から現在に至るまでの歴史を丁寧に要約し、近代進歩主義とは、結局、世界普遍の価値ではなく、西欧という一地域で発生したローカルルールでしかないことを明らかにする。
ハンチントンは、西欧的価値の核心にあるものとして次の8つを指摘した。
1 古典古代の遺産
2 キリスト教
3 ヨーロッパ系の言語
4 聖俗の権威の分離(政教分離)
5 法の支配
6 社会の多元性
7 代議制度
8 個人主義
これらは本質的に西欧的なもので、近代化以前から西欧の価値であった。
よって西欧文明=近代文明とはいえない。
これらの西欧的な価値は、イスラムやインドや中国、ロシアなどが共有できるものではありえないとする立場になっている。
【関連記事】以下に↓つづく。【読書メモ(その3)】「人間は進歩してきたのか―現代文明論〈上〉「西欧近代」再考」佐伯啓思(著)(PHP新書)
