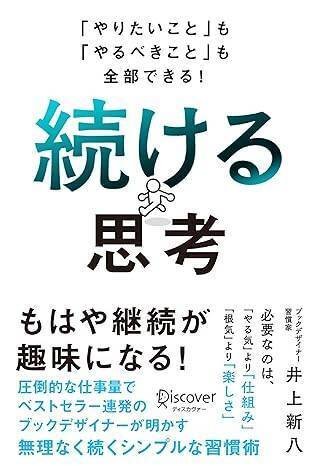【宿題帳(自習用)】「できる」までの道筋:改めて「知ってる」と「できる」は全くの別物だと思った

心折設計である以下の様な「死にゲー」(難しいけど面白いゲーム/リトライ必至の高難度ゲーム/高難易度ゲーム)達に学んだこと。
SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
Bloodborne
DARK SOULS III
Demon’s Souls
仁王
それは、こうして高難易度のゲームを繰り返しやっていると、改めて、
「知ってる」(単なる「知識」の状態)
と
「できる」(「スキルとして身についている」状態)
では、全く違うのだな、といまさらながら、痛感したことがありました(^^;
ゲーム以外もそうだけど、世の中には、やりかたを知っているのに、そのとおり実行できないことが、めちゃくちゃたくさんありますよね(^^;
例えば、ジョフ・コルヴァンのベストセラー本「究極の鍛錬」には、
「究極の鍛錬」ジョフ コルヴァン(著)米田隆(訳)
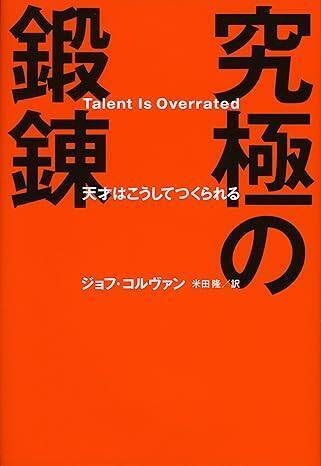
人がスキルを獲得するには段階がある事を記載しているのですが、最終段階は、以下の通り、知識を意識せずに使いこなせる自動化とあります(@@)
「たとえば自動車の運転など、何か新しいことができるようになるには、人間は三つの段階を経るものだ。
第一段階では、いろいろなことに注意を払うことが求められる。
車の制御方法、交通規制などいろいろなことを学ばなければならない。
第二段階になると、知識を連携するようになる。
車、状況、交通規制の知識といろいろな自分の体の動きを関連づけ、スムーズに組み合わせることができるようになる。
第三段階になると、考えることなくひとりでに車を運転するようになる。
これを自動化(automatic)という。」
つまり、対象のやり方を知っても、高スキルの保持者になるには、この自動化への遠い道程が待っており、飽くなき探求を経て、クリアする必要があります。
また、米国の心理学者であるアンジェラ・ダックワースは、著書「やり抜く力 GRIT(グリット)」で、
「やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける」アンジェラ・ダックワース(著)神崎朗子(訳)
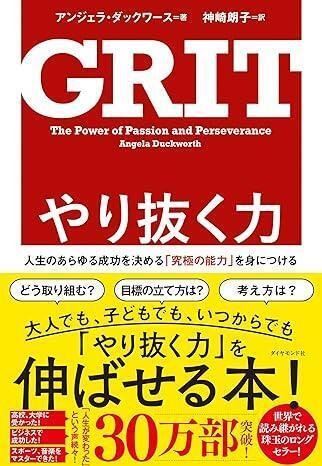
もっと具体的な試行錯誤の方法について述べており、それは、意図的な練習と呼ばれています。
それによると、エキスパートたちは、普通の人々と違い、ただ練習しているわけではなくて、彼らの練習は、次のような特徴があるそうです。
①具体的な弱点を抽出し、それを集中的に練習する。
②「うまくできなかった点」について、徹底的にフィードバックをもらう。
③できるまで、それに特化して反復練習する。
つまり、理想と現状の差分を、常に明らかにして、その差分を、練習によって、少しずつ埋めていく地味な作業を行っている事実が、そこに記されています。
これが試行錯誤の本質であり、スキル獲得に不可欠な活動となります。
しかし、
「あたりまえで、簡単に実行できる」
ことと、
「誰もがあたりまえに実行している」
ことは、イコールではありません。
目標を立てた直後は、やる気に満ち溢れているけど、気がついたら挫折してしまうというパターンは、よく経験しているところではないでしょうか^^;
そこで、本書では、
「やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学」(コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)ハイディ・グラント・ハルバーソン(著)林田レジリ浩文(訳)
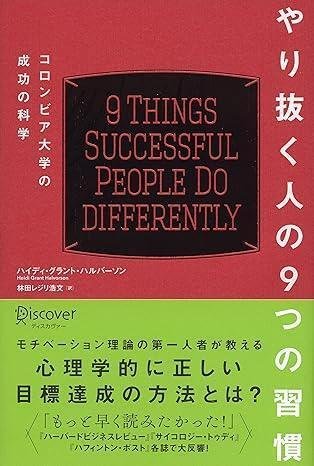
挫折しないための方法、つまり、やり抜くために行うべき習慣が、以下の通り、9つピックアップされていますので参考にしてみて下さい。
①目標に具体性を与える
②目標達成への行動計画を作る
③目標までの距離を意識する
④現実的楽観主義者になる
⑤「成長すること」に集中する
⑥「やり抜く力」を持つ
⑦筋肉を鍛えるように意志力を鍛える
⑧自分を追い込まない
⑨「やめるべきこと」より「やるべきこと」に集中する
「9つの習慣」のひとつひとつは、驚くほど、当たり前のことに感じられるかもしれません。
それに、それぞれを実行に移すことも、それほど難しくはありません。
どれも使い古されたようなシンプルなものですが、シンプル故に、重要な習慣であるとも言えます。
なので、もし、あなたが、目標の達成率を上げたいと願うなら、本書は、非常にオススメです(^^)
最近では、知識労働が増加し、特に、テクノロジーの分野において、気を配って作られたわけではない文献や資料、また、専門書や学際的な書籍を読めないことが、仕事において、しばしば、致命的な要因になってしまう時代であると推測されます。
そのため、前述の「9つの習慣」を手本にして、この点を克服するための必要なスキルを獲得するために、自身の能力を開発するステップである「知る」⇒「わかる」⇒「できる」の観点から、
どの様な学びが必要となるのか?、そのために、どの様な書籍を参考にすれば良いのか?、えいやっと選書してみました。
この習慣の場合であれば、こんな図書が、もっと適切ではないか等ありましたら、コメント頂けると嬉しいです(^^)
問い:「読んだらわかるは特殊な才能」
<参考図書>
「問いの立て方」(ちくま新書)宮野公樹(著)
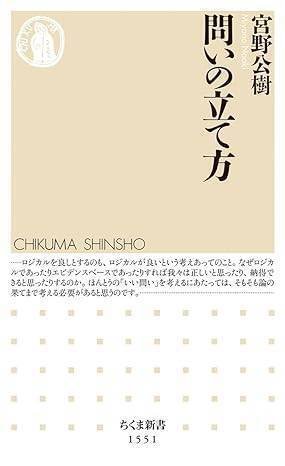
「問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション」安斎勇樹/塩瀬隆之(著)

「問いこそが答えだ! 正しく問う力が仕事と人生の視界を開く」ハル・グレガーセン(著)黒輪篤嗣(訳)
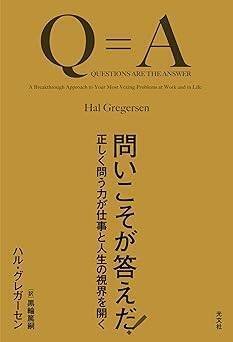
↓
①目標に具体性を与える:目標と現在の自分の差を明確にイメージする
<参考図書>
「知るということ 認識学序説」(ちくま学芸文庫)渡辺慧(著)
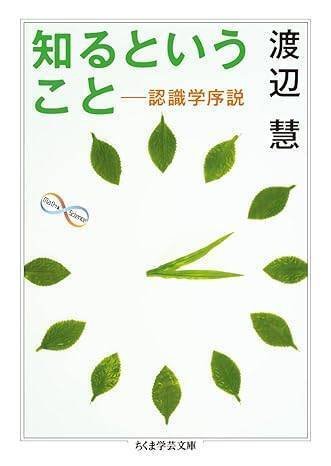
「知識とは何だろうか 認識論入門」ダンカン・プリチャード(著)笠木雅史(訳)
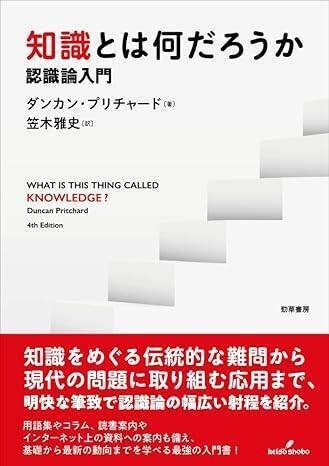
「知識の哲学」(哲学教科書シリーズ)戸田山和久(著)

↓
②目標達成への行動計画を作る:目標への行動はif-thenプランニングで
<参考図書>
「ネガティヴ・ケイパビリティで生きる ―答えを急がず立ち止まる力」谷川嘉浩/朱喜哲/杉谷和哉(著)
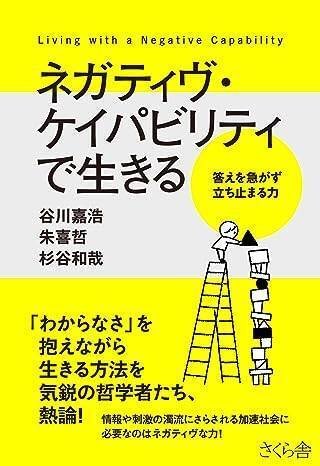
「ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力」(朝日選書)帚木蓬生(著)
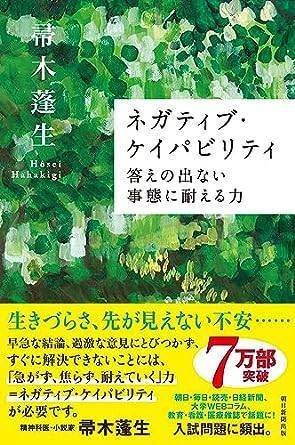
「答えを急がない勇気 ネガティブ・ケイパビリティのススメ」枝廣淳子(著)
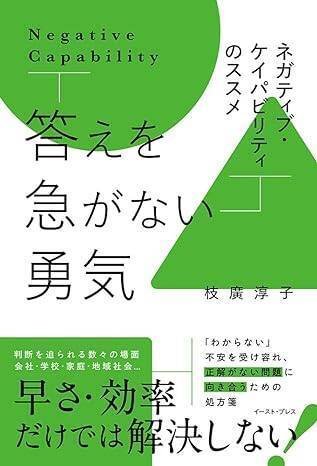
↓
③目標までの距離を意識する:to-date thinkingからto-go thinkingへ
<参考図書>
「論証の教室〔入門編〕ーインフォーマル・ロジックへの誘い」倉田剛(著)

「現代認識論入門 ゲティア問題から徳認識論まで」上枝美典(著)
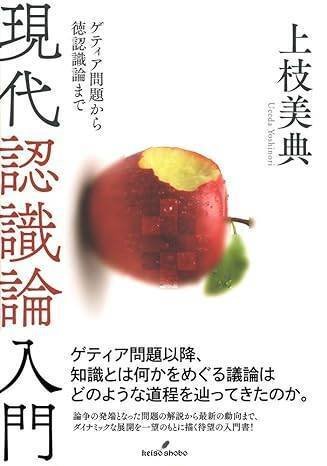
「誤謬論入門 優れた議論の実践ガイド 」T・エドワード・デイマー(著)小西卓三(監修)今村真由子(訳)
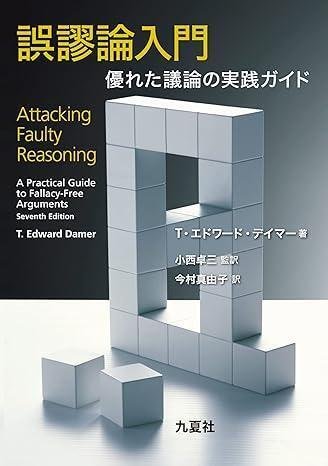
↓
④現実的楽観主義者になる:「やればできる」と「やれば簡単にできる」は違う
<参考図書>
「訂正可能性の哲学」(ゲンロン叢書)東浩紀(著)
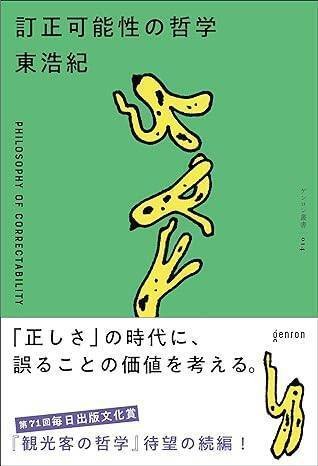
「訂正する力」(朝日新書)東浩紀(著)
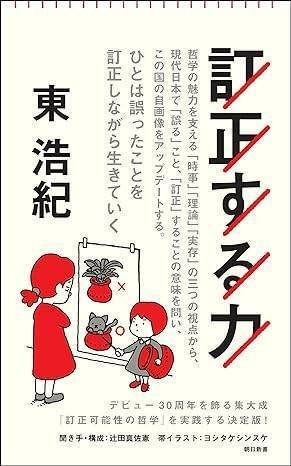
「謝罪論 謝るとは何をすることなのか」古田徹也(著)
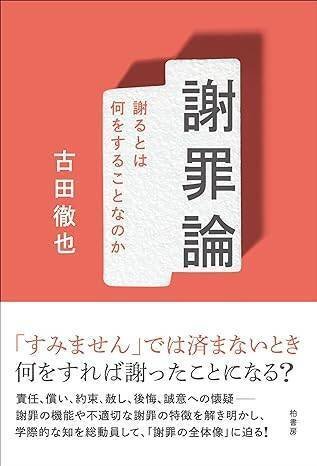
↓
⑤「成長すること」に集中する:能力は「グリッド」があれば伸ばせる(前著参照)
<参考図書>
「やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける」アンジェラ・ダックワース(著)神崎朗子(訳)
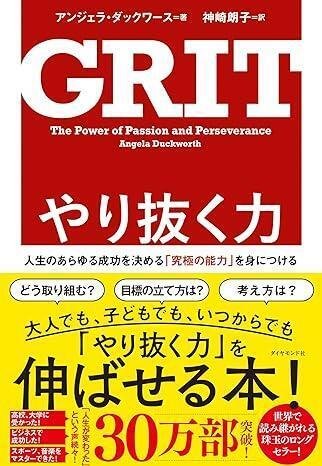
「習得への情熱―チェスから武術へ― 上達するための、僕の意識的学習法」ジョッシュ・ウェイツキン(著)吉田俊太郎(訳)
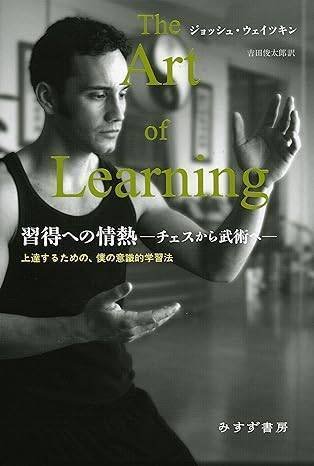
「SKILL 一流の外科医が実践する修練の法則」クリストファー・S・アーマッド(著)宮田真(訳)
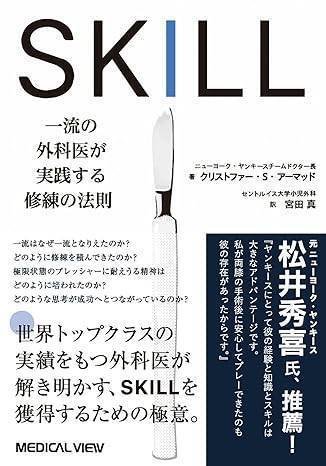
↓
⑥「やり抜く力」を持つ:「楽しむこと」より「興味を持つこと」の方が大事
<参考図書>
「SWITCHCRAFT(スイッチクラフト) 切り替える力 すばやく変化に気づき、最適に対応するための人生戦略」エレーヌ・フォックス(著)栗木さつき(訳)
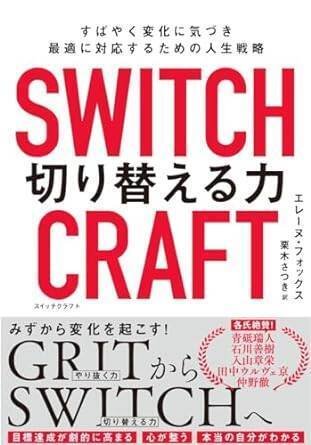
「言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか」(中公新書)今井むつみ/秋田喜美(著)
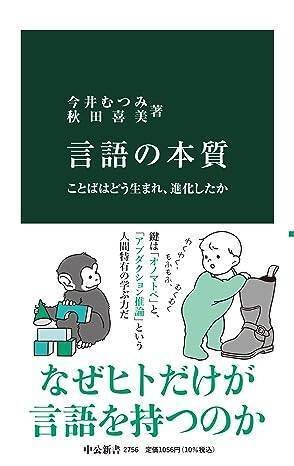
「熟達論 人はいつまでも学び、成長できる」為末大(著)
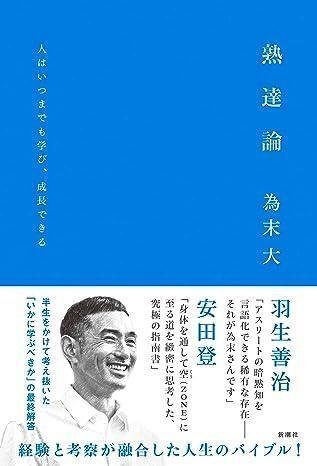
「ことば、身体、学び 「できるようになる」とはどういうことか」(扶桑社新書)為末大/今井むつみ(著)

↓
⑦筋肉を鍛えるように意志力を鍛える:意志力を鍛える
<参考図書>
「〈公正(フェアネス)〉を乗りこなす 正義の反対は別の正義か」朱喜哲(著)
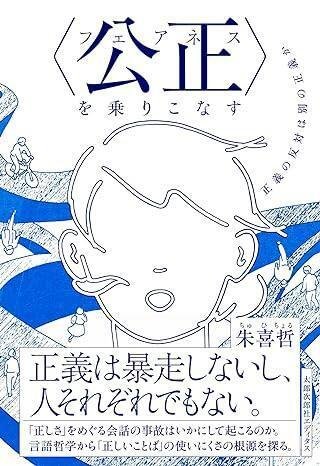
「不正義とは何か」ジュディス・シュクラー(著)川上洋平/沼尾恵/松元雅和(訳)
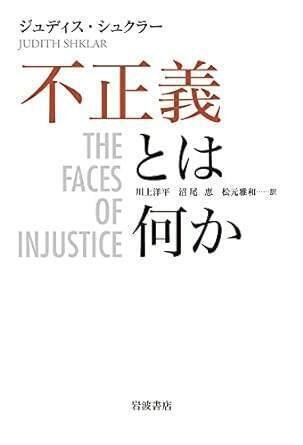
「認識的不正義 権力は知ることの倫理にどのようにかかわるのか」ミランダ・フリッカー(著)佐藤邦政(監修)飯塚理恵(訳)
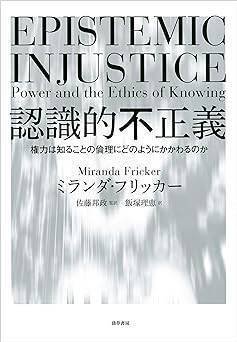
↓
⑧自分を追い込まない:否定的な表現をしない
<参考図書>
「哲学がわかる シティズンシップ──民主主義をいかに活用すべきか」リチャード・ベラミー(著)千野貴裕/大庭大(訳)
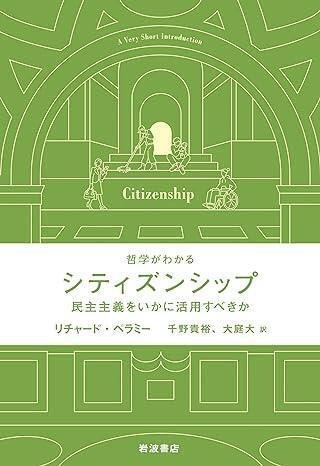
「言語哲学がはじまる」(岩波新書)野矢茂樹(著)
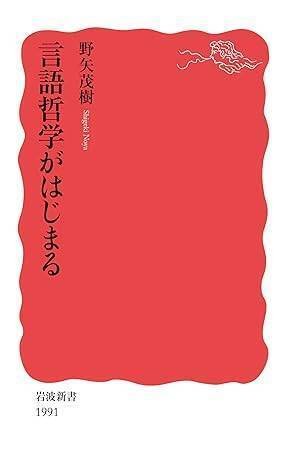
「ヒトの言葉 機械の言葉 「人工知能と話す」以前の言語学」(角川新書)川添愛(著)
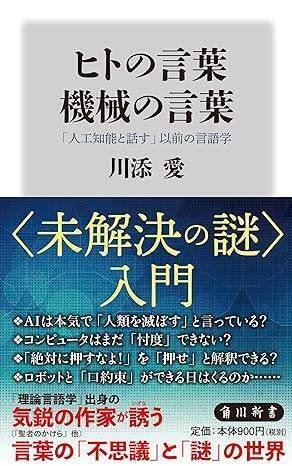
↓
⑨「やめるべきこと」より「やるべきこと」に集中する
<参考図書>
「やる気が上がる8つのスイッチ コロンビア大学のモチベーションの科学」(コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)ハイディ・グラント・ハルバーソン(著)林田レジリ浩文(訳)
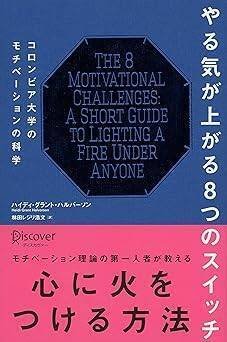
「人生・キャリアのモヤモヤから自由になれる 大人の「非認知能力」を鍛える25の質問」ボーク重子(著)
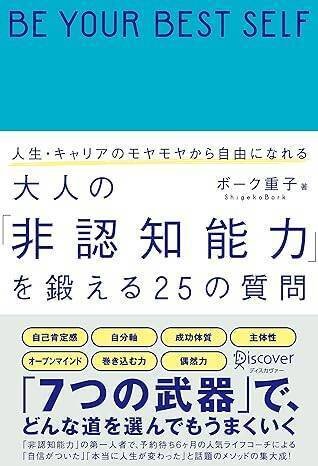
「「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる! 続ける思考」井上新八(著)