
整形外科PTの血管知識応用〜自律神経を中心に〜
どうも、
勝手に2021年のサマーコレクションを
つくりました やまね です。

"理学療法士としての自分"
"1人の人間としての自分"
どっちも大切にしたいですね😊
さて、
今日は血管についてお話をします!
筋肉はよく勉強するのに
血管や神経については勉強避けがち…
そんなことを感じた時に
血管について再考してみました。
今日の記事は
目の前の硬い筋肉やむくみ、スパズムに
対してアプローチしても改善しない時に
役立ててもらえるかもしれない記事です。
それではいきましょう!
なぜ血管を知らなきゃいけないの?
血管の事を考えられていると
アプローチしたい組織に
熱、栄養、ホルモンを与えることに
繋がると考えます。
そしてこれは、
組織の柔軟性の維持、疼痛の改善に
繋がるとも考えています。
学生の頃は血管について
知って何になるんだと思っていました。
今となればその重要性に頭を抱えさせられます。
いざ、臨床にでると
◎スパズムがある
◎筋肉が硬い
◎浮腫や腫脹などの腫れ、むくみがある
◎整形外科テストで絞扼がある
などの現象に日々遭遇します。
僕たちはこれらに対し
スパズム →圧痛なくなってほしい
筋肉 →柔軟性あがってほしい
浮腫、腫脹 →循環よくなってほしい
絞扼 →柔軟性あがってほしい
などを思い様々な介入を行います。
これらの状態には血管の変化も起こっています。
スパズム→血管の攣縮
筋の硬さや絞扼→血管圧迫により虚血
浮腫、腫脹→血管拡張
当たり前のことといえば当たり前のことですね。
ではそもそも血管や血液はどのような
役割だったか思い出してみましょう!
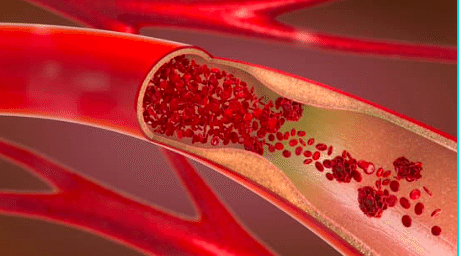
血管、血液のそもそもの機能を思い返すと、
以下のような感じです。
①酸素や二酸化炭素、栄養、代謝産物、
ホルモンなどを運搬する。
②ホメオスタシス維持のために
各々の器官が血液の状態をモニターする。
③血液凝固して止血する。
④血液成分により免疫を機能する。
つまりは、
血管が絞扼されず柔軟であることで
細胞、筋肉、各々の器官は
栄養やホルモンを受け取り
いらないものは送り出すわけです。
このような知識を活かして
整形外科クリニックに勤めている僕は、
主に症状のある部位の循環を促し
血流を改善することで
局所的な栄養不足、疼痛物質の停滞を
改善させる
ように考えています。
こんなこと聞いてると、
なんか血管、血液の知識もってると
少し臨床の見方が
変わりそうな気がしませんか!?
循環系の調節
各臓器に必要な血液は
循環系によって過不足なく供給されています!
<循環系の調節>
①自律神経による神経性調節
②ホルモンなどによる体液性調節
③腎臓による体液量と浸透圧調節
これらを知ってクリニックの臨床応用する
ためにたどりついたことは
◎副交感神経活動を意識する
◎呼吸エクササイズはよい
◎ピラティスはよい
このようなものでした!
なぜそのようにたどり着いたのかは
循環系の調節メカニズムにあります。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

