
移行期の静寂 -谷崎潤一郎『蓼食う虫』の魅力
【水曜日は文学の日】
人が何かを完成させる前、様々な試行錯誤があった時の途中で出来た実験的な作品が、他にはない非常に「味」のある作品になったりします。
谷崎潤一郎が1929年に書いた小説『蓼食う虫』は、そんな移行期の作品であり、初期の『痴人の愛』や『刺青』と言った鮮烈な作品や後期の『春琴抄』や『細雪』といった円熟味のある作品とも違う、独特の緊張感に包まれた名作です。

美佐子は今朝からときどき夫に「どうなさる? やっぱりいらっしゃる?」ときいてみるのだが、夫は例のどっちつかずなあいまいな返辞をするばかりだし、彼女自身もそれならどうと云う心持もきまらないので、ついぐずぐずと昼過ぎになってしまった。
美佐子と要の夫婦は、性的な不一致から、お互いに別れることを決心しています。美佐子は公然と愛人に会いに行き、要の方も離婚しようと色々と友人に相談してみるものの、いざとなると微妙に決心がつかずに先延ばしにしています。
要は義父に誘われて人形浄瑠璃を観に行き、彼の愛人お久に会ったり、馴染みの娼婦ルイズに会ったりしつつ、表面上は美佐子と普通の夫婦を演じて、時は静かに過ぎていきます。。。
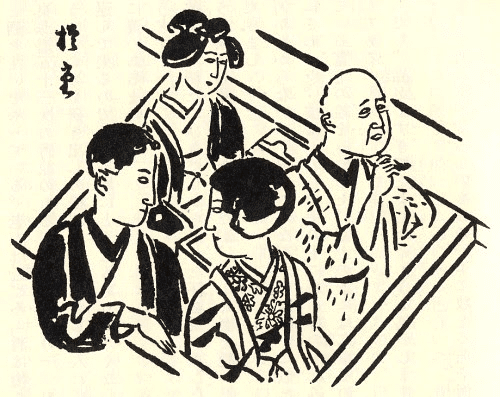
小出楢重画
この作品は、谷崎自身の身に起こった「離婚」騒動がモチーフになっています。
妻の千代との不仲を機に、友人に千代を譲る(!)という話が出て、作家の佐藤春夫が反対。最終的に谷崎夫婦は離婚し、千代は佐藤と即再婚。新聞に三人連名で、この再婚は全員合意ものである、という声明文を出すという、いわゆる「細君譲渡事件」を、『蓼食う虫』の翌年の1930年に起こしています。
今考えても、何をやっているんだ?と思う事件ではありますが、『蓼食う虫』が、割合谷崎の身の回りに基づいて書いているというのは良く言われる話で、その現実がもたらす緊張感が作品を引き締めています。
美佐子と要は別れることはもう決心していても、お互いに悪感情は持っておらず、憎み合ったり激昂したりすることもない。
勿論子供のことを考えつつ、色々と別れるとなれば周囲に波紋が広がるのも分かりつつ、文面だけでは穏やかな会話には、今の状態がどちらに転ぶか分からない、生々しさと張りつめたテンションがあります。
突然何か変な事件があって、二人が愛し合っていた過去を思い出して、よりを戻し。。。なんていうメロドラマ的な展開はなく、それはつまり、本物の人生のように、ある種平坦な作品でもある。それでいて、読んでいて面白いのは、表面的な展開の下の緊張感が持続しているからでしょう。

最初の妻、千代
谷崎は、芥川龍之介と小説観がかなり違い、雑誌上で論争をしたりしています。そうした中で、芥川は自分は作品の最後まで決めてから書く、と言い、谷崎はどう終わるかは分からないまま、とりあえず書いてみる、といったことを述べています。
これは勿論、どちらがいいというわけではなく、方法論の違いであり、実際谷崎は未完の作品も結構あり、書きながら膨らませていったんだろうな、みたいに感じられる作品もあります。
『蓼食う虫』でも、人形浄瑠璃(文楽)の鑑賞場面や文楽論からは、谷崎の「日本回帰」のように言われ、それは間違っていないのですが、単に当時興味があったことを書いただけのような気がします。
しかし、寧ろ興味深いのは、そんな谷崎の作品のクライマックスは、大変劇的にできているということです。
『痴人の愛』の「馬乗り」、『細雪』の暗い一夜、『鍵』や『瘋癲老人日記』のあの痴態、『春琴抄』のあのひと突き等。
それは、何も考えず筆が動くままに書き続けていた物語が高まりを見せ、突如物凄いエネルギーが噴出してしまったような、異様な瞬間でもあります。
しかし、『蓼食う虫』は、とうとうそんな瞬間が訪れずに、張りつめた空気のまま終わります。
ラストの一夜の、殆ど神秘の顕現のような、それでいて妙に静かな感覚は、忘れ難いものです。
それは人形浄瑠璃の中の、表面的な「日本的なもの」だけではない、その奥にあるどこかのっぺりとした薄気味の悪いものが、この夫婦の間にも横たわって、それがじわじわと漏れ出していくような感触です。
風船が膨らんでやがてパンと破裂するのではなく、ゆっくり空気を入れても、どこかに穴が開いていて、しゅうしゅうと空気が漏れて風船が段々と縮んでいくのを眺めている感覚というか。
谷崎作品でそんな感覚が味わえるのは、少なくとも完結した長編では、この『蓼食う虫』以外になかなかないと思います。現在進行形の「どう決着がつくか分からない」作者自身の現実が、とうとう最後までその文章にべっとりと張り付いて、このような構成を導き出したと言えるのかもしれません。
文芸評論家・作家の吉田健一は、新潮文庫版の解説の中でこう述べています。
この作品が発表された当時に、海草が妖しく交錯する海底の世界を覗く思いと評されているのを読んだことがあるが、この表現は今日でもこの作品の特質を正確に言い当てたものであることが感じられるのである。
まさに至言であり、そういう意味でも、かなり貴重な作品のように思えるのです。
芸術において作風の移行期とは、何かの完成が壊れ、次の完成へと向かう時期でもあります。そこで、その人の中にある多様な面が露呈することになる。
実生活でも作風でも移行する時期にあり、いつものふくよかな文体と、泥臭くも華麗な筋の運びとは少し違う、削ぎ落された鋭利さと静謐さに満ちた『蓼食う虫』は、谷崎の中のそんな意外な一面を味わえる作品です。是非体験いただければと思います。
今回はここまで。
お読みいただきありがとうございます。
今日も明日も
読んでくださった皆さんにとって
善い一日でありますように。
次回のエッセイや作品で
またお会いしましょう。
こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。
楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。
