
霧の中で過去をつかむ -須賀敦子のエッセイについて
【水曜日は文学の日】
私がエッセイを書いていて、誰の文体や作品が理想かと言うと、須賀敦子だという気がします。
彼女のような題材は持っていないし、書き方が違うのは自分で分かっている。でも、真似は出来ない理想としての規範みたいなものがあって、私にとって、ことエッセイに関しては、須賀敦子の一連のイタリアでの回想を書いた作品が、それにあたります。
須賀敦子は1929年生まれ。イタリアに渡り、イタリア人と結婚して、翻訳者として活動します。夫と死別し、1971年に帰国すると、教師、翻訳者だけでなく、エッセイも含めた文学者として活躍をしました。

私が一番好きなのは、そんな彼女の1991年の初めてのエッセイ集『ミラノ、霧の風景』です。
冒頭の、『遠い霧の匂い』は、ミラノの濃く、重い霧の話から始まります。そして、霧を愛したミラノ生まれの夫の話、霧の中を友人と遠出した話、そして、友人のローザとその弟デミの、霧に関する思い出、とシームレスに話が進んでいく。そんな、ごく短いエッセイです。
挿話の繋がりが自然で、描写は簡潔にして要を掴んでいます。そのため、本当に短い話なのに、ミラノに住む人々の息遣いが伝わるかのような、何か大きなものを感じたような気持ちになります。

そして語り口は落ち着いていて、気取りや冷淡さ、辛辣さといったものはありません。自分が一緒に過ごした愛情が仄かに滲み出てくるようで、まるで、爽やかで柔らかい風味のミネラルウォーターのように、何度も味わいたくなるのです。
その後も、ミラノの貴族社会のゴシップ本を書く女性の話、ナポリについての父親との会話の思い出、堅物の書店の友人の話等、全ての話が面白く、しかも、豊かで色づいています。
彼女が元々文学者で、仲間たちと出版社というか、書店を経営していたこともあり、本の話が沢山出てくるのも嬉しいことです。
『きらめく海のトリエステ』では、トリエステ生まれの詩人、ウンベルト・サバの詩と、その生涯を短く分かりやすく紹介し、実際に夫の死後に著者がトリエステを訪れた時のまさにきらめくような思い出が語られます。
解説と自分の回想のパートが分離していないのは、熟達の技でしょう。彼女自身が訳して挿入されるサバの詩も美しい。
若いころ、わたしはダルマツィアの
岸辺をわたりあるいた。
餌をねらう鳥が
たまさか止まるだけの岩礁は、ぬめる
海藻におおわれ、波間に見えかくれ、
太陽にかがやいた。
エメラルドのように
うつくしく。
潮が満ち、夜が岩を隠すと
風下の帆船たちは、沖合いにでた。
夜の
仕掛けた罠にかからぬように。
今日、
わたしの王国はノー・マンズ・ランド。
港はだれか他人のために灯りをともし、
わたしはひとり沖に出る。
まだ逸る精神と、
人生への痛ましい愛に、流され。
その他にも、マンゾーニの『いいなずけ』や、トーマス・マンの『ヴェニスに死す』も出てきます。文学の豊かな美しさが、彼女の文の中で、人生の糧として息づいているのです。
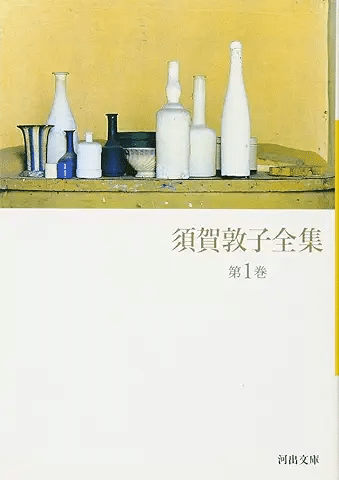
『ミラノ 霧の風景』他代表的なエッセイを収録
私が一番好きなのは、『鉄道員の家』というエッセイです。
夫の父親が鉄道員であったことから実家の鉄道官舎で暮らしていたことから始まり、ヴィットリーニという現代イタリアを代表する小説家と鉄道との関わり、ピエトロ・ジェルミが監督した『鉄道員』という映画の話に続きます。
夫とはその映画の話題を全くしなかったのですが、夫の死後、初めて映画を観る機会が訪れます。
映画を見て、私は夫が死んで二十年以上ものあいだ、これを見ていなかったことの不思議さに打たれた。映画をかたちづくっている言葉はすべて、あの鉄道線路の横で覚え、聞いた、私のイタリア語の原点に立つものばかりだった。
(中略)
ごくはじめのところで、主人公が夜中によっぱらって家に戻ってくる場面がある。ドアに鍵をさしこんで家に入っていくと、家族はみんな出かけていて、あたりは真っ暗だ。
その瞬間、あ、スイッチは左側にある、と私のなかの誰かが言って、私を完全に打ちのめした。どの鉄道官舎も間取りが似ていて、映画に出てくるアパートメントは、それほど、あのミラノ・ローマ本線の線路沿いの夫の実家そっくりだったのである。
ここには、プルーストにおける『失われた時を求めて』のマドレーヌのような、一つの想起が鮮やかに刻印されています。
映画の中にでてきた人物の身振りによって、不意に自分の中に、それと同じものがあることを知る。こうした瞬間や気づきを得ることが、芸術やエンターテイメントを味わう醍醐味といって良いでしょう。
それは、須賀敦子のエッセイを読む時の私たちも同じです。
ミラノやヴェネツィアといった美しい都市に行ったことのある人は限られます。そこで長い間暮らす人となれば、もっと限られてくるでしょう。
しかし、どんな場所にも、人々の生活があって、人類の共通の楽しみとしての本があって、大切な人の喪失や、歴史の厚みを体感する。そうして体験した過去を、忘却から救い出す手段として、私たちの言葉がある。
須賀敦子のエッセイには、鉄道員の家を思い出すように、霧の彼方にあった自分の過ごした人生を、つかみ取るような瞬間があります。
彼女の文章は、文学にあるそのような力を思い出させてくれる、最も美しい散文の一つであり、それゆえに私が愛する作品なのです。
今回はここまで。
お読みいただきありがとうございます。
今日も明日も
読んでくださった皆さんにとって
善い一日でありますように。
次回のエッセイでまたお会いしましょう。
こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。
楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。
