
- 運営しているクリエイター
2020年3月の記事一覧
法隆寺お会式 (3月22日〜24日)
法隆寺お会式 (3月22日〜24日) 法隆寺聖霊院
🔍 法隆寺公式ページ 「お会式ご参拝の皆様へ」「年間行事」「聖霊院」
🔸
(参考)
📷 法隆寺聖霊院 (国宝)
📷 法隆寺東院 (夢殿 国宝)
📷 法隆寺東院鐘楼 (国宝)
📷 法隆寺東大門 (国宝)
📔 ブログ内関連記事 (東大門)
天武天皇が律令制定を命ずる (681年 3月19日 [天武10年2月25日])
天武天皇 (生年不詳-686年) が皇子・諸臣に飛鳥浄御原令制定を命ずる詔を発令 (681年3月19日 [天武天皇10年2月25日])。
高松塚古墳で彩色壁画発見 (1972年3月21日)
高松塚古墳で彩色壁画が発見 (1972年3月21日)。
この古墳にまで「祟りの噂」が有るとは…
棺の遺体に頭部が無いことは、
「盗掘口」を開けた者が冠でもかぶってると考えて持って行ったのでは?
そんな風に言ってしまうと「古代史本の題材」と成らないんでしょうが。
🔍 国営飛鳥歴史公園公式ページ
https://www.asuka-park.go.jp/area/takamatsuzuk
古事記が完成 712年3月9日 (和銅5年1月28日)
古事記が完成 712年3月9日 (和銅5年1月28日)
⚪️ 「古事記」 のリンク 🔍 青空文庫 「古事記」現代語訳 武田祐吉訳
🔍 上同 読み下し 武田祐吉註釈校訂
🔍 国立国会図書館デジタルコレクション 「古事記」 原文 [漢文] (柏悦堂 明治3年出版)
奈良関連読書記録 Reading History
📝 奈良がテーマとなる資料は「古事記」「日本書
薬師寺の金銅仏に感じる若干の不思議
「長屋王の変」に関する同日の記事
から関連したかたちで書いています。
🔸 以前から不思議に感じること
この薬師寺東院堂の「聖観音」 (銅造。国宝) と様式的・技法的に類似しているとされる
同じ薬師寺の金堂の本尊 (つまり薬師寺全体の本尊)「薬師三尊像」 (銅造。国宝) は、
「聖観音像」の鋳造技術や表現技法の更なる発展形、
「天平前期」(奈良時代前期) のモニュメントと見られることが一般
長屋王の変(729年3月14日-3月16日 [神亀6年2月10日-2月12日]) と 「天平」
長屋王の変(729年3月14日-3月16日 [神亀6年2月10日-2月12日])
「続日本紀」『天平元年 (七二九) 二月辛未』の項にある、
長屋王・吉備皇女 (吉備内親王) 一族の邸宅が兵に囲まれた2月10日が、
いまの新暦にすると3月14日 (729年 [神亀6年] ) であり、
長屋王が自害を命じられ
(「続日本紀」原文 [《天平元年(七二九)二月癸酉【十二】》の項 ] では
「令王
国分寺・国分尼寺建立の詔を聖武天皇が出す (741年3月5日 [天平13年2月14日])
国分寺・国分尼寺建立の詔を聖武天皇が出す (741年3月5日 [天平13年2月14日])
奈良の東大寺・法華寺は全国の国分寺・国分尼寺の中心とされていますね。
聖武天皇が一時的に (740年-744年) 都とした、京都府南部の恭仁京。
[ 📷 恭仁京中心の南北線に位置する道。画面奥は大極殿跡 (学校の裏手に基壇) ]
[📷 恭仁宮大極殿跡・(後に大極殿を転用した) 山城国分寺金堂跡の基
「続日本紀」完成 ( 797年3月15日 [延暦16年2月13日])
「続日本紀」(しょくにほんぎ) が完成 ( 797年3月15日 [延暦16年2月13日])
697年 (文武天皇元年) から791年 (桓武天皇の延暦10年) までの日本史を扱った勅撰の史書で、奈良時代の基本史料とされますが、
編纂は平安初期で菅野真道らが完成。
「日本書紀」に続く「六国史」 (りっこくし) 第2篇。原文は漢文、40巻。
🔍 国立国会図書館デジタルコレクション「国史大系
和辻哲郎 (1889年-1960年) の誕生日 (3月1日) 倫理学者・著述家
和辻哲郎 (わつじ・てつろう 1889年3月1日 - 1960年12月26日) 倫理学者・著述家
代表作「倫理学」「風土」「古寺巡礼」(こじじゅんれい)
🔍 青空文庫 和辻哲郎「古寺巡礼」1946年改訂版 (初版は1919年)
📝 1979年に岩波文庫にもなり広く読まれているバージョンは、この改訂版です。
私は文庫化される以前に「古寺巡礼」( なんと読むのかも分からず「ふるでらじ
正岡子規が 「根岸短歌会」 を創設 (1899年3月14日)
正岡子規 まさおか・しき (1867年10月14日 [慶応3年9月17日]-1902年[明治35年 9月19日])俳人・歌人。
正岡子規は、技巧に走らない万葉集の素朴な「ますらおぶり」を踏襲した写実的短歌の制作を提唱。
前年の1898年(明治31年)に門人の高浜虚子、河東碧梧桐 (かわひがし・へきごどう) ら俳人を東京根岸の自宅に集めて歌会を開いていますが、
おおよそ源流とみなされているのは
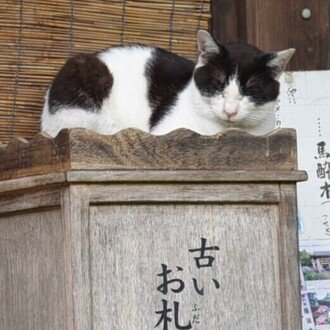





![長屋王の変(729年3月14日-3月16日 [神亀6年2月10日-2月12日]) と 「天平」](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/23124844/rectangle_large_type_2_e217717b751a6f5a1e65bc59a72b142f.jpg?width=800)
![国分寺・国分尼寺建立の詔を聖武天皇が出す (741年3月5日 [天平13年2月14日])](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/22720318/rectangle_large_type_2_37ebdf293ee080c8b3b267f8869bee9b.jpeg?width=800)

![「続日本紀」完成 ( 797年3月15日 [延暦16年2月13日])](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/22506996/rectangle_large_type_2_6c40ba6f735cec521bd8ffbab2af27db.jpg?width=800)


