
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 22 植物や生き物の世話ができる その1
21に続いて、これにも補助項目がありません。「植物や生き物の世話」ついて「その1」で【解説】します。そして「その2」で、幼児期での【育て方】を書きます。
22 植物や生き物の世話ができる
学校では、動植物を飼育栽培することは、次のような意義があると考えています。
1. 豊かな感情、好奇心、思考力、表現力をはぐくむ
2. 自分以外の相手を思いやる心、他者とのコミュニケーション能力
育てる
3.豊かな人間形成の基礎を育てる
4.命の尊さを学べる
5.何かをやりとげる責任感を養える
この中では、5番の「責任感」が一番大事だと言う先生が、多いようです。核家族化が進んでいるので、小学校にあがってくるまでに「死」と接した経験のある子どもが少ないので、4番の「命の尊さ」が1番大事という人もいます。
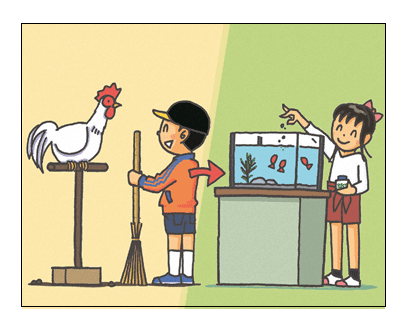
発達の凸凹タイプにとっては、2番の「人の気持ちが分かる」と「他者とのコミュニケーション」が、効果が大きいです。
これを受けて学校では、次のような動植物を飼育栽培してきました。
・にわとり、アヒル、ダチョウ、インコ、孔雀、うさぎ、ハムスター
・じゃがいも、さつまいも、ゴーヤ、ハーブ、ブロッコリー、稲、麦
しかし、近年では次のような理由で、これらを飼い続けていくのが難しくなりつつあります。
・「ニオイが臭い」「声がやかましい」と近所から苦情が来る
・休み期間中に子どもに餌やり、水やり等の世話をさせるのは、登下校
が危険である
・予算がなかなか取れない
・動物が死んだときや植物が枯れると、ショックを受ける子どもがいる
それでも、がんばって続けている学校もあります。低学年に生活科ができてからは、1年生の段階で「朝顔の栽培」をさせる学校が増えています。
先生の中にはそれだけでは足りないという理由で、クラスでも動植物を飼育・栽培する人もいます。次のような物を飼育・栽培しています。
・ザリガニ、カメ、メダカ、カタツムリ、カブトムシ、ダンゴムシ
・ハーブ、二十日大根、さつまいも、じゃがいも、スイセン、
ヒヤシンス、ミニトマト
それだけ「生き物を飼うことは、子どもの成長に大きな影響がある」と考える先生が、多いということです。
つまり、学校に進学すると何らかの動物の世話をしたり、植物を育てたりすることが必ずあるということです。
因みに、私が小学生のときに何を飼育・栽培していたかを書いておきます。
学校➪ガチョウとうさぎ
クラス➪ヒヤシンスとカメ
私は飼育係で、ガチョウが卵を生むともらえました。それでゆで卵を作って食べるのが楽しみでした。かなり、大きいですよ。
いいなと思ったら応援しよう!

