
【過去の災害から学べ!】ゆるく楽しむ日曜地質学:2022年8月21日号
ついに8月も残り10日となってしまいました。
まだまだ暑い日が続きますので、お身体を大切に。
などと言ってる私自身は、ここ最近体調の低空飛行状態が続き、どうしたものかと思案中です(;^_^A
羽越豪雨とは?
先週からの続きになります。前回記事へは以下リンクからどうぞ。
前回は山形県長井市のハザードマップ(洪水浸水想定区域図)に想定雨量の記載が無かったとお話ししました。
では近隣の他の自治体は?と、川西町の洪水・土砂災害ハザードマップを見てみます。

縦長で大きかったので一部を抜粋しました。
等高線が表記されていて、河川や土地の区画がはっきりしていて、とても見やすいマップです。
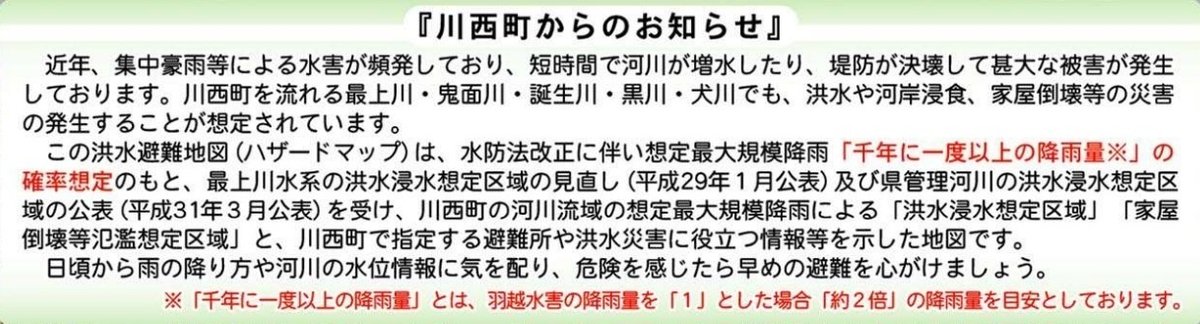
ハザードマップの右上に解説がありました(上画像参照)。
ここでは残念ながら具体的な想定雨量は記載されていませんでしたが、「羽越水害の約2倍」と言う説明がなされています。
羽越豪雨(うえつごうう)とは、1967年(昭和42年)8月26日から8月29日にかけて、新潟県北部から山形県南部にかけての地域で発生した集中豪雨です。
死者104名、被害総額約4000億円という大災害だったようです(ウィキペディアより)。
この時の雨量は、新潟県北部の関川村での30時間雨量700mmが最大で、山形県南部の小国町では24時間雨量532mmでした。とんでもない雨量です。
これに対し、8月初旬の雨量を気象庁のデータで確認してみると、小国観測所では2日間で359.5mmでした。
今回の豪雨では橋が流されたりなど甚大な被害が発生していますが、それでも55年前の豪雨の約2/3だったのですね。
やはり、過去の災害から学ぶことは非常に重要です。
今週の予告
すみません!
冒頭でも話した通り、体調不良で記事を書けておりません。
また今週は仕事で集中的に取り組む案件もあるため、おそらく投稿できないと考えております。
ですので、以下は「あくまで目標」として、あげておきます。
もし記事が投稿された場合は「体調戻ったのだな」と思っていただければ幸いです(;^_^A
〇8/23 火曜日:ジオ散歩 鎌倉市の巻
朝夷奈切通しでシャコー層理を見よう!【ジオ散歩vol.2:鎌倉市No.1-7】
〇8/25 木曜日:都道府県シリーズ 富山県part2
ポッコリ山はどのようにできた?:東部山間地域
では、今週もよろしくお願いいたしますm(_ _)m
