
<書評>『ヨブへの答え』
『ヨブへの答えAntworr Auf Hiob』カール・グスタフ・ユング著 林道義訳 Carl Gustav Jung ラシェールフェルラーグ社、チューリッヒ Rascher Verlag, Zurich 1952年、日本語版は、みすず書房 1988年。
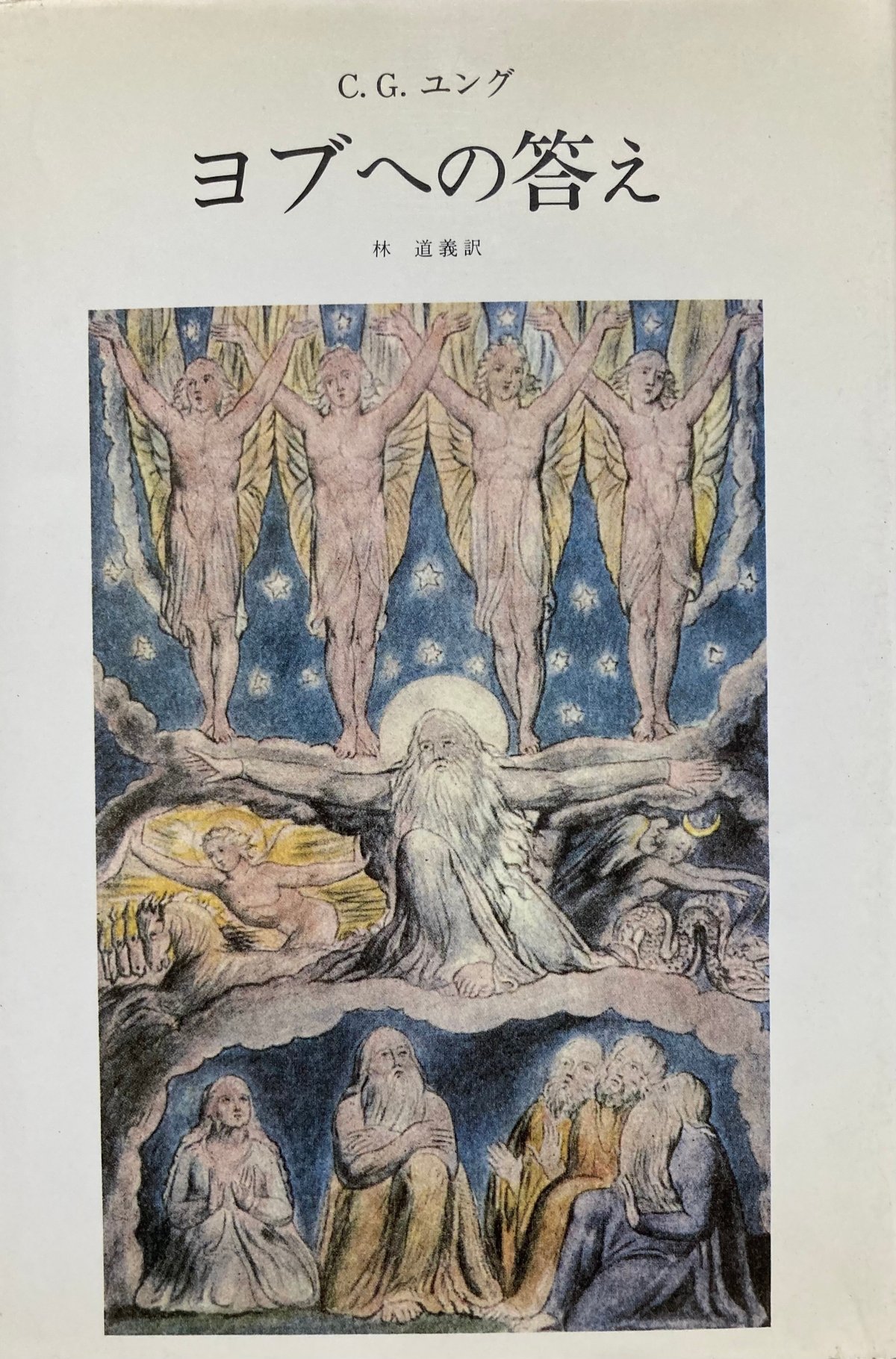
旧約聖書の中で、最も報われない不幸の連続に遭う可哀そうな代表が、「ヨブ記」のヨブだ。なにしろ、ヨブは熱心に神を信仰するのだが、信仰が進むにつれて次々に災難に遭うという、まさに「天は我を見放した」という人生を送る。それでも、ヨブは神への信仰を捨てることは決してなかったという物語である(正確には、ヨブの信仰心が揺らぐのをみた神が、自分の破壊力を見せつけて脅すことによって、ヨブに強い信仰心を持たせた)。
これに対して、昔から多くの人たちが様々な解釈をしてきた。なぜなら、ハッピーエンドに終わらない上に、どこか「神を信仰しても、良いことがないばかりか、悪いことが起きる」と言わんばかりの展開だからだ。さらに、神が自らの絶大な力で脅しつけるようにして、ヨブの信仰心を強くさせる下りは、(今流行りの?)パワハラによって部下の忠誠を得るような悪徳上司の典型に見えてしまう。
しかし、それでも「なぜヨブは(神から虐待とパワハラを受けながらも)信仰を捨てなかったのか」というのが、今日まで続く難問なのである。そして、その難問に対してユングが、自らの集合的無意識理論を適用することで解釈したのが本書である。ところが解説にあるとおり、こうした解釈は、キリスト教徒から強烈な批判にさらされることになった。別の言い方をすれば、フリードリッヒ・ニーチェが『ツァラトゥストラはかく語りき』で「(キリスト教の)神は死んだ!」と宣言したのと、同様の衝撃をキリスト教会に与えたのだった。
そうした経緯を踏まえて、ユングがヨブの虐待を得た理由と信仰を捨てなかった理由に関する、斬新な解釈=回答を期待して読んでみたが、結論としては、ユング心理学の元型という理論を、このヨブと旧約聖書の神であるヤーヴェ(ヤハウェ)との間に展開し、簡単に言えば、ヨブ=意識、ヤーヴェ=無意識という図式を展開しただけのものだった。これには、正直がっかりしてしまった。もっと「ヨブの本当の気持ちはこれだ!」式のものを期待していたからだ。
なお、この解釈はさらに、イエスが意識=人間と無意識=神を仲介する存在であり、そうした仲介者の先達として、エノクとエゼキエルの二人がいたが、イエスはその進化したものだと論考を進めており、これは期待していたものとは別だったが、エノク・エゼキエル・イエスの関係が新たに理解できて、とても興味深く読めた。
また一方でユングは、ヤーヴェの持っていた善と悪の二面性が、イエスの登場により、イエス=善・慈愛=意識、サタン=悪・暴君=無意識という形に分かれたとしている。そして、イエスを通して神からの善・慈愛を受け継いだ福音書作者の使徒ヨハネは、実はサタンから悪・暴君も受け継いでいたのだが、これを隠匿し続けることができず(つまり、無意識のパワーが意識に上昇するのを抑圧できず)、そうした感情が「ヨハネの黙示録」という終末の地獄絵に表現されたとしている。
これらイエスや福音書作者(四人の使徒)亡き後も、この意識対無意識の戦いはキリスト教世界で継続しているとユングは述べ、サタンに代わる無意識を代表するものしてアンチキリストの出現を予想する。そのアンチキリスト(及び黙示録の世界)のイメージは、20世紀に新たな信仰対象となった科学技術がサタンと化した、二度の世界大戦及び核兵器として具体化した。
そしてこれに対抗するために、イエスが、人間として死んでいった母マリアから生まれたのでは神人としては不十分であると、大衆の深層心理が切望することになったという。それが、20世紀初頭のルルドやファティマ、そして1950年代を中心に世界各地で出現した「マリアの降臨」であったとする(数回出現したカイロを筆頭に中南米などで多くのマリア降臨が目撃されている)。
そして、これに対するローマ教皇の対応策として、マリアをイエスと同じように昇天させ、聖母であるだけでなく女神の地位にすることになったと説明している。実際、これ以降「マリアの降臨」の目撃は減少した。
以上の論考はなるほどと頷けるものがあるし、実際そういう部分があるのだと思う。しかし、「古代の宇宙人来訪説」を信望する私としては、ユングがUFOを実際に存在するのではなく、自らの元型論から考察して、「無意識をイメージ化」をした人々の錯覚・幻視であると見なしたのと同様、その真実は異なると考えている。つまり、UFOが実在するのと同様に、「空から炎に包まれた乗り物で地上にやってきた」というエノク、エゼキエルをはじめ、イエスと昇天したマリアは、地球外生命体が地球に送り込んだロボットだったと考えている。そして、彼らロボットたちは、人類が滅亡に向かう最終戦争を起こさないようにするための監視役だったのではないか。
以上の観点から、ユダヤ教の神ヤーヴェもキリスト教の神もその他世界の神々は皆、地球外生命体を別の名前で称したものだと理解しているので、地球外生命体であるヤーヴェが、人類に対する慈愛だけでなく、喜怒哀楽を持った人間に近い存在であったとしてもまったく不思議でないと考えている。また、「ヨハネの黙示録」は、人類への注意喚起としての預言書という意味合いとともに、実際に遠い宇宙であった地球外生命体同士の核戦争の記録を基にした、迫真に富む忠告だと理解している。つまり、ヨハネは神から核戦争のビジュアルな記録を見せてもらい、それを文章に記録したのだろう。
こうした観点を含めて、以下の箇所が私の琴線に触れたので、ご参考までに紹介したい。メインとなる部分を太字にしてある。また、冒頭のページ数は日本語版のものである。
P.21
以上の考察から[ヤーヴェの]性格を判断すると、それは客体によってしか自分の存在感をもてない人格に相当することがわかる。主体が自己反省をせず、したがって自分自身への洞察を持たないときには、客体への依存は絶対である。主体は自分が存在していることを確信させてくれるような客体を持っていることによってのみ存在できるかのように見える。
P.68
打倒され、迫害された者が勝利するのは当然である。なぜならヨブはヤーヴェより道徳的に上に立ったからである。この点では被造物が創造主を追い越していたのである。
P.80
昔から(神の)人間化は一回限りの歴史的な出来事であると教えられてきた。同じことが繰り返されることや、ロゴス(論理)がもう一度啓示されることは期待できない。なぜならそのことは約二千年前に一回限り起こった、人間となった神の地上への現れ(イエス・キリスト)によって完結しているからである、と言われている。この啓示の根拠と究極の権威は聖書であり、また神が新約聖書を承認したという意味でのみ神である。神の真正の告知は、新約聖書が終わるとおしまいになる。なんというプロテスタント的立場!歴史的キリスト教の直接の相続者であり継承者であるカトリック教会はこの問題についてもう少し慎重である、なぜならカトリック教会は教義が聖霊の助けによってさらに発達し、発展することができると考えているからである。
P.127
この『(ヨハネ)黙示録』はある初期のキリスト教徒によって体験されたものであり、彼はおそらく権威者として模範的な生活を送り、正しい信仰・謙遜・忍耐・献身・無私の愛・この世のすべての快楽の放棄・といったキリスト教的な徳を一つの教団に示さねばならなかったのであろう。そのような生活はどんな立場の人にとっても、長く続けると負担にならざるを得ない。いらいら、不機嫌、かんしゃくは、徳のある生活を長い期間続けていると現れる典型的な症候群である。(原注:キリストは使徒ヨハネに「雷の息子」というあだ名をつけたが、不当ではない。)
(以下は、翻訳者林道義による解説からのものである。)
P.175
受肉の準備を意味する現象としてユングが注目したのは、ソフィアの想起と、「人間の息子」の出現であった。
・・・ヤーヴェが知恵の女神ソフィアを想い起したのである。それはヨブとの角遂の中でヨブの鋭い批判に出会って、「義の神」ヤーヴェがもはや不義をなすことができず、「全治の神」がもはや無知な振舞いをすることができなくなったからであり、そのために「知恵」が必要になったからである。
・・・彼(エノク)は人間の息子でありながら、神の息子たちの一人であるかのように振舞っており、四者性という神的な性質も示している。「人間の息子」が天の世界で活躍することは、一方では神が人間になりたがっていることを意味すると同時に、他方では人間も神の世界に関与することができるということを示しているのである。言うまでもなくエノクはイエスの先駆形態であり、神が人間になるというイメージに対する心理的欲求が高まっていることを示すものであった。
P.183
・・・人間の神化を示唆する内容が見られるのは、「人間神化」の観念が元型的なものだからではない(であろう)か。この観念はキリストの復活というイメージの中にも見られる。つまり人間になったキリストが再び神になるのであるが、実際にはキリストが人間になりきっていないで初めから神であるので、「神になる」というイメージが薄くなっているにすぎない。
それでは「人間が神になる」あるいは「人間の中に神的なものが宿る」というイメージは心理的には何を意味しているのであろうか。それは救いが外から与えられるものではなく、救いの働きは人間の内に存在しているのだという思想を表しているのである。「パラクレート(ギリシア語で「弁護者」「助け主」の意。『ヨハネ福音書』では、聖霊がキリストによって「別のパラクレート(助け主)の宿り」と呼ばれている。)というイメージはグノーシス(キリスト教異端派の名称。グノーシスとはギリシア語で「知識」または究極の知恵・叡智)の種子が人間の中にひそかに埋め込まれているというグノーシス主義の観念と同種のものである。それは人間が外的な業やその制度化によって救われるのではなく、人間の中には神的なものが内在しており、人間はその内なるものの働きによって救われるのだということを語っているのである。
*この最後の解説からは、グノーシス主義やユングの述べるパラクレートという概念は、仏教の「一切衆生仏心(仏性)あり」という、「生きとし生けるものはすべて心の奥底に仏の心を持っている」という概念や、禅でいうところの大悟(己自身の存在を再確認する)と同様の考え方が読み取れる。
これはまた、人類が神=地球外生命体による被造物であるという前提に立てば、神は人類の中に「パラクレート」や「仏心」を予め設定しておいたとも読み取れる。しかし、それが十全に機能していないのが、人類が抱える問題として未だ解決されていないが、その理由としては、人類が神の被造物としては未だ「試作品」状態であるということかも知れない。
もっとも「プロトタイプNO.1」のヨブは、試作品としての試練を乗り越え、人類の地球上の反映を担保してくれた。また、神による「リセット」である洪水を乗り越えたノアは、さしずめ「プロトタイプNO.2」なのだろう。我々はノアの子孫であるので、今後「プロトタイプNO.3」が登場する前提となる、黙示録のような「リセット」がないことを祈りたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
