
<書評>『シンボル形式の哲学』
『シンボル形式の哲学』全4巻 エルンスト・カッシラー 生松敬三、木田元、村岡晋一訳 1989年 原題は 『Die Philosophie Der Symbolischen Formen』 Ernst Cassirer 1923年

第一巻「言語」、第二巻「神話的思考」、第三巻「認識の現象学(上)」、第四巻「認識の現象学(下)」にわたる大著である。もともと内容が難解なドイツ語原文を日本語に翻訳しているため、さらに難解な内容となっている。つまり、日本語の文書をそのまま読んでも、簡単に頭で理解できない、理解するのに時間がかかる書物だ。さらにそれが、4冊もあるのだから、これは苦行に等しいものになる。
そのため私は、毎日頭が一番冴えている朝の最初に読む本に決め、毎日10ページを目途にして読み続けた。そして読了までに約半年かかった。難しかった。しかし、読了したときの達成感と満足感は、非常に大きいものがあった。読めて良かった本だ。
本書の最後の結論部分では、アインシュタインの相対性理論とボーアの量子力学によって、プラトン-アリストテレス-デカルト-ライプニッツ-カント-ニュートン-とつながってきた、哲学=物理学という概念が、一気に物理学的思考が優位に立つ、つまり時間と空間と物質(原子)による四次元概念が、そのまま世界認識の哲学になるということを説明している。
それはまた、相対性理論の果たした人類史上の貢献の巨大さを意味するだけではなく、人の世界認識とはすなわち、この宇宙をどう理解するかということに直結しているということを述べていると思う。人が宇宙(の仕組み)を理解することは、そのまま人の身体(と心の仕組み)を理解することになり、その結果、人の精神(心)が何であるかの答えを出してくれる手段であることにつながる。まさに、相対性理論=現代哲学なのだ。
そうした結果、今や旧来の哲学(概念)は消え去り、もはや用なしとなってしまい、物理学がそれまで哲学が担っていた分野を一身に背負っているかに見える。今や人は、これまで哲学を参考に生きてきたのが、物理学を参考に生きるようになった。もっと言えば、哲学という神が、物理学という神に移転したのだ。
こうした移転は、相対性理論の出現によって、突然に生じたのではない。移転が行われる前提として、ニュートンの近代力学(つまり重力)概念があり、この概念が17世紀末から300年経つことによって、「ニュートンの万有引力の法則」として(その原理は別としてイメージは)小学生でも理解できるものになっていたことが大きく影響している。いまや、万有引力の法則を知らない人はほぼいない。
しかし、ニュートンの万有引力の法則概念を根底から覆すアインシュタインの相対性理論が20世紀初頭に発表され、発表直後から「相対性理論」という言葉が世界的な流行語にすらなったものの、この基本概念(時間と空間の理論及びE=mc2)については、もちろんその難しい原理を理解することは別としても、100年経った現在でも知らないという人が多い。第一、時間と空間が曲がるとか歪むという、現実の生活感覚と非常に異なるそして日常生活にほとんど関係ない概念を、普通の人たちが知るようになるあるいは知りたいと思うことは、なかなか難しいことだ。
そのため、物理学=哲学に移転したことすらも、普通の人々は意識していないしまた意識する必要もない。ただ物理学の見える成果として、ロケットが宇宙空間に飛行し、月や彗星を構成するサンプルを実見できることに、まるでエンターテイメントのように反応しているだけだ。そこには、哲学的な思考が入る余地はない。
しかし、私としては、あと100年ぐらいしたら、「ああ、相対性理論ね」と誰もが言うようになっていて、また小学校低学年の授業でも、「アインシュタインの相対性理論は・・・」と先生が教えることになっていることを期待したい。そしてそうなった時には、人類がさらに進化できた結果として、ニーチェが夢想した「超人」になることを願っている。
ところで、本書の最終章「第五章 自然科学的認識の基礎 3 現代物理学の体系における<シンボル>と<図式>」の冒頭には「1」とあるが、「2」以降はない。そして、最後の文章を読むと、これまで延々と繰り広げられて来た考察の最後となる「結論」に該当するような部分もなければ、それに近いニュアンスも全く記述されていない。いわゆる「尻切れトンボ」という感が非常に強い。
「これはおかしい、もしかしたらこれは未完の書ではないか?」と私は思いつつ、最後に掲載されている訳者の訳注とあとがきを読んだら、まさに文字通りの「未完の書」であったとの解説があった。つまり著者であるカッシーラーは、この後に「2」として、「<生>と<精神>-現代哲学批判」、または「シンボル形式の形而上学のために」という題による考察が予定されていた。しかし、カッシーラーはこうした構想が大きく膨らんだことにより、最終章ではなく独立した著作としてまとめることに進路変更したという。ところが、カッシーラー自身は、この著作を発表することなく亡くなってしまったのだった。これが「未完の書」となった理由なのであった。
以上の理由から、カッシーラーが本書で何を主張したかったのか、つまり「シンボル形式の哲学とは何か」という明確な記述は、未来永劫知りえないことになってしまっていた。一方、訳者によれば、現代物理学等20世紀の急激に発展した諸科学の成果を反映したカッシーラーの哲学研究は、その後メルロ・ポンティに受け継がれたとのことである。つまり、「シンボル形式の哲学とは何か」という問いに対する答えが、メルロ・ポンティの著作に探すことができるということだ。
幸いに私は、メルロ・ポンティの『眼と精神』と『言語と自然』の著作を持っている。そして、両書ともに日本語翻訳は、本書と同じ方(木田元)がされている。つまり、木田氏はカッシーラーとメルロ・ポンティが関連することを理解しつつ、両者を翻訳していることになる。現在の私が選択できる、カッシーラーが本書で言わんとしたことのイメージを把握する道はただひとつ、既に早世してしまったメルロ・ポンティの著作を読むこととなった。(注:『眼と精神』はこれから再読する予定だが、最近『言語と自然』を読了した限りでは、「シンボル形式の哲学とは何か」という明確な答えは見つからなかった。私の目指す道は、果てしなく遠く、ゴールはないのかも知れない。)
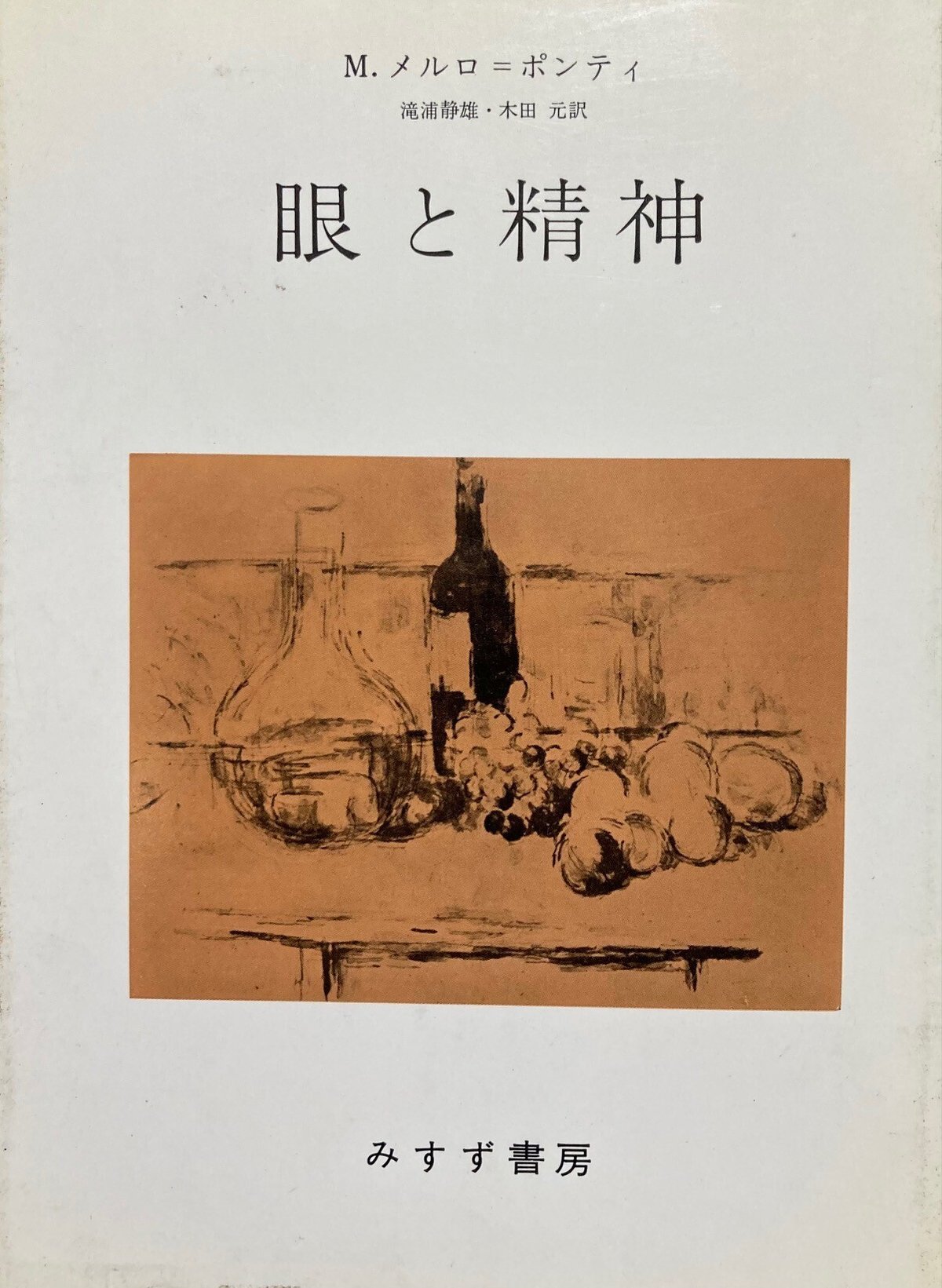

ところでカッシーラーは、記憶力が異常なほど優れていて、著作に引用する古典文献を、原書を見ることなく暗記したものをそのまま記述していたという。また、多くの文献をほぼ全て暗唱できた上に、何か学ぶ場合でもノートを取ることが必要なかったそうだ。下世話な話だが、こんな人が日本で受験勉強をしたら、医学部だろうがなんだろうが、どこでも容易に入学できたことだろうと想像する。
しかし、その「秀才」あるいは「天才」カッシーラーが目指したのは、(日本の有名大学に入学・卒業することではなく)ドイツにおける現代哲学の研究であり、なかんずく20世紀初頭に飛躍的に発展した、宇宙物理学、言語学、神話学を元にした研究だったことは、人類にとって何か特別な意味合いがあったように思う。
一方、仮に今の日本でカッシーラーのような頭脳優れた人が現れた場合、果たしてカッシーラーのように哲学を志向するだろうか、という不安がある。おそらく優秀な子供を得た親は、まず東大に入れ、その後一流企業に就職させ、数年後には億万長者の投資家になるのだろう。そして、(金銭の)数字というイメージ=シンボルが常時動いている世界で、巨万の富に包まれてドバイやニューヨーク(現代のソドムそのものであろう)で豪奢な生活をするのだろう。たぶん、怒れる神の鉄槌が落ちるその時まで。
