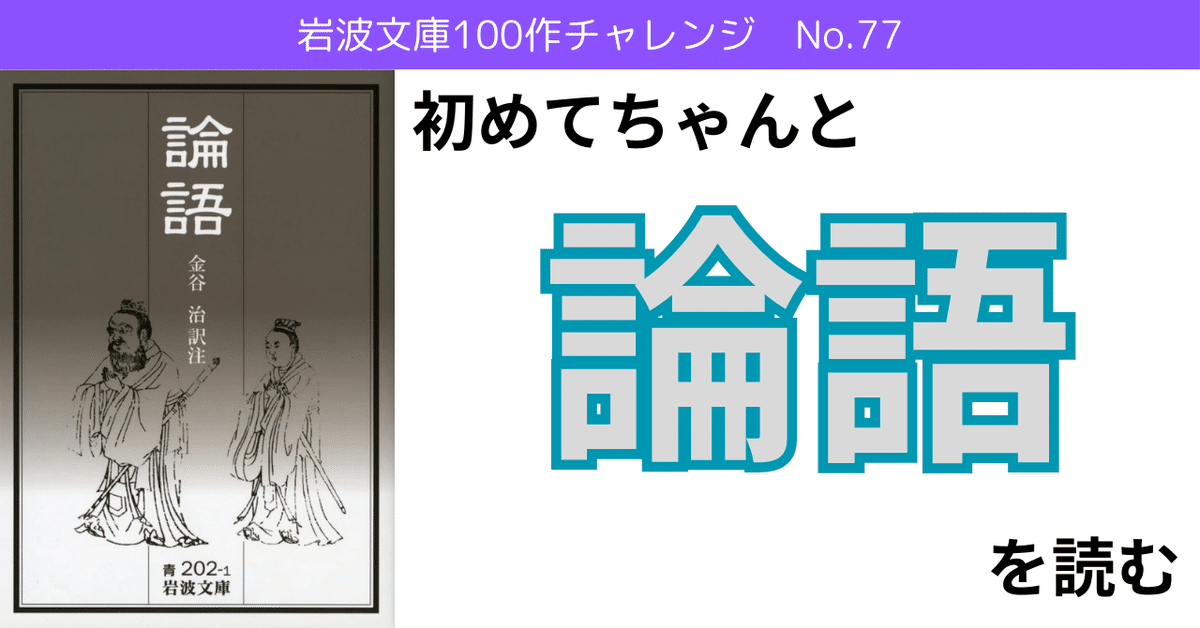
No.77「論語」全編を読んで感じたこと
社会で生き抜いていこうとするならば、まず「論語」を熟読しなさい
新紙幣に切り替わって数ヶ月。ようやく千円札の北里柴三郎を拝むことがチラホラ。新1万円の渋沢栄一は銀行やATMでないとお目にかかれそうにもないが、紙幣切替依頼ずっと気になっていた渋沢栄一「論語と算盤」をようやく読んだ。
「論語=道徳」と「算盤=経済」は、かけ離れているように見えて、両者はとても近いもの。明治維新の追いつけ追い越せで、“物質文明が進んだ結果、精神の進歩を害した“として、道徳をおさめる事、精神修養の必要性を説いている。
そしたら案の定「論語」をきちんと読みたくなった。
岩波文庫の「論語」は大変わかりやすい。原文(もちろん読めない)、読み下し文、現代語訳と3種並べてあり、読みやすい部分を読めば良い。
渋沢栄一は原文を読んだのだろうか。講義を聞いたり勉強会をしたり。解釈の仕方で意見が出るのはなかなか面白いと語っている。自分の知識欲が刺激されたのもこの辺り。解釈が色々なのだと知って、「論語」を読んでみたくなった。
「論語」は、紀元前に生きた孔子の言葉を弟子たちがまとめたもの。おそらく明治頃までは、あらゆる日本の教養人が通った道。人として、国をまとめるものとして、大事なことがまとめられている。
書かれていることはベーシックとも取れる。けれど幹がしっかりしていなければ、いくら枝葉が多くとも木は倒れてしまうように、人としての根幹、大事なことが書かれている。
古いとは微塵も思わなかった。むしろ、日本を作った偉人のほとんどが通った道であるならば、これからの人たちも、特に人生の早い段階で読むべき本であるとさえ思う。
周囲に手本となる人がいなくとも、ロールモデルが見える。近くに大人物がいなくとも、本であれば紀元前まで遡れる、これこそ醍醐味。
安政の大獄で、わずか25歳で斬首になった橋本左内。彼が残した「啓発録」には、15で学問を志すと書かれており、若いうちから立派だと感心したものだが、その言葉は「論語」に重なる。
吾れ十有五にして学に志す
三十にして立つ(独立)
四十にして惑わず(不惑)
五十にして天命を知る
六十にして耳順う(人の言葉を素直に聞く)
七十にして心の欲する所に従って、矩を踰えず(思うままに振る舞って道を外れない)
天を怨みず、人を尤めず、下学して上達す。我を知る者は其れ天か。
(天を怨みもせず、人を咎めもせず、ただ自分の修養に努めて、身近なことを学んで高遠なことに通じていく。私のことをわかってくれるものは、まあ天だね)
西郷隆盛座右の銘「敬天愛人」や、「世の人は我を何とも言わばいえ、我がなす事は我のみぞ知る」と言った龍馬も重なって見える。
天下泰平260年続いた徳川政権を成立させた家康の言葉の多くも、「論語」と重なると渋沢栄一も指摘する。
解説書では見えない部分
「論語」ネタの本は多い。かくいう自分もビジネス本としての「論語関係」の本は読んだことがあった。だが今回「論語」をちゃんと読んで改めて感じたのは、解説書というのは分かり易いが、自分の考えは発展しにくいという事。
有名な箇所を選り抜きしてくれる解説書は、時間が省けたりなどありがたい部分もあるけれど、そんなに有名ではない部分も含めて、全体を読み通すことで初めて感じ取れる要素もあると思った。
例えば次の2つ。
①対話は最強の学び
孔子と弟子たちの会話で成り立つ「論語」。対話と言えばソクラテスだって同じ手法。師との対話を通じて、弟子は自ら感じ、学びとる。対話を通して自己の考えを深め発展させていく。
アメリカの授業がこれにあたるらしい。教授と生徒の対話が大事な学びの要素として捉えられている。真に納得。日本の授業でも、先生が一方的に話して終わりというスタイルを脱している学校もあるだろう。
幕末の長州藩には、藩校明倫館と吉田松陰の私塾・松下村塾があった。明倫館では、時勢もあってか時事を論ずることが監督され、字句解釈が重視されたのに対し、松下村塾では自由闊達な議論が推奨されたという。
松下村塾の学習内容はこちら。
・講釈
・会読、同じ書物の読み合い
・順読(輪講)、塾生が順番に講義をして質問に答える演習
・討論
・対読(マンツーマン)
・看書(読書)
・対策、課題を与えて答案を書かせ、松蔭が批判・添削(個性観察)
・私業、読書した後に皆の前で所感を述べ批評を受ける
さぞ活発な授業だったろう。維新を成した長州人がほとんど松下村塾の門下生であったというのも偶然には思えない。
②人間的な、あまりに人間的な
これはニーチェの著作であり、今回の内容に直接関係はないのだけれど、文字づらだけを捉えれば、「論語」はあまりに人間的で現実的。西洋での紀元前のバイブル、キリスト教との違いに目がいった。
聖書がキリストの奇跡を扱っているのに対し、「論語」には“宗教的神秘的な性格が少ない“(“ ”内は解説者の言葉そのまま)。実に現実的な内容であり、両者を比較してみるのも面白い。
聖人には私は会うことはできないが、君子の人に会えればそれで結構だ。無いのに有るように見せ、からっぽなのに満ちているように見せ、困っているのにゆったりと見せて(見栄を張って)いるようでは、むつかしいね。
原典に当たった後こそ、解説書を読むとまた面白いのだろうと思った。このために「論語と算盤」を読んで「論語」に走り、上のような思いでもう一度「論語と算盤」に戻った所、新たに認識することもあった。
例えば、キリスト教と論語の違いは渋沢栄一も指摘していたのだが、初読では気にならなかった。自分で西洋と東洋の違いに思い当たって初めて、渋沢の言葉の理解が深まった所。要は自分で気づいたのでなければすぐ忘れてしまう。
論語の言葉
全編を通して「論語」から感じ取ったものは仁と礼。仁とは、内に我が身を謹む事、「有れども無きがごとく」の精神。外では礼を欠かない事。加えて当たり前ながら親を大事にすること。
人によって、時期によって、その時々で心に沁みる言葉は違うだろう。今の自分には、普段から心に思う事あってか、礼と親に関する言葉が特に沁みてくる。
和を知りて和すれども、礼を以てこれを節せざれば、亦た行なわれず
(調和していても、礼で折り目をつけなければ、うまくいかない)
フラットな関係を重視するあまり、目上の人に対して礼を尽くすことは、ややもすると軽視されがちなようにも思う。フラット、対等なのは権利であり、敬語を使わなくて良いとか、そういう事ではないと改めて思う。
もちろん年が上だから偉いとも言えない。そこに仁が絡んでくる。徳のある人には上でも下でも礼儀を尽くした方がうまくいく、というメッセージと捉える。
父母に事うるには幾くに諌め、志の従わざるを見ては、又た敬して違わず、労して怨みず。
(父母に仕えて、その悪いところを認めたときには穏やかに諫め、その心が従いそうにないとわかれば、さらに慎み深くして逆らわず、骨を折るけれども怨みには思わないこと)
親の言う事にも反感を覚えることはある。そんな時に大事にしたいのが、最後の「骨を折るけれども怨みには思わないこと」これだ。
有名な言葉7選
「論語」にはこんな言葉があると言うのをほんの少しだけ紹介する場。あまりに有名なので、紹介するまでもないだろうけれど、これは「論語」が出自の言葉だったのだと、思ってもらえればそれで良き。
学んで思わざれば即ちくらし(学んでも考えなければ物事ははっきりしない)
思うて学ばざれば即ちあやうし(考えても学ばなければ(独断に陥って)危険)
朝に道を聞きては、夕べに死すとも可なり
(朝に正しい真実の道が聞けたら、その晩に死んでもよろしい)
一を聞きて十を知る
これを知る者はこれを好む者に如かず
これを好む者はこれを楽しむ者に如かず
知っている<好いている<楽しんでいる
楽しんで行える者が最強、ということで好きな言葉。
「道に志し、徳に拠り、仁に依り、藝に遊ぶ」という言葉もある。
正しい道を目指し、徳を根拠とし、仁によりそって、芸(教養のなか)に遊ぶ、という意味で、最後遊んでしまう所が余裕の現れ。好き。
亀仙人の修行「よく動き よく学び よく遊び よく食べて よく休む」。なんとなく思い出してしまった。武の道は精神の道。

仁者は己れ立たんと欲して人を立て、己れ達せんと欲して人を達する
(仁の人は、自分が立ちたいと思えば人を立たせてやり、自分が行きつきたいと思えば人を行きつかせてやる)
未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん
過ぎたるは猶お及ばざるがごとし
(行き過ぎたのは足りないのと同じようなもの、どちらも中庸を得ていない)
中庸とは、極端に走らず中ほどを守って行くという処世の徳。なるほど頂上に上りつめればあとは落ちるだけ。
ずいぶん昔にとある俳優が、あえて主演はやらず脇役で生きていく主義なんですと、インタビューで答えていた。変わった人もいたものだと当時は思ったが、長く俳優として生きていくための処世術として優れているのかもしれない。
以上、
「論語」は読んだ良かったタメになったで終わらせるのでなく、渋沢栄一が事業の指針としたように、読書百遍意思自ずから通ずのように、常に心にある状態、常態にまで昇華させて初めて身になるのだろう。繰り返し読んでいこうと思った。
岩波文庫100作チャレンジ、残り23作🌟
