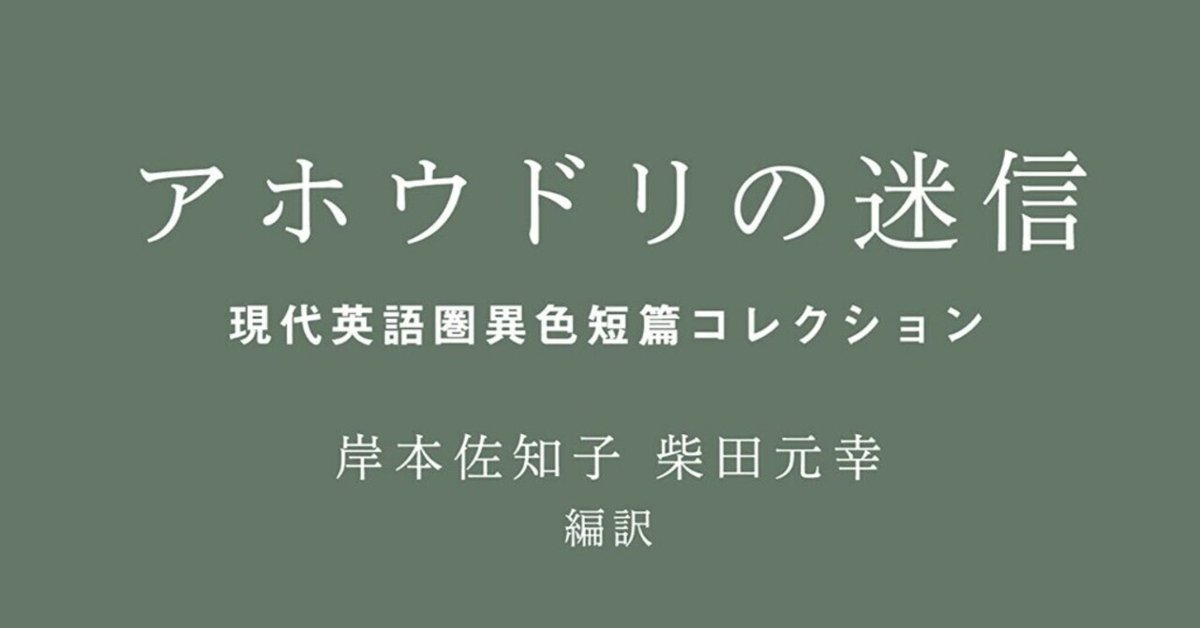
滝野沢友理評 岸本佐知子/柴田元幸 編訳『アホウドリの迷信――現代英語圏異色短篇コレクション』(スイッチ・パブリッシング)
評者◆滝野沢友理
翻訳の名手ふたりが発掘したどこか不思議な作家たちの傑作短篇集――普通なのにどこかおかしい。ありそうであり得ない
アホウドリの迷信――現代英語圏異色短篇コレクション
岸本佐知子/柴田元幸 編訳
スイッチ・パブリッシング
No.3567 ・ 2022年11月19日
■文芸誌『MONKEY』23号(二〇二一)で好評を博した特集「ここにいいものがある。」が、すてきな短篇集になった。補足すると、同特集では『MONKEY』の責任編集を務める柴田元幸と翻訳家の岸本佐知子が、「英語圏全体を対象とし、それぞれ三~四作品、合計で四〇〇字一二〇枚以内、作家は本邦初訳が望ましい」という条件の下でそれぞれ三人の作家の作品を紹介したのだ。このたび単行本として刊行されるにあたり、そこにもう一作品ずつの訳し下ろしとふたりの対談が一つ追加され、二三二ページの一冊の本となった。
柴田と岸本が各々持ち寄った短篇が交互に収録されているにもかかわらず、ひとりの訳者が訳したとしか思えない。現代作家に限定されているからとか、結果として八名中七名が女性作家になったからではない。根底に流れる緩いつながりをしいて言葉で表現するなら、「現実八割、幻想二割くらいのバランスの作品」が集まっているからだ。だが言葉以上に、『MONKEY』掲載時に「野良のミルク」の表紙を飾った挿絵を思い起こさせる印象的な装画が、各短篇を貫く一本の糸を的確に物語っている。普通なのにどこかおかしい。ありそうであり得ない。
この独特の世界観をお伝えできるとは到底思えないが、まずは本書のタイトルでもあるデイジー・ジョンソンの「アホウドリの迷信」と、タイトルからして異彩を放つアン・クインの「足の悪い人にはそれぞれの歩き方がある」について触れたい。
「アホウドリの迷信」は、ポリーという十代の女の子に宛てた手紙からはじまる。送り主は酔ったはずみでポリーを妊娠させたルーベン。妊婦である彼女を家に残して船乗りの仕事に出たまま戻らなくなる。お金のためか気を紛らわせるためかポリーもパブに働きに出るものの、ルーベンが戻らないこともあり次第に妙な考えに取りつかれるようになる。しかし、ある朝食卓の上にいたアホウドリは彼女の妄想ではなかった。窓ガラスを粉々にして本当に入ってきたのだ。アホウドリの中には死んだ船乗りの魂が入っていると迷信深いルーベンがかつて語っていたが、それはルーベンの死を意味しているのだろうか。状況的に想像の域を出ないことばかりだが、突然登場するアホウドリが残すインパクトは計り知れない。
状況が把握しにくいという点では、「足の悪い人にはそれぞれの歩き方がある」も負けてはいない。描かれる場面は女の子が祖母とふたりの大叔母と四人で暮らす家のみ。女四人で子どもの父親であるモンティが帰ってくるのをひたすら待つ。モンティの詳細についても母親についても一切言及されない。モンティは実際に帰ってくるが、「明日コンサートがあって」ということでまたすぐに出ていく。あらすじとしてはそれまでだが、本短篇にあらすじは重要ではない。重要なのはカンマのない原文、読点のない訳文からにじみ出るこの家全体の空気であり、そこにいる四人の不思議な存在感だ。
なお、訳し下ろしの二作のうち一作は、「私が列車に轢かれて死んだ夜の話をしたい。ただし――そんなことは起こらなかった。」という冒頭から意表を突かれるローラ・ヴァン・デン・バーグの「最後の夜」。もう一作は、二〇一六年に著名人の講演を配信するTEDで名を知られるようになったリディア・ユクナヴィッチの「引力」だ。
いずれも一読しただけではわからないかもしれない。もしかしたら何度読み返してもわからないかもしれない。
それでよい。理解などできなくても、たった一文でも強烈に惹かれる何かを感じることができれば十分だ。海外文学にご興味のある方なら誰もが知る翻訳の名手ふたりが「発掘」した作品とあれば、まずは何も知らず何も調べず、目の前に出された一品をそのまま味わってみたい。
(翻訳者/ライター)
「図書新聞」No.3567 ・ 2022年11月19日(土)に掲載。
http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/index.php
「図書新聞」編集部の許可を得て、投稿します。
