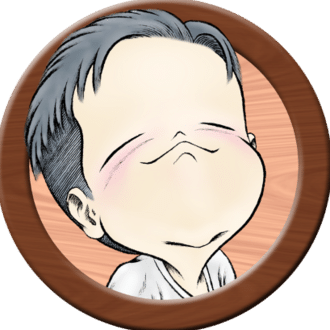博多ラーメンの白濁トンコツスープは仕込みの失敗が生んだ偶然の産物だって!
九州ラーメンの代表格である博多ラーメンは
そのルーツが久留米ラーメンだという説もあると
先日投稿したこちらの記事でもお伝えしました。
で、今回はその博多ラーメンの白濁スープが
仕込みの失敗からの、偶然の産物であることを
お届けしたいと思います。
ここからの話は、前回の記事を
ご覧になっている前提で話を進めたいけど
それだと不親切なので転載しておきますね。
昨今のラーメンブームの影響と、比較的に修行期間が短いことや開業における設備費用の資金面などで、独立開業がしやすいこともあって全国的にラーメン店が増えているようだけど、ラーメン好きとして博多ラーメンのルーツについて書いてみたい。
今やご当地ラーメンという地元産のラーメンが、ある程度の規模を持つ地方都市であれば必ず目に付くくらい、猫も杓子もの状態でラーメン店がひしめいていますよね。
おまけにコンビニチェーンが競い合って、有名店の味を再現したカップラーメンを発売しているものだから、名前の売れているラーメン店の味は簡単に家庭や職場で味わうことができる、便利な世の中になったものです。
コンビニで競っている新商品も、手を替え品を替え発売が続くから、ラーメンも種類も増えるけど、売れ行きの悪い商品は静かに退場させられ陳列棚から姿を消すから、残る数としてはさほど変化はないかも知れない。
・・・って、コンビニの売れ筋分析をしてるわけでも、カップラーメンの販促の話をしようというのでもありません。
九州でラーメンといえば?
そう、これをテーマにしたかったのですよ。
九州ラーメンというと博多ラーメンが有名だけど、その博多ラーメンのルーツが久留米ラーメンだというのもご存じでしたか?
要するに「とんこつラーメン」としての発祥が、福岡県久留米市の「南京千両」さんという屋台ラーメンから始まったとのこと。
残されている記録では、この「南京千両」さんが屋台ラーメンを始めたのが昭和12年の春のことなのですね。
これ以前には、屋台にしろ店舗にしろ「とんこつラーメン」を提供していたラーメン屋は、他に存在しなかったということで発祥となったわけです。
博多ラーメンのルーツは久留米?
博多ラーメンのルーツが久留米だという説とは別に、博多ラーメンでも中州の川沿いで昭和13年~15年頃に「三馬路(さんまろ)」という屋台を始めた森さんという人がいて、この屋台が博多ラーメンのルーツになっています。
そして興味深いのが、この「三馬路」のラーメンスープは、同じとんこつでも澄んだスープだったという点です。現在のような白濁スープは「赤のれん」のラーメンが元祖になるらしい。
澄んだとんこつのスープに平麺という三馬路のラーメンは、上海から引き上げてきた先述の森さんが始めたけど、開業時期は先述した昭和13年~15年とも、昭和16年~17年とも伝わるものの記録がなく、はっきりしないところがあるようです。
その後、森さんと一緒に味を工夫していた森山さんという方が「五馬路(うまろ)」という店を始めたけど廃業。
そのあとに甥御さんに受け継いだ味が「うま馬(うまうま)」というラーメン居酒屋に受け継がれて、今に至っているようですね。
いずれにしろ三馬路の創業が昭和13年~17年の間であることは間違いないようなので、昭和12年春創業の久留米ラーメンのほうが、とんこつラーメンの発祥としてはルーツになるようです。
まだまだ話せば長くなるので、この続きはまたの機会にでも。(^_^)b
最近のインスタントラーメンは、麺もスープも格段に味が向上してバカにできませんよね。
わざわざ外食でラーメンを食べる機会がなくなりました。
家ラーメンでお昼ご飯にすることもけっこうあるけど、どれにしようかと迷うのも楽しみの一つです。
この記事書いていたら、明日の昼はラーメンにしたくなってきた。🤣
ここまでが、昨日の記事。
白濁トンコツスープのルーツが久留米なのか?
南京千両の久留米ラーメンも他の屋台も、当時は澄まし仕立てのとんこつスープだったらしいのです。
その澄んだスープを仕込む最中に、うっかり火力を落とさずに買い物に出かけてしまって、煮込みすぎて白濁スープにしてしまったことが、白濁スープの誕生につながることになりました。
仕込みに失敗して廃棄処分にしなくちゃいけない白濁したスープに、ちょいと味付けして食べてみたら・・・・・・😲
これが案外と美味しいじゃないか!
いけるじゃないか!
・・・となって、久留米系の白濁トンコツスープの誕生となったのです。
このうっかり八兵衛のようなうっかりミスで、澄まし仕立てのトンコツスープを白濁させてしまい、瓢箪から駒を出しちゃったのが、現在は休業してしまった久留米屋台の「三九」さん。
トンコツラーメン好きなら、三九さんに、サンキューと言いたい!
そもそもスープの仕込みに寸胴を使うと、火力が充分に行き渡るのに時間がかかり、羽釜(はがま)の倍以上の時間になるらしい。
だから久留米ラーメンでは、老舗といわれるラーメン店のスープの仕込みは羽釜を使っている店が多いようなのですね。
昔ながらの竈だと、すっぽり羽釜を置けるのです。
羽釜の腰の羽根で蓋をした状態になって、熱を外に逃がさないから、強い火力で炊き上げることができるわけです。
確かに羽釜の構造を考えると、納得できる話ですよね。
澄んだスープをとる仕込みなら、スープが炊き上がったらすぐに火力を弱火にして、コトコトとじっく煮込んで旨味を引き出すのが、世界共通のスープの仕込み方らしく、その用途に適っているのが寸胴なのです。
羽釜で煮込む久留米ラーメンの白濁スープ!
トンコツスープを白濁に仕上げる場合は、炊き上がったまま強い火力で長時間煮込むことで、白濁のトンコツスープになるわけです。これが久留米ラーメンのスープになるのです。
博多ラーメンは澄んだスープで平麺だったのが、白濁スープの細麺を特長にする長浜ラーメンに変わっていき、白濁スープについては、久留米から受け継いで赤のれん系白濁スープとなったのだと思います。
長浜ラーメンが細麺になった理由は、魚市場が長浜に移転してから市場前にラーメン屋台が出るようになったのですね。
その屋台で出したラーメンが、当時の流行だった白濁スープに、市場で働く人たちが短時間で食べられるように、茹で時間が短くてサッと茹でて早く食べられる細麺に変わっていったということらしい。
だから博多トンコツラーメンも、元祖は澄まし系の「三馬路」と白濁系の「赤のれん」に分類されるし、赤のれん系の白濁スープも平麺だけじゃなく細麺も登場したということです。
それもお客さんが市場で働く人がほとんどという、需要に合わせた細麺に変わったのが長浜ラーメンと呼ばれて主流のようになり、博多ラーメンといえば長浜系のラーメンだと、同一視される誤解も生んでいるようですね。
なので順番で言うと白濁とんこつラーメンの系譜は
久留米ラーメンの白濁スープ
⇒博多ラーメンの赤のれん系白濁スープ
⇒細麺が特長の長浜ラーメン
という白濁とんこつラーメンの系統。
もう一つの、澄まし系とんこつラーメンの系譜が
平麺が特長の三馬路とんこつラーメン
⇒五馬路
⇒うま馬
という系統になるのか?
ちなみに、この記事で取り上げた店舗名や考察については、ワタクシやらぽんの個人的見解が含まれており、その起源や根拠については諸説ある・・・・・・かも知れないことをお含み置きくださいね。😅
豚骨スープの豚骨ラーメンの味が、最近は洗練されてきて、美味しいカップラーメンや袋麺も出回っています。
いい加減な味管理の店舗の味を、凌ぐのではないかと感じるくらいのインスタントラーメンも増えてくるだろうから、ラーメン専業店はよほど頑張らないと繁盛店を維持するのは難しくなるかも知れませんね。😅
安くて、早くて、熱くて、美味いラーメン。
いつでも、手軽で、どこでも、美味いラーメン。
それがカップラーメンや袋ラーメンだ。
いやぁ~~いい世の中になったものだ。
ってことで、今回は
「博多ラーメンの白濁トンコツスープは仕込みの失敗が生んだ偶然の産物だって!」という博多ラーメンの白濁トンコツスープのエピソードでした。😄
※見出し画像のイラストは、メイプル楓さんからお借りしました。
では!
ラーメンに 舌つづみ打ち のほほんと
<昨日投稿のサブアカの記事がこちら!>
いいなと思ったら応援しよう!