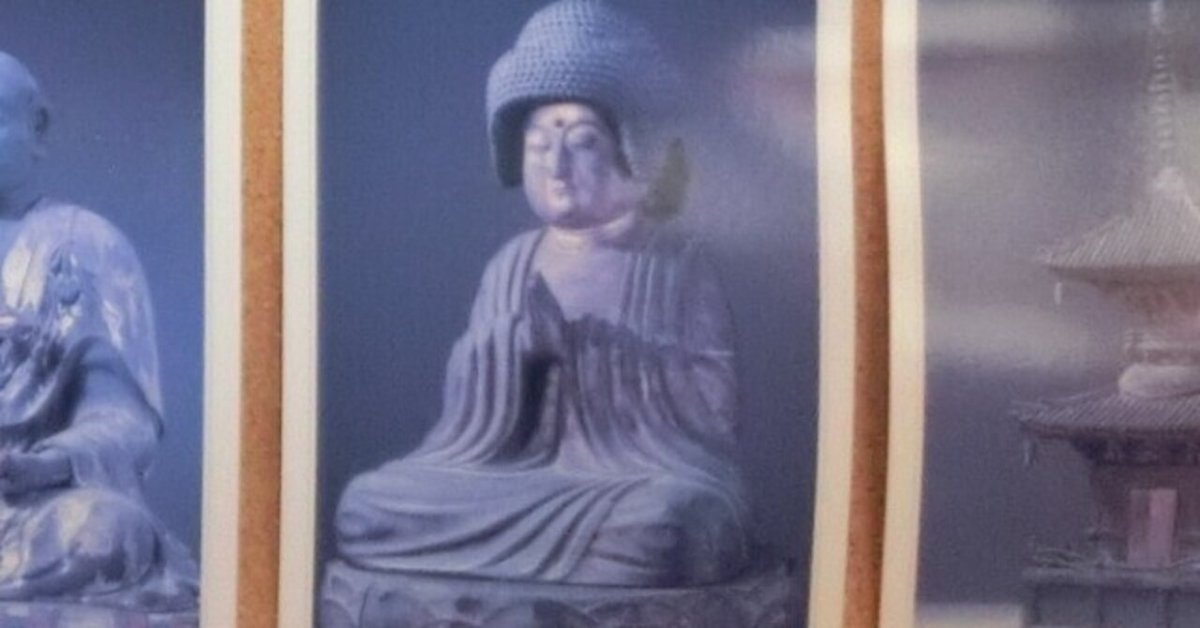
拝見しないと損!アフロ仏!歓喜天「十輪院」石仏龕!両頭愛染明王【奈良まちシリーズ】
前から知っていた国宝の本堂に安置されている本尊は石の厨子!石仏の地蔵菩薩立像!!で、超レア仏像のアフロ仏こと「五劫思惟阿弥陀坐像」がいることを!!!
しかし、それを超える衝撃が!!!!密教では絶対秘仏とする「歓喜天」が普通に2体安置されている!!!!!高野山(私のNOTE)の天野社と京都・石清水八幡宮(私のNOTE)と門戸厄神こと東光寺(私のNOTE)のみだと思っていた「両頭愛染明王像」も・・そして背中を合わせあっている毘沙門こと「双身毘沙門天立像」(纏めている方のブログ)も・・・この仏像たちが揃っているとは。。
ということで、「!」を多用するぐらいビックリし続けた良い寺である!皆さん参拝してください。
2024年2月に行われた『奈良市街地をぶらりと巡る冬のキャンペーン「路地ぶら」』で公開!!
変更履歴
▼HP
▼アクセス
奈良市十輪院町27
▼祭神・本尊と脇時
※後述「▼見どころ」参照
▼見どころ
奈良時代、元正天皇の勅願による寺
遣唐使・吉備真備の長男・朝野宿禰魚養(あさのすくねなかい)の開基
朝野宿禰魚養の母親は唐の国の人だったらしく、国際結婚の走りかも
元は元興寺(私のNOTE)の子院
鎌倉時代には、地獄に落ちた人々を救済する地蔵菩薩信仰が広まり、十輪院は平安時代からの地蔵菩薩像を祀る寺院として一躍脚光を浴びたようだ
本堂@国宝には珍しい「石仏龕(せきぶつがん)@重文」が本尊
「龕」は仏像を納める厨子で、その内部に地蔵菩薩立像、釈迦如来立像、弥勒菩薩立像などを彫っている
不動明王、仁王、七星九曜なども浮き彫りになっている
1283年、『沙石集』では、十輪院は地蔵菩薩の霊場として紹介されている
明治の廃仏毀釈により、宝物を失ったようだが、鎌倉時代のものは、本堂、石仏龕、南門、十三重石塔、校倉造の経蔵がある
元興寺を出て南へ、2本目の角を東に入ると南門。


岐阜県「養老の滝」を命名した元正天皇勅願寺で「元興寺」の子院。右大臣・吉備真備の長男・朝野宿禰魚養(あさのすくね なかい)の開基と言われる古寺。
「本堂」は国宝で、「護摩堂」には不動明王@重文が安置されている。最後に、「興福寺曼荼羅石」というものがある。この曼荼羅は興福寺(私のNOTE)の諸堂に安置された仏さまや五重塔などを描いたもので、石に彫ってあるのが面白い。

→南門@重文
本堂の正面に建つ表門。って、重要文化財だったんだ・・。


→本堂@国宝
本堂は国宝で、内部にある石仏を拝むための礼堂として建立。本尊内部の本造は石仏で中央に「地蔵菩薩」脇侍に「弥勒菩薩」「釈迦如来」の三尊形式で珍しい。基本、期間限定の公開である。
元興寺(私のNOTE)というよりも、唐招提寺(私のNOTE)や秋篠寺(私のNOTE)の本堂に似ている。

本堂は本尊が安置されているところで、手前を増設したようで国宝なんだそうな。拝観すると説明が聞けます。



https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/123507

本堂の天井は低く、圧迫感を感じるが、ホットカーペットが温かい!?この本堂は本尊が居るところだけだったが、鎌倉時代に平安貴族のツクリのものを増設している。つまり、拝むところは増設部分ということになる。
ブルーノ・タウトもビックリしただろうな~。わかるわ~。
ドイツの著名な建築家ブルーノ・タウト(1880-1938)は、1933年より1936年まで日本に滞在し、その間多くの日本建築を見て回り、日本美の素晴らしさを世界に広めました。中でも桂離宮を称賛しました。十輪院については彼の著作『忘れられた日本』(中公文庫)の中で、「一般に外国人は、官庁発行の案内書やベデカーなどに賞賛せられているような事物に、東洋文化の源泉を求めようとする。しかし奈良に来たら、まず小規模ではあるが非常に古い簡素優美な十輪院を訪ねて静かにその美を観照し、また近傍の素朴な街路などを心ゆくまで味わうがよい。」と述べています。

→本堂・本尊「石仏龕@重文」
拝観すると説明が聞けます。
元々、石仏龕は外にあり、後に本堂ができる。のちに拝む場所・覆屋として増設し、本堂と覆屋を結ぶ場所が出来たようだ。つまり、神社でいえば本殿を守る覆屋が本堂という感じだな。
石仏龕@重文の中尊は「地蔵菩薩立像」。左右の石材にが浮き彫りの釈迦如来立像と弥勒菩薩となっており、過去・現在・未来となるので、吉野の蔵王権現や、如来三尊(過去:薬師如来、現世:釈迦如来、未来:阿弥陀如来)と同じですね。
本尊は、釈迦が亡くなり弥勒にバトンタッチをするまでの間、人々を救い続けた地蔵を安置している。そのほかには仁王、聖観音、不動明王、十王、四天王など仏様が彫られ、極楽浄土を願う地蔵菩薩の世界を表しているよう。説明では「六道」というキーワードが出てきましたね。
地蔵菩薩の横壁の「十王」は、地獄で死者を裁くときの裁判官で、お偉いさんは有名な「閻魔王」で、地蔵菩薩が姿を変えた存在と考えられている。
石仏龕の上部には北斗七星、九曜、十二宮、二十八宿の星座を意味する梵字がある。十二、二十八とあるので28部衆も関わっているのかなと思って質問したが、それは関係ないとのこと。
石仏龕前には、死者の棺や遺骨などを安置する「引導石」という石が置かれており、何回かは貴族や皇族で使ったのではないかとも言われているようだ。
→そのほか仏像「アフロ仏」「歓喜天」「両頭愛染明王」
本尊の説明が終わり、私の気持ちはアフロ仏の説明を期待するが、それでは、あちらのケースにも宝物があるので、どうぞと言われて説明が終わる。 もしや、アフロ見れないのか・・?

そして指示された方に行くとアフロ仏(https://jurin-in.com/img/img_butsuzo01.png)がいた!!!!おお~東大寺のアフロ風味だ!大きさはないけど佇まいは5本の指に入るアフロ仏である。
次の瞬間、私は大きな声を出す。「おお~歓喜天や」と。そう、密教ではお馴染みの歓喜天は絶対秘仏とするところがほとんどである。たまに歓喜天とあるので見ると、十一面観音とかでありガッカリする。6月6日のみ歓喜天公開する寺(こちら)があるが、ここは常時、見仏できそう。いや~びっくりした。。
そして、その横に「双身毘沙門天」が。。2回目だ・・・。また、「両頭愛染明王坐像」である。愛染と不動は一体のものとする考えから生まれたもので、「高野山・天野社(私のNOTE)」と京都「石清水八幡宮(私のNOTE)」と「東光寺(門戸厄神)(私のNOTE)」だけだと思っていたが、ここにもあるとは・・。他のNOTEに追記だな・・。
→境内


下の写真の通り河童がいる。詳細は寺のパンフレットと説明書きですね。南門のところにありました。



庭園には多数の石仏があり、鎌倉時代の「石造不動明王立像」が見どころ。本尊も昔はこんな感じで安置されていたんでしょうね。




境内にある「護摩堂」には不動明王三尊が安置されている。
中尊は「不動明王」で、脇侍は「矜羯羅(こんがら)童子」と「制多迦(せいたか)童子」のようです。




▼メディア情報
これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。
▼旅行記
▼セットで行くところ
#アフロ仏
#歓喜天
#十輪院
#石仏龕
#両頭愛染明王
#奈良まちシリーズ
#国宝
#地蔵菩薩
#五劫思惟阿弥陀
#双身毘沙門天
#奈良市
#朝野宿禰魚養
#沙石集
#ブルーノ・タウト
#神社仏閣
#やんまあ
#やんまあ旅行記
#旅行記
#やんまあ神社仏閣
#仏像
#わたしの旅行記
#一度は行きたいあの場所
#人文学
#奈良
#奈良シリーズ
#奈良まちシリーズ
#旅行・おでかけ
