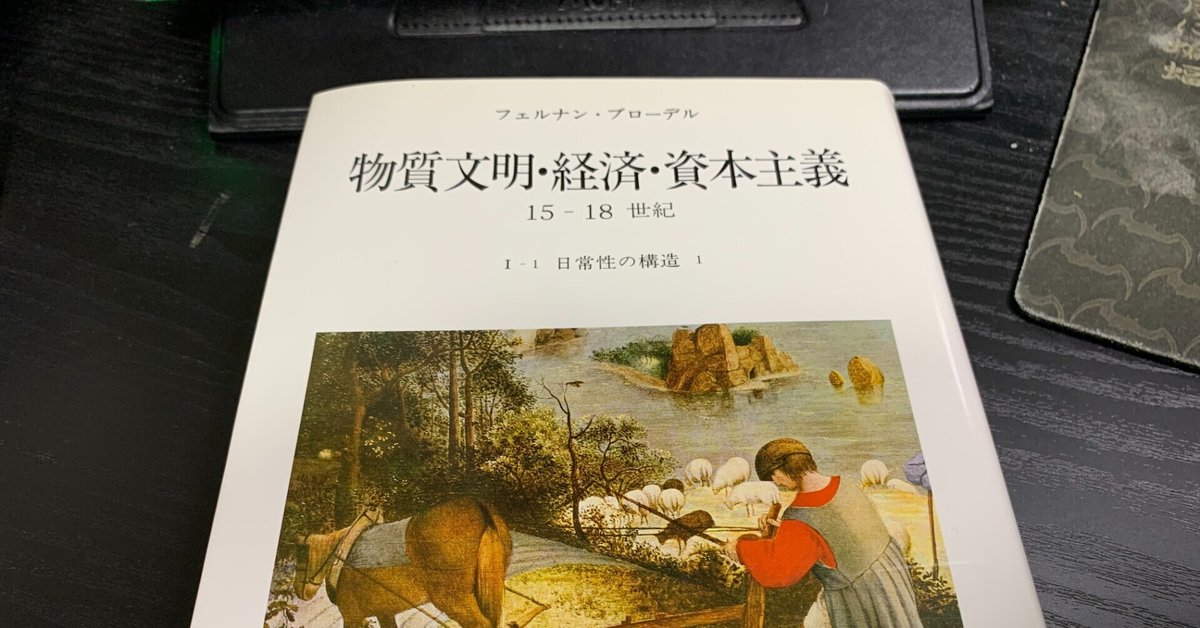
交換のための言語としての貨幣。ブローデル『物質文明・経済・資本主義』を読む(15)
ブローデル『物質文明・経済・資本主義』の読書会第14回のメモ。第1巻の第2分冊。第7章「貨幣」のうちの冒頭と「不完全経済と不完全貨幣」「ヨーロッパの外側では ――揺籃期における経済と金属貨幣」を中心に読みます。
摘 読。
今回から、貨幣をめぐる思索へと進む。
貨幣を問題にするというのは、上の階に登ることである。ただ、そこから全体を眺めてやると、貨幣がいくらか動きの早まった交換生活にとって、道具であり、構造であり、これを根底から規制するものであることがみえてくる。貨幣はどんな土地においても経済的・社会的関係に組み込まれていた。それゆえ、すぐれた《指標》として役立つ。
貨幣に門戸を開いた社会は、すべていつかは既得の均衡を失い、国内の諸力に対する統制が効かなくなって、それらの力が野放しになった。新しいゲームが始まって、ごくわずかな幾人かが特権的な地歩を得るとともに、あとの人は弾き出されて、ツキの悪さをかこつことになった。ただ、貨幣が社会経済のすべてに浸透しているかどうかは、時代や地域によって異なる。しかし、多くの場合、いずれは貨幣による交換へと巻き込まれざるを得なかったのも歴史的な事実である。ともあれ、貨幣はある特定のところに集積し、それに与れない民衆は恒常的に不信感を抱いていた。初期の経済学者たちも、貨幣に不信感を抱いていた。
では、どのような状況で貨幣経済は根づいたのか。まず、人々が貨幣を必要とし、そのための出費に耐ええた地域に限られていた。経済にはさまざまなリズムや体系、状況があり、それだけの数の貨幣や貨幣体系が生まれた。それは、あるひとつのはたらきのなかで万事がたがいに関連しあっている。それは、〈交換〉である。もともとは不完全貨幣であったのが、紙=信用貨幣へと進んでいった。この点において、貨幣は言語である。貨幣は対話を求め、それを可能にする。貨幣は対話が存立する度合いにおいて存立するに過ぎない。そして、交換の範囲が広くなる、つまり国や地域を超えた交換が増えてくると、貨幣による対外政策も生じてきた。遠隔通称ないしは大規模商業資本主義の功績は、世界的規模における交換のための言語を話すことができた点にある。それらの交換は〈旧制度〉の世界を導き、貨幣がそれらの交換に奉仕した。交換が経済の方向を定めたのである。
不完全経済と不完全貨幣
商品の交換が始まったとたんに、貨幣の発する片言がたちまち聞こえ始めた。いちだんと欲しい商品、あるいはいちだんと豊富にある商品が、貨幣の、つまり交換規準の役割を果たすか、果たそうとした。アフリカにおいては、地域によって異なるが、塩や木綿、銅の腕輪、砂金、馬、貝殻、さらにはなぜかトスカーナで加工された珊瑚などが貨幣と同じ役割を果たしていた。アイルランドでは干魚であったり、ロシアでは毛皮であったり、北米の植民地ではタバコや砂糖、カカオ、貝殻玉などが用いられたりしていた。
このような「貨幣」の利用と同時に、ヨーロッパにおいても貨幣経済と並行して物々交換という初歩的経済は生き延びていた。これは、アダム・スミスの頃においてもそうであった。17世紀や18世紀になっても現物支給というのは頻繁に行われていた。大市ではそういった商品の為替手形の決済がなされていた。金額としては大きくても、扱われている金貨それ自体はわずかなものだったのである。
ヨーロッパの外側では ――揺籃期における経済と金属貨幣
ここでは、ヨーロッパ以外での貨幣経済の展開が概観されている。対象となっているのは、日本とトルコ、インド、そして中国である。
日本とトルコ帝国
ここのところでの日本についての記述には、ちょっと疑問もある。日本では金貨・銀貨・銅貨の流通が多くの大衆にとって関わり合いがなかったと述べられているが、少なくとも室町時代には宋銭などが流通していたのは事実だからだ。それはひとまず措くとしても、米が貨幣として幅を利かせていたというブローデルの認識は誤ってはいない。ただ、ブローデルが指摘するように、江戸時代が進むにつれて、貨幣経済が幕府・商人・都市という三重構造に入り込んでいった。実際、柳沢吉保と荻原重秀による元禄改鋳などは、貨幣経済が深く入り込み始めていたことの証左の一つであろう。
一方、イスラム圏で貨幣経済が発達して利益を得たのは、活気ある十字路に位置していたペルシア、オスマン帝国、そしてイスタンブールであった。ことにイスタンブールの通貨が、バスラやバグダード、モスル、アレッポ、ダマスカスを経てエジプトやインド諸国まで影響が及んでいた。それらの都市にはアルメニア商人の居留地があって、貿易を振興していた。ただ、その貨幣価値は下落していった。そこで、トルコ帝国は外国貨幣を両替を通じて取り込んでいった。しかも、取り込まれた外国貨幣はすべて造幣局で鋳直さなければならなかった。
インド
インドでは、紀元前から金貨や銀貨がすでに用いられていた。その後、13世紀、16世紀、18世紀と貨幣経済の膨張があった。ただ、それは完全かつ全国統一的なものではなかった。北部では銀貨と銅貨の併用が、南部では金貨がメインで銀貨と銅貨が貝殻貨幣を補うものとして用いられていた。ただ、インドではこれらの貨幣の素材はほとんど産出されなかった。他国の貨幣が閉ざされることのない門戸を潜り抜けてきて、インドの貨幣原料の大部分を供給した。全世界の貴金属がムガル帝国とその支配下にある諸国家とのために、組織的に吸い上げられつづけた。
ただ、そのためにインドは果てしなく支払いを続けなければならなかった。それゆえに、インドの民衆は生活苦に悩まされることになったし、同時に素の補填のために産業が飛躍もした。たとえば、グジャラート州の織物業はインド経済にとっての推進装置として役立った。18世紀にはインド更紗と呼ばれる木綿織物が商人たちによって大量に輸入され、ヨーロッパを席捲することになった。
このようにインドの貨幣は、他からの流入によっていたがゆえに、遠隔操作されていた。それゆえに、貨幣事情が混乱をきたすこともあった。
中 国
中国それ自体が大きな塊であるが、中国と連繋し、また中国に依存する諸々の近隣原始経済からなる世界の中央に据えて考察する必要がある。ただ、マラッカやスマトラ島西端、ジャワ島のような貨幣経済がいくらかなりとも発達した例外もあった。
その点で、中国において貨幣経済が大きく発達することはなかった。しかし、元朝における紙幣の発明は大きな革新であった。外国の商人は元に入る際にそれぞれの現金を紙幣と両替せねばならず、出国の際にその現金は返却された。ただ、それが元朝であったために、明朝以降においては忌避されることにもなった。
中国において上層階で幅を利かせたのは、銀の延べ棒であった。特に、大規模な交易には銀が欠かせなかった。そして、その銀の延べ棒は鋼鉄のはさみで必要な分だけ切って渡されていた。この銀は、政府の決定や措置によってその流通量が操作され、それによって物価も操作された。ただ、一般的には銅銭が用いられていた。その意味で、銀=銅複本位制であった。その両替率は日や季節、年によって変動し、政府の放出量によっても変動した。一方で、18世紀の広州ではヨーロッパとの通商によって、貨幣革命と信用革命が古来の経済に浸透していき、物価の上昇ももたらした。
私 見。
われわれの生活が交換によって可能になっている以上、どのような現象形態を採るにせよ、交換媒体として、また共約(通約)を可能にする評価尺度としての貨幣が不要になることはない。ただ、同時にすべてがいつも貨幣を通じて交換されるとも限らない。ブローデルは、これを原始的な経済と位置づけている。近年しばしば注目される“使用価値重視”なる発想は、ここへの回帰ともみることができよう。私は、こういった貨幣を用いない交換を否定しないし、ネガティブにも位置づけないが、それを一般化することが果たして好ましいことなのかどうか。むしろ、コミュニティ参入が難しい人たちが、かえって困窮する危険性さえある。かといって、貨幣経済があれば、困窮の問題が解決するというわけでもないのも事実である。
となると、われわれは交換という事態から逃れられないこと、そこには評価の差が生じること、そしてそれを測定するために貨幣が生まれること、その評価の差を利用して収益を獲得しようとする者が出てくること、この一連の事態をまずは冷徹に見定めることが先であろう。そして、この評価の差を利用して収益を獲得しようとする者こそ、カーズナー(Kirzner, I.)が注目したさや取り(arbitrage)をめざすEntrepreneurなのである。
この点は、おそらく次に読むところでも出てくるのではないかと思うが、それは次回にしよう。
そういえば、ルーマン(Lumann, N.)は経済というシステムを捉える際に、貨幣、そしてそれによってあらわされる価格を軸にして、社会システム理論的に捉えようとしたのであった。
このなかで、ルーマンはコミュニケーション・メディアとしての貨幣という章を設けている。これもブローデルが貨幣を交換のための言語として捉えようとしていることと通じるようにも思う。
いずれにしても、貨幣がどういう文法を持つ言語なのかを歴史的に捉えることは、即断的な浅慮を避けるためには、一つの大事なアプローチであるとはいえるだろう。
