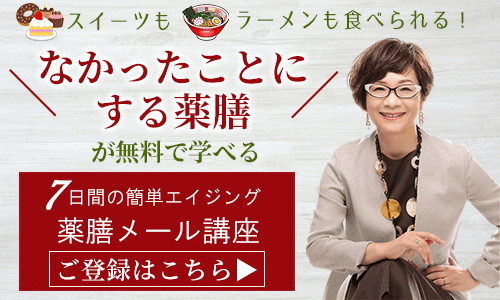一番簡単で身近な薬膳は?
洋食や中華では、肉の骨やスジから取ったフォンドボーや鶏の骨から取った鶏ガラだしなどがあります。
和食の出汁は、乾物を使ったものがメインで、代表的なものはかつお出汁、昆布出汁、いりこ出汁などです。
海に囲まれた島国なので、昔から天日干ししたり干した上に発酵させたりして保存食として使ってきたものですね。
先人の知恵に感謝です。
なぜなら和食を作る上でなくてはならないものになっているからです。
薬膳では、全てのものに体を温めたり、こもった熱を冷ましたりという性質と、それぞれに効能があると考えます。
効能は栄養学のようなものですが、成分で言うのではなく全体で言うため食べる量を何グラムという数字で表しにくいところが特徴です。
ただ、家庭で母から子供へと伝えやすいのも特徴。
例えば、私も幼い娘にレバーを食べさせる時「これを食べると白雪姫みたいに、ピンクのほっぺで可愛くなるよ。」というように、鉄分が豊富だから食べると貧血予防(薬膳では補血)になることを伝えたことがあります。
あながち嘘ではない(笑)この場合娘の容姿は問いません
(笑)
出汁にも、性質や効能があると聞くと驚かれることがあります。
それほど日本人には身近で、いつも使っているものを「うちは〇〇出汁。主人の実家は〇〇出汁」のように各家庭の好き好きだと思っているケースが殆どなのです。
ですが、実はその時の体調や天気などによって出汁を変えれば、それが一番簡単な薬膳になります。
ここでは代表的な鰹出汁、昆布出汁、いりこ出汁について書いていきます。
風邪をひいて寒気がする時、サラサラの鼻水が出る時。
鼻がつまってドロッとした黄色の鼻水が出る時では出汁を変えることで、楽になるのが早まるかもしれません。
鰹だしの特徴とおすすめの使い方
鰹は体を温めも冷やしもしない平性です。
伝統的な作り方は、一匹の鰹を三枚におろし、それをさらに背中側と腹側の二枚に分け、それぞれを茹でてから燻製にしたものが、荒節(あらぶし)です。
スーパーで見かけて一般的に家庭で買う「花かつお」は、この荒節。
荒節の表面をきれいに削り、上にかつお節菌をつけて発酵させた後、天日干し、更にかつお節菌をつけ天日干しと何度か繰り返してできたものが、本枯節です。
下の写真のような塊の鰹節が本枯節ですが、最近は家庭ではあまり使われず貴重品ですね。
荒節は鰹の風味と燻製の風味が特徴で、本枯節はスッキリした旨みが特徴。
料亭など出汁にこだわる場合は本枯節が使われます。

いろいろランクがあり鹿児島県(枕崎・指宿)や静岡県(焼津)が主な産地です。
生の鰹は体を温めも冷やしもしない平性ですが、燻したり発酵しているので身体を温める性質になります。
中医学の体の構成要素「気・血・津液」の「気」や「血(けつ)」 を補い胃腸を丈夫にする効能があります。
簡単に言うと、疲れた時や病み上がりなどの体力が落ちている時に必要な栄養が含まれていると言うことです。
風のひき始めや花粉症で透明でサラサラの鼻水がとめどなく流れるのは、体が冷えている現れです。
こんな時は、鰹出汁がおすすめになります。
朝、味噌汁が作れなければ、温かい出汁だけを飲んでも良いのです。
鰹節エキスが十分に出汁に抽出されています。
味が欲しければ、塩を一つまみ入れるか味噌を少し溶かして具無しの味噌汁に。寒さを感じる時に飲んでみてください。
次に昆布出汁です。
昆布出の特徴とおすすめの使い方
昆布をはじめとする海藻類は体にこもった熱を強く冷ます性質です。
産地の90%が北海道でその他は青森、岩手、宮城などの三陸沖になります。

乾燥させて売られていますが、ヌルヌル成分を持っていて、これは水溶性食物繊維。
身体に溜まった余分なものを絡め取って排泄させます。
薬膳で言われる昆布の効能は、体に溜まった余分な水分が体温や食べた物(主に、揚げ物、アルコール、コッテリしたもの)、ストレスなどで熱化され、粘度を増したものを溶かして排泄させるとされています。
現代人は、美食やストレスで粘度を増したドロドロ成分(私はどぶの水がjヘドロになったと説明しています。笑)を溜めている人が多いのです。
そのため、適度に昆布を食べるか昆布出汁を使うことをおすすめします。
風邪や花粉症で鼻がつまったり、ドロドロで粘る鼻水が出る時は炎症が起こっているので、体に熱があると考えます。
その場合は、熱をさらに加える揚げ物やアルコール、スパイス、唐辛子やにんにくなどは避けて昆布を摂ることをおすすめします。
昆布の注意点
昆布については、注意点があります。
含まれるヨウ素は、人の体に不足しても多すぎても良くありません。
女性に多い甲状腺疾患の方は、主治医と相談して摂るようにしてください。
昆布そのものは食べてはいけなくても、昆布出汁なら摂っても良い人もいるようです。
いりこ出汁の特徴とおすすめの使い方
いりこは別名煮干し。
小さめのかたくちイワシを煮て干したものを言います。
中には、マイワシ、うるめイワシなども混ざっていることもあるようです。

イワシ自体は、体を温める性質で「気」「血(けつ)」を補い、またサラサラにする効能があります。
これは、イワシだけでなく、鯵やサバなどの青背の魚全般にも言えることです。
齢を重ねると記憶力も怪しくなってきますが、脳への血流アップが期待できるため、脳を活性化させて健忘症予防にもおすすめです。
出汁を取る時は骨ごと煮るため、骨のエキスも摂ることができるのがエイジングケアに良いと言われるところ。
薬膳では、骨や筋肉にもよいという強筋骨の効能もあります。
日本の中でも関西は水が柔らかく軟水気味、関東は関西に比べると硬い水です。
そのため、出汁文化では関西が昆布出汁文化なのに対して、関東はいりこ出汁文化だとも言われます。
これは、昆布は軟水の方が良くエキスがでるのと、関東では硬い水に対して煮干しのパンチのある出汁が合うとも言われています。
単独で出汁を取るより合わせ出汁にすると良い理由
以上が代表的な出汁の特徴と使い方でしたが、よく「合わせ出汁」と聞きませんか?
複数の材料を合わせて取る出汁が「合わせ出汁」です。

昆布と鰹の合わせ出汁は有名ですが、スーパーなどの市販の出汁パックには、その他に干し椎茸が入っていることもあります。
合わせ出汁にすると良い理由を薬膳と旨み成分という二点から解説します。
薬膳の視点から合わせ出汁にすると良い理由
薬膳の視点からは、例えば昆布出汁だと体が冷えている人には不向きですが、家族の中に体が冷えてサラサラの鼻水が出ている人と鼻がつまっている人がいたら、どちらに合わせたらよいかと迷ってしまいますよね?
そんな時は昆布と鰹の合わせ出汁にしましょう。
両方のいいところ取りができます。
温めるか冷やすかで言えば、両方を使っているので冷やす性質が緩和されます。
効能で言えば。鰹のパワーや血(けつ)を補う効能にプラスして、体に溜めているドロドロのヘドロを出す効能、両方を兼ね備えているのです。
更年期世代以降の女性は、必要なパワーや血(けつ)は足りなくて不要なヘドロを溜めている人が少なくありません。
そのため、最も簡単に更年期世代が取り入れられる薬膳は、合わせ出汁と言うことになります。
ここに、いりこもプラスしたら、血巡りにもアプローチできて、これから弱って来る足腰の衰え予防にもなるのです。
このように「合わせ出汁」には、一つの食材の性質をプラスマイナスゼロにしたり、その食材にはない効能を加えて、「出汁」に栄養を集めることができるという利点があります。
旨み成分の点から合わせ出汁にするとよい理由
鰹節、昆布、いりこがなぜ出汁として使われるかと言えば、旨み成分が含まれているからです。
鰹節にはイノシン酸。昆布出汁にはグルタミン酸。いりこ出汁は鰹節と同じイノシン酸が含まれます。
ちなみに干し椎茸の出汁はグアニル酸と言います。
旨み成分は、一つだけの時より複数を合わせた方が格段においしくなるのです。
二つの鍋を用意して、一つは合わせ出汁、もう一つはどれか一つの出汁で具も味噌も全く同じもの、同じ量で比較してみてください。
合わせ出汁の方が美味しく感じるはずです。
わが家は通常、鰹出汁か昆布出汁をその日の天気や体調で使い分けていますが、合わせ出汁にすると家族が「いつもより美味しい。味噌を変えた?」と言います。

味噌は変えていなくて出汁が合わせ出汁にしただけです。
まとめ
出汁一つでも、簡単な薬膳になるのは、食材一つ一つに性質や効能があるからです。
今回だ代表的な三種類を解説しましたが、一つ一つを目的に合わせて選んだ出汁は、最も簡単な薬膳です。
朝起きてお白湯を飲む人もいると思いますが、お白湯を出汁に変えるだけで栄養もアップしますし、体調にも影響してくることが期待できます。
鰹出汁を取るのが面倒でしたら、コーヒーフィルターを使って上から熱湯をかけるだけでも即席出汁になりますし、パックの花かつおをお茶パックに入れて鍋で沸騰させてもいいのです。
昆布は前の晩から水に浸けて一晩置けば、昆布水ができています。
料理人さんから見たら、「そんなのは出汁ではない。」と言われるかもしれませんが、まずは出汁を体調に合わせた薬膳として取り入れるところからやってみてはいかがでしょうか?
【関連記事】
▼この記事を書いた人▼

なかったことにする薬膳が学べる7日間の無料メール講座を配信中です。下のバナーをクリックしてお申込みください。