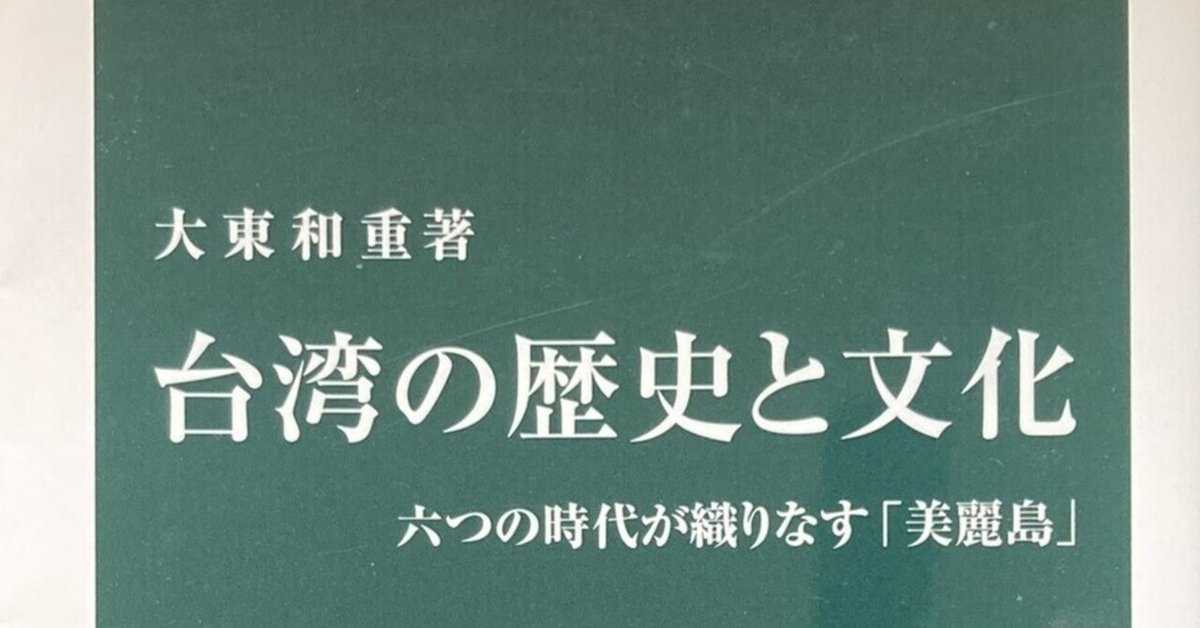
歩いてみたくなる古都の風景『台湾の歴史と文化』大東和重
最近、台湾について読みやすくて専門的な本が入手しやすくなりました。読者としては単純にうれしいです。そして、大東先生の本もまた、そんなすばらしい読書体験でした。サブタイトルの「6つの時代」ってなんだろう?と思いましたが、なるほどの構成です。
九州ほどの面積に、関西2府4県ほどの人口が住む台湾。このフレーズが全6章のそれぞれで繰り返されるので、日本の読者はイメージしやすいです。そして、台湾の基礎知識や、中国文化とのつながりも、だいたい繰り返されるので、興味ある章のどこから読んでもいいところがうれしいです。
1,台湾の先住民
2,平埔族とオランダ統治
3,港町安平と鄭成功
4,古都台南に堆積する清朝文化
5,日本植民地時代の壁と共存
6,国民党の独裁と民主化運動
重なる部分もありますが、一応、台湾の歴史と文化について、6つの切り口で語られる章は年代順になっています。そして、それぞれの時代をつなぐ物語は日本語で書かれたもの。植民地時代の台湾に赴任したり、親の仕事の都合で台湾で生まれた人たちが、台湾の人々と暮らしていく中で、より台湾を知るために、考古学や民俗学、文学などをベースに残した記録をたどります。
海が荒れているからと云うのを無理に頼んで、僅かの間上陸さしてもらう事になり、憧れの小舟にゆられて島に向かった。赤黒い皮膚のloin-choth(ふんどし)一つの島人が彼らの共有の舟を彼らの手製の櫂で漕ぐのである。彼らは岩礁の間をうまく操って、波浪の猛烈なしぶきを全身に浴びながら、僕たち数人の上陸者を島に上げてくれた。造礁珊瑚の間をぬう危険な、しかし爽快な陸あげ作業をすませると、彼らは又本船に引きかえしていった。
大東先生は、多くの人の記憶や台湾で制作された映画などの断片をつなぎ合わせて、私たちに万華鏡のような物語を見せてくれます。かつての日本人が見た台湾の風景、異国の町並みの記述が、まるで街歩きガイドのように、地図や写真、時代背景の説明を添えて、テンポよく紹介されます。食べ物も、もちろんおいしそう。この本の副読本というか、写真資料集(兼地図)を出してもらったら絶対に買いです。
豆を使った甘いものといえば忘れられないのが豆花である。ちょうど午後のおやつ時分に、天秤棒を担いで売りに来る。前と後ろに下げた桶はなにか保温の仕掛けがしてあった。底に炭火を入れる二重構造にでもなっていたのだろうか。中身はいつもほかほかしていて、蓋をとるとふわっと温かないい匂いがする。デザート用の豆腐といってもいいようなもので、白くとろりとして豆腐よりずっとやわらかい。おたまですくって皿にとり、蜂蜜とザラメを煮たような蜜をからませて食べる。
なにより、古都台南や港町安平からながめた台湾の記述は、とても新鮮です。本書に登場する日本人の多くは、日本人のエリートコースに乗れなかった人たちですが、だからこそ、どんなふうに台湾で仕事をするようになったか、地元の人たちとどんなきっかけで知り合い、台湾に惹かれていったのかが、くわしく書かれています。
そして、あたりまえですが、台湾の歴史は日本とのつながりだけではありません。歴史的にスペインやポルトガル、オランダとの関係も大事。とくに、オランダが台湾を経営したときに、台南周辺の原住民を支配し、対岸の福建省から漢族(中国人)を移住させて、稲作やサトウキビの生産を始めたことが、その後の中国大陸からの大勢の移民につながりました。今では漢族が台湾の人口の9割を占めます。
現在の台南の水仙宮は、古めかしい、ごみごみした街中に立っているが、創建当時は、厦門にあるものなどと同様に、廟前近くを海水が洗い、船舶の集まる所となっていた。赤や青の戎克(ジャンク)船が、彩帆を降して停泊するほとりに、廟の高い甍が、その影を映じていたのである。されば、黒水溝の難航を凌ぎ、鹿耳門の険を越えて、はるばると台陽(台南の古称)に来着した旅人等は、その第一印象として、先ず、此の廟を脳裡に止めたものが多かったであろう。
人が来ると、神様もやってきます。航海の女神媽祖や、学問の中心になる孔子廟。台南では英雄鄭成功も神様になるし、いろんな人達が祀られます。ごみごみした裏通りの活気ある様子や、原住民の神様を調査して山歩きする研究者たちの話は、とてもいきいきしていて、だけど失われてしまった文化もあって、ニンゲンたちの営みが堆積する台湾を感じます。
日本人が去ると、今度は中国大陸から大勢の兵隊がやってきて、それから毛沢東の共産党軍に敗けた人々がやってきます。理不尽な状況を打開しようとした人たちは処刑され、居場所を失った人は日本に亡命しました。そして、自分や親兄弟、そして友人たちの無念を日本語でつづりました。占領者の中にも、「自由」を目指して逮捕された人たちがいました。
ようやく戒厳令が解除されたのは、1987年。その後、民主化が進んだ台湾。台湾海峡をはさんだ中国との関係は難しいままですが、経済も文化も大きく成長しただけでなく、対立の形もより複雑に変化しています。現在では、新しく東南アジアからやってきた人たちが、台湾で結婚したりして、より多様な社会になりつつあるようです。
そんな台湾の歴史や文化のガイドとして、本書巻末の付録「読書案内」は充実の内容。入門書から事典、歴史、自伝・回想、台湾歩きガイドまで、かゆいところに手が届く1冊です。おすすめ。
