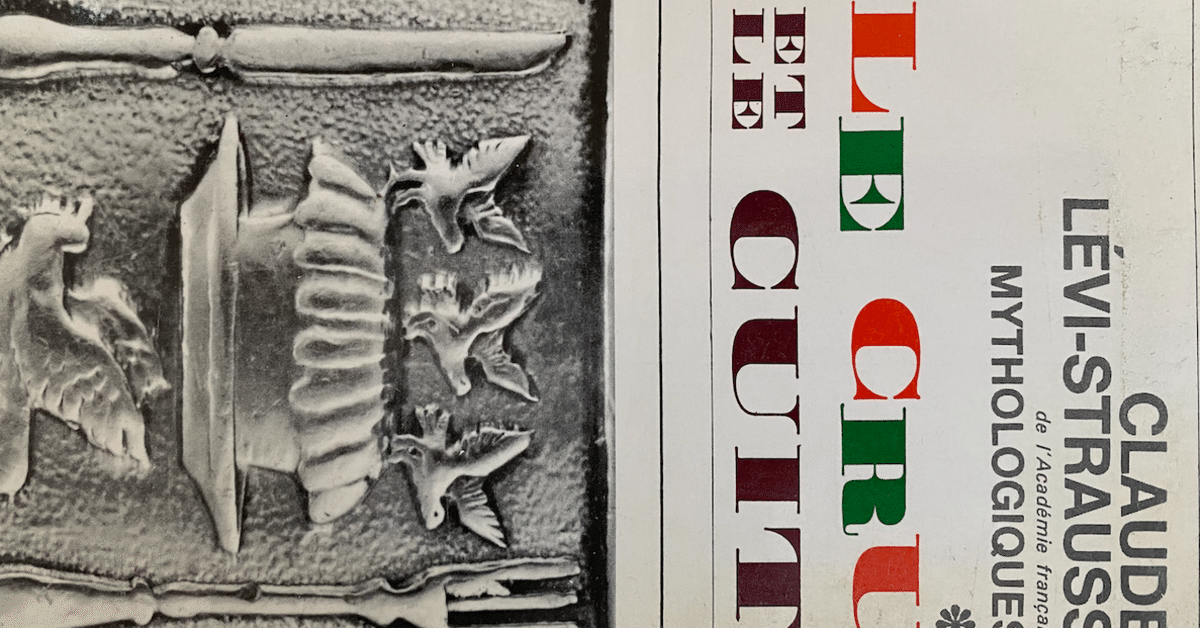
クロード・レヴィ=ストロース著『神話論理』の奥深い世界 ー神話の発生メカニズム
(このnoteは有料に設定していますが、全文無料でお読み頂けます)
♪
クロード・レヴィ=ストロース氏の大著『神話論理』は時々手に取っては何度でも読み返したい一冊である。否、五冊である。
レヴィ=ストロース氏といえば、いわゆる構造主義の火付け役として有名である。レヴィ=ストロース氏は1908年に生まれ2009年に亡くなられている。1908年は明治四十一年、第二次桂内閣成立の年であり、愛新覚羅溥儀が清の「ラスト・エンペラー」宣統帝として即位した年でもある。この数年後1914年には第一次世界大戦が始まるという、まさに激動の20世紀が蠢き始めようとしている時であり、レヴィ=ストロース氏もまたその後の歴史の流れに飲み込まれることになる。
※
ユダヤ系であるレヴィ=ストロースは、ナチスドイツに占領されたフランスからアメリカに亡命することになる。レヴィ=ストロースはこの亡命の旅での経験を『悲しき熱帯』に記し、今日の読者である私たちにもありありと追体験させてくれる。
レヴィ=ストロース自身によって描かれた亡命の旅は、「熱帯」の中を移動する物語である。
そこで「熱帯」は人類学者としてのレヴィ=ストロースにとっての研究"対象"(研究者の外部に、研究者自身とは本質的に無関係に、それ自体としてあるべきもの)でもあると同時に、あるいはそれ以上に、彼自身を媒介し変容させた通過儀礼のフィールドであるとも言えるかもしれない。
生と死、死と生
旧世界と新世界、ヨーロッパとアメリカ
文明と野生、人間と動物
神話では、こうした二つの「極」の「あいだ」を移動しながら、あちらに行ったりこちらに行ったりする"トリックスター"たちが活躍する。トリックスターたちは、二つの極のあいだで両義的な媒介者として立ち回り、二つの極が近づき過ぎればこれを引き離し、離れ過ぎればこれを近づけては、つかずはなれずのいい関係を保とうとする。
神話の思考は、二つの極のどちらか一方を排他的に選択するというシロモノではなく、二つの極のどちらでもなく、どちらでもある中間の領域を保ち続けようとする。そうすることで二つの極の双方をそれとして存在させる。
大西洋を水平移動する一隻の船、避難民を満載した船と、その船が辿り着いたカリブ海に浮かぶ小さなフランス植民地マルティニーク島での危険な足止め。これはどちらも、そうした二つの「極」の「あいだ」を分離しすつ結びつける媒介項のようである。
船と島は、どちらも空気と水の境界としての水面に浮かぶ中間的な何かである。一方は動いている中間的な何かで、他方は止まっている、ちょうど「波」のような中間的な何か。
生死どちらに転ぶかわからない、なんともあやうい曖昧な時空間の旅が、この「動」と「静」の境界、水と空気の境界を開いていく。
このモチーフは、後にレヴィ=ストロースが『神話論理III』で詳しく取り上げた「カヌーに乗った太陽と月の旅」の神話を思わせる。
「カヌーに乗った太陽と月の旅」については下記のnoteに書いたことがあるのでご参考にどうぞ。
◇
さて、『神話論理』である。その厚さを前に「読む」という営みの広大さと、それに捧げることのできる人生の短さに目眩がする書物である。

なおこの四巻(五冊)を読めば終わりというわけではなく、『やきもち焼きの土器づくり』と『大山猫の物語』と『仮面の道』という続編が続いていく。

♪
なぜこれほど分厚いのか?
それはこの本が、ある基本的な操作を繰り返し繰り返し、反復するからであり、どこかで「おわる」必要がないからである。その基本的な操作は反復されながら少しづつその動き方を変容させていく。その反復は終わらない。どこかで不意に一旦停止することもできるが、気がつくとまた再開しているという具合である。
例えるならそれはレヴィ=ストロース氏があるところで書いているように、ラヴェルの"ボレロ"のような具合である。
『神話論理』はなにか結論なるものに向かって一直線に進む本ではない。あるいは頂上に向かって一段一段階段を上っていく本でもない。『神話論理』は、それが本である以上、そのテキスト自体は一列に並べられていくが、その線形性は仮の姿である。その正体はぐるぐると回りながら螺旋状の痕跡を残していく動きである。ある地点でぐるぐると回転運動をはじめ、いつの間にか別の場所で回っていたかと思うと、また元の地点に戻っていたり、戻っていなかったりする。どこにも向かわず、はじめから終点はないし、そもそも始点もない。
レヴィ=ストロース氏は大著の『神話論理』を、日々慣れ親しんだ音楽を奏でるように綴っていったらしい。レヴィ=ストロース氏自身、神話と音楽をむすびつけて考えている。人間において音楽が発生するメカニズムと、神話が発生するメカニズムは、同じであると考えられる。この辺りの話は中沢新一氏の『レンマ学』が参考になる。
『神話論理」の第一巻『生のものと火を通したもの』、その冒頭の「序曲」は次のように幕を開ける。
「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」(『生のものと火を通したもの 神話論理I』p.5)
経験的区別が道具となって抽象的観念の抽出とつなぎ合わせが行われる。
そして、この区別のつなぎ合わせ方には論理があり、法則がある。
のっけから唐突に何のことかと思われるかもしれないが、これはまさに、幕が開いてみたら、もうすでに演奏が始まっていた、という具合である。観客としては吃驚だが、ついていけば良い。
『神話論理』が全巻を通じて繰り返し浮かび上がらせようとするある基本的な操作とは、経験的な区別を抽象的な観念同士の区別と重ね合わせること、そして抽象的観念のペアを付かず離れずの関係に「つなぎ合わせ」ることである。
○ ●
区別することは反復されながら、次から次へと新たな区別を生み出していく。また、ある区別と別の区別を重ね合わせることもまた反復されながら、次々と新たな区別同士の重ね方を生み出していく。
神話は完成されることなく、動き続ける。
神話は、それが実際にあるひととひとの口と耳のあいだで語られるつど、変奏されていく。ある神話は、特にそれがひとによって語られるものであるときには、語る人と聞く人の間でつどその形を変えていく。神話は発生し続ける。どこかで完成することも、その発生が止まることもない。それはまるで生成変容し続ける生命のようでもある。「これが神話です、以上です」という具合に何かの完成形を固めて止めて置けるようなものではない。
「神話の研究はたしかに方法論上の問題を提起する。問題を解決するために必要な数の部分に分割するというデカルトの原則に合わないからである。神話分析には真の意味での終わりがなく、分解の作業の終わりで捉えうる秘められた統一性も存在しない。(『生のものと火を通したもの 神話論理I』p.11)
神話を語るということは、完成されて固められた台本を一言一句間違えないように読み上げるような営みではない。読む人と聞く人の間で、つどつど変奏されて、変容していくのが神話の姿である。そうした語られた神話が文字で記録され、保存されるようになったとしても、それはたまたまあるひとつのバージョンが記録されたということであり、いつ、どこで、だれから採集したかによって、その内容、その文字列の配列は他でもあり得たはずである。
そのいくつものバリエーションのうちどれがオリジナルでどれがコピーかという区別は全く問題にならない。強いてどちらか選べと言われれば、すべてがオリジナルだしすべてがコピーだということになろう。
この話については、以前『神話論理』の最後の1ページを読んでみるという筋でnoteに記事を書いたことがあるので参考にどうぞ。
◇
神話の「論理」もまた、石の表面に文字として声を固めた碑文のようなものではなく、この生命のような生成変容プロセスを動かしている、基本的な操作の動き方である。
ではその基本的な操作の動き方とはどういうことか?
レヴィ=ストロース氏は上に引用した文章に続けて、次のように書いている。
さまざまな主題が果てしなく二つに分かれてゆく。それらを整理分類し、分離したとおもったところで、予想外の関連に応じてふたたびくっついてゆくのをみるしかない。」(『生のものと火を通したもの 神話論理I』p.11)
二つに分かれていく。
そして再びくっついてゆく。
なんともシンプルである。まず分けること、分節すること、区別すること。これらはすべて区別分節「すること」つまり動きである。
この区別する動きが一番基本的だということに重大な意味がある。
区別分節することは、なにかどこかから拾ってきた出来合いのもの二つを、あとから横並びにするということではない。区別"された"「あれ」と「これ」は、区別するという動きの後に、互いに相手方とは異なるものとして発生したのである。区別"されたもの"は区別"すること"の後に生じるのであって、先にあるということはない。
そして人間と動物の区別、文明と野蛮の区別もまた、そういう「区別すること」のひとつの変奏なのである。
※
『神話論理』のはじまりは「経験的区別」であった。
経験的区別とはどういうことかといえば、レヴィ=ストロース氏が書いている通り、生のものと火を通したものの区別とか、湿ったものと焼いたものの区別とか、そういう区別である。そうした区別は、私たち一人一人が日常生活の中で何気なく、特段深く考えることもなく、当たり前のように区別している区別である。熱いと冷たい、明るいと暗い、嬉しいと悲しいといった区別であれば、ごく小さな子どもの時分からできるのが、私たちである。
成長するにつれて私たちはいくつもの区別を日常のあらゆるミクロな場面に発見できるようになる。皿にのったパンは食べられるが、地面に落ちて砂まみれになったパンは食べられない。いや、落ちても3秒以内に拾えば食べてもいい、いやいや、砂まみれになっていなくても、ただ床に落ちたというだけでもう食べない方がいい。などなど。
私たちは学校で教えられたり、強いて何かマニュアルを丸暗記するような勉強をするまでもなく、こういう具合の区別を日常生活を通じて習得しつづけている。これだけなら当たり前のことだと思われるかもしれないが、ここには大変な秘密が隠れている。
「もの」同士は即自的に区別されない
その秘密とはすなわち、これらの日常的経験的な区別は、「もの」の側にあるのではない、ということである。
ものとものが区別されるのは、ものたちがそれ自体として自ずから互いに異なっているからではない。さまざまなもの同士が、それぞれ他と違っているのは、それぞれのものが最初からそれ自体の内部に他とはことなる本質を持っているからではない。
私たちが日常経験する身の回りの様々な「もの」たちは、それ自体として、自ずから(即自的に)「本質」をもって存在しているような顔をしているけれども、実はちがう。
区別する動きを「ひと」に帰属させない
ものが自ずから互いに分かれていないとする。
そうなると、ものとものの「違い」はどこに由来するのか?
ものともとが異なっているのは、わたしたち「ひと」が「区別する」からだろうか?区別は私たち人間の主観が作り出すものだろうか?
この問いに対して「はいそうです」と答えたくなってしまうところであるが、ここであえて答えず、踏みとどまってみよう。
例えば、水揚げしたばかりの魚と、刺身になった魚を「区別」するのは、私たち「ひと」の側が行っていることにみえる。日本の文化に慣れ親しんでいる人であれば、「刺身」と「生魚」を区別している。刺身はそのまま食べて良いたべものものであるが、釣り針が外されたばかりの生魚を鵜や鷺がやるように丸ごと口に入れるひとには滅多にお目にかかれない。ところが、お刺身を食べる習慣のない文化圏の人たちの中には、「刺身」と「死んだ生(なま)魚」を区別しないひともいる。その人たちからすると、刺身を食べるということがとてもオソロシイことに思えるのだという。
文化の違い、ひとのちがいによって、ものごとの区別の仕方が違うということはよくある。そうなると、ものごとの区別、ものとものの区別は「もの」それ自体の本質的な何かではなく、「ひと」の側の行いだと言えそうな気がするけれども、なにがマズイのだろうか?
「ひとでないもの」と区別される「もの」としての「ひと」
問題は「ひと」である。
「ひと」というのが「ひと」であるのは、「ひと」が「ひとではないもの」から区別されるからである。「ひと」もまた、区別する動きが発生させる互いに区別される両極のペアのうちの片方である。
区別する動きは、「ひと」の側に属すのか?
それとも「もの」の側に属すのか?
このような問いは予め「ひと」と「もの」が区別されていると置いた上で、そのどちらに「区別するということ」を帰属させるか、という議論の立て方になっている。人間と事物、主観と客観が、あらかじめ区別されており、その両者の間に何らかの繋がり方(一方が他方を規定するとか)がありえる、と置いた上で、その一方の機能として区別するということをくっつけようというやり方である。
※
ここで考えなければいけないのはこの「ひと」と「もの」、「ひと」と「ひと以外」の区別はどこから発生したのか、という問題である。
仮に、区別する動きが、あらゆる出来合いのものに見える区別に先行するのだとすれば、区別する動きの手前に予め区別されたひととものがあるとは言えなくなる。
それとも、この「ひと」と「もの」の区別だけは、他の無数に蠢く「区別する」動きとは別の例外的で特権的な高みに固定された根源的な区別だといえば筋は通るのかもしれないけれども、しかしこの特権的な区別を区別する「区別する動き」は、それ自体いったいはどこで動いているのだろうか?? まさかさらに別の区別される二項対立のどちらかに帰属させられるのだろうか??
◇
話がややこしくなってしまった。
少なくともレヴィ=ストロースは、何か出来合いの区別が「区別する動き」に先行するというようには考えていない。『神話論理』を読む限りそう取れるのである。
端的に、区別する動きが動いている。それに先行する何かを考える必要はない。区別する動きは区別以前から始まり、とにかく動く。そして多重に組み合わされ、重ね合わされる。その組み上げられた構築物のファサードのひとつが、主観と客観の区別だったり、ひととものの区別だったりするわけであるが、しかしその深層では区別以前のところに区別を刻み込む動きが動いている。
区別以前から互いに区別される何かと何かのペアにはいろいろとあるなかで、特に強烈なひとつが主観と客観の区別、「ひと」と「もの」の区別であった。
ここで重要な点は、区別することは「もの」に対する「ひと」がそのなんらかの内部の仕組みを使って行う処理を超えているということである。
神話は、確かに生身のひとりの人間が語っている姿を見れば、「ひと」から発生しているという外観を呈する。けれどもよくみると、その声、その言葉、その登場人物たちの名前、その筋書き、その全てがある一人の個としての「ひと」を超えたところからやってきていることがわかる。声は以前食べたランチのタンパク質を借りて作った肉体を震わせているものであるし、その肉体の振動に共鳴して振動している「空気」などは、地球史を通じてたまたま今日のような組成になっているものだ。言葉は親たちから、祖先たちから伝承されたものを転用しているわけであるし、神話の筋書きもまた誰かから聞いたものを変奏しているわけである。「ひと」がぽつんと孤独に居たとしても、それは神話の発生源にはならない。ちょうど作曲家や演奏家が一人も存在しない世界にiPodがひとつ置いてあるようなものだ。
要するに神話を語っているようにみえるわたしたち「ひと」の一人一人は、連綿と反復される無数の「区別する動き」がたまたま重なり合い、浮かび上がらせたひとつの波紋のようなものなのだ。
神話を生み出している区別する動きは、あらゆる出来合いの区別に先行する。ここでいう出来合いの区別には「ひと」と「もの」、「主観」と「客観」の区別もまた含まれる。そうなると区別するということを、「ひと」と「もの」、「主観」と「客観」のような予め区別された二項のどちらかが持っている機能だとは考えられないのである。
ここでかの「構造」ということにつながるのである。
「ひと」と「もの」、「主観」と「客観」といった区別を出発点に置かず、そうした区別さえもが発生してくる動き捉えること。特にその動きをランダムなカオスとしてではなく、あるパターンを示す動きとして捉えること。レヴィ=ストロースが「構造」という言葉に託して記述しようとしたことは、ここに浮かび上がるパターンのことなのだと、『神話論理』をそのように読むこともできる。
ちなみにこの、区別分節二分して対立関係に置き、そして対立関係を複数重ねることで「意味」を発生させるという話は、かの南方熊楠による神話分析『燕石考』にも登場する。どちらも人類の言語による思考の底の底の一番上のところに到達したのであろうか。
すっかり長くなってしまったので、今日のところはここまでに。
このnoteは有料に設定していますが、全文無料で公開しています。
気に入っていただけましたら、ぜひお気軽にサポートをお願いいたします
m(_ _)m
関連note
ここから先は
¥ 500
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
