
潜在眼で心の深層を「見る」/卵の殻としての言語 -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(5)
精神の考古学。
私たちの「心」は、いったいどうしてこのようであるのか。
私たちが日常的に経験している「心」は、よい/わるい、好き/嫌い、ある/ない、真/偽、結合している/分離している、同じ/異なる、自/他、といった二項対立を分別するようにうごいている。通常「心」というと、こういう識別、判別、判断を行うことが、その役割であるかように思われている。
しかし、こういう分別する心、分別心は、いったいどこからやってきたものだろうか。
分別心は、自/他を分け、「自」分にこだわる(執着する)働きもする。
ところがこの「自」は、日々移ろい、変化し、思うようにはならず、そして必ず病んで、老いて、死んでいく。「それは自然なことだ」と思えない分別心は、どうして自分がそんなヒドイ目に遭わなければならないのか、どうすれば逃れられるのか、と迷い、苦しむ。
ここで苦しまずに済むために、この苦しみが他ならぬ「心」、分別する心に依るのだと見通して、その「心」の生成の仕方を徹底的に解明してみようという人類史上の試みのひとつが仏教である。
心の深みを、言語ではとらえられないが、「見る」ことはできる?!
「心」を、その経験的な姿をほどいて、その裏側、深みで生じていることを解明するために言語は十分な手段にはならない。なぜなら言語は「心」の表層を埋め尽くすように張り付いている”分別されたものの痕跡”だからである。
*
精神科医の渡辺哲夫氏が『二〇世紀精神病理学史』の冒頭に書かれていることが示唆に富んでいる。
「人間は動物性から離脱した。自然直接的な瞬間的生命から解放された。しかし、この離脱は高貴な自由への脱出ではなく、<歴史>という牢獄に閉じ込められることでしかなかった」
ここでいう<歴史>とは超個的な「言葉」のことである。言葉は、私たちひとりひとりの外部から訪れて、私たちが”もの心つく”ことを可能にするものであるが、それは他者たちの声であり、もっといえば死者たちの声の残響である。そういう「言葉」としての過去から降り積もった分節の蓄積としての<歴史>が、「「大自然」を自然生命直接的に「見る・千里眼」を全的に阻害」するのである(渡辺哲夫『二〇世紀精神病理学史』p.13)。
* *
中沢氏が『精神の考古学』で紹介されているように、心の深層を仏教の用語で「法界」と呼ぶこともできる。
法界は、情報を生じ・蓄えつつ、振動する。
あるいは、振動が、そのまま「情報」である。
振動は、いくつもの座標軸上で検出可能な差異を充満させている。
この差異。つまり分けつつ分けず・分けるでもなく分けないでもなく、という”線たち”が走り回り、からみあう。これが知性の始まりである。ここから分別するということが可能になり始める。
このような法界を出来合いの固まった差異の体系としての「言語」によって静的は捉えることはできないが、「眼」でもって「見る」ことができる、というのが『精神の考古学』の今回ご紹介するところの話である。

言葉でもって、「心」の深層を探索し、そしてまた現世の常識的分別世界に平然と帰ってくるためには、通常の日常的経験的感覚的な意味伝達型コミュニケーションのモードで動く言葉を一旦止めて、全く別のモードのコトバに切り替えやる必要がある。レヴィ=ストロース氏が論じる「野生の思考の神話論理」はこの別モードの言葉のあり方をとらえたものである。あるいはさまざまな詩的言語にも、この別モードのコトバをみることができる。
通常の日常的経験的感覚的な意味伝達型コミュニケーションのモードの言葉が出来合いの二項対立関係を静的に繋げていくような処理をするのに対して、別モードの野生の思考・詩的言語のコトバは、対立する二項が対立できるようになってくるプロセスを動かし、対立関係を結び合わせたり切り離したりする処理を自在に動かす。

「心」の深層を探索する手段としてこのようなコトバを自在に使いこなせるようになるのはなかなか簡単なことではない。井筒俊彦氏のいう「意味分節の修行」といったようなことに相当入り込まないといけない。
+ + +
生物としての眼を、内部からの光の通り道にする
「心」の深層を探索する方法として「眼」を使うこともできる。

視覚のモデル
現代の私たちは、視覚といえば、「眼」と「脳」とこれをつなぐ「神経」からなる仕組みをイメージする。外界の光が「眼」を刺激し、電気的化学的な信号が発生し、これが神経を伝わって脳に辿り着き、脳で処理されて、私たちが意識する「これが見えている、あれが見えていない」という感じが出来上がる。
心臓ー水晶管ー潜在眼ー生物としての眼
中沢氏が修行したゾクチェンの教えでは、眼を上記のようなモデルとは異なるモデルで捉える。即ち、”心臓”、”水晶管”からはじまり、”生物としての眼(これが上述の感覚器官としての眼)”を生成させると同時に、”潜在眼”を生成させつつある”脈動する光の通り道”と考える。
「人間の心は妄想に歪められた分別心と純粋な無分別心との「混合識」としてできている。[…]眼を通して、生物は対象との間に距離を作り出し[…]それは分別の働きに力を貸して、欲望を発生させる。それと同時に同じ眼は分別を超えた無分別・無妄想なリクパに繋がってもいる。」
この”生物としての眼"と”潜在眼”とが多重化した状態で「光をみる」。このことを「心」のありのままの動きを見る修行のための方便として活用する。

生物の眼だけでなく、そこに心臓と直結した”潜在眼”の視覚を重畳させることで、眼が「内面の心=法界にたえまなく生起している「あらわれ=現象化」のありさまを、如実に見届けることのできる器官」に変成する。
この視覚を利用して、「言語」によっては捉えることはできない(不可得)「セムニー=法界」を「如実に」観察するのである。
*
「光」の「通り道」を開くために、いわゆるいわゆる三業、身体と言葉とイメージする力とを、特別に「調整」しておく必要がある。例えばこの特別な調整のために、言葉で言えば、一切の言語活動を禁じたりする。それこそ「マントラを唱える」ことまで含めて禁じるという(p.191)。
そしていよいよ、四段階「リクパ灌頂」がはじまる。
具象と抽象の両極の間の振動状態に入る
「生物としての眼」は「妄想に歪められた分別心」と共振する。
一方、光の通り道たる水晶管に生じる”光の波動でできた潜在眼”は「純粋な無分別心」、つまり”セムニー=法界”と共鳴する。
通常、ものごとを分別してやまない”生物としての眼”に頼りきりで生きている人間が、”光の波動でできた潜在眼”を目覚めさせるには、一段一段ステップを踏むように、修行を重ねていく。
その修行は、
自/他
主体/対象
といった日常の経験や感覚を織りなす基本的な分別の固着性を少しづつやわらかくほぐし、二項対立する両極の間に通路を開き、一方から他方へ、共感したり、通じ合ったり、変身したりするといったことから始まって、そしていよいよ中沢氏がここで紹介されている「トゥガル(跳躍)」の行に至り、分別心(セム)の視覚と無分別(セムニー)の視覚とを”分別しつつ分別しない状態”に励起するに至る。ここで「光」の「通り道」を開くために、いわゆるいわゆる三業、身体と言葉とイメージする力とを、特別に「調整」する。
曼荼羅に入る
まず「三身の曼荼羅に入る」というプロセスがある(p.201)。
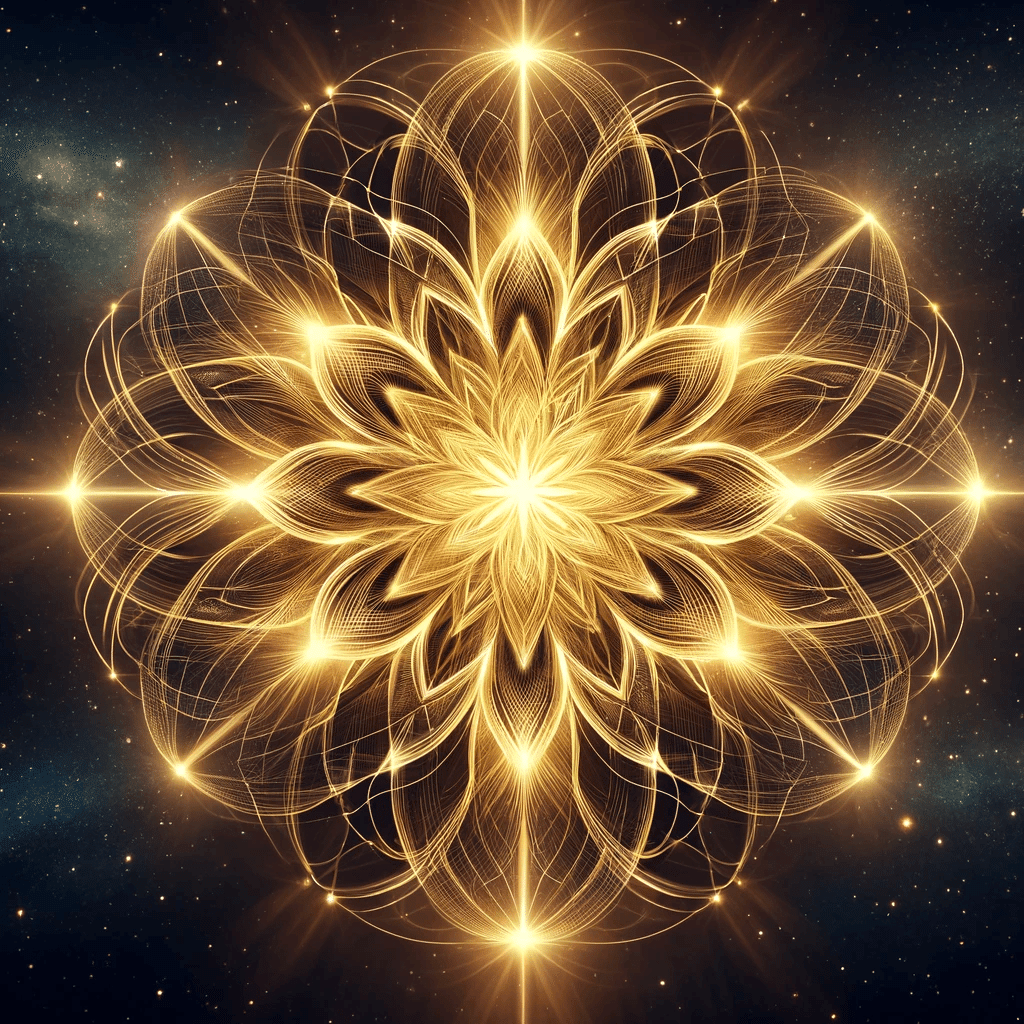
曼荼羅に入るために、次のようなステップを踏むという。
思念が物質的な表象を伴って表現される段階
具象表現を否定し抽象性へ移行する段階
さらに抽象化を進め「表面をめざしていく現象化の過程」に「逆行」する「潜在界に沈潜していく」段階
完全な抽象化が成し遂げられ、純粋な形態情報だけになった法界になる段階
物質的な「確かさ」に覆われた具象的経験・感覚から、抽象性へ、そして純粋な情報(差異と同一性の戯れ?)へ。そこから転じて、抽象的な情報から、また具象的な「生き物の世界」へ。
「抽象度の高い完全情報体から出発して、具象的世界との境界領域を目指す報身に向かう運動が起こり、それは具象化された生き物の世界である応身に達する。」
具象された生き物の世界を応身、抽象世界と具象世界の境界領域を開くのが報身、そして抽象的な完全情報体が法身と呼ぶこともできる。
この具象表現と抽象表現のハイブリッドとしての「曼荼羅」を構築していく。東南西北に仏を観想し、曼荼羅を建立する。
「想像力によって私のまわりに応身の浄土を建立して、その内部に私をしっかりと住まわせたのち、先生は報身と法身の曼荼羅を、次々と築き上げていった。各レベルの曼荼羅の構造はほぼ同一であったが、存在様態はそのつど変化している。それらが同じ空間につぎつぎと出現してくる有様は、想像されたものにすぎないとはいえ、その荘厳さで私を圧倒した。」
「曼荼羅を建立する」というのは、なかなか言葉で説明されても、理解するのは容易ではないことである。中沢氏は後の方のページで、曼荼羅の建立について次のように書かれている。
身口意の三業を清浄にして
「身口意を清めた参加者が集まって、みんなの前に想像力によって協同して神々の曼荼羅を立ち上がらせるのである。想像力によって生み出された曼荼羅は、法界のありさまを再現している。ゾクチェンの哲学では、法界は分別で歪められていない原初的知性だけでできているので、光も色も味覚も、通常の分別による知覚がとらえているものとは、根本的に違っている。つまりそれは「浄土(分別から浄化された知性空間)」をあらわしている。」
分別から浄化された知性空間である”法界”を、再現するのが「曼荼羅」である。そこには『華厳経』の世界が広がる。
法界の諸存在は、各自の形をよく保ち、各自が身にまとう荘厳には、くっきりとした差異がある。
諸仏が光を放つなか、妙音が響き、不思議な声がたえまなく聞こえる。
妙音は十方の空間にみなぎる。あまねく法輪を転ずる声がある。
仏は法界の清浄な空間にあって、自在な音をあらわす。
法界の中で、音声とならないものは存在しない。
中沢新一『精神の考古学』pp.250-251より
こうした法界の様子を、人間の身体、口(声)、そして意(想像力)を用いて、現世において作り上げるのが、ここでいう曼荼羅の建立、ということになる。
「身」においては、姿勢を正し、視線を固定し、ゆっくり呼吸する。
「口」においては日常の表層言語を語らせないこと。日常の表層言語を封じられた口から、表層言語が表層言語に定まる手前で響く響きをそのまま発する。その響きとは「原言語が日常言語になろうとする直前の形態を音声化した音」(p.252)であり、これを「詩的言語」や「真言」と呼ぶ(p.252)
「意」においては、「視覚的想像力」を働かせ、「ヴァーチャルに」「神仏のイメージをつくりだす」のである。
+ +
人も、鳥のように二度生まれなければならない
二度目の誕生のために
このようにして、身と口と心を、日常の働き方とは異なるモードに切り替える。
ここで中沢氏は「人間は鳥のように、二度生まれなければならない」という教えを紹介する。
鳥はまず卵の姿で親鳥から一度目の誕生をして、そして卵の殻を破って二度目の誕生をする。
人間においてはいわゆる誕生、親から生まれ言葉を獲得し日常生活をこなせるようになることは、いわば卵の中で二度目の誕生の準備が整った段階に相当する。なんと、わたしたちが立派な人間だと思って生まれて以来やってきた分別識を社会(常識的な死者たちの声)と同期させて効率よく動かすという意味での”人間であること”は、実はまだ卵だったのである。
「人間もまず母親の体から自然状態で生まれてくる。そこで子供は無自覚なまま成長を開始する。親たちの教えることを学習し、社会的な言語を習得する。こうして心が発達してくるが、その心は分別によって歪められたセムにほかならず、純粋な知性作用であるセムニーは、心の内部空間にしまいこまれたままである」
私たちが子供の頃からがんばって(?)獲得した「社会的言語」は、鳥でいえば卵の殻のようなものであり、これを破らないことには二度目の誕生はない。

「だから人間は鳥のように、もう一度うまれてくる必要があるのだ。分別心という心の卵の殻を破って、純粋な知性作用によって世界を見ることができる存在へと、変性をとげる必要がある。」
分別心は、卵の殻のようなものである。
殻は、生まれてすぐに立ち上がったりすることができない無力な人間のベビーとして生まれた私たちを、護り、育てる上で、大きな役割を果たしてくれたかもしれない。生卵からヒナへ、殻に囲まれることで私たちは成長する。
ところが、十分に殻の中で成長しきったと気づいた人は、この殻が、残念な「壁」に見え始める。そしてこの壁=殻のなかで、殻をひたすら眺めながら、苦しい所に閉じ込められている、と感じるようになる。鳥の雛がそうであるように、内側から殻を破るのは簡単なことではない。表層言語の分節体系は、思いのほか硬い殻なのだ。その中にいる時は、まさか破り割って、その外に出られるなどとは、とても想像できないほどに。
ここで中沢氏は次のように書いている。
「鳥のように、二度生まれた心が「見ている」のは、現実と現実を純化した曼荼羅としての姿との二つが、同時に共存している様子である。ここでも大乗仏教の根本である「色即是空」の思想が生きている。」
殻を破って二度目に生まれたからといって、どこか現世とは関係のない所に飛んでいってしまうわけではない。あいかわらず、どこにも行っていない。単にさきほどまでは殻の中にいたので見えなかったということである。
ご存知の通り、卵の殻を割ったからといって、殻が消えてなくなるわけでない。バラバラになった殻が、そのまま転がっているのである。二度目の誕生を経た知性は、分別識である殻を捨ててしまわず、しっかりとその断片ちをた集めておいて社会的な表層の言語を保つ。と、同時にその断片たちが「曼荼羅として」の心の深層の上にいくつも浮かんでいる小さなものだということをよく見通している。

「光」の脈動が析出する”内部”と”外部”
金剛連鎖体のような光を「見る」ことについて、詳細は『精神の考古学』を読んでいただくとして、ポイントは心臓で輝く光(これが”リクパ”の原初的知性)が、「水晶管」を経由して、眼から「外部空間」へと飛び出すというところである。
「法界に出現するたくさんの光点の中にリクパの「金剛連鎖体」の顕現を認めて、それと離れないでいることが大切です。[…]金剛連鎖体を見つめることによって、宇宙の根源で活動しているダルマを認識することができます。[…]すべての法の完成状態を知りたいのなら、金剛薩埵の心につながっていることを望むのなら、金剛連鎖体から離れてはなりません。」
この光、「金剛連鎖体」が「諸々の如来の身口意を無尽に荘厳する法輪」であることを知る。ただ単に「何か光っているように見えるなあ?幻覚??」という感じになることではなくて、「光」が「如来の身口意を無尽に荘厳」していることをありありと実感する。このとき、想像の世界に飛んでいくのではなくて、あくまでも、目の前の、生物としての眼の視覚にうつる「外部空間」に、内なる水晶管から照射された光が重なり合い、共振する様を「見る」のである。
生物としての眼を通して水晶管の中へと反射してくる様子を潜在眼でもってしっかりと捉える続ける。「外部空間」に飛び出した「心臓」からの「光」をみる潜在眼の視覚と、「生物の眼」が分別する光景とを重ね合わせることから離れない。

薄明
「あたりはまだ薄暗く、家や畑の輪郭もおぼろげで、知覚している世界と空性の認識を瞬時に重ね合わせていく作業は、日中よりもはるかにやりやすかった」
日の出前に、潜在眼による視覚と生物の眼による視覚の「重ね合わせ」は始まる。そして日が昇る。外からの光もまた溢れ、中からの光と重なり合って、どちらがどちらか分からないようにきらめく。
光が飛び込んできて暴れる
「眼の中に強烈な光が飛び込んでくる。[…]しばらくそれに我慢していると、オレンジ色の光の中に黒い塊があらわれ、激しく振動しながら、絶え間なく形態を変化させていくのである。赤や青の色をした光があらわれては消えていく。」

この激しい流れが落ち着くと、様々な光の流れの「形態」が見え始めるという。
形態・パターン・差異
まず、
オレンジ色 / 黒
この色の差異。そして、
「眼前の青空にゆらゆらとした波状の光のストライプが現れる。光のストライプは淡い虹色をしていて、それが縦になり、斜めになりながら、出現と消滅を繰り返す。斜めになっていた光が交差して、虹色の格子状をなすようになってくる。このような光の変化が起こり始めてからだいぶたって、あの「金剛連鎖体」が青空に出現してくる。」
波状のストライプの
縦 / 斜め (方向の差異)
そして
出現 / 消滅
格子構造・・・つまり
枠線 / 枠線で区切られた領域
「生物の眼」が捉える光を超えた、太陽からの光と心臓からの光が共鳴し合うところで、こういった区別、対立、差異がゆらめく。

これが分別する分別心のはじまりである。
「金剛連鎖体はすぐには出現してこない。まず青空にあらわれてくるのは「ティクレ(心滴)」とも呼ばれる、大量の光の粒である。光の粒子はチカチカという瞬きを繰り返しながら、確かな脈動を持って青空に現れてくる。[…]そのうち見開いている視野の全体が、この光の粒子群に覆われるようになっていく。」
この「視野の全体」を覆い尽くす脈動する粒、光子群こそ「水晶管」を通して「心臓」から「眼」へと放出される「リクパの原初的知性」である。

「存在=法界が内蔵する力であるリクパは、内と外の空間に充満しながら、縦横に横断的運動を繰り返している」
この光子群の流れが、「金剛連鎖体」へと変化していく。
「そこに金剛連鎖体が出現してくる。大量のティクレの中に、安定した動きを示すいくつかの大きめの光の粒があらわれる。それらがゆっくりと動きながら、連繋を示すようになる。数学の無限大記号を押し潰したような形をした光の粒子の連鎖が、青空の中で静止する。その時金剛連鎖体は脈動している。連鎖をなす一つ一つの光の粒が、鼓動を打っているように感じられる。」
「安定した動きを示すいくつかの大きめの光の粒」とある。

こういうのが見えるというのは、実にたいへんなことである。
一度こういうのを「見て」しまうと、世界の見え方が変わる、といった言い方では無難すぎるくらい、なんというか感覚的で経験的な世界の自明性のようなことが溶けて、流れて、どうなってもどうでもいい、という感じを与えつつ、それでいて瞬時に元の経験的な姿を浮かび上がらせる。そうしてありとあらゆるすべてのもの・ことは、見えないほど微かであり圧倒的でもある振動たちが、なんというか”おもしろがって”やっていることなのだ(自受法楽)ということを、深く深く実感することができる。
この魅力というか、静けさ、落ち着きは、言葉では形容することができないのであるが、しかし、どうにかこうにか工夫して、言葉”でも”言ってみたいな、という、「野生の思考」が勝手に走っていく楽しさ(?)を励起してくれる。
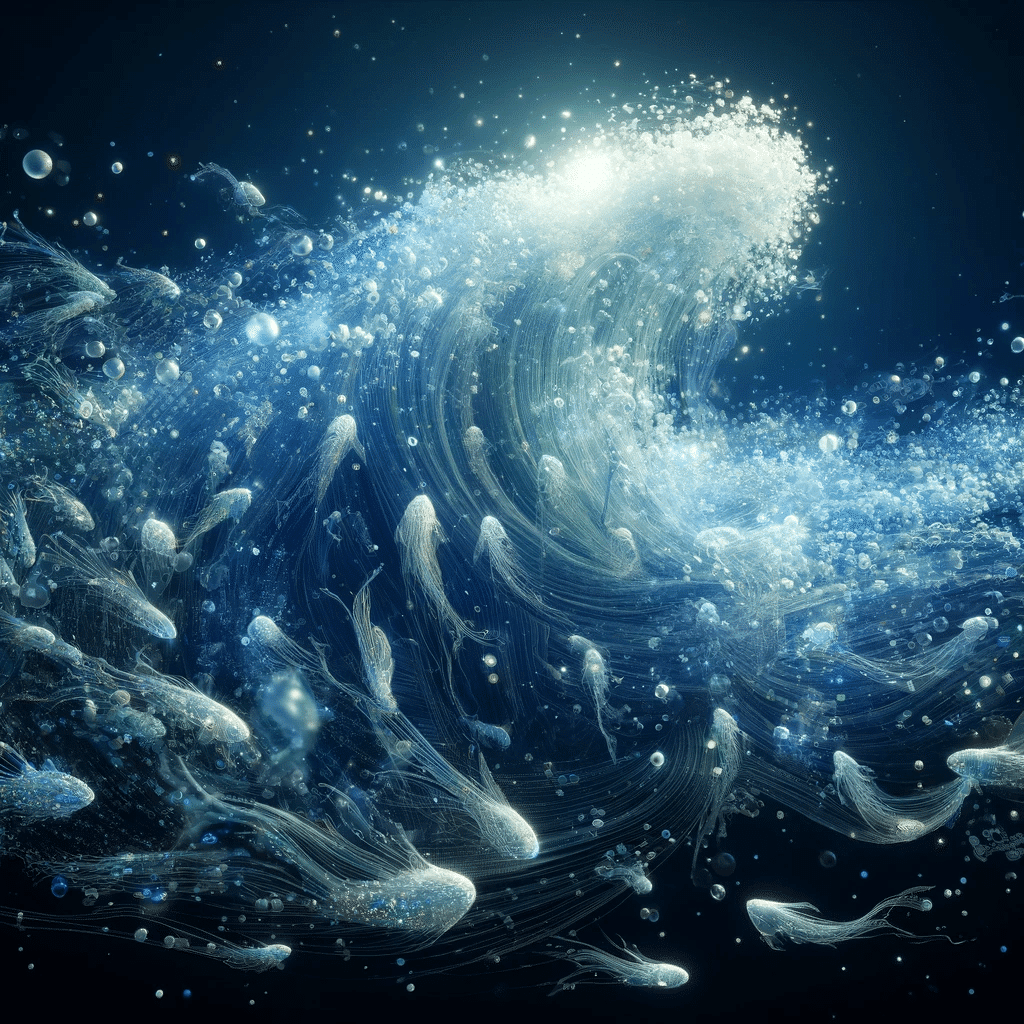
他の個体に食べられ、飲み込まれ、溶けて、
その飲み込んだやつもまたいずれは溶けて海になる
光の連鎖の脈動する塊は、「魚」とそっくりであると思う。
そういえば、弘法大師の幼名は「真魚」であった。
*
見えたからといって、対象化しない
ここで中沢氏は、師匠から受けた注意を思い出す。
「あなたは金剛連鎖体の形をしたリクパの動きを見届けることになりますが、それをこれこれの形をしたものとして対象化したり、自分は確かにリクパをこの眼で見たなどと言って、喜んだり執着したりしてはならない。」
金剛連鎖体のような素晴らしい光が見えたとして、それを対象化し、執着し、こだわり、求め、金剛連鎖体こそがホンモノで、それ以外はニセモノだよ、などと分別してみたりするようではマズイことになる。
金剛連鎖体もまた、あくまでも人間の眼と心臓をつなぐ神経ネットワークにおいて現象する極めて人間的なことである。それはいわば、人間の心が作り出した「法身」のモデル・象徴・サンプル・ピンぼけしたスナップショット、と言ったようなものである。
「金剛連鎖体はあくまでも、心臓と眼を結ぶ水晶管を通して光の滴に変容をとげた、リクパの存在や動きを示している影のようなものに過ぎないと思いなさい。リクパ自体にかくかくのものと言えるような自性はありません。[…]金剛連鎖体にもかくかくのものと言えるような実体性はありません。あなたはあくまでも青空にあらわれる金剛連鎖体を拠り所にして、その奥に隠されているリクパのほんとうの存在を、直観で知ることができるようにならなければなりません。」
金剛連鎖体は「リクパ」の「存在や動き」が人間特有の「心臓と眼を結ぶ水晶管」に投げかけた「影のようなもの」である。
実体がない、影のような
もちろん「影」と言われて「ああ、価値がないんだ、ダメなんだ」などと妄想分別する必要はない。「影」だって立派なものである。
なんと言っても影を投げかけている本体が影と不可分にすぐそこにあるからこそ、影のようなものが見えるようになるのである。影さえ見えれば、もう大成功である。
影 / 本体
こういう分別も分別なのである。つまり差別によって二項対立を立てて止まない心(セム)によって仮構されたものである。
本体 / 影
||
本物 / 偽物
||
価値がある / 価値がない
金剛連鎖体を、「ホンモノだ!」とか「ニセモノだ!」とか、どちらでも同じことだが、このような対立する二極の「どちらか」のポジションに放り込む必要は全くない。
金剛連鎖体は、「それ自体」として他と異なる本質を持ったスペシャルな何かではない。金剛連鎖体であっても、人間の心に映る他にあれこれと全く変わることなく、自性はなく、実体性はない。
「見えた!」からと言って、それを眼識による分別の対象としてしまっては分別心(セム)の内部にありながら、その深く絡み合った根?が法界・セムニーから立ち上って生えてきている様子をありありと観じるようなことはできなくなってしまう。
*
中沢氏は師匠から、次のように教えを受けたという。人は大昔から、この「光を見る」ことはできていたのであるが、多くの場合、古の人々はこの光を「人間の心を超えた尊い神のような存在」だと思ってしまった。しかしこの光もあくまでも、人間の心に「充満するリクパの影」なのだが、そのことを知らないと、金剛連鎖体に「執着」することになってしまう。
「見えた!」の瞬間、ここで、教え・哲学・思考が、「これもまた、あるでもなくないでもない」「これとこれ以外の、分別と無分別が分別されるでもなくされないでもない」というレンマの論理で持って脈動を刻む言葉で以って、この言葉で「見える」とか「見えない」とか、「見えてるあれ」とか「よく見えていないなに」の名前と、輪郭と、形態を、それこそ流れる光が見えるでもなく見えないでもないような感じのところに送り返しつつ、しかしありありと「みる」。
*
金剛連鎖体も、あるでもないでもない
ここで、「見える」ことと、教え・哲学・思考とが両輪となって支え合うという前回の記事で紹介した話に帰ってくる。
「リクパはあるでもないでもなく、それの青空への投射である金剛連鎖体もあるでもないでもない、心性(セムニー)そのものです。[…]金剛連鎖体が出現している空間は、内部空間でもなく外部空間でもない、いわば空間の狭間です。そこへ心を集中して、トゥガルのヨーガを修習しなさい」
経験的、感覚的に、「他とは違って、それとしてある」と感じられるものは、たとえそれが何であれ、ことごとく「あるでもないでもなく」であること、そのことに「心を集中」する。
ありありと見ながら、感覚し、経験し、感覚しているわあ、と充実した実感に溢れながら「あるでもなくないでもないなあ」と言う、言い続ける、唱え続ける。そして「今、セムが、分別心が、"あるでもなくないでもない"ことを”ある”か”ない”かのどちらかに分別したくて堪らずうずうずしておるなあ」と、言う、言い続ける、唱え続ける。
そして、特に覚えておきたいところ、この師匠の言葉である。
「あなたの心に納められているものを、あなたは見ているだけです。
そのことに子供のようにうれしがったりしてはいけません。」
どれほど光り輝くものが見えたとしても、それは「自」の「外部」にある「対象」などではない。
自/他
内/外
価値がないもの/価値があるもの
内でもなく外でもなく、自分のものでもなく自分のものでないこともなく、価値はあるでもなくないでもなく。そういうところから「心」が始まるのだと知るために、この光を見るのである。
「光」の概念について
理趣経で、諸”法”は”空”であり”光明”である、と説くところがある。
この光明、見える光。この「光」は粒子というよりもまさに波動、場(”空”)の多様な微小振動が共振して「フーン」と唸り震えているような、視覚的な対象というよりも、どちらかといえば聴覚的な「音」であるような”光”である。
”光は、遠い宇宙のある星から出発して、何億光年だかかかって、地球まで到着する”、というような具合に、まるで荷物輸送用の宇宙船にパッケージされて積み込まれた「もの」が、何億年もかけて「空間」の「中」を光速cで「移動」して、「ここ」に辿り着く、と、距離lと時間tがあらかじめかっちりと分節され終わった空間の中を移動する”もの”(まさに人間がこちらからあちらへまっすぐ歩いていくように)として「光」を考え、記述し、分別することもできる。しかし、今問われている「見える光」は、もっと「音」である。
音の発生源である「そこ」と、音を聴く耳がある「ここ」は、はじめから、すでにもともと、一つに連なっている。金剛連鎖体として見えている光の束の脈動は、この連なりの人間用の影だろうか。
この連なりの中では、何も移動していないし、距離ということもない。
距離であるとか、そして時間であるとか、ここ/そこ、遠/近の分別などは、この連なりの脈動する波紋の極々一部=周囲とは異なるごく一部としてのある人としての”心”たちが、そのように分別して環世界を立ち上げたものである。
対象ではない光
私たちの心は、普段は「光」と言っても、それを分別済みの”この”世界の”内部(外部ではない)”に”ある(ないではない)”あれこれの分別されたものたちのうちの一つのことだと思っている。
しかし、金剛連鎖体を影として投げかける、それと不可分である「光」の本体は、分別の手前、分別の裏側である。もちろんそれは分別と離れてはいない(分別から分別されて切り離されてはいない)。
ここでセム(人の分別心)とセムニー(”空”そのもの、絶対無分節)との関係を思い出そう。
「セムニーはセムを包摂し、セムの基体をなしている知性である。この根源的知性が「リクパ」として、眼から外に放出されて、「どこにもない空間」に金剛連鎖体を出現させるのである。遠方に対象物を見出し捕獲するセム型知性と、金剛連鎖体となって青空にあらわれている眼のセムニー型知性とは、じつは不二一体である。しかしリクパこそが知性の基体であることを知らなければ、視覚といえば対象捕獲のための眼のことしか頭に浮かばない。」
現代の科学的世界観に馴染んだ私たちは、通常素朴にはこの「遠方に対象物を見出し捕獲するセム型知性」とともに働く眼=視覚に映るものを切実な”真実”だ信じて疑わず、逆に人が「金剛連鎖体」のようなことを語るのを聴くと、それを「妄想」だとか「幻覚」だとか、要するに”取るに足らない虚妄”だとする。
ここに
ホンモノを見ること / ニセモノを見ること
の分別が効いており、科学的手法で観測計量できるものが「ホンモノ」、客観的に観測計量できないことは「ニセモノ」と分けることをしている。
*
あるいは別の考え方だと、人の感覚に捉えられる現実は、これは全て虚妄(ニセモノ)である、とする考え方もある。そして目に見えないこと、観測も計量もできないことにこそ真実(ホンモノ)がある、という言い方もできる。
これはどちらがどちらでも、「ホンモノ / ニセモノ」を分別して、ホンモノの方に何を充当すべきかで争うという点では、どちらにせよ同じことである。しかしまた、そうだからといって、このような分別をすること自体は悪いことではない。良い/悪いの分別すら離れている。
この本物偽物、良い悪いを、清浄/汚穢の分別に言い換えてもいい。
中沢氏は次のように書いている。
「ゾクチェンは[…]眼が見ている世界は妄想であるとは言わない。[…]心が「色界」を捉えていることを、あるがまま認める。しかしこの色界にはまだ「世界は見えていない」のである。その眼が空の眼と不二一体に結びついた時(「色即是空」)、はじめていままで見えなかった世界の姿が見えるようになる。」
どうも私たちは「分けても分けななくても同じ」と言われると、「ああ、分けない方がいいんだ」と、なぜか分別して片方を選ぶ言い方に自動翻訳してしまうことがあるが、まさに文字通り「分けても分けなくても同じ」なのであるならば、大いに分ければいいし、そして分けなければいい。
どちらにせよ、分けた後の片方に止まる、固まる、固定すると(それはそれで一向に構わないのだけれども)、なんだか辛くなるよね、ということである。辛さに固まった自分とこの世界の対立の裏側には、「知性の基体」である「空」が、分別をすることを可能にしており、また分別の仕方を自在に組み替えることを可能にするジェネレータが、くるくると回転しつづけている。この回転をじぶんのまわりでだけ止めてしまおうとするから、エレベータに閉じ込められているような、いや、卵の殻の中にいて、破り方がわからないような具合になるのである。
*
”あれ”は”なに”であるか、”これ”は”なに”であるか。と、分別して置き換え、分別して置き換え、「事物を対象化する」セム(分別心)によってではなくて、「セムを包摂する無分別のセムニー」でもって、目の前に浮かぶあれこれの事柄(諸法)を眺め、その「意味」をコトバでもって説く(p.213)。
+ +
これに続いて『精神の考古学』は、いよいよ「如来蔵」の話へと進んでいく。
関連記事
+
いいなと思ったら応援しよう!

