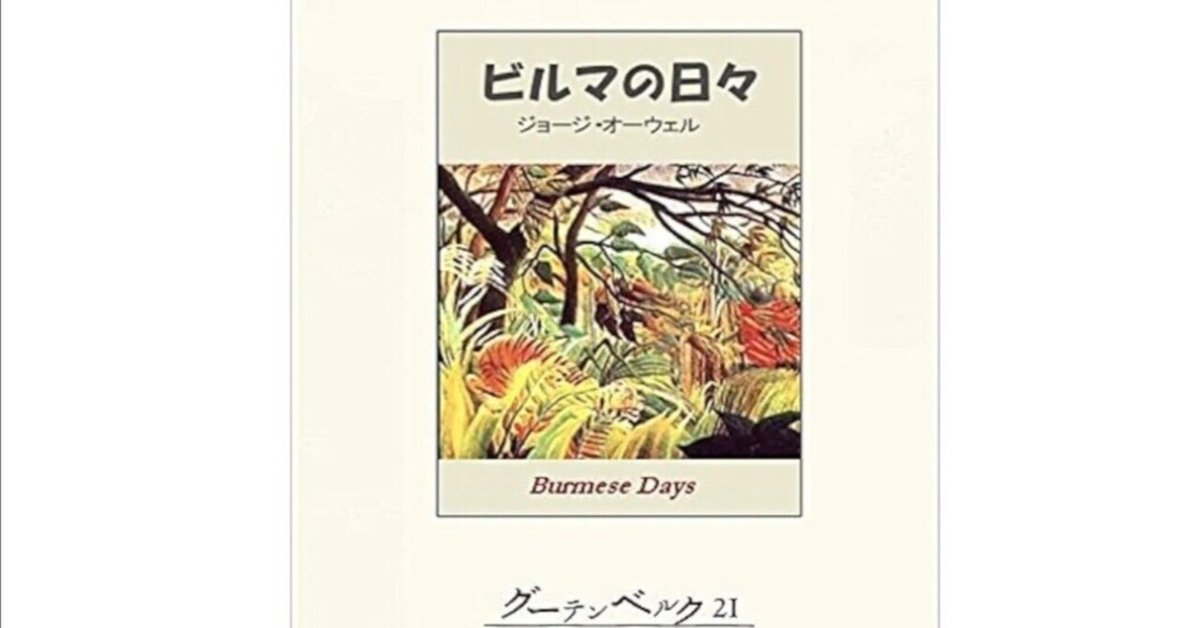
『ビルマの日々』ジョージ・オーウェル著 宮本靖介・土井一宏訳 イギリスの帝国主義支配を、支配する側・警察官として、ビルマで体験したオーウェル。後のディストピア小説の先駆となる暗澹たる内容でした。
『ビルマの日々』
ジョージ・オーウェル著
宮本靖介・土井一宏 訳
Amazon内容紹介
オーウェルはイートン校を卒業後、19歳で警察官となり、当時英国の植民地だったビルマに赴任、各地で5年間の駐在生活を経験した。本書はそれを元に、帰国してから7年後の1934年に書かれた長編処女作。沸騰する現地の反帝国主義感情、原地民を毛嫌いする英国人たちのなかにあって、チーク材会社に勤める英国人主人公フローリーは揺れ動く気持ちのままに墓穴を掘っていく。
ここから僕の感想
『1984』を書いたジョージオーウェルの処女作。
オーウェルはイギリス人だけれど、当時イギリス植民地だったインドの生まれ。父はインド高等文官、母はビルマ育ち(どちらもイギリス人白人である)。つまり植民地支配層イギリス人の子供。
オーウェルは幼いときにイギリスに戻って超名門パブリックスクールのイートン校を卒業するが、(年齢的にはパブリックスクールは13~18才だから、日本の中高一貫超進学校、昔の一中一校高、というかパブリックといいつつ学費の高い私立だから開成とか麻布みたいな感じか)、卒業生普通はオックスフォードやケンブリッジに進むのだが、オーウェルはイギリスを離れ、ビルマのマンダレーにあるインド警察の訓練所に入る。(ここ、複雑だが、ビルマはイギリス植民地のインドのその支配下にあったのだな。)、そしてビルマ各地で警察官として勤務する。イギリス植民地支配の現場での支配側として20代半ば過ぎを過ごしたんだな。その体験から生まれたのがこの小説。
イギリス帝国主義の意識と実態、現地人、社会とのひどい関係がまるまんま描かれた小説である。
僕がこの小説を知ったのは、以前書いたnote、(イギリスの植民地支配を書いた小説『イギリス人の患者』『ケルト人の夢』二つをまとめて論じた「鬼畜米英論考」)に、感想をくれた「木」さん(ハンドルネーム)という方のコメントの中で。
引用します。
今、主人がジョージ・オーウェルの「ビルマの日々」を読んでいます。植民地下の惨状をなかなか克明に描いた物語のようで…感想を聞いても、日に日に寡黙になるばかりです。」
「木」さんは、イギリス人男性と結婚して、今はギリシャに住んでいる。夫さんの実家一族にはオックスフォード・ケンブリッジ出身の方がたくさんいるのだそうだ。この本を読んで寡黙になっていくい夫さんは、そういう、日本人と結婚した知的階級のイギリス人なのである。
で、それはどんな小説だろうと読み始めたのである。Kindleでの読書は苦手なので、だいぶ時間がかかってしまった。
■イギリス帝国主義の、生々しい現実。
オーウェルが、寡作ではあるが20世紀最高の政治小説家となり得たのはなぜか。最高のディストピア小説『1984』を書き得たのはなぜか。
ここまでオーウェルを3作(『1984』『動物農場』と本作)を読んで思ったのは、
近現代の政治の中でも最悪の3種類。「イギリス帝国主義支配」「ファシズム(フランコ~ナチズム)」「スターリニズムの共産主義」というのを3種類全部、立場はいろいろだが、身をもって全部リアルに体験したからなんじゃないか。
初めて『1984』を読んだとき不思議だったのは、その中で描かれるディストピアって、もとネタ、オーウェルがイメージしたのがファシズム・ナチズムなのかスターリニズムなのかよくわからないこと。
しかもあの世界、3つの大国勢力に分かれて延々と戦争をしているんだよな。その、3つがどんな政治体制の違いなのかは説明されていなかった記憶がある。
その後『動物農場』を読んで、そしてこの小説を読んで、オーウェルの経歴をおよそ知って、なるほどなあと思ったわけだ。
最悪の政治形態ってひとつじゃない。ナチズムもスターリニズムもひどかったけれど、イギリス帝国主義の植民地支配もひどいもんだった。
本書解説で翻訳者宮本靖介さんと土井一宏さんが書いている
「 後年オーウェルはイングランド北西部で不況下の炭鉱地区に取材したルポ『ウィガン波止場への道』(一九三七)の中で次のように言っている。帝国主義を憎悪するには、その一部分として自ら機能する機会を持たねばならない、そうすれば比較的穏健に見えるイギリスの植民地支配も結局のところ弁解の余地のない圧制であることが分かってくる、」
そう、イギリス植民地支配について、僕が「鬼畜米英論考」で書いたのも、その点なんだよな。「比較的穏健に見える」一面と。一皮むいたときの恐るべき残忍さと。
今、バイデンの最後の目茶苦茶悪あがきのせいで、ウクライナとロシアが長距離ミサイルを打ち合ったりアメリカは対人地雷を供与したり、もうわやくちゃになっているが、そのことへの批判というか、基本構造考察について書いた文章なのである。イギリス帝国主義からアメリカ帝国主義というアングロサクソン海洋世界帝国の二面性というか、上部構造下部構造について。
合わせて読んでもらえると、タイムリーなんではないかと思う。
