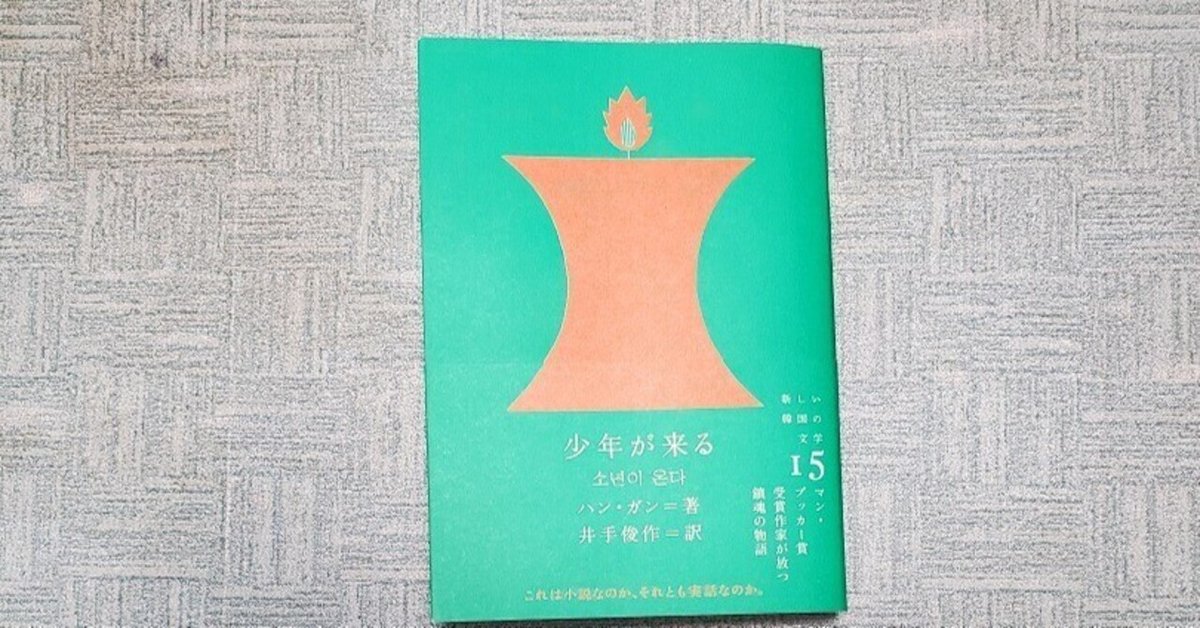
『少年が来る』ハン・ガン (著), 井手 俊作 (訳) 読むだけでこれだけ重たい。書いたハン・ガンさんの心に与えた影響はいかばかりか。この作品を中心に前後の主要作品を読んでいくのがいいように思われた。それほど重要。
『少年が来る』 (新しい韓国の文学 15) 2016/10/27
ハン・ガン (著), 井手 俊作 (翻訳)
Amazon内容紹介
1980 年5月18 日、韓国全羅南道の光州を中心として起きた民主化抗争、光州事件。戒厳軍の武力鎮圧によって5月27日に終息するまでに、夥しい数の活動家や学生や市民が犠牲になった。抗争で命を落とした者がその時何を想い、生存者や家族は事件後どんな生を余儀なくされたのか。その一人一人の生を深く見つめ描き出すことで、「韓国の地方で起きた過去の話」ではなく、時間や地域を越えた鎮魂の物語となっている。
本の帯 表
これは小説なのか、それとも実話なのか。
本の帯 裏
光州事件から約三十五年。あのとき、生を閉じた者の身に何が起きたのか。生き残った者は、あれからどうやって生きてきたのか。未来を奪われた者は何を思い、子どもを失った母親はどんな生を余儀なくされたのか。三十年以上の月日を経て、初めて見えてくるものがあるーーー。
丹念な取材のもと、死者と生き残った者の声にならない声を丁寧に掬いとった衝撃作。『菜食主義者』でマン・ブッカー賞国際賞に輝いた著者渾身の物語。
ここから僕の感想
なぜハン・ガン氏にノーベル賞が贈られたのかということは、実はここまで『菜食主義者』を読んでも『すべての白いものたちの』を読んでも、あんまり腑に落ちていなかったのだが、これを読んで、それはそうだ。と心の底から思った。
これほどの重さを持つものを書いたことが、これ以降の作品執筆につながっているようである。この本のことを中心に、ハン・ガン氏の前後の作品を理解していかないと、なんか、よく分からなくなるのだと思う。
『菜食主義者』は、この本を書く以前のハン・ガンさんであって、ある衝撃(この光州事件をめぐる)で幼い時に自分が壊れていることを、まだその核に触れることなく、その壊れていること自体を書いた小説だったのだな、と思う。「なぜ菜食主義者になったの?」ということの答えは結局あの『菜食主義者』の小説には書かれていない。その答えはこの『少年が来る』の中に、ちゃんと書いてある。
『すべての白いものたちの』は、この本を書いたことで負った精神的ダメージからの恢復の一年の間に書かれた本だったのだな。そう考えると、いろいろ納得できる。
『すべての白い者たちの』の後ろについている「作者の言葉」にはこうある。
ユスチナはまじめな顔で私に尋ねた。「私が来年ワルシャワに招待したら、いらっしゃいますか?」私は長く考えず、行くと答えた。ちょうど『少年が来る』の原稿を書き終えたころであり、その本が無事刊行された後、しばらくどこかへ行って休むのはよさそうに思えた。
同じ河出文庫の、平野啓一郎氏の解説「恢復と自己貸与」も、上のハン・ガン氏の文章を引用した上でこう書く。
『少年が来る』を書き終え、「しばらくどこかへ行って休む」必要があったというその言葉に、小説家の日常の光景以上の、腑に落ちるものを感じた。
『少年が来る』は韓国の民主化運動史に於ける最大の悲劇の一つ、光州事件を主題としているが、その犠牲になった死者たちを描き切った後、作者は、自分にとって最も近しい人間の一つの命について考えるところから、精神の恢復を図ったのではなかったか。
さらに、これから読もうと思って手元にある『別れを告げない』の、カバー背表紙の内容紹介冒頭にこうある。
作家のキョンハ(「私」)は、2014年の夏、虐殺に関する本を出してから、何かを暗示するような悪夢を見るようになる。何度も脳裏に浮かぶ黒い木々の光景がずっと気がかりで、よい場所に丸木を植えることを思い立つ。
読者として読んだだけで、それはもう受け止めるのが難しいような重い重いこの本を、作者として書くことがどれだけ精神に負荷をかけたか。この本の重さと衝撃について、中身については読んでもらうのがいいと思ったのでこれ以上書かないけれど、「その後のハン・ガンと作品」への影響から、そのことが伝わるのではないかと思って、ここまでいろいろ引用してみたわけでした。
光州事件については、何年か前に映画『タクシー運転手 ~約束は海を越えて』を観て、初めてどんなことが起きたのかを知った。くらい不勉強なのだが、韓国という国が民主化したのは1987年、日本で言えばバブル景気の頃、僕が広告マンとしてごく短い会社員生活をばたばたとしていた頃。光州事件は僕が高校三年生、受験勉強真っ最中だったころか。
今はすっかり立派な民主国家となり、経済も民主主義度合いでも、世界に通用する映画や音楽なんかの大衆文化の洗練度合いでも、いくつかの側面、指標で日本を追い越しちゃった感じもある韓国だが(なんて書くとネトウヨの皆さんがいきりたちそうだが、まあまあ、怒らずに。お隣の国が軍事独裁国でいるより、政治文化スポーツなどでお互いを尊敬できるライバル国になったほうが、日本にとっても良いことでしょう。)、僕の10代から20代の頃は、軍事政権で、金大中事件とかなんとか、民主主義ではない、恐ろしい国のイメージがあった。イメージだけあって、正直、僕はよく知らなかった。
光州事件はそういう軍事政権・韓国の時代から民主化に向かう、大きな転換点となった大事件だったのだなあ、と今、いろいろ知ると思うが、とにかく僕は不勉強で知らなかったのである。小説を読むのが面倒な人は、まずはこの映画を観ると、どんな酷いことが起きちゃっていたかは伝わると思う。映画としてもすごく良く出来ている。
その光州事件が起きた1980年5月、ハン・ガン氏は10歳、その事件の起きた光州で生まれ育ってはいたが、1980年1月にはソウルに引っ越していた。
それでも、その事件が10歳のハン・ガン氏とその家族にどのように影響が及び、それがこの本の執筆にどうつながったかという経緯はこの本のエピローグで語られる。
だから、帯にあるように「これは小説なのか、それとも事実なのか」というのは、そこまで読んで、読者がどう感じるかなのだが。ひとつ言えるのは、小説家としての想像力と筆力がなければ絶対に書けない本だ、ということ。
被害者・犠牲者の話、ではない。
この本の重さ、というのは、かなり固有で特異だと思うのである。それは例えば、アウシュビッツの体験について書かれた本や小説、最近読んだものであればプリモ・レーヴィの本なんかとも、何というか違うのである。
国家の暴力である軍によって、虐殺、弾圧、拷問、そういうことがあって、それで死んだ人のことを、ハン・ガン氏はできるかぎりの資料にあたった上で、そこに小説家としての想像力を極限まで働かせて、その体験をこの作品にしているのだが。あるいは、それを体験しつつ生き残った人の様々な人生、思いについても、取材できることと取材できないこと、取材しえないこと、そこに小説家としての想像力をもって迫っていく。そこの迫力、いやまさに文字通り「迫る力」の凄まじさ。
なんだけれどね、その中で、死んだ人、ひどい拷問を受けてその後生き残った人、家族子供を失った人、そういう人たちは、たしかに国家の、軍の、信じられないような暴力によって死んだりひどい目に合うのだけれど、でも、少年であっても、それぞれ、その過程で、何かを選択して、決意してその場所にいて、ある行動をしているということなんだな。
韓国の民主主義と日本の民主主義、というものに何か違いがあるかと言われると、その根本に、「戦って勝ち取ったか」、「民主革命」のようなものがあったかなかったか、ということが指摘される。日本は先の大戦、太平洋戦争といっても大東亜戦争といってもいいけれど、で負けてアメリカに占領されて、アメリカがいろいろと民主主義とそのための社会変革を、占領政策として進めてくれた。国民が戦争の惨禍に耐えたご褒美のように、民主主義がアメリカさんが持ってきてくれた。被害者として耐えに耐えた結果としての、恩寵のように与えられた民主主義。
韓国の場合、朝鮮戦争があったから、アメリカは韓国には軍事独裁政権しか持ってきてくれなかった。共産主義と対峙する最前線の国には、どんなひどい軍事独裁政権も、アメリカは支援したわけだから、世界中で。
韓国は、日本のように「悲惨な体験に耐えたご褒美での民主主義」はもらえなかった国だと思うのだな。大日本帝国の支配からは解放されたけれど、その後には米国が後ろ楯にある、自国の軍部による軍事独裁政権の時代が長く続いたのである。
だから「民主化」というのは、自国の軍事独裁政権に対して、自国の市民が銃を持って立ち上がる、という経験のことを指す。そういう体験を韓国はしている。この光州事件のように。
もちろん、そこには著しい力の非対称性があって、光州事件では、結果的には市民側は一方的に殺され、捕まり拷問されたわけだけれど、それでも、そこに参加した人たちには、ここではまだ中学生の少年から、女子高生、大学生、若い労働者市民、そういう人たちのことが書かれているけれど、とにかく彼らはすごく幼い若者たちだけれど、自分で選んでそこにとどまったのだということが、この本では繰り返し描かれるのだな。
犠牲者のことを書こうと、ハン・ガン氏はおもったわけだが、最後に「彼らを犠牲者だと思っていたのは私の誤解だった。」と本の本当の終わりの方で、書いている。
そこが、日本人である僕が読むと、さらに重たいのである。単に「ひどい軍による市民の弾圧があって、悲惨な被害者の、悲惨な体験が赤裸々に書かれている」というだけの本ではないのである。
まあ、そんな風に読むかどうかは、人によると思うけれど。なんにせよ、ハン・ガンさんノーベル賞、どういう小説を書いた人なんだろう。ノーベル賞を与える側は何を評価したんだろう、みたいなことに興味関心があるのであれば、これは必読です。でした。
