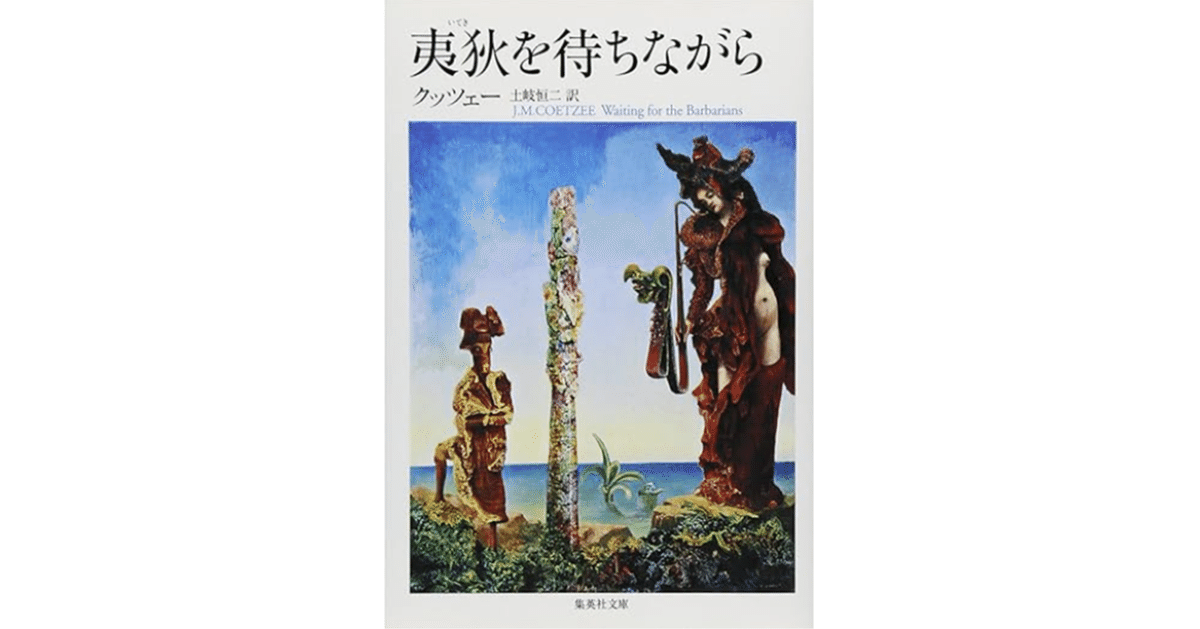
『夷狄を待ちながら』 J・M・クッツェー (著), 土岐 恒二 (訳) 今の政治情勢で読むのもつらいし、初老の主人公と同年代の男性としてその赤裸々で辛辣な描写を読むのもつらい、つらいのがつらすぎて気持ちいいに変わるのがクッツェーの魔法。
『夷狄を待ちながら』 (集英社文庫) 文庫 – 2003/12/16
J・M・クッツェー (著), 土岐 恒二 (翻訳)
Amazon内容紹介
「野蛮人は攻めてくるのか? 静かな辺境の町に首都から治安警察の大佐が来て凄惨な拷問が始まる。けっして来ない夷狄を待ちながら、文明の名の下の蛮行が続く。2003年度ノーベル賞受賞作家唯一の文庫!」
(今は『マイケルK』も『恥辱』も文庫になっているので、この内容紹介、今となっては嘘。)
「静かな辺境の町に、二十数年ものあいだ民政官を勤めてきた初老の男「私」がいる。暇なときには町はずれの遺跡を発掘している。そこへ首都から、帝国の「寝ずの番」を任ずる第三局のジョル大佐がやってくる。彼がもたらしたのは、夷狄(野蛮人)が攻めてくるという噂と、凄惨な拷問であった。「私」は拷問を受けて両足が捻れた夷狄の少女に魅入られ身辺に置くが、やがて「私」も夷狄と通じていると疑いをかけられ拷問に…。」
ここから僕の感想
クッツェーは1940年生まれで、この作品が書かれたのは1980年、南アはまだアパルトヘイトの時代である。当時の現代の具体的政治状況について直接触れない、架空の、あるいは過去の、ある帝国の、ある辺境の話である。
作中、主人公含め帝国の人は、敵役の軍人に碧眼の人がいるようにすべて白人であり、辺境の夷狄については、解説で福島富士男氏は「物語はいやおうなく十八世紀末の東ケープの地誌を想起させる」「十八世紀末の南アの東ケープの辺境ならば、先住民と呼べるのは少数民族遊牧民コイコイ人をーで、褐色の肌の人々である」と書いているが、コイコイ人は今は差別用語となっている旧称ホッテントット、その近縁のサイ人は映画ブッシュマンの人たちなのだが、小説からイメージされるのは、ちょっと違う感じだと僕は感じた。色の肌で黒い髪と眉だが、イメージ的には北アフリカのアラブ系か、アジア人のようなイメージである。この小説、クッツェー本人の脚本でイタリアの監督で映画化され、敵役ジョル大佐はジョニー・デップが演じ、夷狄の女性はガナ・バヤルサイハンという東洋系の人が演じている。映画予告編動画を見ても、だいたい僕がイメージしたような帝国人と夷狄の外観である。
これを書いたとき、作者クッツェーは40歳だが、主人公は50代後半から60代前半くらい、ちょうど今の僕くらいの年齢の初老の男である。クッツェーの小説の男性主人公、例えば後の『恥辱』の主人公とも共通するような、「初老の」「インテリで」「社会的地位としては権力権威体制側にいながら反権力的な考えを持ち」「性欲、女性への欲望に強く支配されていて」という人物が、小説が進むにつれ激しい暴力に巻き込まれていく。
今、イスラエルとパレスチナの紛争のさなかに読むと、帝国が、夷狄に囲まれて、過剰な暴力で夷狄を弾圧し、それが夷狄からの攻撃を誘発し、その中で帝国側が、夷狄の捕虜や女性への激しい拷問、暴力を行いという話はなんだかもうそのまんまでつらい。
支配し弾圧する側の感じる恐怖と、それゆえの過剰な暴力性。ううむ。つらい、
というような状況について考えると同時に、初老の男性のインテリの、帝国側なのに暴力的ではないと自認している主人公の、衰え死に向かうだけの年齢における、様々な欲望が、冷徹な自己観察の目と表現で描かれていくのを読む、というのがもうこれまたつらい。
そういう権力側なのに反権力的なインテリかつ、様々な欲望の初老の悪あがき的主人公が、より剥き出しの暴力に巻き込まれその極限まで引きずり回されるのを読むのも、これまた本当につらい。
政治的状況についても一個人の人生の最後の段階についても、何もここまで追い込んで描かなくてもというほどの苛烈さで、容赦なく描いていくから、この人、ノーベル賞なのである。ブッカー賞史上初、二回受賞者なのである。
この人の本、読みはじめはあんまりよく分からないなあと思って読んでいると、話が進むうちにどんどんとんでもなくつらい状況に主人公が追い詰められていくというのが多い。読者が、なんか、逃げられないようなひどい現場を目撃させられてしまうというか、主人公のひどい体験を読者もむりやり体験させられてしまう。小説を読むということがここまでなんか、生理的につらい体験になるとは、読み始めた時にはそう思わずに油断して読み始めるのだが、クッツェーの文章にとっつかまって、ひどいところを連れまわされる、そういう読書体験になってしまうのである。
というのが初期から2000年の『恥辱』まではそんな感じだった。
ここからは本作からは離れての脱線。
クッツェーが70代後半から80代に入っての『イエスの幼子時代』『イエスの学校時代』という連作も、二作目途中までは不思議なふわふわした、そんなに読んでいてつらくない小説だったのだが、二作目後半から急激に「きたきたクッツェーきたあ!!、という展開になってきたのである。
『イエスの学校時代』についてnoteに感想文を書いたところ、翻訳者の鴻巣友季子さんがそれを読んでくれて、感想文への感想をツイッターに書いてくれたのは良い思い出である。『イエスの少年時代』鴻巣さんの「あとがき」には、三部作最後の『イエスの死』というのが次にあると教えてくれているのだが。あのnoteを書いたのがもうちょうど3年前の11月。そろそろ三作目、翻訳が出るのではないかなあ。この『イエスの』シリーズも、架空の、どことも知れぬ国を舞台とした、ものすごく不思議雰囲気の小説です。三作目が『死』なわけだから、どんだけつらいことになるのか。早く読みたいなあ。
世界には「小説を読むって、こんなすごい体験なんだ」と思い知らされる、個性的でものすごい小説を書く作家がいるのだけれど、クッツェーはその中でも本当にトップの1人だと思う。
この本も、いやもう、強烈でした。そういう体験をしたい方にはおすすめです。あと、装丁の絵、M.エルンスト「荒野のナポレオン」が、すごく美しいので、それを眺めるのも楽しかった。
