
きれいに止まる、意識はどこか
どうも。藁科侑希(わらしなゆうき)です。
普段は大学教員やスポーツ現場でコーチやトレーナーをしております。
今日が389日目のnote投稿です。
本日はこちらのツイートから▼
止まる動きが苦手な人とかは
— 奥村正樹(スポーツトレーナー/physio) (@Masa19901) August 14, 2021
動画内でインレル選手が行っているように、ポールなどを手で触るという条件を設定してこのようなアジリティのドリルを行うのもありだと思う。
手を出すことで肩甲骨、背中周りの筋肉にも刺激が入って自然と上半身の形はきれいになったりすることは多いと感じている。 pic.twitter.com/uqjpCu71QM
ぜひ動画も見ていただきたいのですが、こちらの動き方を見ただけでも、どれだけの意識を「止まる」ことに割いているかがわかります。
とてもきれいに止まっていますよね。
今日はそんな、「止まる」ことの重要性と意識の向け方について。
●より速く、より高く、だけではない巧みさ
オリンピックのモットーとしてよく引用される、「より速く(Citius)、より高く(Altius)、より強く(Fortius)」は、競技スポーツの代名詞のように使われますよね。
ただ、それだけが競技スポーツの面白さでもなくて、まして指導をする上でそれだけを追い求めていると、競技における成長を阻害してしまう場合もあります。
その中の一つとして示すことができる動きとして、「止まる」動作が挙げられます。
少し専門的にはなりますが、このような▼用語がトレーニングやリハビリテーションでよく飛び交うんです。
ストップ動作
減速動作
アジリティ
クイックネス
アプローチフェイズ
プレローディング
これらがそれぞれ何を表しているかを説明していると、とても長くなってしまうので。
ざっくり言えば、「止まる」ということに対して、何をどうするかという方法論や考え方が山のようにある、ということです。
単に動かなくなるだけでしょ、と思うかもしれませんが、動きをしている中で、「静止する局面をつくる」ということは、非常に難易度が高く。
さらにそれを"きれいに"止まるようにするとなると、その難易度がまた跳ね上がるんです。
このような動きの巧みさが、トップのアスリートたちの魅了するプレーにつながっていることは間違い無いのだと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●「止まる」意識をつくりあげるプレイメージ
もう少し各論に踏み込むと。
「止まる」動作をきれいに行うためには、止まる動きに向かう中で『プレイメージ(先行意識)』が必要になってきます。
これは何かというと。
自分が「こうやって止まるんだ」という、時系列的に未来の自分の体の動きや相手との位置関係、地面との距離や関節の角度など、それらを制御した後の身体感覚をイメージしておくことです。
言葉がつながりすぎてとても難解になってしまっているのですが。
要するに、「止まった時のイメージを先取りしておく」ということですね。
それをどれだけ高精細にイメージできるか。
あるいは、その時系列をどれだけ分解して、細部に渡って意識を張り巡らせられるのか。
それが、「止まる」意識の深さと高さにつながっていくのだと思います。
よく、アスリートがファインプレーをした時に"未来視"したような、流れるような動きをしたのを見たことがあるのではないでしょうか。
そうした、洗練された・無駄のない動きには、この「止まる」(あるいは減速)という動作が必ずどこかに含まれていて。
その動きの巧みさが、パフォーマンスに大きな影響を与えることもあるんですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●動きの中の意識のつながりに目を向ける
このような動きを分解したり、選手の中の意識に対して目を向けると。
指導の中で、何をどう言葉がけすればいいのか。
あるいは、言葉にあえてしないほうがいいのか、ということが段々とわかってくることがあります。
もちろん全部が全部選手の考えや思考をトレースできるわけではありません。
しかしながら、指導者側がどれだけ選手に潜って、憑依するように選手が何を考え・意識しながら動きを行なっているのかを想像し続けることは、動きの改善はもとより、パフォーマンスの向上に対してとても大きな意味を持つんですね。
その中でこの「止まる」ことに対する意識がどれくらいあるのか。
主運動と呼ばれる、注目を集めるような動きではなく、影の動きとして自分の巧みさや技術を支えるような技術をどう磨いていくのか。
その磨き方を、実際に言葉をかわしながら、イメージを共有しながら、育んでいくことが望まれるのだと思います。
動きは連続的で、「止まる」動作をしたとしても、その前後には動きや意識が連なっています。
その動きと意識の連なりをどれだけ憑依して捉えることができ、選手とも共有ができるかで、指導の中の言葉も動きの修正も、その質が変わってくるのかな、と常々思っております。
今後も、このような観点を追求して、自身のコーチングに活かしていきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日はここまで。389日目おわり。
最後までお読みいただきありがとうございました!
それではまた明日。
【わらし監修】おすすめのバドミントンエクササイズ動画&解説
-----
今日の #standfm
#わらし式トレーニング 【通称】 #わらトレ
#わらし式トレーニング🏸実践編[Push-up系]
— わらし (@warawarac) August 15, 2021
Push-up challenge
【目的】
上腕三頭筋・大胸筋筋力向上
【ポイント】
❶上肢の動きと体幹・下肢を連動
❷体幹がブレないようにリズムをとる
❸背中を丸めない#normal #homeworkout#毎日投稿 #WithoutTrainingPartner#わらトレ #TikTok pic.twitter.com/kSDh1hr9yR
【今日の #コアチャレンジ】102日目
— わらし (@warawarac) August 15, 2021
今日は少しからだが重かったです💦#体幹トレーニング #Day102#CORE #core #corechallenge#ダイエットメニュー #積み上げ#おうちトレーニング pic.twitter.com/nrOT0VW2z2
今日の #マイキーチャレンジ 【通称】 #マイチャレ #朝活
【日曜日|四つ這い系】#マイキーチャレンジ
— わらし (@warawarac) August 15, 2021
《10repsずつ|全てゆっくり》
●Cat&Dog
●片手あげ 交互
●片脚あげ 交互
●両肘つけ
●両膝浮かし#毎日投稿 #マイチャレ #朝活#workout #exercises#homework #よい週末を pic.twitter.com/jo2ZQrrREr
-----
毎日のトレーニング投稿は基本以下の3つ。
#マイキーチャレンジ |マイキーのためのシェイプアップベーシックトレーニング
#わらし式トレーニング |バドミントンパフォーマンスアップのための現場向けトレーニング(一部自宅トレ)
#コアチャレンジ |体幹を楽しく鍛えるためのおうちトレーニング
よければフォローやいいね!RT(特にリツイートが嬉しいです!)をしていただけると大変喜びます。
今後とも引き続き楽しく頑張ります!
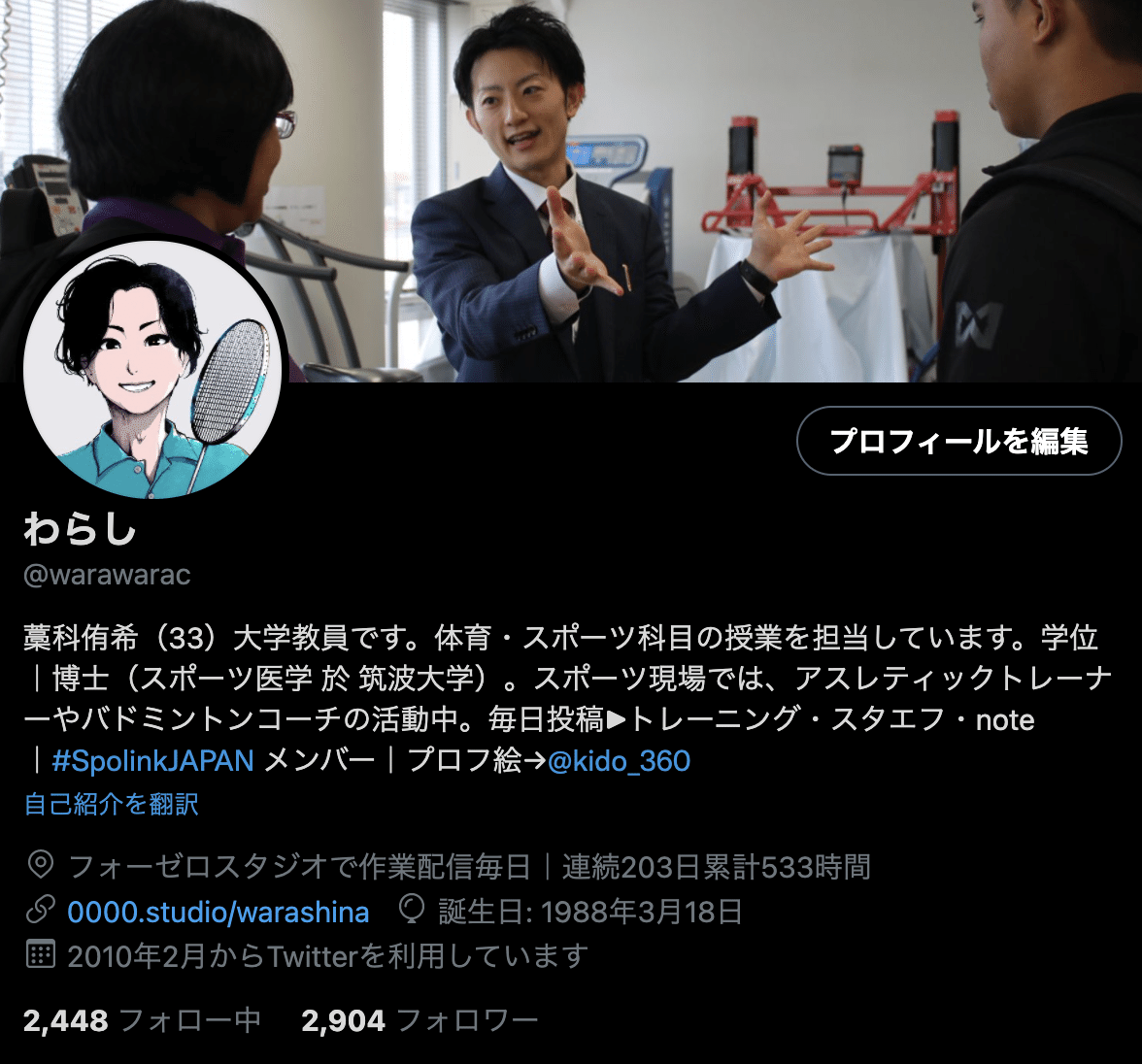
【保有資格】
博士(スポーツ医学 筑波大学)
日本スポーツ協会公認バドミントンコーチ3
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツコーチ
日本障がい者スポーツ協会公認中級障がい者スポーツ指導員
日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツトレーナー
NSCA認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト
NSCA認定パーソナルトレーナー
高等学校教諭専修免許(保健体育科 茨城県)
中学校教諭専修免許(保健体育科 茨城県)
赤十字救急法救急員
【現在の大学担当授業】於:東京経済大学・千葉大学・東洋大学
<体育実技>
●バドミントン ●卓球 ●バレーボール ●トレーニング理論実習 ●フィットネス
<ワークショップ科目>
●テーピング・マッサージ実習 ●スポーツ医学理論実践
<講義科目>
●健康の科学a ●健康の科学b ●スポーツとの出逢い
いいなと思ったら応援しよう!

