
未来を担う日本人として学び続けるための一手『物のあはれ』に学ぶ心の教育観(完結編)~物のあはれに学ぶ心の教育観とは?~ー『日本人のこころ』49ー
こんばんは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すという主題のもと
小学校教諭をさせていただきながら、
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
令和6年も残りわずかになりました。
皆様にとって令和6年はどのような一年だったでしょうか。
私は、
和だちプロジェクトを始めてから3年。
準備期間を含めては6年を終えようとしています。
日本国を学んでいく中で、
先人たちがどれほどの思いをもって我が国を受け継いでくださったのか。
その大本にある「和の精神」について触れることで
和とは逆行している現代において
そして終わりの見えない戦争が行われている世界において
私たちは先人から受け継いできた「和の精神」を伝えていくことが
大切だと思うのです。
今回は、いよいよ最終章。
『物のあはれ』から学ぶ心の教育観について
お話をさせていただきます。
今回もよろしくお願いいたします。
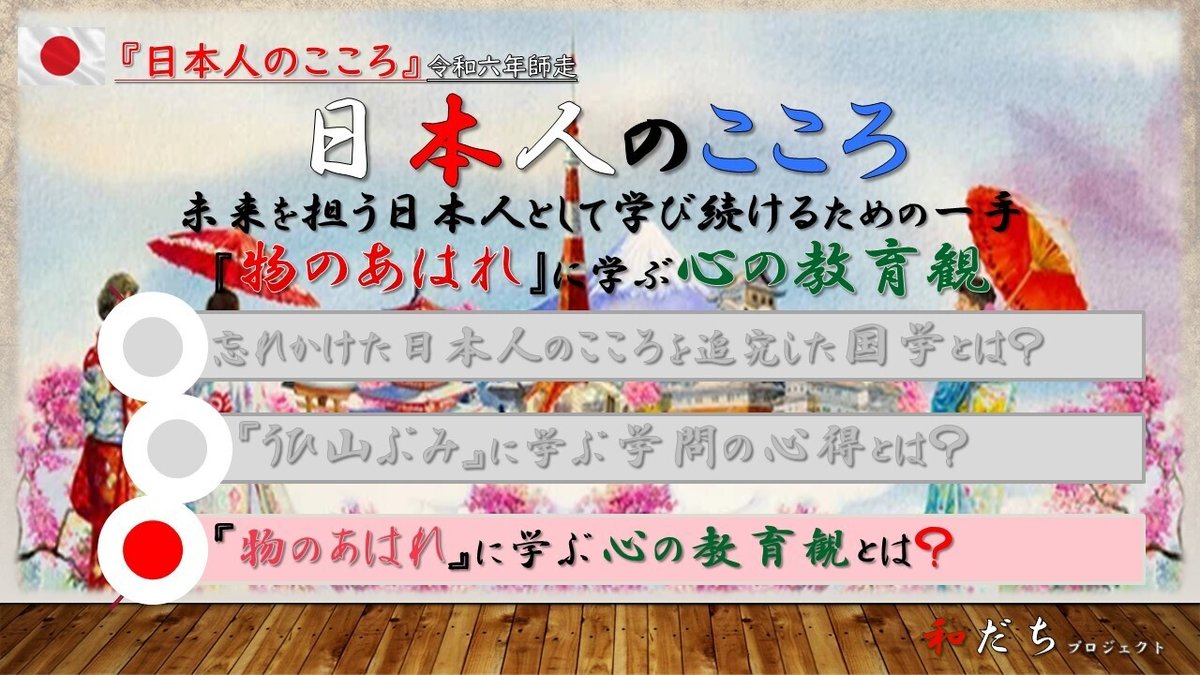
本居先生が生涯をかけて大切にしてきたお考えに触れ、
現代に活かすことができる観を養っていきましょう。
1)本居先生に学ぶ人間観とは?

子供の頃はだれしも
周囲のことに驚き、そして大人に「なぜ?」と問います。
国学者・本居宣長は
このような
「驚く心」と「なぜだろう?」という問いかけを生涯もち続けた人でした。
それこそが本居宣長のすべての出発点となっているのです。
本居先生は言います。
「考えてみたら、
地球が浮かんでいることも、人間の存在も
身のまわりで起こっていることもすべては不思議なことではないか。
それを感じないのは、人間の知を過信して尊大になっているか、
また慣れっこになっているからだ。」
と。
理性を過信すると、
自分の勉強した世界や目の前に広がる風景の中でしか
イメージを描くことができません。
本居先生にとって、
先入観や常識はサングラスのようなものだったのではないでしょうか。
サングラスは私たちの眼をまぶしい外光から守ってくれます。
しかし、
時にはサングラスを外し、
その向こうに広がっている道の世界の広さに思いを致すことも
また必要なのです。
そのようなとらわれない自由な目。
本居先生はこれを「古学の目」と呼んでいます。
この目をもっていからこそ、
本居先生は常に前向きに生きていくことができたのです。

本居先生は、
自分で考えて判断するという態度を
子供の時から生涯もち続けた人です。
先入観を配したその考え方はとてもシンプルです。
例えば、
お金には興味がなさそうなそぶりの学者に対して、
お金があれば本が買えるのではないか?と笑います。
本居先生は言います。
「誰でも美味しいものは食べたいし、
よい着物は着てみたい。
立派な家に住んで地位や名誉、
そして財産、長寿に恵まれたらと夢見ることは同じです。
それが人間の本当の心、真心なのです。」
と。
欲望をむき出しにしろということではありません。
ただ、
本当の心は秘められているという自覚が必要であるということです。
人の心には迷いや欲望もあれば、誤ることもあります。
それを直視し、時には怒り、
また許し合いながら上手に付き合っていく。
それが生きていくということなのです。
2)本居先生に学ぶ「日本人論」とは?

本居先生は、
『古事記伝』や『紫文要領』を執筆したり、
さまざまな古文を読んだりする中で、
「人の心」を徹底的に考え抜きました。
本居宣長さんの養子である大平は、
『恩頼図(みたまのふゆず)』という
お陰の観点から見た本居宣長の系譜を描いています。
この図を見ると、
神や両親、師の賀茂真淵、中国の孔子だけでなく、
対立する立場にあった儒学者たちからも
お蔭を被っているということになります。
「恩頼」は、
始めは神のご加護を意味していましたが、
時に人も神様となる我が国では、
いろいろなお蔭全般にまで広がっていきました。
わたしたちも日常ごく自然な形で「お蔭」という言葉を使います。
なにかしもらったとか、
特別なことでお世話いただいたという具体的なことより、
もう少し無形の恩恵にあずかった時に使います。
論理や理屈よりも、
むしろあいまいなものを好むいかにも日本人らしい言葉です。
これは、本居先生に限らず、
私たち一人一人はみな自分の『恩頼図』を持っています。
神様やご先祖様、これまで出会った人たちなどから
たくさんのお蔭を受けて次へとつないでいくのです。
そのように考えるとおのずと大切にしたい姿勢が見えてきます。
「感謝」です。
本居先生は、
このお蔭と感謝の連鎖の中に日本人の生はあると考えたのです。

本居先生は、
常識とか従来ある価値基準に対して
それは外国文化からの借り物ではないかと疑い、
絶対視することを「漢意」と呼んで批判しました。
借り物であることを忘れて
我が国に最初からあるように錯覚する日本人への警鐘なのです。
では、
「漢意」を清くぬぐい去るとどうなるのか?
その姿こそ、
「物のあはれ」を知るという
本居先生が最も大切にした考えに行きつきます。
「物のあはれ」とは、
物や事、また人の心を深く理解し、それに寄り添うことです。
そのようにすると四季のうつろいにも敏感に反応することができ、
人間関係も深みを増すのです。
人間の弱さに向き合うことでもあります。

人間というものは、弱いものであると悟った時に、
それを克服しようとする人もいますが、
仕方がないとあきらめる人もいるでしょう。
本居先生は、
静かに心のありようを分析したのです。
「男は、女子どもみたいにめそめそするなと言うが、
人は男も女も子供も同じではないか。
例えば、武士が戦地に赴いて、一命を潔く捨てるというのは武士にとっては当たり前のことだが、
故郷に残してきた妻や子をいとおしいと思わないことがあるのだろうか。
年老いた親にもう一度会いたいと思わないのだろうか。
鬼のような勇猛果敢な男でも、一抹の悲しみを感じないとどうして言えるのだろうか。
悲しみや哀れを感じる心というものは全ての人に共通することで、
立派な人であろうとなかろうと変わりはないのだ。」
と。

さらに、
このようなことも言います。
「人の心は今も昔も、
また日本も中国も変わりはないのに、
漢詩に比べると和歌は頼りないし、
また浮気っぽくて思慮に欠けるという人がいるが、
ごらんなさい。孔子が選び儒教の経典の一つと尊ばれる『詩経』三百編は、
夫婦の情愛や一人寝の寂しさなど、他の人から見れば情けない人間の心を映し出しているではないか。
漢学を学んだ人が和歌のことを情けないと言ってけなすのは、
聖人である孔子の心も、また人の心も理解できていないからなのです。」
人の心というものは、
悲しい時に誰かに同情してくれたらそれだけでずいぶん癒されます。
また嬉しさや感動は、人に語ることによって増幅していきます。
3)「物のあはれ」に学ぶ『心の教育観』とは?

人の感情は繊細です。
例えば、
気の毒と同情することもあれば、
面白いとか、妙だ、珍しい、憎いなどさまざまです。
それを感じることによって、
対象を自分の中に受け止めているのです。
本居先生は、
そのような感情の動きすべてを
「物のあはれ」を知るととらえたのです。
世の中は、一人では生きられません。
周りとの協調、時には距離も大切です。
それにより、逆に自分もまた救われもするのです。
上に立つ人はもちろんのこと、
ふだんの生活でも、心の練れた人がそばにいると住みやすくなります。
逆に物のあはれを知ることがないと
思いやりのない殺伐とした社会になってしまうのです。
変化しないところはもちろんありますが、
例えば、
花や月を見るときの心
恋する心などは
昔の方がはるかに繊細であったと言います。
現代と本居先生の生きた時代を比べれば、
昔の方が随分時間がゆったりと流れていたように思います。

『古事記』の世が明ける描写などを読むと、
その鋭敏な感覚に驚きます。
本居先生は、
『源氏物語』をはじめとする我が国の物語は、
人間の、世の中の本質を丁寧に描写していると言います。
感性も時代によって違いがあるのです。
そして、
その感性は、古典を読むことで磨かれるのです。

本居先生は、
生涯をかけて
「日本人とは何か?」「日本人のこころとは何か?」を
徹底的に探究した人でした。
本居先生は、
「大和心(日本人のこころ)」とは何かを歌で表しました。
しき嶋の やまとごころを 人とはば 朝日ににほふ 山ざくら花
満開の山桜を見て、美しいなあと思う心。
それが
本居先生がもっている「大和心(日本人のこころ)」なのです。
「私は山桜が朝日に照り輝いているのを見ると感動するんだ。
ああ美しいなあとため息をもらしてしまうんだよ。
それが私の持つ日本人としての心、やまとごろこなのだ。」
と言うのです。
山桜の美しさに敏感に反応する心を失ってしまったら、
学問も生活も意味をなさないと本居先生は考えました。

桜が散っていくという儚さ。
まさに「物のあはれ」を表すものです。
この「あはれ」という言葉は、
他の言語では到底表すことのできない我が国特有の言葉です。
しみじみとした。
哀愁。
哀感。
悲しみ。
同情。
哀れみ。
そのすべてが含まれています。
我が国の文学には、
この「物のあはれ」という考え方はずっとあります。
目で見て、耳で聞くごとに触発されて生ずる
しみじみとした情趣や無常観念的な哀愁。
日本人がずっと大切にしてきた感性です。
歴史において、
滅びない者はありません。
その滅びゆくもの。
弱いもの。
負けたもの。
それらのものに対する「哀れみ」の気持ち。
特に、
権力を預かる者は負けた人間に対する
哀れみや共感の気持ちをもつことを忘れてはなりません。
本居先生が表してくださった「物のあはれ」という
日本人にこそ宿るこころを大切にしていきたいですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国民一人一人が良心を持ち、
それを道標に自らが正直に、勤勉に、
かつお互いに思いやりをもって励めば、文化も経済も大いに発展し、
豊かで幸福な生活を実現できる。
極東の一小国が、明治・大正を通じて、
わずか半世紀で世界五大国の一角を担うという奇跡が実現したのは
この底力の結果です。
昭和の大東亜戦争では、
数十倍の経済力をもつ列強に対して何年も戦い抜きました。
その底力を恐れた列強は、
占領下において、教育勅語と修身教育を廃止させたのです。
戦前の修身教育で育った世代は、
その底力をもって戦後の経済復興を実現してくれました。
しかし、
その世代が引退し、戦後教育で育った世代が社会の中核になると、
経済もバブルから「失われた30年」という迷走を続けました。
道徳力が落ちれば、底力を失い、国力が衰え、政治も混迷します。
「国家百年の計は教育にあり」
という言葉があります。
教育とは、
家庭や学校、地域、職場など
あらゆる場であらゆる立場の国民が何らかのかたちで貢献することができる分野です。
教育を学校や文科省に丸投げするのではなく、
国民一人一人の取り組むべき責任があると考えるべきだと思います。
教育とは国家戦略。
『国民の修身』に代表されるように、
今の時代だからこそ、道徳教育の再興が日本復活の一手になる。
「戦前の教育は軍国主義だった」
などという批判がありますが、
実情を知っている人はどれほどいるのでしょうか。
江戸時代以前からの家庭や寺子屋、地域などによる教育伝統に根ざし、
明治以降の近代化努力を注いで形成してきた
我が国固有の教育伝統を見つめなおすことにより、
令和時代の我が国に
『日本人のこころ(和の精神)』を取り戻すための教育の在り方について
皆様と一緒に考えていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
