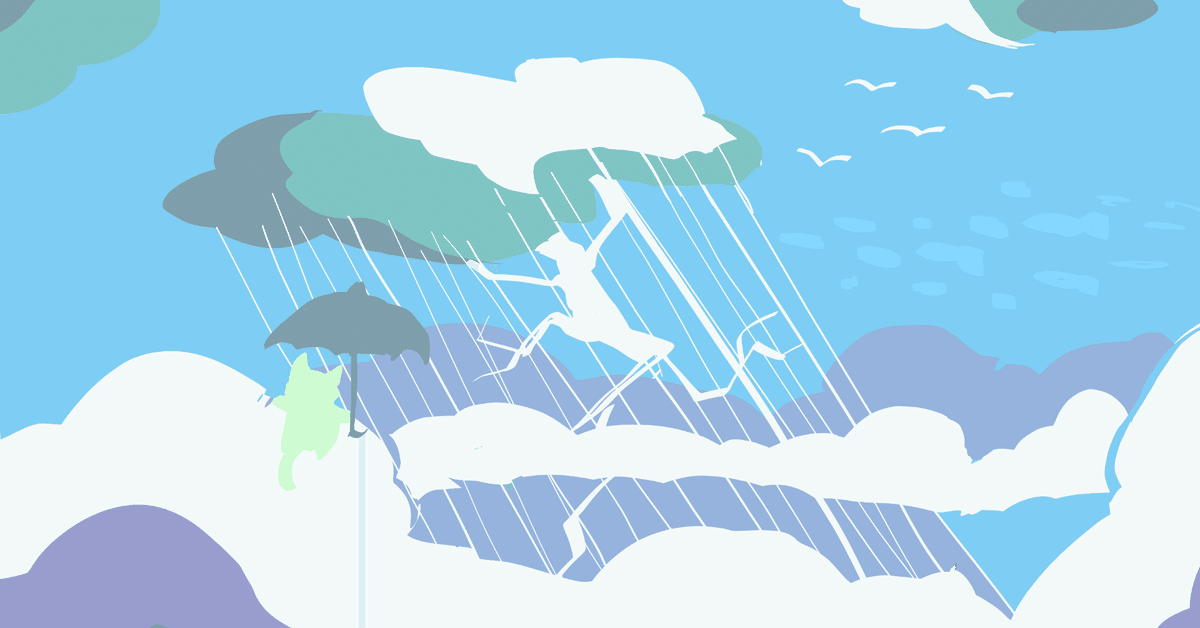
私なりの「観光ノ本質」
noteも含め、ネット上には、「観光学」について(個人的な)記事というものが、あまり多くは無い。まぁ、哲学に比べれば、百年もない赤ん坊のような学問でもあるうえに、近代においてのみ有効な社会学からの派生なので、あまりに認知度は高くないということには、肯ざるを得ない・・・。
さて、今回気になった記事は、「林 幸史」さんという方が書いた記事だ。
「観光の本質」について、少々の引用をしながら、述べていらっしゃる。中々、観光「学」からの見地と、観光そのものの本質を見ようとする記事はほぼ無いので、興味深い所ももちろんある。
この私の記事では、私が思う、「観光の本質」と、林幸史さんが述べた、観光の本質との差異や、それについての意見を述べようと思う。
では参ろう。
グリュックスマンとオギルヴィエ
まず、林さんは、「観光の本質」として
①よその土地に移動すること
②その土地の地域資源に触れること
③土地に暮らす人々と話をすること
を挙げている。確かに、これも一理あるところ。この三つをまとめれば、「他者に触れる」ということが、うかがえる。
この林さんの「観光の本質」は、グリュックスマン(R.Glücksmann)の提示する観光の定義と似ていると、私は思ったんよね~。
孫引きになってしまうけど、引用します。
彼は観光の本質が「ある土地における一時的滞在者とその土地の住民との間の諸般の関係」にあると考えた。(田中[1950])(岡本伸之、4、2001)
これが、グリュックスマンの提示する、観光の本質ですが、やはり林さんの言うような観光の本質は、グリュックスマンに似ているなと思います。
一応、オギルヴィエ(F.Ogilvie)の観光の定義とも比較してみましょう。
「一時的滞在地において他所で取得した収入を消費すること」(岡本伸之、3、2001)
オギルヴィエとの比較から分かることは、林さんの提示する観光の本質は、オギルヴィエよりも、グリュックスマンに近いということですね。より具体的に言えば、いわゆる他者との交流に重きが置かれているか、それとも、消費行動という側面に重点が見いだされているか、の違いでしょうか。
私なりの観光の本質
では、私なりの観光の本質を書きたいと思います。わかりやすく、三つに絞って書いてみましょうか。
①よその土地に到着すること
②その土地の演出に触れること
③非日常に日常を持ち込むこと
これが、「現状の!」私なりの観光の本質(定義?)になります。
林さんの言っている
①よその土地に移動すること
②その土地の地域資源に触れること
③土地に暮らす人々と話をすること
と比べると、
①よその土地に到着すること
②その土地の演出に触れること
③非日常に日常を持ち込むこと
と、所々違うところがありますね。
①よその土地に到着すること
まず、林さんの①番目と、私の1番目を比べてみましょう・・・!
「よその土地に移動すること」「よその土地に到着すること」。林さんは、「移動」と書いていますが、私は「到着」と書いています。
というのも、私は、観光客が、「移動」という過程を重視しているとは思えないからです。というか、移動というものを無視する、或いは移動が観光客にとって、退屈なもの、よって無い方が良いものという認識をしているのではないかという予測から、「到着」にしました。
林さんの言いたい「移動」とは少し意味が異なるかもしれませんが、「移る」「動く」という過程に重きを置いたものは、少し違うのかなかぁと思います。(これは、観光が移動を本質とするのは気に食わないという感情からではなく、残念ながらそうなっているからという理由からです。)
ワンダーラスト(知識欲のある人)なら、移動や過程を重視する人もいるかもしれませんが、大抵の人は、観光地という目的地に到着することが、まず大事だということは、あまり驚くことではないと思います。
観光は、「国の光を観ること」そして、「その光を魅(観)せること」でもあります。観光においては、到着する対象としての観光地が重要だなということで、「①よその土地に到着すること」としました・・・!
分かってもらえたかな・・・?
では、次に「②その土地の演出に触れること」としたことについて、書いていきます。
②その土地の演出に触れること
林さんの定義では、「②その土地の地域資源に触れること」となっている部分を、私は「演出」に変えました。
これは、ブーアスティンやマキャーネル、あるいは、ボードリヤールの影響といってもいいかな。
林さんの観光の本質においては、「地域資源」という言葉が使われています。この言葉から、(少しかもしれないけど)CBT(community based tourism)のイメージが観光に対して強く張り付いているのかなとおもいました。
敢えて「資源」という言葉を使うとしても、私はおそらく「「②その土地の【観光】資源に触れること」と書くと思います。「地域資源」そして、「観光資源」は、ある意味では同じものかもしれませんが、やはり異なる印象を与えるものでもあると思います。
それに、地域資源といっても、全く、何も手が加えられていない状態で、観光客(strangers)に曝されることは、あまり無いと思うのです。必ずと言ってよいほど、何かしらの手が加えられています。(観光地は、綺麗に見えた方が、良いですしね・・・。)
そういう意味で、私は「演出」と書きました。「演出された真正性(staged authenticity)」にバチバチに影響を受けてますね~。
③非日常に日常を持ち込むこと
林さんの場合は、「③土地に暮らす人々と話をすること」と書いてありましたが、私は「③非日常に日常を持ち込むこと」と書きました。
なぜかというとですね、正直観光において、その地域の人と関るような機会なんてそもそもそんなに多くは無いと感じたからです。(主観ゲーです。ごめんなさいね)
思い出しても見てください。(例外はあるとは思いますが)、学生が修学旅行で、本当に学びを修めたがりますか? って話です。大抵の修学旅行生は、(これはやはり私個人の経験なので、ただの蓋然敵真実でしかないのだけれど)「思い出作り」にやってきます。特に今の学生なら、何を学ぶかよりも、誰かと修学旅行に行くこと、写真を取ること、あわよくばロマンスを作ること、という類のことの方が、大事に感じるはず。
いや、これは今の学生に限らず、大抵の学生に共通していることだろう。そして大方の観光も、この延長線上みたいなもので、「③土地に暮らす人々と話をすること」のような、ワンダーラスト型の観光を行う人は、そうそうはいないのではないかと、私はやはり考える。
(というか、修学旅行に行くやつ自体、そういう目的しかないとさえ思っている)
換言すれば(つまり)
観光に行く人は、(もちろん例外はある!)大抵、日常からの逃避によるごらくや休養を求めているのだろう。
ここで、「林幸史」さんの記事から、引用したいと思う。
その土地の地域資源と住民とのかかわりを知るためには、土地に暮らす人々と話をしてみる必要があります。〔中略〕彼らにとってのアイデンティティや精神性にまで触れることができるかもしれません。地域の人々と同じ目線で話を聞くことで、彼らのものの見方や考え方を知ることができるでしょう。(林幸史、2020)
この引用文で想定されている観光客の層って、「めちゃくちゃレベルが高いというか、教養や好奇心にあふれているんじゃない?」と私は思ってしまいました。
「観光」の元々の起源は、トマス=クックが、労働者の余暇時間における大量の飲酒を避け、その余暇時間を又別の活動で過ごしてもらいたいという健康運動の一環として始まったものです。
ちなみにその前に、(私の記事では何度も書いているのですが)グランドツアーという、特権階級貴族による教養旅行というものがありました。掛かる時間が、10年以上にあるということもあり、目的地は、イタリアという17~18世紀において、貴族の皆が憧れるような土地でした。(レオナルドダヴィンチやボッティチェリなどが有名かな・・・?)
林幸史さんの、「観光の本質③」は、この貴族によるグランドツアー、教養旅行に似ているなぁと、私は感じました。
否定しているわけではないですが、(本当に否定しませんよ!)
「その土地の地域資源と住民とのかかわり」「アイデンティティや精神性」「彼らのものの見方や考え方」というものを、一般の観光客は求めているのでしょうか?。
修学旅行のように、そんなに「非日常」や「他者性を持った他者」を、観光客が、求めているとは思えません。むしろ、非日常であるはずの「観光」に「日常性」を求めていると言った方がよいかもしれないと、私は思います。
観光は、一見それ自体「非日常」の領域に存在するものに見えますが、観光客は、むしろ日常性(安全性)を、その中に求めてしまうような、日常の延長線上の存在に見えてしまうのです。
観光地(特に海外)で、wi-fiが繋がった時、
安心しませんか?
日本の店があった時、(スタバとか)
日本の料理屋、日本語を耳にしたとき、
安心しませんか?
観光という非日常的空間では、人間は、不思議と日常性を求めてやまないと、私は考えます・・。
観光は、もう日常である。
私は、「林幸史」さんの「観光の本質」は、むしろ三木清の云うような「旅」の本質に近い気がしてしまうのです。実際、林さんは、記事の中で、三木清の「人生論ノート」の、「旅について」という章から引用していることがうかがえます。
そういった点からも、林さんは、「観光」において、「旅」というものを意識しているのかなぁと思います。確かに、逃避という要素が強い観光は、旅に似るところがあるのかなぁと。
さて、ここまで色々と、書いてきました。
「観光学」「観光」について、ただ単に「観光客」の視点だけから書いている人が、あまりいないので、こういう林さんが書くような記事は、読んでいて楽しいです。
読んでくれて、ありがとうございます。長文失礼しました。
と
今日も大学生は惟っている。
引用・参考文献
岡本伸之.(2001).観光学入門 ポスト・マス・ツーリズムの観光学.有斐閣アルマ
note.(2020).『観光の本質とは?』.https://note.com/yo_hayas/n/nfb139d689f35(2020/9/01アクセス)
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

