
貧困と脳 「働かない」のではなく「働けない」 |鈴木大介 幻冬舎新書 レビュー
案外ちょっとした拍子に脳みそがまともに働かなくなる。
こんなことあるのかもしれないと思った。
というのも、今は大丈夫になったんだけど実は一昨年の年末コロナ直後の症状としては一人暮らしがままらないというほどではなかったんだけど、理解力が落ちて、微妙に集中できなかったし、以前より長時間PCの前に座ってられなかった。
2024年の記事がモノの話に始終してるのは特に前半は本がマジで読めなかった。
そして、自転車を運転しててずっと視野が狭い気がしてた。
そんなんで車買ったのかといわれそうだけど、契約したころで友達とそんな話をしながら、ふと思い立って鏡もみないでやったからどんな顔になってるかわからないけど、手とかは使わずに右目と左目をできるだけ外側に向けるような意識をして2〜3回キュキュッってしたら全てが元に戻った謎。
ついでにそれまで若干霞がかってた脳も晴れた。なぜそれで治ったかわからんのだけど、すっきりとした状態で車運転してるから大丈夫。コロナ後しばらく寄り目だった?かどうかは鏡みても思わなかったし、別に眼力だけで外側を向けようとしたあとに鏡見てもロンパったりしてない。
でも、なぜかそれと供に理解力も復活して本も読めるようになった。
なんだったんだろうね。
ということで今回はこの本を読んで思ったこと。
女性と貧困に対して取材した著者が「高次脳機能障害」になったことにより、話の本質を理解したという内容の本。
元々は普通に働けていた人が、脳の疲労により考えられなくなっちゃう、認知がおかしくなるという内容なのだけれども、ヤミ金が圧力という意味ではなく職場まで赴いて銀行へ一緒に行って返済料金を回収するのを「サービス」としてやっている理由や、行政書士が「破産させることによって、不安が解消されて顧客の頭が動き出す」話とかなんだけど、これさちょっとわかるのよ。
お金への不安が思考を止めさせる
どこの社長だったか失念してしまったけど学生時代に読んだ本の中で「借金をすると頭がまわらなくなるから無借金経営している」っていう言葉が結構印象に残ってて。宇佐兎三自身別にそうなるほどお金がなかったことがあるわけじゃないんだけど。
ホリエモンとかは「勝てるならどんどん借金して事業を回したらいいじゃん」っていっててそれはそれで、論理的にはめっちゃわかるの。
あとは不動産経営とかも基本は借金をして、他人の金で返すことで自分の資産を増やすが基本だったりするってのは本で読んでて知ってるし、そもそも経済自体を成長させるには借金でレバッジをかけるのも理論としてはわかる。
そして、特に住宅ローンの金利を考えたらどう考えてもローンを組んでその分を投資に回した方がお得に決まってる。
頭ではわかってる。
でも、宇佐兎三の心情は、キャッシュでこの家を買ったらめっちゃ心が落ち着いた。
管理費とかかかるマンションにしなくてよかったと思ってるし、なんならもっと田舎で月3万くらいの家賃で暮らした方がお得かもしれない。
でも、実際はリフォームしてるし自分でメンテをしなきゃいけないとかあるけど別にあるからお金払って変えてるだけで、どっちにしろ払わなきゃいけない光熱費とかの固定費はともかくとして、とりあえずのところは年間3万円程度の固定資産税払ってたら追い出されないとか、気持ち的にめっちゃ楽。
あと3〜4年で引っ越そうとはおもっているけれど、別にいい物件がみつからなかったり、お金に都合がつかなかったら住み続ければいいし。1年長く住むごとに100万浮くくらいの計算だし。現時点ではリフォーム代出るくらいに上がってるけど出口の時点では相場次第で持ち出しが発生するかもしれないけどまぁそれぐらいは。
そして、この安心感は新築の綺麗な家に住む快適さとも変えがたい気がしてる。
コロナ後、なんか脳みそいまいち働きが悪かったけど、そこまで悲観的にも不安にもならなかったのって、払い切ってる家があるってのがめっちゃ大きい。何が起きても前ほど不安じゃないんだよね。これは理屈じゃない。
追い詰められてるってほどじゃなくても、なんとなくそう思う部分があったわけだから借金で追い詰められてたらなおさらの話なんだよね。
認知能力の得手不得手はある
思考が止まってないナチュラルな状態でも。
宇佐兎三はの場合
口頭+ランダムな組み合わせにものすごく弱い
モンハンというゲームで珠を装備してステータスを割り振るっていうのがあるんだけど、正直に複数プレイヤーでの通話で誰かが誰かにその説明をしててもあの早さだと言われたら理解してないから覚えてないんだけど、同じことを聞いてさっきも説明してたじゃんっていわれることがたびたびあった。
その中で一番頭が良かった子に
「脳内で映像化できるようなイメージがない、ランダムっぽい組み合わせは基本口頭で言われても理解できないし覚えてられないからスクリーンショットで頂戴。見たらわかるから」
と伝えたことがある。
ここの難しさは、映像化できるようなストーリーのある話だと相手の話が正確で詳しいほどに、相手の言ってないことまで見えたりする。
それを馬鹿正直に言うと、「え?霊視?」って言われるが別にそんなことなくて、状況を映画みたいに映像でリアルタイムレンダリングをしている。
透視なんてできない証拠に、話で聞いた場所が宇佐兎三の想像通りだったことなんて一度もないし、なんならリアルの方がいつだって100倍解像度が高くて素敵だ。(といってみたが観光地に関しては例外もあるw)画家とか漫画家に向いてないなぁと思ったのはそのあたりなんだけど。
でも、そこで見えた映像は覚えてられる。
デザインをするには便利だけどね。相手の言ってることを割と再現できてるっぽいから。
でも相手からしたらそれができてこっちができないのかがわからないってなりがちなんだよね。
英単語は学校を卒業したあとに勉強した時に結局漢字の部首と作りみたいなかんじで接辞から覚えてみたり、街を歩きながら見えるすべてのものを英単語と結びつけるってやっていったら克服できたけど、習いたての英単語も化学も自分がどう記憶してるのか知らないころはランダムな文字列にしか見えなくて本当に覚えられなくて地獄だった。
数字に弱いのと数学に弱いのは別であり
文脈の中での数字はもちろん意味があるんだけれども、その数そのものは大抵がランダムなわけで正確には覚えられない。
口頭で言われた数字は、日本語ならわからないことはない。ただ口頭で聞いただけじゃ暗算はできない。
さらに、外国語で二桁以上の数字を言われると、フリーズしちゃう。
英語もフランス語もダメ。
30秒くらい考えたらわかるんだけど相手からしてみたら普段そこそこ早口なのに数字出した途端止まるとテンポがアレすぎて、一緒に海外旅行へいった妹には「え?他の会話全部やってくれてるのに数字わかんないの?レジで数字きいたらいいだけなら私できるから聞くよw」といわれ、日本語が喋れるフランス人の友達が難しい話を英語ではなしてるときも数字だけは普通に日本語、日本語が喋れないドイツ人の友達も数字だけは日本語を覚え始めて「日本語の数字簡単だから大丈夫w」と数字は「ハチ ヒャク ダラー」みたいなかんじで日本語で言う。
だいたい外国語で数字をきいたとき一桁目で止まってフリーズしちゃう

マジでモヤモヤもみえるんよなぁ
いつもなんで?って聞かれるし練習もしたし相手も練習に付き合おうとしてくれるけど、フリーズするものはフリーズするし正直なんでかはわかんない。
でも暗算で掛け算をするときに、九九を苦労して覚えた時につかってたチャレンジの付録だった指であたためると色が変わる表のその部分だけがあったまってるのが未だに見える。
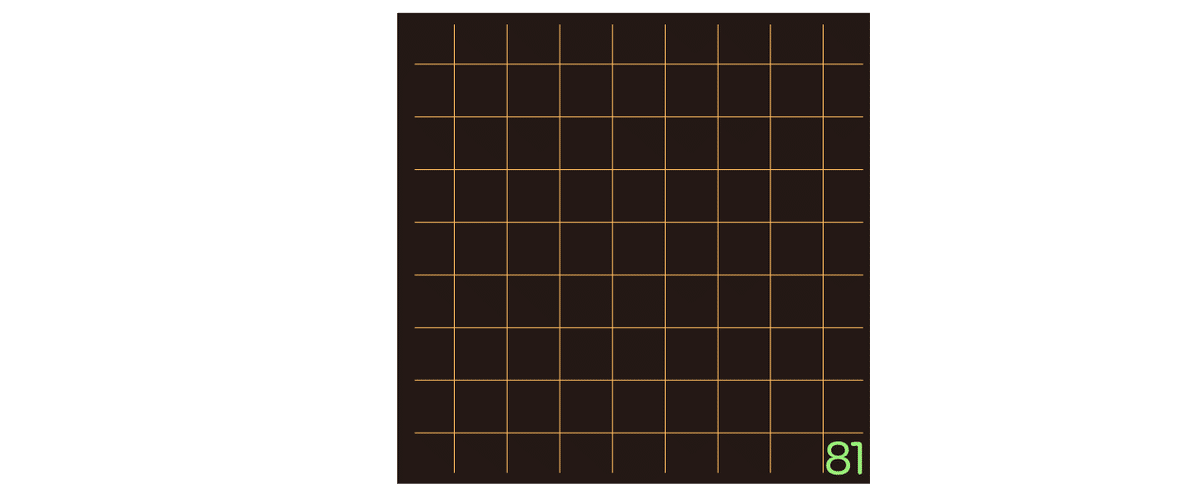
下手すると子供のころの自分の指まで見えたりする
たぶんこの覚え方が問題な気がする。
掛け算がこんなかんじな時点で気づけと思うんだけど、映像でしか物が覚えられてないってはっきりと気づいたのが社会人になってからだったりして、もっとそれに早く気づけてたら学生時代もっと楽だったんだろうけど、そもそもが天才と呼ばれる人が映像記憶だと聞くけどそこまでじゃない中途半端だったから余計に難しいんだろうなぁ。
でも、別にだからって数学がめちゃくちゃ苦手かというと、公式が覚えきれなくて高校2年生くらいで挫折しちゃって文系大学に行ったのは確かなんだけど、公式なんか覚えなくても式をひねりだしたらいい高校1年生くらいまでは理系のクラスを選択してたくらいには数学得意だったんだよね。
で、大人になったら大概の話は紙と鉛筆と電卓のあるところで数字を書きながら考えたらいいから、生活にはあんまり支障はない。
理解力と記憶
宇佐兎三の場合はフリーズしちゃうポイントがたまたま口頭で言われた外国語の数字くらいだったりするので、日本に住んでいる限り特に問題ないし(電子マネーの普及でますますストレスを感じなくなってる)海外旅行も基本はクレカ使ってるから問題ないし、レジがなくて現金しか使えないところでも「Write down, please」って言ったら、みるからに向こうからみたら外国人なので仕方ないって書いてくれる。
でもこのフリーズポイントが日本語の数字もだったり、日本語で特定ジャンルの単語だったら?
ってあたりなんだよね。
まぁ日本語喋ってても英語をしゃべっててもわかんなかったら宇佐兎三の場合は聞くんだけど、その説明すらわからないとかだったらまぁ目も当てられない。で、宇佐兎三の場合は口頭できいてわかんなくてもきっちり文章で書いてあれば読んでわからないってことがよっぽどの専門書を予備知識なしに読み始めるとかじゃない限りそんなにないんだよね。
ただ、世の中には口頭で聞けばわかっても、文章が読めないという人も多いっていうのはそうだと思うし、どっちにしたって理解できてないことなんて覚えてられない。
それは確かだと思う。
役所の申請申し込みがわからない
そんなこともまぁありうるって思ったよ。で、本の中で指摘されてたんだけど特に役所の申請書見づらい問題があって、なるほどって思ったのがWEB申し込みであれば基本上から全部記入していきゃいいんだけど、役所の申請書ってなんか縦も横もツメツメで、さらに役人用摘要欄がへんなところにあったりする上で一色刷りだったりするのは、確かにわかりづらい。
たとえば年末調整の紙とか、アレ、マジで提出する側から見たデザイン最悪じゃん?w
あれはマジで記入例見ないとわからないし、苦手じゃなくてもめんどくささは感じる。
ウェブの申し込みフォームは割としょっちゅう作ってて、紙の申し込み用紙も何度か作ってる身からすると、紙の常識の話でフリガナは小さくとか電話番号は生年月日と並んでてってレイアウトをやりたくなりがちなんだけど、上から全部必須項目で余白をケチらずに全部同じ文字の大きさで書いたら良いWEB形式の申込書が、いかにやさしいのかを本を読んで気づいたんだよね。
次からは絶対そうしようと思った。
あと、わかりづらいケースでも保険を契約しにいったときに窓口のお姉さんが必要箇所全部鉛筆で印つけるか、内容まで書いてくれるパターン。あそこまで人海戦術的に対応してくれるならいいと思うけど、基本はWEBっぽい形式の申込書がそもそもわかりやすい。
全部チャット形式のはちょっとイラッとしたけど、あれのが親切って人も少なからずいるんだろうなぁ
総合すると
結局のところ、みんながみんなそのレベルの話理解できると思うなよってことなんだろうなぁ。他のところは理解できたり、それまでは理解できてても何かの拍子に理解できなくなったり、またはその部分だけ理解できない人もいる。
そもそもこの本を読もうと思ったのが、岡田斗司夫氏の動画でこの漫画と供に紹介してたからなんだけど。
で、この漫画の主人公は一番初めにセミナーで騙されるところからはじまるらしいんだよね。
1000円で売ってる本の内容を噛み砕いたような薄い内容に嘘を追加したようなセミナーに10万払う人がいるのが不思議で仕方なかった。
でも、なんか情報商材売ってる今は縁が切れてしまったnoterの話を総合するとね、「はじめて本を読みきりました!」って言われて気づいたって言ってたんだよね。儲けられそうな情報は知りたい、でも普通の本だと理解できない人を導くのが役割だと。
つまり、1000円で売ってる内容を薄いけどわかりやすい言葉に翻訳してくれたと思う人に10万払う人がいて、そこに需要があるってことなわけで。
それが情報弱者向けのぼったくりになっているならばいまいちだけれども、もしかしたら適正な価格でそういうサービスをするというのも案外サービスとしては重要なのかもしれない。
あーでも考えてみればね、高校2年生以降の数学って挫折してて自分では赤点だったんだけど、平均点程度の友達や妹から解説文の翻訳を頼まれるってことが度々あってな。完全に投げてて前後の話がわからないから、そこに書いてあることだけを理解した中でただただ噛み砕いてするんだけどなぜか相手は納得して帰っていく。宇佐兎三は前後がわからなくて答え出せないのに相手は宇佐兎三の解説を聞いたら答えを出せるという不思議。なんで私に聞くのかきいたらどうもわかってる友達の解説は当然わかってる前提として話されるところが自分でよくわかってないから、結局わかんないんだそうだ。宇佐兎三の場合はそもそも分かってないから、文章からとりうるだけの解釈を並べてく。こういうことならこうなるし、こういう感じならこうなるって感じで選択肢を出してって、これな気がする!って言われたので話を進めてく。
なお妹に解説をしてるところを親に目撃されたときは、「なんで赤点だったくせに解説できんのよ」ってなってた。そりゃそうだw
そう、わかってる人の「当然わかってるべきこと」ってのが曲者。
ビジネスで間口を広げたかったり、行政みたいな市民全員を相手にするサービスをしているならば特に。
で、インターネットがまだどちらかというと大学生だったり馬鹿高いパソコンが買える一部の人のものだった時代は知的レベルが良くも悪くも幅が狭かった。
でももっとインターネットが広がったことで、いままでだったら見なかった知的レベルがそこから出る言葉から見えるようになってきた。だからこそこういう話が可視化できる形で出てくるようになったのではないかと思う。
いままでならおそらく小学生ほど幼すぎず、ふるいにかけられる前の中学の先生だけがこの問題を知ってたとかそんなところだと思う。
自分が普通だと思ってる人も、そういう人もいるってこと、そして何より自分がそうなるかもしれないと思いつつ読んでみると、他人への理解が深まる。
是非みんなにオススメしたい本だなと思った。
いいなと思ったら応援しよう!

