
世界を、何となく覆う「悲しみ」~新美南吉『川』(他)

今回は、『ごんぎつね』であまりにも有名な新美南吉の作品群の中で、彼が晩年に残した「少年もの」を中心に取り上げていきます。
また、スタイルを変えながらも彼が一貫して表現しようと努めてきた「悲しみ」とはどのようなものだったのか等も、あわせて辿っていきます。

主な作品と執筆年
まず、29才という短い生涯における南吉の作品群を、初期・中期・後期と、大きく三つの時代に分けてみます。(太字は、今回言及するものです)
初期
昭和3年~15歳「赤蜻蛉」・童謡「喧嘩に負けて」・詩「詩人」
昭和4年~16歳「張紅倫」「巨男の話」
昭和6年~18歳「ごんぎつね」・童謡「窓」「ひる」
昭和8年~20歳「こどものすきなかみさま」「丘の銅像」「手袋を買いに」
南吉は、愛知県の半田町に生まれました。4歳で母を亡くし、6歳のとき継母を迎え、8歳で亡き実母の実家へ養子に出されました。さびしく、孤独な生い立ちだったとされています。
旧制半田中学校(5年制)へ入学した彼は、2年生のころから童謡、童話をつくりはじめ、さかんに雑誌に投稿しました。たくさんの作品が掲載され、彼は創作の力を伸ばしていきます。
北原白秋が主宰する有名な「赤い鳥」にも作品が取り上げられるようになります。
また、旧制中学を卒業してから、小学校の代用教員の職に就いた経験も、南吉の創作人生に大きな影響を与えます。

最も初期の「巨男の話」は、こんな物語です。
ある日、巨男の母親の魔女はお姫様を白鳥に変えてしまいました。
元のお姫様に戻すためには、白鳥が涙を流さなくてはなりません。
心優しい巨男は、どうにかして彼女の涙を流す試みをしますが、白鳥は一粒の涙も流しません。
巨男は最後の手段として、自らの命を捨てます。
お姫様は泣いて言います。人間になど戻りたくなかった、
白鳥のまま、ずっとあなたの肩にのっていたかった、と。
彼は多くの作品を残しましたが、恵まれていたのは、そのあらゆる段階において「読者」や理解者・協力者がたいへん身近にいたことでした。
『巨男の話』を子どもたちに朗読したときのことを、南吉はこう記しています。
づっと前に作った創作童話「巨男の話」を子供にしてやった。ひそひそと泣く子があった。私はうれしくなった。私の頭が作りあげた話が、子供の美しい涙に価するのが。
また、『ごんぎつね』は南吉18才の時に『赤い鳥』に掲載されますが、その原稿を大幅に赤入れしたのが、「児童文学の父」と呼ばれる鈴木三重吉でした。ここで南吉は、最高峰の添削指導を受けることにより、創作上の技術を磨くことができたのです。
山の中の森に住み、村にやって来てはいたずらばかりする、ひとりぼっちのごんぎつね(以下・ごん)がいました。
ある日ごんは出来心で、村人の兵十が捕まえた魚やうなぎを逃します。
しかし兵十の母の死をきっかけに、ごんはいたずらを後悔し、償いの気持ちから兵十の家に毎日食べ物を届けるのです。
ある日ごんが家の中に入っていくのを見掛けた兵十は、火縄銃でごんを撃ってしまいます。
そして土間に置かれた栗を見て、食べ物を毎日届けてくれていたのがごんだと気付くのでした。
この「ごんぎつね」でも知られるように、すでに初期から、南吉の主な作品の中心には深い「悲しみ」があります。そしてその味わいは徐々に深まり、純度を高めていく感があります。
中期
昭和9年~21歳 詩「貝殻」
昭和10年~22歳「でんでんむしのかなしみ」「ひとつの火」「木の祭」「赤いろうそく」「かげ」「にひきのかえる」など幼年童話約30編・小説「中学二年生の時」「除隊兵」・詩「ペンだこ」「去りゆく人に」「墓碑銘」「弟」
東京外語大に進学した南吉は、英文学を中心に西洋の文化を学び、ドストエフスキー等に感銘を受けます。
また、ここでも彼は文学仲間たちに恵まれます。
「かきねの かきねの まがりかど」で知られる童謡「たきび」の作者巽聖歌と知り合ったのもこの頃でした。
聖歌は南吉の死後、大戦が終わってから、たいへんな労を注いで南吉が残した作品を全集に編纂し、彼の名を世間に知らしめたのでした。

早期から漂うペシミズム
多くの童話や詩、小説を残した南吉ですので、様々なタイプの作品がありますが、童話を発表し始めた10代から、根底にある「悲しみ」は、ある面頑固なまでに彼の以降の作品群に表れています。
この時代に書かれた『でんでんむしのかなしみ』は、こんな話です。
一匹のでんでんむしが、ある日、自分の背中に、悲しみがいっぱいつまっているのに気づきます。
でんでんむしは、その悲しみに押しつぶされそうになり、友達のところへ助けを求めに行きます。
しかし、友達は言うのです。
「あなたばかりではありません。
わたしの背中にも悲しみはいっぱいです」と・・・
つぎつぎと尋ねる友達たちも皆、同じことを言うばかりです。
とうとう、でんでんむしは気づきます。
悲しみは誰もがもっている。
そして、自分も悲しみを乗り越えて生きていかねばならないのだと・・・
若くして、読者である生徒に相対し自作を朗読した経験を通し、南吉の中に確信が生まれます。
それは、こどもたちが何に心を動かされ、何がその心に深くのこるのか、ということでした。
当時のことばに彼の生涯を貫く創作の核が記されています。
やはり、ストーリィには、悲哀がなくてはならない。悲哀は愛に変る。(中略)俺は、悲哀、即ち愛を含めるストーリィをかこう。
大戦の最中にあって、当時は、このような悲観的な内容のものは異質でした。国威を高揚させる教育が掲げられる中、反骨心の強い南吉は、我が道を貫きます。
彼は、国策に準じる同年代の作家たちに辛辣な言葉を投げています。
−−− その辺にざらに見うけられる、郵便切手ほどの愛国主義を貼りつけている作品、ミカン水ほどの感傷をたたえている作品、豚のしっぽ程の童心をふりまわしている作品 −−−
彼にとって、「読者に向けて書く」ということは生きることそのものであり、国政や状況が変わればコロコロと表現や主題が変わるべきものではない、という文学的な志が人一倍強かったのでした。それだけ真剣に、読者であるこどもたちに向き合い、一途に文学に取り組んだのでした。
後期(晩年)~この世界にただよう、原初的な「悲しみ」
南吉が大学を出るころ、日本はちょうど太平洋戦争に向かっているさなかでした。景気は悪化し、南吉もなかなかよい職にありつけず、苦労をします。
しかし、そんな彼を見かねて、彼の才能を確信していた教育関係者らの尽力によって、彼は愛知県安城市の女子高校(当時は小学校を卒業すると、女子は4~5年の「高校」に進学した)にて国語と英語の教職に就きます。
昭和14年~26歳「最後の胡弓弾き」「久助君の話」・小説「花を埋める」・詩「牛」「合唱」
昭和15年~27歳「川」・小説「自転車物語」「家」「銭」・詩「疲れた少年の旅」
昭和16年~28歳「良寛物語 手毬と鉢の子」「嘘」「うた時計」
昭和17年~29歳「ごんごろ鐘」「貧乏な少年の話」「おじいさんのランプ」「花のき村と盗人たち」「牛をつないだ椿の木」「耳」
昭和18年 「狐」「小さい太郎の悲しみ」「疣」・小説「天狗」(絶筆)
この約5年間は、結果的に南吉にとって晩年となってしまいます。
しかし、創作に集中するための経済面及び環境面に恵まれた、最も幸福な時代でもありました。
生徒たちとの交友は生涯続きました。中でも各生徒への作文指導に力を注ぎ、手製による交換詩集を6冊出しています。
この時代に並行的に書かれたのが、「久助もの」を中心とした、少年たちの日常と心理を描いた一連の小説群でした。
ここで南吉は、これまで日本の児童文学になかった領域を開いていくことになります。

南吉は、20過ぎに結核を発症します。この時代、結核は死病として恐れられており、特に青年が早逝することが多い病でした。
南吉は結核によって母を29で亡くし、叔父も同じ歳に同病にて他界しました。自分も同様に早逝することを予感していたのかも知れません。
この時期も、南吉は童話を発表し続けました。しかし、この頃から後に「少年もの」と呼ばれるようになる作品群を集中的に書きます。

これらの「少年もの」は、小学校高学年の主人公「久助君」のシリーズが中心となります。
設定は様々なのですが、どの作品の主要シーンを切り取っても、同様の空気が漂っているのです。まるで画家が、同じモチーフを何度も繰り返し描き出そうと試みているように・・・その「本質」を、「純度」を見極めるために。
その「空気」とは、「ばくぜんとしたかなしみ」のようなものでしょうか。評論家の谷悦子氏は、以下のように端的に表しています。
南吉が感じる孤独や寂しさは、何か理由や原因があるわけではなく、人間の深層に潜む普遍的な感情なのです。
少年もの①「久助君の話」
例えばまず、26歳の時に書いた「久助君の話」は、以下のような内容です。
主人公の久助君は、学校で優秀な成績をとってしまったことがきっかけで、
学校から帰ってきてすぐ一時間、お父さんの言いつけで勉強しなければならなくなります。
勉強を終えて外に遊びに出た久助君が、兵太郎君の姿を見つけます。久助君は兵太郎君に遊ぼうと誘うが、兵太郎君は乗り気ではありません。
焦れた久助君は兵太郎君に組みつきます。そしてしばらく冗談半分の取っ組み合いが続きますが、そのうち、相手が冗談なのか本気なのか、久助君にはわからなくなってきます。
半日かかった取っ組み合いを終えて、起き上がった兵太郎君の顔を見て久助君はびっくりします。
久助君の前に立っているのは兵太郎君ではないのです。見たこともない、さびしい顔つきの少年がそこにいたのです。
これは誰だろう? しばし呆けていた久助君は、すぐにいつもの兵太郎君であることに気づきます。
しかし、あの不思議な思いは、久助君にとって一つの新しい悲しみとして刻まれてしまいます。
世界(他者)と自分との間に垣間見える「違和感」のようなものでしょうか。

少年もの②「川」
次の年に書かれた「川」では、同じ久助君と兵太郎君が登場します。
しかしここでは、現実離れした、少し不思議な話が展開します。
ある秋の日、少年たちが川べりにやってきます。
久助君、兵太郎、薬屋の音次郎、森医院の徳一の四人です。
「川の中に一番長く入っていた者に、これやるよ」音次郎がそう言って美味そうな柿を取り出します。
音次郎の提案にのって服を脱ぎ川へと入ると、水は冷たく、川の中に残ったのは兵太郎だけとなります。
勝負は決まったのに、見栄を張りたいのか、なかなか川から上がってこない兵太郎を尻目に、三人は懸賞の柿を食べてしまいます。
ようやく川岸に着いた兵太郎はじっとして動かず、顔は真っ青です。しかし、日頃から「死んだふり」で人をよくだます兵太郎のことなので、皆はさほど気にとめません。
翌日、兵太郎は学校を休みます。そして、五日、七日、十日……、兵太郎は学校へ来なくなってしまいます。
久助は、音次郎と徳一だけは兵太郎のことで心を痛めているのを感じていましたが、誰もそれを口には出さず、互いに避け合うようになってしまいます。
数か月が過ぎ、冬が訪れます。そして、兵太郎の机が教室から廊下へ出されてしまいます。
久助と音次郎は薬を持って兵太郎の家をたずねます。しかし中から人の気配は感じられず、二人はそのまま家の前を通り過ぎてしまいます。
久助は友達と話したり笑ったりするのが嫌になり、暗く沈み込んでぼんやりすることが多くなります。
そして三学期の終わり頃、兵太郎が亡くなったという噂が流れます。
しかし、久助の心は、その報に接して驚かぬほどくたびれていたのです。
ところが、ある六月の夕暮れ・・・
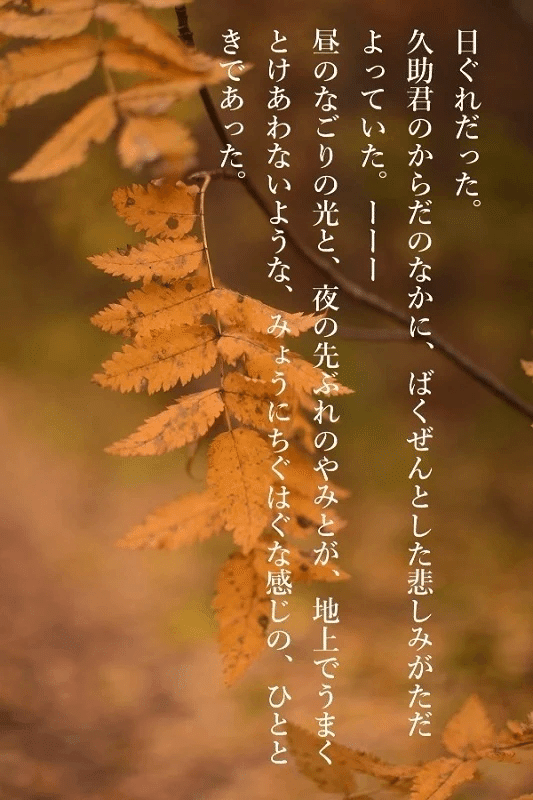
少年もの⓷「疣」
あるいは、『疣』でそれ・・・「悲しみ」は、以下のような設定で表されます。
夏休み、田舎に住む松吉・杉作兄弟のところに、いとこの克己が遊びにきます。三人はたらいをかついで山の池に行き、それにすがって池を横断しようとします。
調子よく泳ぎ出した三人でしたが、池の真ん中で疲れて動けなくなってしまいます。泣き出しそうになる杉作と克己を見て、松吉は「よいとまアけ」ともと来た方向にたらいを押しはじめます。
それは田舎のかけ声で、町の子の克己に聞かれるのは恥ずかしかったのですが、三人は「よいとまアけ」と声を合わせて、なんとか土手まで辿り着きました。
家に帰ると、すっかり絆で結ばれた松吉の右手のいぼがほしいと、克己は言い出します。松吉はいぼが克己に移るようにおまじないをします。翌日、克己は町の家に帰っていきます。
秋、松吉と杉作の家では収穫のお祝いにあんころ餅を作ります。二人はそれを町の克己の家へ届けに行くことになりました。
二人が克己の家に着くと、おじさんもおばさんも、克己も留守でした。克己の家は床屋をしていて、そこには二人と同じ村出身で、修行にきている小平がいました。
どうやらみんな出かけているらしく、松吉と杉作は帰りを待つ間、小平に髪を刈ってもらうことになります。昔は一緒に遊んでいた小平が、仕事をしている姿を見て、松吉は一抹の寂しさを覚えます。大人になるというのは、ふざけるのをやめて、まじめになる約束のように思われたのです。
そうしているうちに、克己が学校から帰ってきます。しかし克己の松吉と杉作を見る目は、知らない人を見るように冷淡でした。そして誘いにきた町の友達と一緒に出て行ってしまいました。
帰り道、青々とした坊主頭の松吉と杉作は、魂の抜けたような顔をして歩いています。すると突然「どかアん」と、弟の杉作が大砲の音マネをはじめます。松吉は思います。
――人にすっぽかされるような、こんなことはこれからさきいくらでもあるに違いない、俺たちは、そんな悲しみになんべんあおうと、平気な顔をしていけばいいんだ――
そして二人は、ドカンドカンと大砲をぶっぱなしながら、心を明るくして、家に帰っていきます。
このような景色や感情は、程度の差こそあれ、誰しもが体験するものではないでしょうか。普通はやり過ごされるものですが、後になって振り返ってみると、人生に大きな意味を持っているものなのかも知れません。

また、「小さな太郎の悲しみ」では、さらに幼い少年が主人公ですが、早くから「諦念」さえ感じさせます。
お婆さんと二人きりで暮らす太郎が、捕まえたかぶと虫で遊ぼうと友だちを訪ねて回ります。
金平ちゃんは腹痛で寝ていました。ひとつ年上の恭一君は三河の親戚に預けられていました。
そこで彼は最後に、車大工の息子で遊びの名人である安雄さんを訪ねます。
しかし、真剣な表情で道具を研いでいる安雄さんに小声で声をかけると、おじさんに「安雄はもう大人だから、子どもとは遊ばん」と突っぱねられてしまいます。
病気なら治ればまた遊べる。よそにもらわれても盆や正月にはまた会える。 しかし、大人になった安雄さんとは、もう 二度と同じ世界で遊べないのです。
そして、こう続きます。
もう、ここにはなんにものぞみがのこされていませんでした。小さい太郎の胸には悲しみが空のようにひろくふかくうつろにひろがりました。
ある悲しみはなくことができます。ないて消すことができます。
しかしある悲しみはなくことができません。ないたって、どうしたって消すことはできないのです。いま、太郎の胸にひろがった悲しみはなくことのできない悲しみでした。
そこで小さい太郎は、西の山の上に一つきり、ぽかんとある、ふちの赤い雲を、まぶしいものをみるように、眉をすこししかめながら長いあいだみているだけでした。かぶと虫がいつか指からすりぬけて、にげてしまったのにも気づかないで――
これはもはや、単なる「子どもの悩み」の域を超えています。
南吉の作品は当時、「このような少年は子供らしくない」として一般の文学的評価は低かったと言われています。
しかし、子どもであっても、このような体験をしたり世界の不条理をうっすらと垣間見る瞬間があるのも、事実ではないでしょうか。
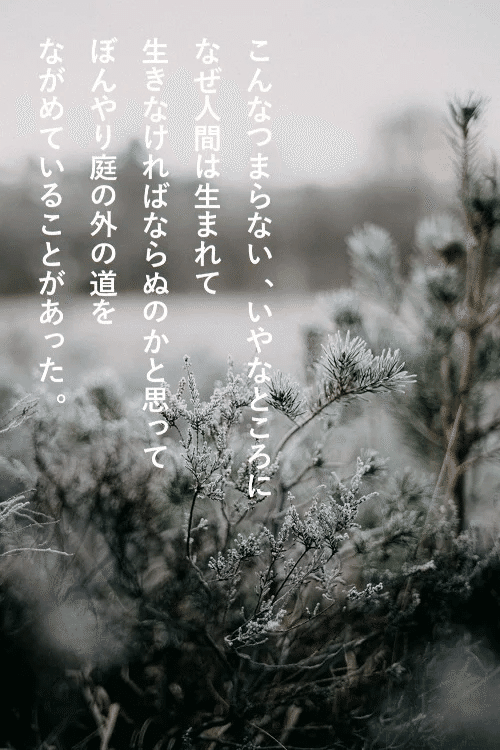
そして南吉は、こんな考えも綴っています。
人間の心を筍の皮をはぐようにはいでいって、その芯にエゴイズムがあるといふことを知る時われわれは生涯の一危機に達する。つまり人というものは皆究極に於てエゴイストであるということを知るときわれわれは完全な孤独の中につきおとされるからである。しかしここでへたばってはいけない。ここを通りぬけてわれわれは自己犠牲と報いを求めない愛との築設に努めなければならない。こういう試練を経て来た後の愛はいかにこの世をすみよいものとすることであろう。
南吉の詩
この晩年の数年間は、南吉にとって創作上、最も幸福な時期でした。
高校教師として安定し、かつ、好きな文学をその生徒に直に指導できるという環境の中、南吉のインスピレーションは大いに発揮されたのでした。
この時期に、先に挙げた複雑な心理を扱った「少年もの」が書かれています。登場するのは主に少年たちですが、きわめて文学的な内容を理解する辛辣な「読者」として、女学生の彼女たちは適していたのかも知れません。
また、この時期に南吉は、生徒たちに「詩」を指導するとともに、自身もいくつかの重要な作品を残しています。
生徒たちとの平穏な文学的交流の時期でもあって、南吉のあたたかい心情が素朴に語られた以下のような作品があります。
「合唱」
私は少女達のコーラスの中に
花束のやうな心を抱いて立っている
ーーー
少女たちのコーラスは私をすぎて流れ
少女たちのコーラスの届くところから
ことしの春がはじまる
しかし、その一方で、いかにも暗く不気味な「現代詩」を同時期に残しているのも、南吉らしさと言えるかも知れません。
「疲れた少年の旅」---
カランカラカラ
カランカラカラ
カランカラカラ といふ
音が
遠い遠い
ずっと遠い
西から
疲れた少年に
聞こえてきた
--- とうとう来たなと
疲れた少年は思った
‐--「ヂヤさいなら」
「ア、サヨナラ」
それから疲れた少年は
空缶の行った方へ
長い旅にたった
南吉の志は半ばにしてついえてしまいましたが、彼はそれまでの児童文学に、かつて誰も踏み込もうとしなかった表現領域を切り拓いたのでした。

黒井健・絵 1988 偕成社

新美南吉(1913―1943 愛知・児童文学者)
10代の末にすでに『赤い鳥』に「ごんぎつね」その他が掲載された。1932年(昭和7)東京外国語学校英語部入学、小説、童話、童謡を書く。卒業後、貿易商に勤務したが喀血で帰郷。不遇な時代を経て、38年安城高等女学校教諭となる。また巽聖歌編の『新児童文化』に「川」「嘘」などを発表。41年『良寛物語・手毬と鉢の子』を、42年第一童話集『おぢいさんのランプ』を刊行。同年5月には「牛をつないだ椿の木」「百姓の足・坊さんの足」ほか数編の傑作を集中的に書くが、翌年3月咽喉結核で没。死後、第二童話集『牛をつないだ椿の木』、第三童話集『花のき村と盗人たち』(ともに1943)が刊行された。その作品は第二次世界大戦後高く評価され、宮沢賢治と並び称せられるに至る。

Planet Earth
いいなと思ったら応援しよう!

