
原人にだけ見える風景~梶井基次郎『檸檬』(他)

今回は、有名な『檸檬』を中心に、梶井基次郎の作品といくつかのエピソードをあわせて紹介していきます。

野性の「詩美」
夜の果物屋に陳列された果物たちを、彼はこんなふうに描写します。
何か華やかな美しい音楽の快速調の流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面――的なものを差しつけられて、あんな色彩やあんなヴォリウムに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。
文庫版で10頁ほどの『檸檬』は、「私小説」とも「掌編小説」とも言えます。あるいは、「起承転結のある散文詩」というのがより具体的かも知れません。
既存のどんなジャンルも枠をも超えたエネルギーと独特な詩情が、『檸檬』には満ちあふれているのです。
この異才に対して、多くの文学者が様々な賛辞を送ってきました。中でも評論家の 井上良雄が梶井の本質を的確に表しているように思われますので、先に紹介しておきます。
恐らく原始人だけがこの様な風景を知つてゐた。石の中にも、樹の中にも、己の中と同じように蠢いてゐる精霊を感じて、それと闘ひ、怖れ、火を焚いて祈つた、あの原始人だけがこの様な感覚の初発性を持つてゐた。
~ 井上良雄「新刊『檸檬』」

つきまとう「えたいの知れない不吉な塊」
『檸檬』の内容はすでに広く知られているかと思いますが、まずは簡単に紹介しておきます。
(あらすじ)
舞台は大正末期の京都。
「私」は、肺の病と神経衰弱を患っている上に、「背を焼くような」借金にも追い立てられていました。
そのため、「えたいの知れない不吉な塊」に悩まされ、それから逃げるように街路を歩きまわる日々を送っています。
ある夜、彼は小さな果物屋で一個のレモンを気まぐれに買います。
そのレモンを手にしていると、不思議なことに憂鬱な気持ちが晴れていくように感じられてきます。
気が付くと彼は、以前に大好きだった丸善の前に来ています。
しかし、店内をめぐるうちに、あの憂鬱な気分がまた重く立ち込めて来ます。
それを振り払うように、西洋の画集を開いては次々と積み上げていった末に、彼はふと、あるとんでもない行動を思いつき、袂のレモンを取り出します・・・
本文からの引用をまじえながら、さらに詳しく彼の足どりを追っていきます。

熱に浮かされ心を病んだ彼は、自分を癒してくれる「みすぼらしく美しいもの」に強く心惹かれています。
あのびいどろの味ほど幽かな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼時のあまい記憶が大きくなって落ち魄れた私に蘇えってくる故だろうか、まったくあの味には幽かな爽やかななんとなく詩美と言ったような味覚が漂って来る。
(15頁)
しかしやがて、そのようなものたちでさえも、彼を愉しませてくれなくなります。
そしてあの「不吉な塊」に追い立てられるように、病んだ胸で息を切らしながら、あてもなく京都の街路や裏道を歩きまわります。
ある晩に彼は、前から気に入っていた寺町通の果物屋の前で足を止めます。
そして、闇の中に浮かぶ果物群の美しさに目を奪われます。

ーー周囲が真暗なため、店頭に点けられた幾つもの電燈が驟雨のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、ほしいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電燈が細長い螺旋棒をきりきり眼の中へ刺し込んでくる‐――
黄色い不思議なかたまり
そこには珍しく、彼が好きなレモンが並べてありました。彼はそれをひとつ買います。
そのレモンを握っていると、不思議なことに始終心を抑えつけていた憂鬱が軽くなり、彼は高揚した気分で街路を闊歩します。
一体私はあの檸檬が好きだ。レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰まった紡錘形の恰好も。
(中略)
あんなに執拗かった憂鬱が、そんなものの一顆で紛らされる――(中略) それにしても心という奴は何という不可思議な奴だろう。
彼は久しぶりに、かねてからのお気に入りであった丸善に立ち寄ってみることにします。
しかし、店内をめぐるうちに、歩き過ぎた疲労からなのか、憂鬱のもやが再び立ちこめてきます。
大好きだった画集のどれを開いてみても、重い気分は晴れません。
ふいに彼は、買ってきたレモンを思い出します。
ある奇行が頭に浮かびます。
・・・高く積みあがった画集の頂点に、その檸檬をそっと置いてみてはどうだろうか・・・
見わたすと、その檸檬の色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえっていた。私は埃りっぽい丸善の中の空気が、その檸檬の周囲だけ変に緊張しているような気がした。私はしばらくそれを眺めていた。

『檸檬』は、試作を重ねた末、梶井が25歳のとき文芸誌「青空」に発表されました。作品は、当初は全く売れませんでした。
肺には卵大の穴が空いていたと言います。それでも吐血しながら彼は放浪を続け、触覚に触れてくる事物や体験を独自の感性によって描き続けます。
周囲に愛された、心優しい「熊」
梶井は、そのごつい体躯や風貌から友人らに「熊」と呼ばれていました。
彼は、その破天荒さでも有名でした。
泥酔してラーメン屋の屋台を引っくり返したり、家賃が溜まった下宿から逃亡したり、料亭の池に飛び込んで鯉を追ったり、また、街中での大喧嘩も一度や二度ではありませんでした。
病と貧困にあえぎながらの破滅的な日々でしたが、彼の僥倖は、文芸誌の同人らをはじめとする友人たちに助けられてきたことでした。
荒くれな反面、彼は人懐こく心優しい好漢でもありました。
茶目っ気やユーモアがあり、それは作品のちょっとしたところにも顔を出しています。
またそこの家の美しいのは夜だった。(中略) それがどうしたわけかその店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。(中略) もう一つはその家の打ち出した廂なのだが、その廂が眼深に冠った帽子の廂のように――これは形容というよりも、「おや、あそこの店は帽子の廂をやけに下げているぞ」と思わせるほどなので、廂の上はこれも真暗なのだ。
浮浪する彼を、様々な知人友人たちが自宅に泊めてくれます。
2歳年上の川端康成にも可愛がられ、「伊豆の踊子」の校正を任されたほどでした。
梶井君は大晦日の日から湯ヶ島に来てゐる。「伊豆の踊子」の校正ではずいぶん厄介を掛けた。「十六歳の日記」を入れることが出来たのは梶井君のお蔭である。私自身が忘れてゐた作を梶井君が思ひ出させてくれた。(中略)梶井君は底知れない程人のいい親切さと、懐しく深い人柄を持つてゐる。植物や動物の頓狂な話を私によく同君と取り交した。
また、そこには、野放図さとはかけ離れた彼の繊細さと才能の片りんが記されています。
・・・梶井君の細かい注意にも、私はどうでもいいと答えた。しかし、私がそう答えたのは、校正ということを離れて、自分の作品が裸にされた恥しさの為であった。彼は私の作品の字の間違いを校正したのでなく、作者の心の隙を校正したのであった。そういう感じが自然と私に来た。彼は静かに、注意深く、楽しげに、校正に没頭してくれたようであった。温い親切である。しかも作品の誤魔化しはすっかり掴んでしまった。彼はそういう男である。
他にも多くの作家や文学者が、追想の中で、その才能のみならず彼の人柄に触れています。
恋

梶井は、歌会で知り合った作家の宇野千代に、終生片思いの恋情を抱き続けました。宇野は彼より4歳年上で、夫(尾崎士郎)がいました。
二人の仲を勘ぐった尾崎との間は険悪になっていきます。
尾崎は当時のこんなエピソードを遺しています。
ダンスの出来ない梶井と私とはウィスキーを呻りつづけた。私たちの感情はぐいぐいと高まり、もはや言葉でゴマ化すことのできないところまで来てゐた。(中略)私はすぐ立ちあがり、右手に握りしめた煙草を火のついたままふりかざして一気に彼の面上にたたきつけたのである。(中略)それから彼は視線を私の顔から離して、じつと考へ込むやうに眼を瞑ぢた。しかし、すぐ猛然として立ちあがつた。そのときの彼の顔を私は今でもありありと思ひ描くことが出来る。内にひそむ野性が彼の情熱をゆすぶり動かしたのである。
宇野千代とは、終生結ばれることはありませんでした。
叶わぬ恋ではありましたが、彼女が遺した回想記に、男女を超えた二人の絆が覗えます。
「或る種の男と女との間では、浮世の世界で言う恋愛には決してならない、しかし或る高揚した心の瞬間を感じることがあるものです。形はどこにも現われないし、また、この瞬間を名付けるべき言葉も見当たらないのですが、私はやはり愛の一種だと思うのです。梶井基次郎との短い交友の間にも、しばしば、この瞬間があったのではないか、といまでは考えます」

彼は、子どもたちにもよく慕われました。
貧しい五人兄弟の次男であった彼には、幼い腹違いの妹もいました。この子も彼にたいへんなついていましたが、3歳で病死してしまいます。
梶井の悲しみの表現は、ここでもどこか常人離れしたものが感じられますので、挙げておきます。
妹の看病をしてゐる時私はふと大きな虫がちいさな虫の死ぬのを傍に寄添つてゐる――さういふ風に私達を想像しました それは人間の理智情感を備へてゐる人間達であると私達を思ふよりより真実な表現である様に思はれました、全く感情の灰神楽です。
夕立に洗はれた静かな山の木々の中で人間に帰り度いと思ひます。
~梶井基次郎「近藤直人宛ての書簡」(1924)
病状がさらに悪化するにつれて酒量は増え、素行も荒れていきます。鯨飲の末の大立ち回りも茶飯事であり、ヤクザにビール瓶で頭を殴られたりもしました。
そして彼の作品は死の色をさらに濃くしていきます。

死への猛進
『檸檬』以降、彼の作品の闇は広がっていきます。それでも彼は疾走を続けます。そして闇に呑み込まれるにつれ、作品は妖しい発光を帯びていきます。
おまえ、この爛漫と咲き乱れている桜の樹の下へ、一つ一つ屍体が埋まっていると想像してみるがいい。何が俺をそんなに不安にしていたかがおまえには納得がいくだろう。
短編『冬の蠅』では、温泉地に療養に訪れた際の暗澹たる体験が綴られています。
彼は、その温泉地の郵便局へ行った後、気まぐれに乗り合い自動車に乗り、でたらめに山中まで走らせてから降車します。
無人の山道を歩くうちにやがて陽は落ち、彼は完全な闇の中に埋もれてしまいます。
「なんという苦い絶望した風景であろう。私は私の運命そのままの四囲(しい)のなかに歩いている。これは私の心そのままの姿であり (中略)
なんというそれは気持のいいことだろう。定罰のような闇、膚(はだ)を劈(さ)く酷寒。そのなかでこそ私の疲労は快く緊張し新しい戦慄を感じることができる。歩け。歩け。へたばるまで歩け」
私は残酷な調子で自分を鞭打った。歩け。歩け。歩き殺してしまえ。
燃え尽きる
残された最後の生命を絞り出すように、彼の彷徨は加速していきます。
果なき心の彷徨――これだ、これを続けてゐるにきまつてゐる。それが一つの問題が終らないうちに他へ移る。いやさうではなしに一つの問題を考へると必然次の考へへ移らねばならなくなる、それが燎原の火の様にひろがつてゆく一方だ。これの連続だ、然しこれも疲れるときが来るのだらう。
~『中谷孝雄宛ての書簡』(1927)
そして遂に倒れ、生地である大阪の病床にて力つきます。
最期は母らに看取られ、「解りました。悟りました。私も男です。死ぬなら立派に死にます」と合掌し、涙を流しながら息絶えたといいます。
極限まで張り詰めた流浪の日々が、ようやく終了したのでした。31歳の若さでした。
ーーー大阪の街で梶井と会ひ、ときには一緒に街を歩いたりした。
「宇野さん、僕の病気が悪くなつて、もし、死ぬやうなことがあつたら、僕の家へ来てくれますか」と、例によつて、眼を糸のやうに細くして笑ひながら言つた。
「ええ、行きますとも」と私は答へた。「そして、僕の手を握つてくれますか」と重ねて梶井は言つた。「ええ、握つて上げますとも。」と私も重ねて答へた。(中略)梶井はそれからぢきに死んだーーー

全編が緊密な詩の塊ような作品なので、抜粋を続けるとそれは「全編」になってしまいそうです。ですので、ここでは割愛しがたい描写をあといくつか紹介するに留めます(注・ただし、エンディングも含まれます)。
私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみた。(中略) そしてふかぶかと胸一杯に匂やかな空気を吸い込めば、ついぞ胸一杯に呼吸したことのなかった私の身体や顔には温い血のほとぼりが昇って来てなんだか身内に元気が目覚めて来たのだった。
――つまりはこの重さなんだな。――
その重さこそ常づね尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての善いものすべての美しいものを重量に換算して来た重さであるとか、思いあがった諧謔心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり――なにがさて私は幸福だったのだ。
梶井の作品は、その短命もあって20編ほどしかなく、ほとんどが発行部数の少ない同人誌に書かれたものでした。
当時は、芥川、谷崎、志賀、島崎らが華々しく活躍していた時代でした。
彼はその遠く離れたところにおり、「文壇」からは無視され続けました。
しかし、三好達治ら友人たちが力を合わせて梶井の作品集『檸檬』を刊行したのでした。そしてやがて、世間は梶井の存在を知るようになりました。
「視ること、それはもう“なにか”なのだ。自分の魂の一部分あるいは全部がそれに乗り移ることなのだ」
死と隣り合わせに生きる中で研ぎ澄まされた感受性、そして鬱と躁の両極が強く引き合う緊迫から発火したような幻想的なイメージ群・・・
それらは、「原人」梶井基次郎の無垢な目がこの世界に観た、ありのままの景色だったのでしょう。
最後に、『檸檬』の結末を挙げておきます。


梶井基次郎 (1901-1932~大阪・小説家)
早くから頽廃的な生活を送り肺結核に罹患したが、作家の中谷孝雄らと知り合い、文学への道を志した。その中谷らと雑誌『青空』を創刊し,同誌に『檸檬』『城のある町にて』(1925)など後に梶井の代表作とされる作品を発表したが、文壇からは注目されなかった。26年から伊豆の湯ヶ島温泉に転地療養し、その間に『冬の日』(1927)や『冬の蠅』(1928)など、生と死の極点を凝視した作品を書いた。その後病状が悪化し、『交尾』(1931)、『のんきな患者』(1932)を発表したのちに他界した。ボードレールの『パリの憂鬱』を座右の書としていた。
(記事では『檸檬』本編の1/5近くも抜粋してしまいました。どこを切っても同様な美しさが味わえますので、是非全編をお楽しみ下さい。朗読版もいくつかあります~個人的には上掲 のものがお勧めです。)
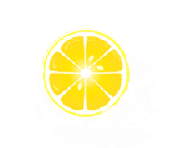

Planet Earth
いいなと思ったら応援しよう!

