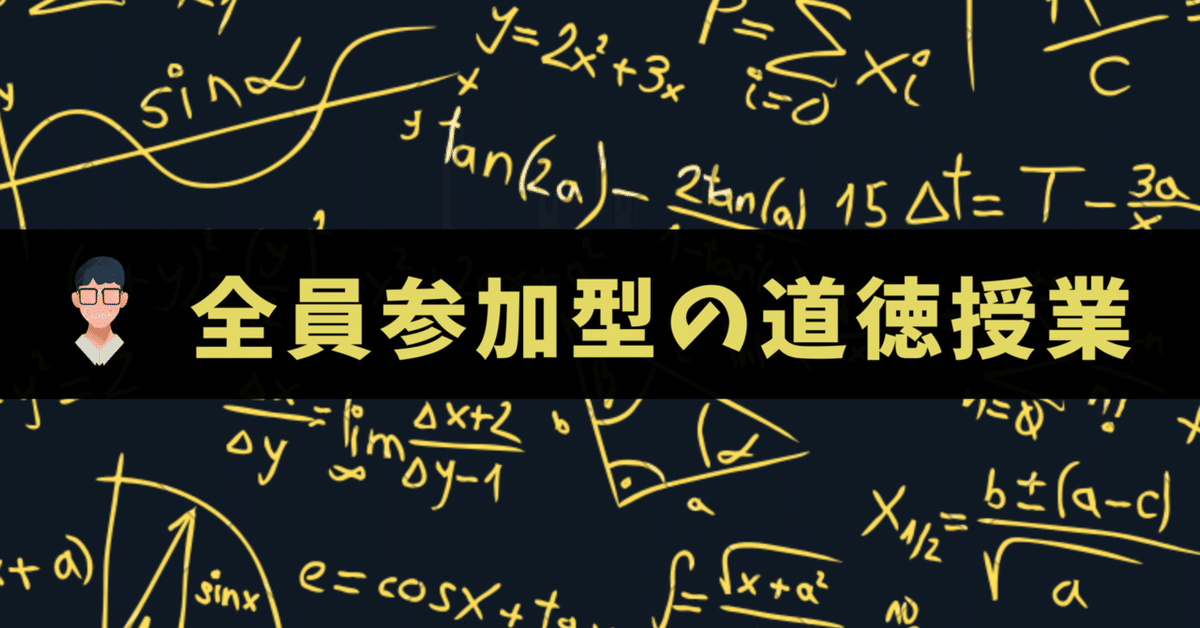
道徳授業で大切なこと(3)
1号では「本気で考えたくなる『問い』」について、2号では「困っている子どもに目を向ける」について述べてきました。
本号では、道徳授業で大切なこと「第3号」の「挙手に頼らない」について述べていきたいと思います。
(3)挙手に頼らない
「挙手に頼らない」とはどういうこと?
前号でも少し触れましたが、授業スタイルとして次のような手順を踏まれることが多々あります。
教師の質問(発問)する→児童が挙手する→教師が指名する→当てられた児童が発言する→教師が発言内容を授業へ位置づける。
*上記の、「児童の挙手で授業が進行していくスタイル」を、ここでは「挙手進行型」と呼ぶことにします。
多くの教師が、この挙手進行型を何の違和感も持たずに活用していると思われます。
しかし、挙手進行型には弱点があるのです。
それは・・・
【挙手進行型による授業スタイルの3つの弱点】
❶挙手しない子どもの安全地帯
❷緊張感のない雰囲気づくり
❸児童の発言の機会を奪っている(教師の間違った思いやり)
❶挙手しない子どもの安全地帯
挙手進行型では、挙手をする子どもの発言で授業が展開されます。
ということは・・・
裏を返せば、挙手をしなければ絶対に当てられることのない「安全地帯」なのです。
つまり、挙手をしない子どもにとって「自分が考えなくても授業が進んでいく」という楽な状態を作ってしまっていることを忘れてはいけません。
そうなると、子どもは自分の考えを持とうとしません。
それどころか、どんどん授業への参加率が下がってしまいます。
❷緊張感のない雰囲気づくり
人が成長するのは、何かを乗り越える時(その段階のプロセスや結果の時)です。
そういう時には、ある程度の緊張感が必要です。
それは授業でも大事なのではないでしょうか。
「失敗するかもしれない。でも挑戦してみよう」
「自分にできるかな。少し心配だ。でもやってみたい」
このような緊張感が集中力を生み出し、学びを深めてくれるのです。
しかし、「自分がいてもいなくても授業が進む」という場所ではどうでしょうか。
やはり、少しやる気を無くし集中力が低下してしまいます。
挙手進行型は、多くの子どもを緊張感のない状態にしてしまい。それが教室全体へ広げてしまう可能性もあるのです。
❸児童の学びの機会を奪っている「教師の間違った思いやり」
「そんなことは言っても、発言が苦手な子どもに無理に発言させるのは可哀想だ」と思う教師も多いと思います。
しかし、よく考えてみて下さい・・・
発言する子どもは、どんどん発表が上手になり、表現力が向上していきます。
また、自分の発言で授業が進んでくれるため、学力も高まっていくことでしょう。
一方で、発言しない子どもは「え?ちょっと待って」「どういう意味か分からない」と思っても、授業はどんどん進んでいってしまうのです。
その結果、授業では置いてけぼりになってしまいます。
そうならないためには、ある程度、自分の意思をアウトプット(発言)できる子どもに育てることが思いやりなのではないでしょうか。
とは言っても、みんなの前で指名して、無理に発言の機会を与えたことで、もしかしたら恥をかかせしまう可能性もあります。
そうなると本末転倒です。
では、挙手する子どもに頼ることなく、誰にでも発言させるためにはどうしたらいいのでしょうか。
本号では、そんな教師の悩みを解消する方法を紹介します。
①練習する機会を与える「ペアトーク」
「発表が得意な子ども」と「発表が苦手な子ども」の違いは何だと思いますか。
それは・・・
場数です。
性格もあるかもしれませんが、多くの要因は「発表した回数」が大きな差を生んでいるのです。
発言が得意な子どもは、自分の発言で授業が進んでいくという経験を何度もしてきています。もちろん、その中には失敗した経験もあるでしょう。
そんな失敗や成功体験を何度も経験してきているのです。
具体的な数で例えると次のようになります。
【発言が得意な子ども】
1日(5校時授業):毎時間2回発言した場合 ・・・10回
1週間(5日、土日休日) 10×5・・・50回
1ヶ月(4週間で20日、土日が休み) 10×20 ・・・200回
1年(約200日 出校日) 10×200・・・2000回
5年間(6年生の4月の段階) 10×1000・・・10000回
【発言が苦手な子ども】
1週間:1週間に1回発言した場合 ・・・1回
1ヶ月(4週間で20日、土日が休み) ・・・4回
1年(12ヶ月で計算) 4×12 ・・・48回
5年間(6年生の4月の段階) 48×5 ・・・240回
その差はなんと、10000➖240=9760回です
これだけの差が出てきているのです(実際にはもっと大きな差が生まれているかもしれません)。
この差を生まないために(または、埋めるために)は、何度も発言する機会を与えることが大切です。
そうは言っても、教師の質問(発問)に対して、発言できる子どもは1人だけだから限界があるのでは?
と思っている教師も少なくないはずです。
しかし、教師の質問(発問)に対して、全員が発言機会を与える方法があるのです。
それは、ペアトークです。
例えば・・・
(教師)命って大切だよね。でも、どうして大切なんだろう。
(子ども)〈数名が挙手〉
(教師)では、今考えていることをお隣さんにお話ししてみよう。
*その時に、一言、次のように付け加えます。
(教師)この後は、誰を指名するかわかりませんが、指名された人は全員の前で発表してもらうからね。
*そして、ペアの友達と話している子どもの机の間を耳を澄ませながら歩いて回ります。そして、「その考えいいな」という子どもを見つけたら、「みんなの前で発表してもらうから、何度も練習しておいてね」と心構えをさせます。そして、ペアトークを終え、次のように投げかけます。
(教師)では、◯◯さんに発表してもらいます。
*その後に、さらに次のように背中を押してあげます。
(教師)◯◯さんの考えは、すごく面白いことを考えているんだよ。
このように、教師の質問(発問)に対して、1人の子どもだけに発言のチャンスを与えるのではなく、ペアトークを間に挟むことで、クラスの全員に発言する機会を与えることができるのです。
それだけでなく、普段はあまり積極的に発言しない子どもにとっては練習の場を作ることができます。また、これまで主役になれなかった子どもの考えを全体の場に広げることができるのです。
*実は、ペアトークという活動には、様々な効果が隠されているのです。その詳細は別号で述べたいと思います。
②リアクションを生かす
積極的に手をあげて発言しない子どもの中にも、しっかりと自分の考えを持ち授業に参加している子どもはいます。

この図で言うと、Bの子どもたちです。
そのような子どもたちは、教師の問いかけに対して、頷いたり呟いたりするなど、何らかのリアクションを示します。
その言葉にならない声を教師が瞬時に取り上げ、全体へ投げかけてあげることが大切であり、
その瞬間こそ発表が苦手な子どもを授業の主役に抜擢する絶好のチャンスなのです。
例えば・・・
(教師)登場人物と同じように、困っている人を助けてあげることができますか?
(子ども)できます。
*低学年の子どもなら、多くの子どもが「できる」と答えることが予想できます。しかし、その中にも、少数ですが「できないかも」と考えている子どもがいます。そんな子どもは次のようなリアクションを見せる時があります。
(Aさん)⦅「ん〜」と首を傾げる⦆
*その瞬間を見逃さず、教師が次のように全体へ広げます。
(教師)今、Aさんが「ん〜、できるかな」と悩んでいるんだけど、その気持ちが想像できますか?
*すると、これまでは「できる」と安易に考えていた子どもたちも、Aさんの考えを想像することで、自分ごとになっていきます。
(Bさん)たぶん、Aさんは「困っている人を助けるのを恥ずかしくてできないかもしれない」と思っていると思う。
(教師)なるほど、それじゃ、Aさん、どうして悩んでいたのかお話ししてもらえかな。
(Aさん)私も困っている人を見て助けてあげることができない時があったから、「すぐにはできないかも」と思いました。
(教師)そうか、みんなもAさんみたいに「やりたいけど、体がいうことをきかなかった」って時はない?
(多数)私もある。私も。
このように、最初はあまり深く考えることなく「困っている人を助けることができる」と発言していた子どもたちが、Aさんのリアクションをきっかけに少しずつ、自分の生活に置き換えて考えるようになっていくのです。
これこそ深い学びです。
教師は、どうしても多数派の声に目を奪われてしまいます。
しかし、多数派の中に埋もれている少数派のリアクションを生かすことで、授業に深まりが出てくるのです。
また、いつも少数派で埋もれていた子どもを授業の主役にすることで、その子どもは自信を持つことができるのです。
③〜の続きが言えるかな
自信を持てない子どもや発表する経験が少ない子どもにとっては、みんなの前で自分の考えを発表することは物凄く高いハードルです。
大事なことは教師がハードルを低くしたり、跳ぶ方法を一緒に考えたりすることです。
その時に有効なのが、
「〜の続きが言えるかな」
と言う教師の質問(発問)です。
例えば・・・
(教師)人間と動物は共存できると思いますか。
(子ども)でないと思う。だって、人間は動物を捨てたり殺したりしているからです。
(子ども)でも、ペットと仲良く一緒に暮らしている人もいるよ。
(教師)ということは、共存できる人と共存できない人がいるってことかな。
(教師)「共存」ができる人とできない人とは何が違うんだろう。
(子ども)〈「ん〜」と多くの子どもが悩む姿〉
(Bさん)動物の見方が違うと思う。例えば・・・
*Bさんが、自分の考えを述べようとした時に、次のように指示をします。
(教師)Bさん、ちょっと待ってもらえるかな。
*と一旦、Bさんに発言をストップしてもらいます。そして、次のように問います。
(教師)Bさんは、どんなことを考えているんだろう。
(教師)「動物の見方が違うと思います。例えば〜」この続きをペアで考えてみましょう。
*①のペアトークを活用して、発言機会を増やします。その後に発言が苦手な子どもを指名します。
(教師)Cさん、Bさんの「動物の見方が違います。例えば〜」の続きを言えるかな。
(Cさん)例えば、共存できる人は動物を仲間や家族と見ているけど、共存できない人はただのモノとして見ているのだと思います。
*この発言で、多くの子どもが「そうそう」と共感したり「そういうことか」と納得したりする姿が見られます。Cさんにとって、自分の発言を友達が共感・納得してくれたという体験が大切なのです。
*もちろん、この後、Bさんにも意見を発表してもらい、次のように称賛してあげます。
(教師)Bさんのおかげで、みんなの考えが深まりました。ありがとうね。
このように、最初から全てを子どもに丸投げするのではなく、最初の一歩は、仲間の考えを手がかりに考えさせあげて、その後を少しずつ歩かせていけばいいのです。そうすれば「やってみようかな」「できそうかも」と少しずつ興味や意欲を持っていくでしょう。
大切なのは、子どもがどこで立ち止まって困っているのかを、教師が理解してあげて、その背中を押してあげることだと思います。
以上、本号では道徳授業で大切なことシリーズの第3弾「挙手に頼らない」について述べてきました。
今回が、「道徳授業で大切なことシリーズ」の最終号となります。最後までお読みいただきありがとうございました。
次号では、「教材研究の視点」について、私の考えを述べていきます。
