
「江雪」を中国語で暗唱したけど通用せず
漢詩のアンソロジー「声に出してよむ漢詩の名作50」を読んで、
「漢詩かっけー! 一首だけ中国語で言えるようにしよう!」
と謎の志を得た話を以前した。
柳宗元の「江雪」を暗唱するぞ、と。
あれからどうなったのか。その報告。
柳宗元の「江雪」を暗唱する
最初の4字を並べると「千万孤独」になるという中〇な理由で選んだ、たった20文字の詩。
私は音読による暗唱が昔から得意なので(ほぼそれだけで語学をクリアしてきた)、
こちらもまあ、暗唱はできるようになるだろう、という見通しはあった。
だって20文字だもん。
最初は荘魯迅先生のモデル音声を繰り返し聞いて練習したが、途中から先生が変わった。
Annie先生である。なんかすてきなお姉さんだ。
↑の動画の5:12あたりから、「一緒に読みましょう」コーナーがあるので、一緒に読んだ。
うむ、やはり自分に近い声の方が真似しやすい。
(余談:高校受験が終わってから、例のイングリッシュ・アドベンチャーでドリッピーをやっていた。カセットテープ(CDより安かった)に吹き込まれた音声は、渋い、ひくーい低いおじさまの声……茶ぶどうは自分が出せるもっとも低い声でおじさまの発音をそっくりまねて練習したのだった……)
How I learned a Chinese poem by heart
一行ずつ、連続で5回も10回もリピートする。
・聞く
・後から繰り返す
・同時読み(オーバーラッピング)
・音声に少し遅れて音読(シャドーイング)
英語の音読練習と同じ要領だ。
英語と違うのは、文字が漢字だということ。
漢字ならわかりやすくて楽じゃない?
いや、違う。
漢字を見ると自動的に日本語音に変換してしまうため、最初は逆に邪魔だった。
文字を見ないで、あえて音だけを入れていった。
音が全部入った、と確信できてからさらにダメ押しの練習をして、
飽きる前に、ようやく文字とつなげる。
そんな風なやり方で覚えた。
やった!! めでたく、漢詩を一首、中国語で暗唱したのだ!
柳宗元の「江雪」は、返り点が一つもいらない、上から読めばそのまま日本語に変換できるような単純さだったのもよかった。
つーか。
20文字だから。
中国語の謎
さて、私は中国語は一切わからない。中高の「漢文」以外では勉強したことがない。
知っているのはニイハオ、ツァイツェン、シェイシェイ、ウォ・アイ・ニー。
以上。(「らんま」と「ふしぎ遊戯」ですね)
あとは、
「現在の文字は日本語の漢字と様子が違う(簡体字)」
「語順は英語に似ているところがある」
「ピンインだか四声だかいう細かいイントネーションが大事らしい」
くらい。
なので、練習しながら色々不思議に思った。
「ある文字はいかなるときも同じ音なのか?」
「北京語とか広東語とか色々あるというが、どのくらい違うのか? 詩の読み方も変わるのか?」
英語だと、cという1つの文字に何種類もの発音がありえる。
ある語の中ではこう、後ろの文字が〇だとこう。
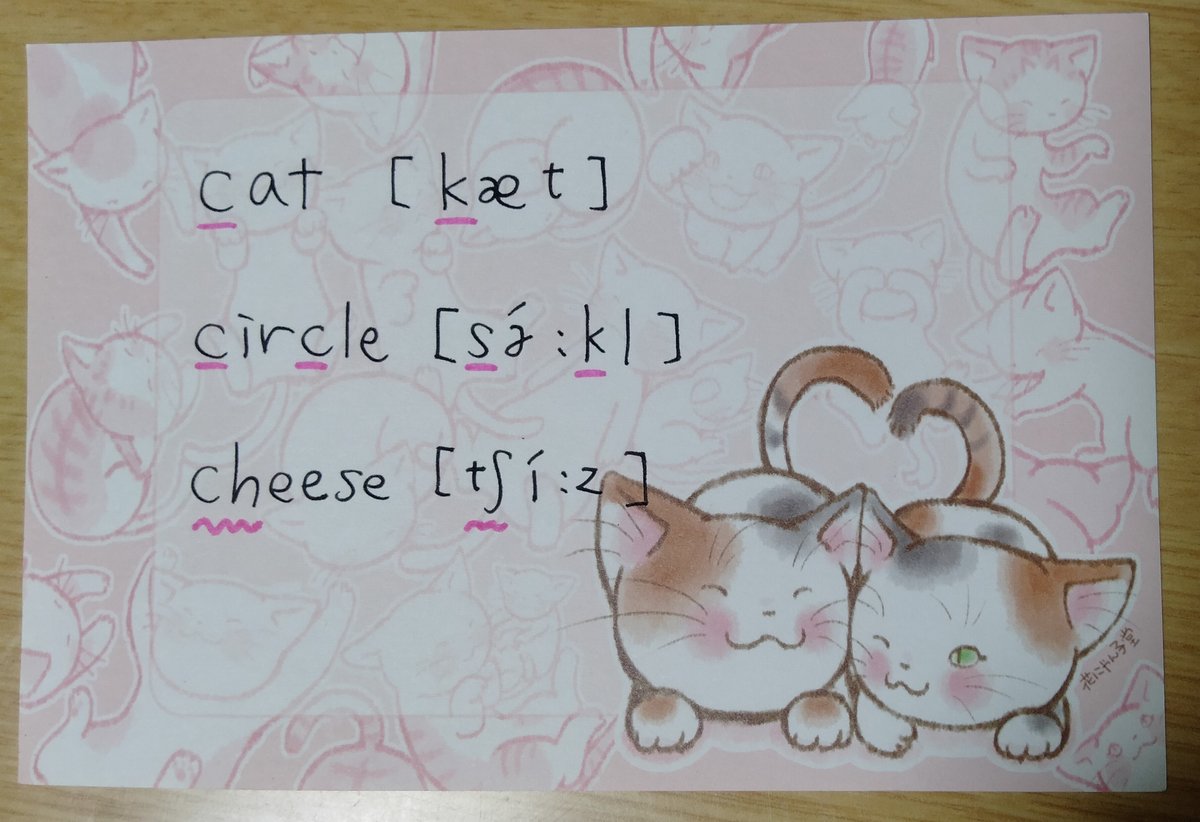
中国語で「千」は、いつも「チェン」(?)なのか? どこにどう現れても??
そういう、言語の概要みたいなのを知りたいんだけれども。
ふつうの入門書って、すぐ「中国語会話」とかになるよね。
ええねん、会話は。しないから。
ニイハオとシェイシェイがあればええねん(極端)。
「実用」じゃなくて、どんな特徴の言語なのか? アウトラインを知りたいんですけどね。
いざ、実践 中国にルーツがある人に突撃
まあともかく、よくわからないが「江雪」の暗唱はできた。
そうなると、試してみたくなる。
中国語スピーカーにわかってもらえるか……!!
私が通う教会には、中国ゆかりの方が何人かいらっしゃる。
そのうちの一人、まだ学生の子に聞いてもらった。
「私、中国の詩を覚えたんだー、わかるかな?
チェンシャンニャオフィーチュイェ……」
「待って、発音が違うからわからない」
「!!!!!」
「漢字を教えて」
漢字を言うと、サラサラッと発音してくれた。
……そうか、文字と音は一致するのだな。
しかし、今、私はまさにその音を発音したつもりだったんだが……
どうも、私の鈍い耳には判別ができないくらい繊細なものらしい。
「有名な詩なんだけど、知ってる?」
「知らない。私、中国には小学校1年生までしかいなかったから」
おう……そりゃそうか……
日本に小1までしかいなかった子が「祇園精舎の鐘の声……」とか吟じられてピンとこなくても不思議じゃない。それと同じだろう。
漢詩は漢字を覚えればいい(ことにする)
こうして茶ぶどうはあえなく撃沈した。
もともと耳は悪い方だ。英語の発音だってよくない。
そんな者の付け焼刃の中国語が通じるはずがなかった。
しかし次の疑問が頭をもたげてくる。
「江雪」を知っている中国人なら、私の間違った発音からでも推測してrecognize(「あー、あれか!」)してくれるのではないか……??
英語なら、アクセントが違いすぎなければカタカナ英語でもある程度通じる。
「オレンジ」は無理にしても、
「オーレンジ」(オーを強く、あとは引く)なら“orange”として通じる可能性が高い。
中国語はどうも、もっとデリケートな発音を要求するようだが……
発音の違いは、どのくらい許容されるのか……??
ともかく、茶ぶどうの「漢詩1首だけ中国語で言えるようにするプロジェクト」は終わりを迎えた。
音声で覚えようというのは難しそうだ。
覚えたつもりでも、発音が違って通じないのでは悲しすぎる。
学んだのは、
「漢字を覚えておけばOK」
ということ。
「江雪」だと日本語読み下し文と原文の文字順が一致するので簡単だったが、
返り点が必要なタイプの詩(ほぼ全部そうだろ)も、その順で書けるようにしたらよい。
日本語の書き下し文を覚え、
漢字の語順を覚える。
……「漢文」に戻ってきてしまった気がするが……
あと問題なのは、日本語の漢字でもOKかどうかだ。
問題が山積している。
この先、続くのか。私にもわからない。
