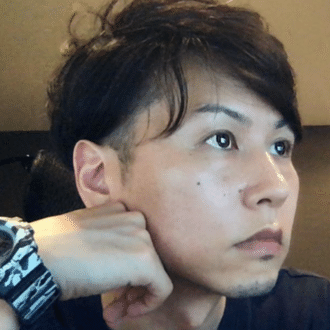リモートでチームのふりかえりに`Circle of Questions`をやってみた
こんにちわ。
メルカリでEngineer組織の組織開発などをしているtweeeetyです。
最近はたまにBMXをやっています。
リアアップという降臨を上げる練習をしていたら上がりすぎて前側に回転する形でコケました。アクロバットですね。
今回はリモートでのチームふりかえりに
`Circle of Questions`
をやってみたnoteです。
直訳で`質問の和`という名のとおり、
「インタビュー形式でチームを知る」ような感じのふりかえりです。
ちなみに前回は、`Movie Critic`について書きました。よかったら合わせてご覧ください。
1. 「ふりかえり」をなぜやるか
ファン・ダン・ラーン(FDL)のnoteでも記載していますが、大事なポイントなのでこのnoteでも完結するように再掲しています。
「ふりかえり」は、アジャイルプラクティスでいう"Retrospective"です。
なぜRetrospectiveをやるか、大事なことは以下2点です。
1. チームをもっとうまくできるようにする
2. 立ち止まって考える機会を作る
その結果として以下のような事が期待できます。
# チームの成長:
チームメンバーの関係性を深め、相互作用の質を高める
# プロセス改善:
少しでも改善し、やり方の質を高める
# 仕事の棚卸し:
やらなくて良い仕事を辞め、成果の質を高める
より詳しい詳細は以下のslideをご参考ください。
2. ふりかえり: Circle of Questionsとは
Retrospectiveには沢山の方法があります。
たとえば、よく知られているふりかえりの1つにKPTがあります。
1人ずつKeep/Problem/Tryを挙げていく形式ですね。
対して、`Circle of Questions`の特徴は、円になり隣の人へのインタビュー形式で行います。 ボードは1つしか使いません。
使用する1つのボード:
- Circleボード
2.1. Circleボードの説明
ボードの説明です。まずはイメージからご紹介を。
Circleボード:

以下、ボードの説明です。
(本来のものと少し変えています)
Circleボードの付箋:
- 赤 付箋: OKR/Objective
- 橙 付箋: 補足
- 青 付箋: 直近やること
本来は、「次のイテレーションで取り組むべきことはなんだと思いますか?」のような質問をしていくことで共通認識やコンセンサスをはかるのに使ったりもします。
2.2. Circle of Questionsの手順
以下が、Circle of Questionsの手順です。
概要:
- 答えをみつける最善の方法は、質問をすることです。
- 今回のレトロスペクティブで、OKRとFirstStepの共通認識を持つために質問をしていきます。
- ひとりずつ、隣の人へ質問して何周かしていきます。
- たとえば2周
- 1週目: OKRとやることブレイクダウン
- 2週目: その中で直近何やるか
手順:
1. 最初の質問者は、Circleをどちらにまわるか決めます
2. 1週目、質問者は隣の人へ次のように質問します
- 例: 「今QのOKRやprojectはなんですか。確定していなくても大丈夫です。」
- インタビューやヒアリングのイメージです。
3. 回答者が回答します。質問者は回答を赤の付箋に記載します
- 質問者は、不明点・疑問点があれば深堀りで追加質問します。
- 例: 「それはなんですか?なぜやるんですか?◯◯はどういう意味ですか?」など何でもOK
- 追加回答は赤付箋のまわりにオレンジの付箋で追加します。
- 質問者、回答者以外は各メンバーの意見に耳を傾けます。
4. 2週目、質問者は、隣の人へ次のように質問します
- 例: 「OKRに対して、直近でやることはなんですか?」
5. 回答者が回答します。質問者は直近やることを青の付箋でマークします
- No.3と同様、深堀りで聞きたいことがあれば聞いても良いでしょう。
2.3. Circle of Questionsの実施イメージ
実際に実施した際のイメージを貼っておきます。
(内部事情もあるので、文章は伏せています)
Circleボード:

2.4. Circle of Questionsの実施のポイント
注意深く聞いたり、逆に聞いてもらったりすることで、新たな気づきを得られたり普段より関心度合いが増します。
この場では、「自分が知りたいこと」はもちろん「他のひとも知りたいと思ってそうなこと」を聞くのも良いです。
たとえば、
- 普段聞けなかったけど疑問だったこと
- 知ってて当たり前だと思うようなこと
- ぼやっと知ってるがその人からもう少し詳細を聞きたいこと
などを聞くのも良いと思います。
チームが各メンバーに平等に注意を払う機会になります。
3. オンラインでのCircle of Questions
ツールは、以下を利用しました。
google docs: チームへの説明やアジェンダに利用
google meets: オンライン会議に利用
jamboard: ホワイトボード代わりに利用
詳細はコチラのnoteにも記載しています。良かったらご参照ください。
4. どんな時にCircle of Questionsをやるか
書籍などでは、「チームメンバーがお互いの意見を聞く必要があるときに使用すると良い」とされています。
もう少し具体的に挙げるとこんな感じでしょうか。
どんなときにやるか例:
- イテレーションやプロジェクトでチームとして何をすべきか意見を交わしたいとき
- 各個人のOKRをチーム内で共有したいとき
期待する効果:
- チームメンバーのOKR/projectの背景が聞ける
- 普段は聞き流してしまいそうな自分以外のメンバーのOKRの理解が深まる
- チームで共通認識を持てる
4.1 Circle of Questionsをどんな感じでやったか
ちなみに、ぼくのteamでは以下の観点で行いました。
観点例:
- 四半期の最初に行いました。
- OKRを設定したころ、それをシェアする目的で行いました。
普段はドキュメントベースでシェアして読んどけ的なことが多かったですが、自分でヒアリングする必要がありより頭に入ります。
おわりに
「ふりかえり」っぽくないアクティビティではありますが、
check-inなどで全四半期や前イテレーションについてかるく話してから行うのもありかもしれません。
気分が乗ったらまたnoteを追加していく予定です。
参考:
- リモートでチームのふりかえりに`Movie Critic`をやってみた
- リモートでのチームふりかえりに`Shooting Star`をやってみた
- リモートでのチームふりかえりに`ファンダンラーン(FDL)`をやってみた
- Effective Retrospective
いいなと思ったら応援しよう!