
『残像に口紅を』筒井康隆 感想まとめ
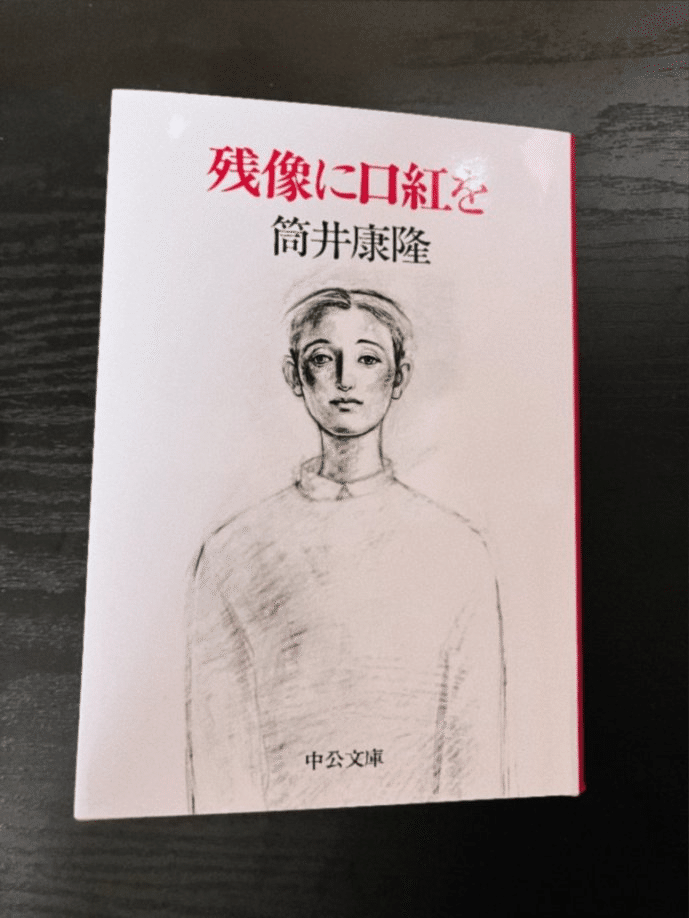
『残像に口紅を』読み終えたので感想を。
一般的ないわゆる物語的な小説とは違い「言葉遊びのおもしろさ」を久しぶりに感じられた一冊。
圧倒的な語彙力、そして作家として物語を作り続け、且つのぼりつめた人間にこそしたためられる天才的な作品。
この物語を説明するのは至って簡単で、「世界から『あ』が消えます」といった具合に、ページをめくるにつれて、小説中の言葉が次々に消滅していく。
「文字が一文字ずつ消えていく」
たったこれだけなのに、作中で起こっていることが強烈的で、慈悲深い。
例えば、世界から『あ』が消えたなら、コンビニ等のお店に行って、何かを買っても買わなくても店員さんに言われるあの言葉。
快いことを相手にしてもらった際に使う、あの簡素で綺麗で美しい言葉。
主に恋人同士や家族など、親しい間柄で使われる、最上級の好意を表すあの言葉。
英語で言えば「YOU」、妻が夫に敬意を込めて使うあの言葉。
これらの名詞、動詞、代名詞、感動詞等々の品詞が1ページ目から使えないという縛り。
であるから、この小説の中で「あ」が使われているシーンは一度もない。
(これを確認しながら読むのも、とても楽しかった)
さらにこれら使用できない文字がさらに続いていき、「ぱ」「せ」「ぬ」……と、制限される言葉は増えていく。
そして最後に消えてしまう言葉はいったい何なのか、そしてこの世界はどうなってしまうのか、考えながら読み進めていく楽しさがある。
登場人物は主に作家の佐治勝男、評論家の津田得治。
佐治はこの物語の主人公であり、この物語を創作する人物。つまり、消された言葉で物語を紡ぎ、消された言葉で人生を左右されてしまう男。
対して津田はこの「文字を消していく」という実験的な物語の提案者。彼が様々なルールを提示して、この物語が始まっていく。
序盤は消えている文字が少ないので、何が消えたか探すのがとにかく楽しい。
例えば「ぱ」が消えている場面で、
・香ばしく柔らかい物の専門店
・ガラスケースからは食品が消えてしまっている
・隅っこにケーキ類がほんの少し置かれている
・辛うじて三つばかりのクロワッサン
となれば、これは「パン屋」が消え「パン」も消えていることに気づくことができる。
しかし、「ぱ」という文字が使えない故、答え合わせができないのもおもしろい。
このように、何が消滅していってしまっているかに注目して読み進めていく楽しさがある。
消滅した言葉に人の名前があればその人物が消滅する。
食べていたものの名前に消滅してしまった言葉があればそれも消滅。
「あれ? 何かあったよな?」「誰かいたよな?」
といった具合に大切な人や物を残像化されてしまう様は実に儚い。
そしてしまいにはまともに会話ができなくなる。
私たちは語尾に「ね」を用いることで、言葉の柔らかさを表現することが多々あるが、「ね」が消滅することで言葉が急にとげとげしく感じたりする。
また、「ぼ」が消失してしまえば、社会的にもプライベートでも使いやすい、主に男子が使うあの一人称が消滅する。
あの一人称を普段から使う人物が急に「俺」などと言い出すと、個性であるとか、らしさであるとかが急に失われてしまう。
このようにして、言葉を次々に失われていく人物たちが、どのような会話を繰り広げるかという点も着眼点になりそうだ。
本作は3部構成であり、私はその第2部に衝撃を受けた。
2部までに消滅してしまった文字は28文字。
さらに2部から3部までの間で20文字程度が消滅する。
その数約50文字。
この制限の中で、甘美で妖艶な官能小説が始まるのが凄まじい。
官能小説はいくらか読んだことがあるが(えへへ)、そのどれよりも文学的で美しく、写実的な表現に舌を巻いた。
ここまで手加減されても、このような文章は一生かけても真似できない。著者の圧倒的語彙力に脱帽。
3部以降は主人公の佐治の精神状態、世界はどうなってしまったのか、そして最後に残る文字は何なのかをありありと楽しめる。
もちろん、残っている文字が少ないがために、支離滅裂な文章が目立ち、何が起こっているのかもよくわからない。
そしてただ、終わっていく。
筒井康隆作品は映像でこそ見たことはあるが、正直意味がわからないものばかりであったし、追及するほど深入りもしてこなかった。
しかし、この『残像に口紅を』を読んで、これほどまでに文章が巧みでうまく、尚且つ言葉遊びがうまい作家を見たことがない。
(僕の読書レベルもたいしたことはないが……)
そして信じられないことに、この作品が書かれたのが、1989年。
スマホもなければパソコンもない。
ギリ、ワープロを使っていたが計算機を使用しなかったという記述さえあった。
こんなことが、現代に生きる私たちに成しえるだろうか?
否、便利なものを使えば使うほど、私たちは書けなくなるし、計算できなくなることを自覚している。
だからこそ、今響いた作品なのかもしれない。
私はこの作品で筒井康隆先生のファンになった。
映像化もされている『パプリカ』あたりもまた読んでみたい。
(これも結構ヤバいらしい……)
結局意味を考え出すとよくわからない作品であったが、執筆でしか表現しえないものを読むと、書物の素晴らしさにまた感動する。
嗚呼、天才の脳をのぞいてみたい……。
いいなと思ったら応援しよう!

