
映画感想 インシディアス5 赤い扉
あれから9年……悪夢は再び目を覚ます。
『インシディアス 赤い扉』はシリーズ5作目。時系列としては、第2作目の後となっている。『インシディアス』は時系列がバラバラに作られてしまったので、整理すると3→4→1→2→5というのが正しい順番。ただし、その前の作品を踏まえた内容になっているので、時系列順に見るとかえってわかりづらくなっている。
今作の監督はパトリック・ウィルソン。『インシディアス』シリーズで主演を務めていたお父さんが、今作では初めての監督を務める。『インシディアス』シリーズは過去に脚本家リー・ワネルが監督を務めていたり、なかなか面白い人材を起用する。
主演はタイ・シンプキンス。『ジュラシック・ワールド』『アベンジャーズ/エンドゲーム』といった大作に出演する若手俳優だ。『インシディアス』シリーズには第1作目からダルトン役として出演し続けている。あの時の子役が立派なイケメンに育ったんだな……。弟役のアンドリュー・アスターも第1作目からの出演。悪魔役のジョセフ・ビシャラも第1作目から続けて出演。ジョセフ・ビシャラは『インシディアス』シリーズで音楽を担当している。
制作費は1600万ドルであるのに対し、世界興行収入が1億8625万ドル。『インシディアス』シリーズ最大の興行収入を獲得した。ただし評判ははっきり良くなく、映画批評集積サイトRotten tomatoでは批評家によるレビューが116件あり、肯定評価38%。オーディエンススコアは70%。その他のレビューでもだいたい低評価となっている。
それでは前半のストーリーを見ていこう。
第2作目の惨劇の後、ジョシュと息子のダルトンは記憶を消す決意をする。催眠術をかけてもらい、あの時の記憶を封印するのだった。
それから9年後……。
ジョシュの母ロレイン・ランバートが死去する。その葬式のために、ランバート一家は久しぶりに集まる。あの9年の間に、ジョシュは離婚していて、家族とは離ればなれになっていた。
葬式が終わり、帰ろうとする時、元妻のルネは間もなく長男のダルトンが大学へ進学だから、大学まで連れて行ってくれ……とジョシュに提案する。
しかしジョシュとダルトンとはもう口も利かないような関係……。ジョシュはおそるおそるメールで息子に「大学まで送ろうか」と問いかけると、ダルトンは「行く」と了解するのだった。
それからしばらくして大学へ行く日になり、ダルトンはジョシュの車に乗る。しかし車の中の空気は重い。ずっと対話のなかった親子……対話をしようとしても続かない。
大学に到着し、荷物を寮の部屋まで運んでいく。なんでもない対話をしていたつもりだったが、なぜか口論になってしまう。
「嫌々だったくせに! 母さんと話をしてるのを聞いた! 父親のことをまだ根に持っているのかよ! 40年も昔の話だろ!」
「ふざけるなよ! さんざん世話になっておいて! いつから恩知らずのクソガキになった!」
二人はお互いに傷ついて別れるのだった。
ダルトンのルームメイトとしてやってきたのは、女性のクリスだった。手違いで男女相部屋になってしまった。寮長に報告すると、明日対応するから、一日一緒に過ごしてくれ……ということだった。
クリスはむしろその状況を楽しみ、お互いのことを語り合うのだった。
間もなく大学の授業が始まる。アルマガン教授は生徒達に描いてきた絵を出すようにいい、次にその絵を「破り捨てろ!」と命令する。ダルトンは教授の言うとおりに自分の絵を破り捨てる。「自分の過去を手放しなさい。殻を脱ぎ捨てて成長するのよ。自分の形作ったものを描きなさい」――ダルトンは言われるまま、思うままに絵を描き始める。できあがったのは、「赤い扉」の絵だった。
ここまでで前半28分。
うん、確かにあんまり面白くないね。しかしどこが面白くないのか、指摘するのはちょっと難しい。基本的な映像作法はきちんと押さえられているけど、重要なところでピントがぼやけちゃっている。そのちょっとの掛け違いで、いまいちに感じられる作品になってしまっている。具体的にどこがまずいのか、掘り下げていこう。

とりあえず、最初の場面から見ていきましょう。
冒頭は『インシディアス2』の直後の場面。惨劇の後でトラウマを負ったジョシュと息子ダルトンは、催眠術で1年間の記憶を消すことにした。

そして9年後……。お婆ちゃんがこの世を去ります。ここに出演している青年役は、第1作目からの続投。あの時の子供が大きくなったものです。赤ちゃんだったカリだけは同一人物なのか確認できなかった。
このシーンですでにまずいポイントが一つ。ジョシュとルネが離婚している……ということがわかりづらい。この後、ジョシュだけ別の車に乗って「あれ?」となるけど、「実は離婚しています」ということが説明されない。離婚したとして、理由も説明されない。もう少し後のシーンで離婚していた事実が言及されて、そこでようやくわかる。
まず、この場面で離婚していた……ということをわかるようにしないと。「久しぶり」「あの時以来か……」ベタな対話だけど、こういうやりとりが必要だった。
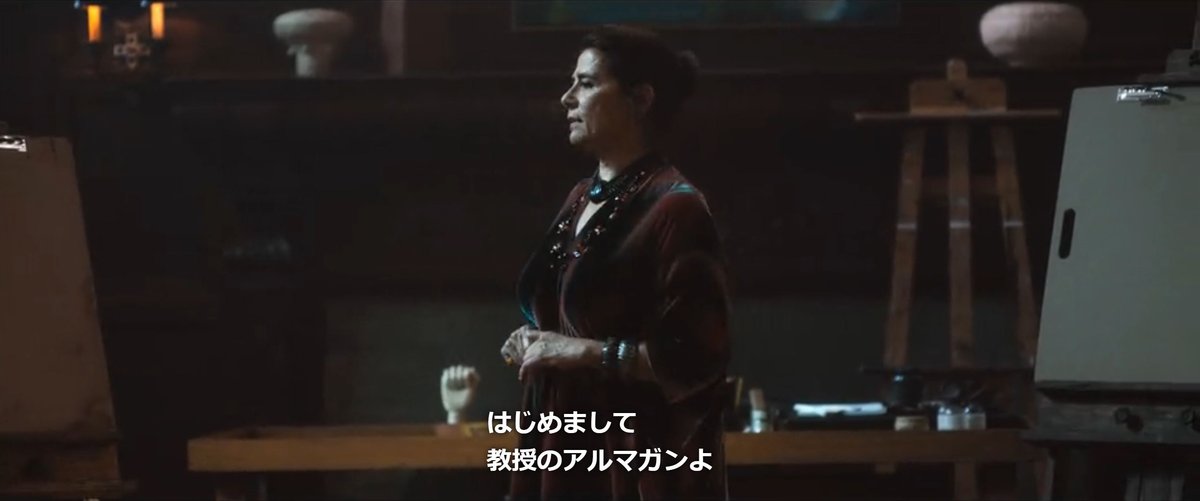
ダルトンは美大へ進級。アルマガン教授に師事する。
この教授が困った先生で……。「作品を出しなさい。その作品を破きなさい」これが嫌というなら、教室から出て行け……と。要するに、「今まで学んだことを全部忘れろ」ということだけど、それを教えるために、わざわざ大学にやってきた生徒を一人犠牲にして追い出す……そんなことやっちゃ駄目でしょ。現実にやったら炎上するわ。

しかしダルトンはこのアルマガン教授に心酔しているので、言われたとおりに持ってきた絵画を破いてしまう。その絵画というのがお婆ちゃんの鉛筆画。シリーズを振り返ると、一家に異変が起きた時、お婆ちゃんがすぐに事態を理解して霊能者エリーズを家に連れて来た。一家を救う切っ掛けを作った人だった。ある意味、ダルトンにとっての守護天使的な存在だったのだが、ダルトン自身でそれを破いてしまう。これでダルトンの心理的な防壁が一つ剥がれ落ちる。
アルマガン教授は生徒達にこう指導する。
「いい? 自分の過去を手放しなさい。殻を脱ぎ捨て成長するの。これから10数える。数が減るごとに、あなたたちは自分の内面へと深く深く入り込んでいくのよ。決して木炭と紙を離さないで。10…9…8…7…6…5…4…3…2…1……心に浮かんだものを描きなさい。自分を形作った経験を。心の奥底の醜い感情を描き出すのよ」
アルマガンの指導には、今まで学んできたアカデミズム的なものを捨てろ、学生の作品なんて誰かの影響を受けたコピー品でしかない、真にオリジナルなものを描くために自分自身の体験に遡れ……という意味もあるのだが、しかしこれによってダルトンは9年前封印したはずの記憶を呼び覚ましてしまうのだった。

ダルトンは心に浮かんだものを、思うままに描いた。それがこの扉だった。これこそ9年前、悪霊が出現したあの扉。この扉を描いてしまったことで、封印したはずの悪霊が再び現れるのだった……。
という展開だけど、これが伝わりづらい。アルマガン教授の指導が意図せず催眠術になっていたこと、これによって封印していた記憶が解放されたこと、記憶が解放されたことによって悪霊が舞い戻ったこと……。普通に映画を見ていて、そういう展開だ、ということに気付かない。「お話しが進まないな……」とぼんやり見てしまう。ここで物語のトーンが変わりましたよ……ということに気付かず進行してしまう。

とにかくも、このできごとの後、ジョシュとダルトンの周囲に悪霊が出没するようになる。
しかし、その表現の仕方が引っ掛かりどころで……。
映画における「ホラー表現」というのは、基本的には「トリック撮影」である。

例えば冒頭のシーンを見てみよう。
静止画像だとわかりづらいが、リアガラスに、亡霊のシルエットが映っている(茶色っぽく見える影)。映画中ではこのシルエットがゆらゆら動きながら、ゆっくり近付いてくる様子がわかる。ワイパーで汚れを落とした跡が入っていて、それが亡霊のいる場所に視線を誘導させている。きちんと絵作りをやっているのがわかる。

ジョシュがこのように姿勢を変えて……

あら不思議。亡霊が消えた。これであのゆらゆら動いていたものが「やっぱり亡霊だった」ということに気付く……という仕掛けだ。
どうやって撮影しているかわかると思うが、ジョシュ役の俳優が姿勢を変えたタイミングで、幽霊役の俳優がかがんでフレームアウトした……とそれだけの話。
こういうトリック撮影をいかに面白おかしく撮るのか……がホラーの醍醐味。

こうしたトリック撮影を映画史的に最初にはじめた人物は、たぶんジョルジュ・メリエス(映画史にそこまで詳しいわけではないので、違っていたらツッコミをくれ)。奇術師だったメリエスは、映画に様々な奇術師的トリックを持ち込んだ。例えばストップ・トリック。撮影中のフィルムをいったん止めて、その間に舞台中の人物などを入れ替えて、再びフィルムを回す。すると画面上の人物がいきなり入れ替わった……みたいに見える。こういうトリック撮影を次々に開発しまくったのがメリエスだった。
トリック撮影の本質というものは、実はこの時代からさほど変わっておらず、こういうトリック撮影を「ホラー」という物語を載せて表現したものをホラー映画と呼ぶ。
例えば、カットが切り替わったタイミングで、目の前にいたはずの人物が、消えたり、後ろに回ったりする。それだけで「奇妙だ」という印象を作ることができる。人は「思い込み」で物事を見るが、それは映画を見る場合も同じで、この思い込みを少し外してやるだけで、人は「奇妙な出来事が起きている」と思い込む。ホラーはそういう人間の思い込みを利用して作るものだ。
ホラー映画の醍醐味とは、このトリック撮影をいかに面白く表現するか……だと私は思っている。しかしこういうホラー的な見せ方……というのは研究されつくしている分野でもあるから、ここで「誰も見たことのない表現」に挑戦するのは非常に難しい。それでもホラーをやる限りはそれをやるべきだ……と私は考えている。「そう表現したか」と思わせるような表現を見ると、私も楽しくなる。

……という、ホラー映画の原理的な話をした理由は、今作における亡霊の見せ方がつまんなかったから。見せ方が教科書的で、それを越える、独自的なホラー表現がぜんぜん出てこない。
例えば幽霊が出てくるタイミングが、いつも必ずカットが切り替わった瞬間。『インシディアス』シリーズ生みの親ジェームズ・ワンはここがうまく、カットは切り替えさせず、ワンカット長回しで表現する。ワンカット長回しで幽霊役の俳優がフレーム内に現れたり消えたり……という表現はそのぶん段取りが大変になるのだが、ジェームズ・ワンはそこを計算した上で表現していた。そうやって表現するから、「怖い」の前に「すごい」「うまい」が来る。
本作の場合、教科書的な見せ方ばかりだったから、「ありきたり」に感じてしまう。つまらなく感じるのはそういうところ。

うまいな……と思う場面もあって、例えばこちらのシーン。ガラスに写真を貼って神経衰弱をやっている。神経衰弱なんてテーブルの上でカードをめくってやればいいのに……それをわざわざガラスに写真を貼り付けてやる。で、こうやって写真をめくるとその向こうに亡霊が現れたり消えたりする……。
映像映えする画面作りに気を遣ってるな……というのがわかるが、しかし写真をパタパタめくって、そのたびに幽霊が現れたり消えたり、という表現がちょっとギャグっぽく見えちゃうのが惜しい。

幽霊表現にはもう一つ問題点があって、ダルトンが扉を描いてしまったことによって悪霊が再び出没するようになるのだが、しかしその悪霊に「追い詰められている」という危機感がまったくない。悪霊によって現実世界に犠牲者が出た……というわけでもない。「今すぐ“あちらの世界”へ行き、悪霊を封じなければ!!」……というわけでもない。幽霊表現と物語が結びついているように感じられないから、なんとなく展開がぼんやりして見えてしまう。最初の物語の転換もわかりづらいが、その後もずっとわかりづらい……というのが本作の難点。

他にも映画作法的にまずいな……という部分もあって、例えばこのシーン。ダルトンが授業初日で急いで大学へと足を進めている。

次の教室のシーンになり、扉から入ってきたのがアルマガン教授。
その前に、ダルトンが教室にいる様子がちらっと映るんだけど、ぼんやり見ていると、この流れだと教室に飛び込んでくるのはダルトンだ……と期待して見てしまう。しかし入ってくるのがアルマガン教授だから「あれ?」となる。
冒頭の「離婚している事実」を描写しなかったり、微妙な映画作法的な失敗があちこちにある。こういうところも本作の難点。

ロケーションも良くない。ホラーは、ロケーションにこだわらなくちゃいけない。幽霊が出そうな、ふさわしい場所でなくてはならない。なぜか、というと、幽霊なんて現実にはいないからだ。幽霊現象は非現実的な現象であるから、そういう現象が起きそうな場所……そういう場所を舞台にすれば幽霊物語は盛り上がる。
ロケーションにこだわる理由は、良いロケーションなら単純に映像映えする……というのもある。構図にこだわれないのなら、ロケーションにこだわれば良い。ロケーションさえ良ければ、自然と画面も良くなるはずだから。

話をまとめよう。
まず、物語上の設定が描写されない。ジョシュとルネがすでに離婚している……ということが伝わらない。次にアルマガン教授の授業で封印していたダルトンの記憶が戻ってしまった……という物語の転換がわかりづらい。その後、亡霊が出没するのだけど、その亡霊に命を脅かされる……という不安感がない。ついでにその亡霊表現も教科書的で面白味が欠ける。
映画は画面で物語を表現しなければならないのだが、それがうまくいっていない。それぞれのシーンの画面はそこそこできあがっているのだけど、しかし物語が表現されてない。だから物語上の設定も、転換も伝わりづらい内容になってしまっている。画で表現する……ということがやりきれていない。
決定的に駄目な映画……というわけではないが、微妙な掛け違いがあちこちにあるせいで、印象が薄らぼんやりし、それで「面白くないな」という後味になってしまっている。
そうはいっても、それぞれの画面はきちんと作られているので、まったく見る価値がない、というわけではない。少なくとも清水崇より映像はうまい。楽しんで見ようと思ったら、楽しめるホラー映画になっているはず。微妙な掛け違いの部分は、編集を変えるだけでもだいぶ良くなるはずだ。
『インシディアス』はジェームズ・ワンの手から離れてからは、脚本家のリー・ワネルが監督を務めたり、マイナー監督にチャンスが与えられたり、今作の場合は主演俳優が監督を務めているので、色んな人にチャンスが与えられた作品になっていた。5作も作られているのに、最後まで大規模化することなく、作品の構成要素も複雑にならなかったから、新人にチャンスを与える作品としてちょうど良かったのだろう。そういう作品だと思えば、ちょっとイマイチかな、微妙かな……という内容でも許せる。『インシディアス』は元々そういう作品だったわけだから。
ただ、今作でどうやらシリーズも終わりらしく、最終作とするにはこの内容はちょっと残念。どうせならジェームズ・ワン監督を召喚して、あともう一作やってくれない? いや、ジェームズ・ワンは今や大ヒット映画監督だから、こういう小規模映画にはもう戻ってこないかな。もう一本、なにかあってほしいな……と心残りになる作品だった。
シリーズ感想文
いいなと思ったら応援しよう!

