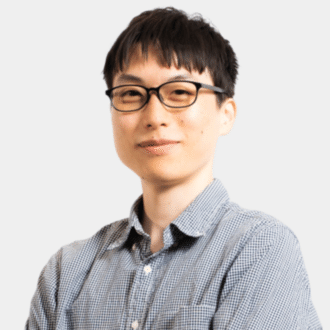生き方を考えることは死に方を考えることなのです。
昨日は舞台劇を見てきた。戦時中の東京から長崎に疎開した4人の女学生と、2人の特攻兵の群像劇である。
感想の具体的な言語化はまた後日に譲るとして、ひとまず現時点で考えていることを言語化しておきたいと思った。
全体を見終わった直後に感じたことは、これまでの自分が舞台劇に対して覚えた感動のしかたとは、また少し違った感覚だったような気がした。
それは、ある特定のセリフが心に刺さったとか、登場人物に自分を重ねたとか、そういう感動のしかたというよりは、劇がエンディングに向かい暗転したタイミングで、何だか心が内側からじんわりと温かくなるような感動のしかただったように思った。
もちろん、登場人物の行動や良いセリフに感化された場面も多々あるが、また違う感覚を得られたという点で発見があった舞台だった。
物語に登場する特攻兵たちは、2日後の出撃が既に決定しており、命を捨てる覚悟を決めた状態にあった。
しかし、あるきっかけがあって田舎の女学生たちに出会い、心から笑ったり、自分の本当の願いを流れ星に叫んだりすることを通して、人間性を取り戻していく姿が描かれた。
若者の命を無下にする特攻作戦そのものがいかに愚かであったか、戦争や軍隊の規律がいかに人間の人間性を奪うものであるか、深く考えさせられた。
2人の特攻兵のうちの1人は、2日後の死が確実視される身である中で流れ星に向かって、心の中に押し込んでいた願いとして、恋人、結婚、良い父親になること、などを叫んだ。
今この現代に生きてなんとなく平和ボケしてしまっている自分からすると、そのような願いは実現し得るものであると安易に考えてしまうが、当時の状況ではそのようなことすらも叶わぬ夢だったのだ。
今この瞬間に自分の目の前に流れ星が流れているとしたら、私は一体何を願うだろうか。
本当の願いや実現したいこと、もう少し極端な言い方をすれば、己の欲望を解放することは、やはり死が意識されなければ到達することができないように感じている。
もし2日後に死ぬとしたら、後悔の無いように今日を生きられているだろうか。
特攻兵の彼らよりもこんなにも選択肢がある生活を送れている今、その「選択肢があること」そのものが大いに幸福であることに自覚的にならなくてはいけないと思った。
だとするなら、今置かれている状況の幸福をしっかりと享受して、死ぬまでにやりたいことを全部やってから死にたいと思う。
生き方を考えることは死に方を考えることなのである。
いいなと思ったら応援しよう!