
【本という名の大樹】彼岸花にまつわる話
あちらこちらで彼岸花を目にする季節になりました。秋の風に繊細な花被片を揺らすこの花を見る度に思い出す話があります。
1:土佐寺川 とは
「忘れられた日本人」という本がある。
著者は 宮本 常一 。民俗学の界隈で知らぬ人はいない人物である。
本書との付合いは長く、僕にとっては「40年来の知己」といった感じだ。
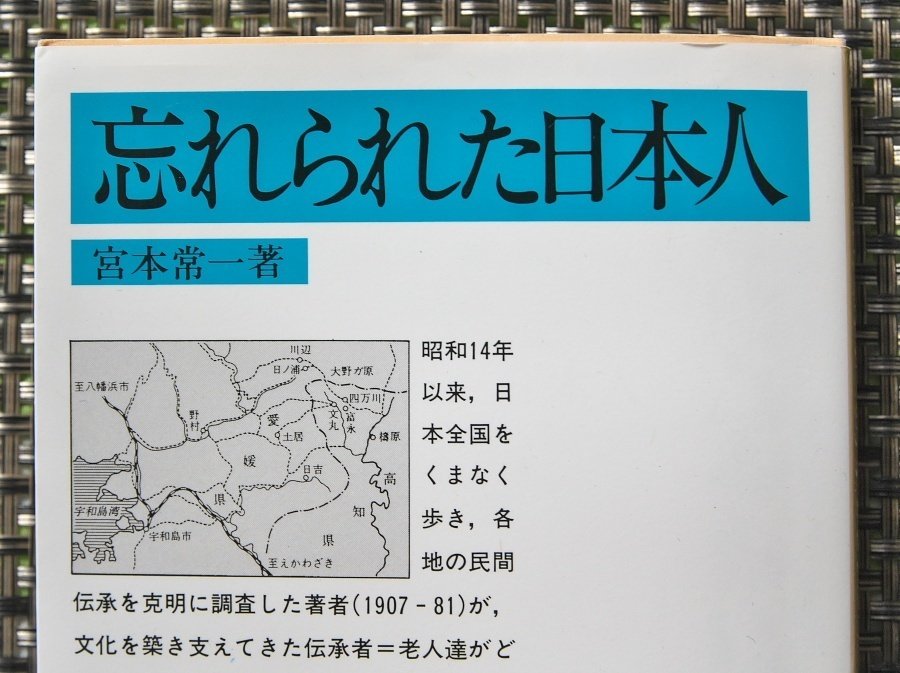
この本の中に 土佐寺川夜話 という章がある。
土佐寺川とは、高知県の北部山間地域にあり、愛媛県の名峰にして日本百名山の誉れ高き石鎚山の東側に位置する山村だ。マップを見れば一目瞭然、高知県と愛媛県の県境が迫っている。それ即ち、山深いことこの上ない地域であることを意味している。

著者の宮本常一は、先の大戦が始まった1941年の12月に土佐寺川を目指して伊予小松を出立している。
我々からすれば「何もこんな時に!」と思うのだけれど、かつて同地の村人と交わした再訪の約束を果たすためだけに、彼は未曽有の事態と師走が重なった時節にもかかわらず歩みを進めたのだ。

同書によれば、土佐寺川の歴史は相当に古いらしい。
” 関ヶ原 ” の頃には村落が形成されていたという記録が、慶長年間の検地帳に残されているとのこと。田畑に供さない厳しい土地柄であったが故に、国境警備の役(主に盗木の警備)を以て年貢を免除されていたようだ。
とまれ、こうした分水嶺(峠や尾根筋)や川境の近似した様相は、日本各地で散見されるので何ら特別なことではない。
而して、年貢に供するような収穫が見込めない土佐寺川の土地柄(原生林)は、皮肉なことに様々な逸話を産み育てた。
「年貢が納められない。」
それ即ち、気候風土のみならず、大型の使役動物が活躍できるような田畑や、荷物の運搬に適した道がなかったことを意味する。その様な山間僻地であったが故に、生まれて初めて牛を見た老婆が「この馬には角が生えている!」と言ったとか言わなかったとか … 。
このように、落語の枕になりそうな滑稽話や逸話が沢山残っている地域というものは、概して僻地であることが多いのである。

さて、これから続く話を首尾よく把握するために、各マップの中に記された「白猪」と名のつく地名を押さえておいて頂きたい。
白猪 … それはまるで「もののけ姫」に出てくる巨大な猪「乙事主」を連想させるような地名である。
伊予小松を出発した宮本常一は、国境稜線上にある白猪谷峠(現在のシラサ峠か?※下の国土地理院地図を参照)から、高知県を流れる吉野川が作った深谷へ下り、山間の急傾斜地に設けられた寺川の集落に辿り着いたことが窺われる。けれども、本書では伊予小松から白猪谷峠までの経路について一切触れられていない。

恐らくは、石鎚山の北東域を流れる加茂川に沿って歩き、十郎あれ(上地図の左上)から現在の登山道(上地図の赤破線:当時は杣道だったと思われる)を通り、鳥越を経て子持権現山に達したのではないかと推測する。
但し、本書の冒頭に記された描写(下引用)や絵図(冒頭から3枚目の画像)を見ると、十郎あれの周辺から沢筋を辿り、国境稜線から派生する尾根を登ってシラサ峠へ行き来できるような杣道・獣道(上地図の青破線:僕の妄想)が存在していた様にも思われるのである。
この道がまた大変な道で、あるかなきかの細道を登ったり、橋のない川を渡ったりして木深い谷を奥へ奥へといきました。
たった二行程の描写であるが、推測しうることは沢山ある。いやはや、謎は深まるばかりなのだ。
いずれにしても、道程の殆どが徒歩で、しかも当時は登山道が整備されていないのだ。更に、季節(12月)を考えれば … 本当に恐れ入る。

この旅の途上、宮本常一はレプラ患者(ハンセン氏病)の老婆と邂逅している。コブだらけの顔をした老婆は「こういう業病で、人の歩くまともな道を歩けず、人里も通ることができない。」と彼に語った。
人跡の少ない原生林の山中にあって、いわれなき偏見と差別に苦しんだ寄る辺なき人々によって拓かれ、そして伝えられてきた「カッタイ道」が存在することを、彼は知ったのである。
※カッタイ:レプラと同様にハンセン氏病の意。梅毒も指したようだ。
清張が著わした「砂の器」の一場面を思い浮かべる。
嗚呼、やるせない。僕の様な暮らしをしてきた人間には、その程度の想像しかできないのだ。そこに一抹の悔しさと安堵が複雑に混在している。
2:彼岸花を食べざるを得なかった人々
本章「寺川夜話」は、寺川再訪の様子や活動の内容をつぶさに書いているというよりも、それまでの間に収集してきた話や、「寺川郷談」に記録された話を紹介する形で物語は進んでいく。
※寺川郷談:宝暦年間に土佐藩の山役人として土佐寺川に赴任した春木次郎八による記録。

その中に、彼岸花にまつわる話があった。
その一節は、僕の心を掴んだ。
ややもすれば、尾籠な話に映るやもしれない。けれども、こうした記録もまた名も無き人々の生活誌であり、且つ人間の性を表している芳ばしい話に思われてならない。
天保のキキンの時はずいぶん伊予からたくさん来て、シライ谷に小屋を建てて住んでおりました。シライ谷というのはシライの多い谷のことで、シライはシレエとも言い、彼岸花のことです。もともと救荒植物として土佐藩では田畑の畔に植えさせたようですが、シライ谷は今行っても初秋には火が燃えているようにこの花が咲きそろうと云うことです。
~ 中略 ~
伊予の人たちは一年近くそこに住んでシライを掘り、それを煮て川水でさらし、毒をぬき、ついて餅にしました。これがシライ餅です。少し食べるには悪くもないが毎日たべると、決して有難い食べものではありません。そのシライを食べ、稗や稗ヌカを食べました。
~ 中略 ~
さて一年ほどして伊予の人たちはまたその家の方へ帰っていきました。小屋もとりのぞいて、もとの山になったのですが、くぼみをつけてひり捨てた糞が山のようだったと申します。そしてその糞が長い間雨風にさらされて、くさみもねばりもとれてしまうと、またもとの稗糠に戻っていたと申します。
~ 中略 ~
村人もこの時(天保の飢饉)は全く困ってシライモチまで作ったと申します。ある男が山へ木挽に行って、べんとうのシライモチを食べたがいかにもうまくない、最後の一つを切株の上にのせておいて帰りました。一年ほとたって行ってみると、モチはそのまま切株の上に白くさらされたまま残っていたと申します。
※文章の中に、ヌカと糠・モチと餅という風に、カナと漢字が混在していますが、原本通りに引用しております。
よもや、この一節に解説は無用だろう。
こうした悲惨さとある種の滑稽さを同時に感じさせる古い話が、悠久の時と世代を超えて精緻に語り継がれたという事実に、僕は胸を熱くする。
3:忘れてはならない人々
この東の果ての島国で生を受けた人々の殆どが貧しかった時代を想う。
間違っても ” その時代 ” に戻りたいとは思わない。さわさりながら、現在の日本、引いては昨今の日本人の有様が望ましい姿なのかと問われれば ………… 僕は素直に頷くことができない。
そんな心の葛藤もまた、古の記録が与えてくれる貴重な時間なのだ。

