
外交を人間の感情で捉え直す『感情外交』と『世界政治の情緒的コミュニティ』の紹介
最近の国際政治学の潮流の一つとして心理的アプローチを取り入れる研究が増えてきていることが挙げられます。
対外政策をめぐる意思決定のプロセスを理解するためだけでなく、国際情勢の変化を国民がどのように受け止め、どのように反応するのかを理解するためにも、人間の心理に対する理解が欠かせないと研究者が考え始めています。戦争の原因に関する研究でも心理学の理論やモデルを対外政策分析に活用する取り組みが進められています(例えば、論文紹介 国内で支持を集めるために国外で軍事的な緊張を高める手法がある)。
今回の記事では、外交政策で感情、情緒に訴えるコミュニケーションがどのように利用されているのかを考察した2冊の文献を取り上げて、それらの成果を紹介してみたいと思います。
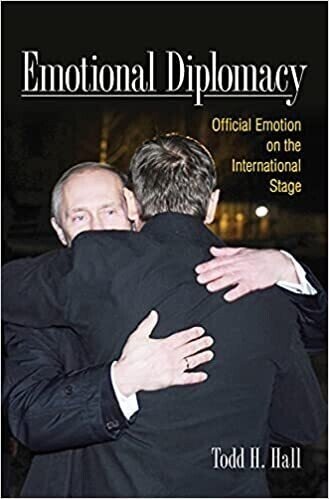
こちらの『感情外交(Emotional Diplomacy)』は国際社会で自国に対するイメージを戦略的に管理し、操作するために、あえて感情的な態度を外交官に表明させる手法を用いた外交政策の研究です。
かつて、外交官は冷静沈着であり、感情の高まりを抑制できることが美徳とされてきました。しかし、現代では外交官にあえて怒りの感情をメディアの前で表明させることがあります。これは、怒りを向けられた相手から反省や謝罪を引き出し、あるいは強い反発を引き出すテクニックであり、この手法を著者は感情外交と呼んでいます。
感情外交の手法はさまざまであり、単にレトリックやジェスチャーが用いられるだけの場合もあれば、経済的、軍事的、法的手段を組み合わせて用いることもあります。ホールの説によれば、感情外交で表明する感情は必ずしも政策決定者の感情と一致している必要はありませんが、表明する感情に真実味と説得力を持たせるためには、外交官が実際に感情的になっていると思わせるような振舞いをとれなければなりません。
感情外交の具体的な事例として著者は、1995年の台湾海峡危機で中国が表明した「怒り」の外交や、2001年の米国同時多発テロ事件でロシアと中国がアメリカに表明した「同情」の外交、第二次世界大戦の戦後処理をめぐる西ドイツの「罪悪感」の外交を挙げています。ただ、著者の研究は報道資料に依存しており、当事者がどのように状況を分析していたのか、どのように方針を選択していたのかは明らかになっていません。
感情外交は単に対外的なイメージの操作だけを目的としているだけではなく、国内の支持層を標的とした選挙運動の一環として行われている可能性も高いので、この研究は政治宣伝の研究として位置づけることもできることもできると思います。
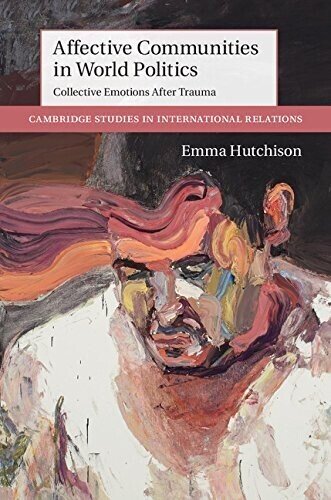
この『世界政治における情緒的コミュニティ(Affective Communities in World Politics)』は、民衆の感情が対外政策の決定に影響を及ぼす政治過程を分析している研究です。著者が特に関心を寄せているのは、社会全体で経験されたトラウマ的な出来事が強い感情的な反応を呼び起こす現象です。テロリズムの被害、戦争の記憶、植民地支配などのトラウマ的な出来事が広く共有された社会では、大規模な政治的動員が可能になります。
2001年9月11日にアメリカで起きた同時多発テロ事件はアメリカ国民にとって衝撃的な出来事でしたが、それは愛国心を呼び起こし、アメリカが全世界的なテロとの戦いに向けて軍事作戦を開始することを強く支持することにもつながったと著者は説明しています。このような対外政策を利害だけで説明することは困難であり、人間の感情がどのように生起しているのか、それによって行動がどのように変容するのかを理解することが重要だと著者は主張しています。
本書で取り上げられているもう一つの事例に、2002年にインドネシアで起きたバリ島爆弾テロ事件があります。この事件ではオーストラリア人に多数の犠牲者が出ましたが、著者は当時の報道がオーストラリアの民族主義的な感情を刺激するように設計されていたことを指摘しています。オーストラリアの有力紙の報道内容を詳しく検討すると、このテロ事件はオーストラリアの価値観や生活様式への攻撃であるというフレームが示されており、これには読者の感情的な反応を一定の方向へ誘導する効果があったと論じられています。
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

