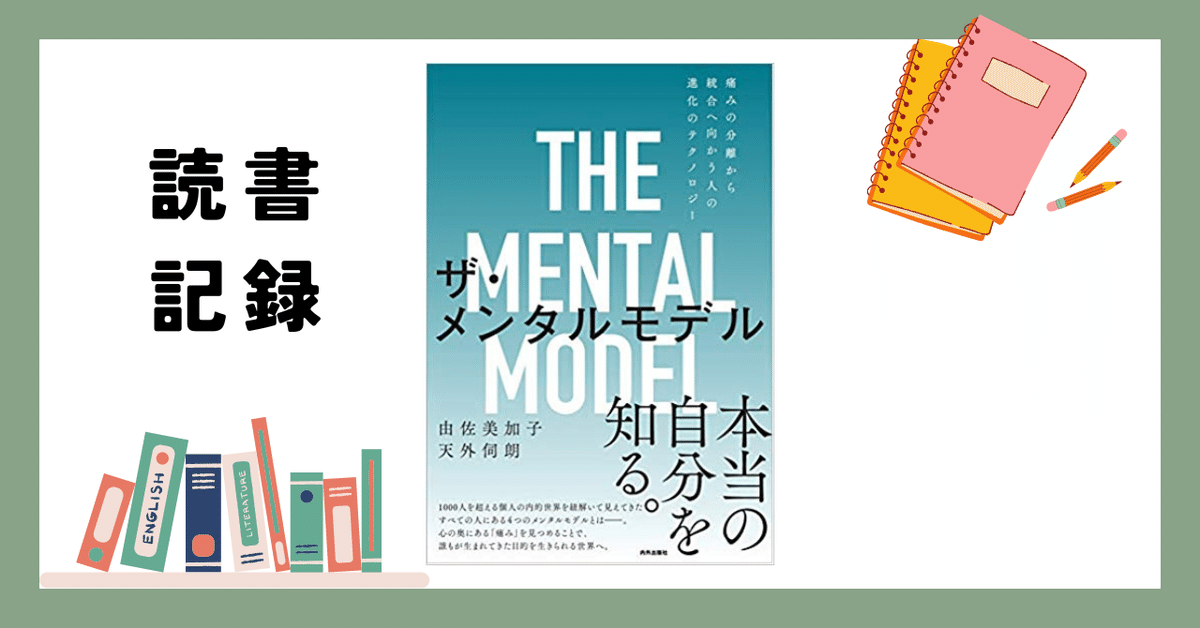
読了『ザ・メンタルモデル』
タイトル:
『ザ・メンタルモデル
痛みの分離から統合へ向かう人の進化のテクノロジー』
著者:由佐美加子、天外伺朗
発行:内外出版社
本の紹介
本書では、人が生まれながら持っているとされる「メンタルモデル」を
由佐塾でのみいちゃん(講師)と生徒の対話を通して知ることができます。
この本で定義する「メンタルモデル」、とは、誰もが無自覚に持っている「自分は/世界はこういうものだ」という人生全般の行動の起点になっている信念・思い込みです。
私たちは幼いころに「この世界にあるはずだ」と思っている大切なものが、期待していた形では「ここには”ない”」 という何らかの欠損の"痛み" を体験します。
その際に、「自分が/世界は ◯◯なんだ、(だから仕方ない)」と思考を使って理由づけし、この痛みの感覚を切り離そうとする、という働きが無意識で起こるようです。
この時に形成される「自分は◯◯だ(だからこの痛みが起きたんだ)」という自分やこの世界に対する"判決" のような完全無自覚な信念・思い込みをメンタルモデルと呼びます。
内容は少し難しいですが、
本の6割程度はみいちゃんと生徒の対話形式で書かれているので、
読みやすくはあります。
この本を読んだきっかけ
現在受けているキャリアコーチング(ポジウィル)で、
課題図書として提示されて読みました。
本からの学び
あなたはどれ?4つのメンタルモデル
メンタルモデルは現在は4つに分類されるそうです。
メンタルモデル
Ⓐ「価値なし」モデル(私には価値がない)
Ⓑ「愛なし」モデル(私は愛されていない)
Ⓒ「ひとりぼっち」モデル(私は所詮ひとりぼっちだ)
Ⓓ「欠損・欠陥」モデル(私には何か足りない・欠けている)
人間は共通してこの4つは持ち合わせている一方で、
特に「生存適合システム」に影響を与えているのは
いずれか1つに絞れると言います。
「生存適合システム」と言うのは、
人間にとっての、PCで言うところのOSに相当するもので、
メンタルモデルはそのOSの大元のプログラムだと説明されています。

http://mentalmodel.jp/
痛みから発せられる不快な感情を感じないようにするために
メンタルモデルというプログラムが作動し、
「克服」や「逃避」といった形で回避行動を起こします。
無自覚に生存適合OSで生きている間は、この痛みの回避だけが実際には人生を動かしているエンジンであり、この痛みが人生のどこかで情熱へと転化すると、そこから本当にはあるはずだと自分が信じていた世界を、現実的にここに「創造する」クリエーターとして情熱から生きる人生が始まります。
求めているものは幼児語みたくシンプル。複雑に考えてもわからない
生存の何が快で不快か、といこうことは、思考で判別されてわかるんですよね。だけど、本当に、自分の奥の命が何を求めているかという世界は、考えても絶対にわからないです。
もっとシンプルだし、もっと大事にしたいことって、人間がごちゃごちゃ考えている世界よりもっと深いところにあって。愛が欲しいとか、繋がりが欲しいとか、もっと自分の人生を自分らしくいきたい、とか。そういう類のものなんですよ。だから、感じて出てくることって幼児語みたいな感じのシンプルな情報なんだけど。でも、すごく大事なんですよ、そこが本当はね。だから、本当には、何が欲しいの? と自分に常に聞いてあげて欲しい。
本からの気づきや感じたこと
まず初めに、自分のメンタルモデルは
「価値なし」モデルに分類されると思いました。
価値なしモデルの人は、
「他の人に対して価値を出せなかったら自分にはここにいる価値はない」
と思い込むという特徴があります。
できない自分ではだめだ。自分が何かしら人に価値を提供できるから、成果を出して期待に応えられるから、だから認めてもらえるんだ、ここにいられるんだ、見てもらえるんだ、つながってもらえるんだ、という体験が価値なしモデルの人たちには共通しています。
たしかに、私は幼少期から塾に通わされ、勉強ができると褒められ、
「自慢の孫」という価値を祖母にずっと提供していました。
その価値提供に疲れ、10代の頃は抵抗もしてきました。
そして、就職と同時に地元を離れ上京しました。
抵抗したからといって
幼少期に形成された生存適合OSは別のものに替わるわけでもなく、
10代の頃は「自分の生まれてきた意味は何だろう」「自分の存在意義とは」
というのを常に考えていました。
そして、ようやく自分の存在価値として出てきたのが
「誰もが自分らしく生きられる社会の実現」というものでした。
最近までこのビジョンを盲信し、
自分の存在価値はこれを達成するために行動することだと
信じてやみませんでした。
「このビジョンを否定すると自分の存在自体も否定することになる」
と思っていました。
今は、まだ道半ばですが、
この本、メンタルモデルという概念と出会ったことで、
こんなビジョンなくても、存在するだけで価値がある
と思えるようになってきました。
この本を読むことで、
みなさんが少しでも生きやすくなればと思います。
