
グローバル・ケア・チェーン(Global Care Chain) 介護労働の国際化(5)介護労働Ⅴ‐5
1.グローバル・ケア・チェーン(Global Care Chain)
国内の介護人材不足への対応として、外国人労働者の雇用を促進するということは、日本の介護現場がグローバル・ケア・チェーン(Global Care Chain:以下「GCC」と略す。)に組み込まれるということです。
介護関係者には、積極的に「GCC」という言葉、概念を使ってほしいと思っています。
千葉大学大学院社会科学研究院教授の小川玲子さんはGCCを次のように説明しています。
「ホックシールド[1](2000)は、ケア労働がより貧しい地域出身の移住女性たちによって担われるようになったことを指して Global Care Chain (GCC)と呼んだ。先進国の家庭でケア労働を提供する途上国の移住女性のケアの責任は、さらに貧しい地域出身の移住女性によって担われなければならず、ケアチェーンの末端においてはケア労働の不足が生じる。」
参考:上野加代子「国境を越えた女性の移動―今日の南北問題」https://core.ac.uk/download/pdf/268375069.pdf
また、上野千鶴子(東京大学名誉教授)さんもGCCについて次のように言及しています。
「マクロ的に見れば、日本もまたグローバルなケア・チェーンの一環を占めることになるのは不可避であろう。日本の高齢者のケアを発展途上国のケアワーカーが担う。出身国では中産階級に属する移民労働者が祖国に残してきた家族のケアを、さらに低階層の家事労働者が担う。地方や農村出身の家事使用人の故郷の家庭では、祖父母が孫の世話をする。その孫たちが外へ出て行けば、高齢化した祖父母のケアを担う者は誰もいない。先進国の高齢者の手厚いケアが移民労働で担われる一方で、グローバル・ケア・チェーンの末端では、ケアの崩壊が起きる。」
日本の介護人材不足を外国人労働者で賄うということは、GCCの末端のケア崩壊に加担しているということで、政治的かつグローバルな問題なのです。
GCCは介護領域の「アボガド」のような事象だと思います。
斎藤幸平さんはチリのアボガドを例に、先進国の食物調達チェーンの末端で起こっている不公平で不条理な負担について次のように指摘しています。
『南米チリでは、欧米人の「ヘルシーな食生活」のために、つまり帝国主義的生活様式のために、輸出向けのアボガドを栽培してきた。「森のバター」とも呼ばれるアボガドの栽培には多量の水が必要となる。また、土壌の養分を食いつくすため、一度アボガドを生産すると、ほかの果物などの栽培は困難になってしまう。チリは自分たちの生活用の水や食料生産を犠牲にしてきたのである。』
資本主義が世界を呑み込んでしまっている現代社会において、介護業界もグローバリズム、グローバルノース(Global North)[2]によるグローバルサウス(Global south)[3]の収奪と無関係でいられるわけがないのです。
このGCCについて無自覚でいてはいけないように思います。
まずは、このグローバル・ケア・チェーンという言葉、概念を知ることから始めることが大切だと思うのです。
このGCCを知らなければ、問題そのものが存在しないことになってしまいます。
2.貪り喰らう資本主義
アメリカの政治学者のナンシー・フレイザー(Nancy Fraser)は、資本主義体制においては、グローバルノースの労働者は資本家に搾取されているが、この搾取構造の成立条件として、グローバルサウスの労働者とその家族たちは収奪されていると指摘しています。
「・・・収奪のことである。被征服民やマイノリティの富を継続的に、強制的に奪い取る行為だ。収奪はたいてい、資本主義に特有の搾取というプロセスの対立物とみなされるが、搾取を成り立たせてる条件として捉え直したほうがいい。」
「その理由は、搾取と収奪もただ方法が異なるだけで、どちらも蓄積(資本蓄積)に欠かせないからだ。」
もう少し詳しく見てみましょう。
同氏は、グローバルノースの労働者は自分の生活費用を稼ぐ以上に労働することによって、資本家に搾取されていると次のように指摘しています。
①搾取
「自由な契約の交渉と称して、搾取は価値を資本に移転する。労働力の見返りとして、労働者は生活費用を賄う(とされる)賃金を受け取る。いっぽうの資本は「剰余労働時間」を私物化し、少なくとも「必要労働時間」分は支払う(ことになっている)。」
②収奪
「その反対に、収奪では、資本家はそのような慎ましさはかなぐり捨てて、ほとんど、あるいはまったく支払いもせずに他者の資産を暴力的に取り上げる。奪い取った、労働か土地、鉱物、エネルギーあるいはそのすべてを事業につぎ込んで生産費用を引き下げ、利潤の引き上げを狙う。このように搾取と収奪は排除し合うどころか、手と手を取り合って作用する。」
ナンシー・フレイザーは、グローバルサウスは資本家により収奪され、その収奪によってグローバルノースの労働者たちに安い消費財を提供して彼らの生活費用を低減し、その結果、労働者の賃金を抑制することが可能となるのだと指摘しているのです。
同氏はさらに、このような「収奪-搾取」の構造は資本主義に固有な構造であるとしています。
「・・・収奪は搾取の根底にある。搾取が利益を出せるのも収奪のおかげだ。・・・収奪も搾取と同じように、本質的かつ構造的に資本主義社会に組み込まれている。」
ようするに、資本主義体制では、グローバルサウスから労働力、土地、鉱物資源、エネルギー等を徹底的に収奪することにより、グローバルノースで労働者の賃金を下げることが可能となり、このことによって、より効率的にグローバルノースの労働者を搾取できるようになるというのです。
政策的に、国内の介護労働力不足をグローバルサウの外国人労働力で賄うということは、グローバルサウスの労働力を債務労働として、収奪する仕組みと言えるのかもしれません。そして、グローバルサウスに介護崩壊を招来させるGCC維持・強化する政策でもあるのです。
③己を喰らうウロボロス
紹介、引用してきました、ナンシー・フレイザーの「資本主義はわたしたちをなぜ幸せにしないのか」という著書の英文原題は『Cannibal Capitalism』です。直訳すれば『共食い資本主義』です。
この原題からも推察できるように、この著者は、資本主義は、己の存在を支える、社会、政治、自然、再生産労働、家庭、グローバルサウスなどを貪り、喰らい尽くしていく構造を持っていて、それはまるで、ウロボロス[4]のようだと喝破しています。
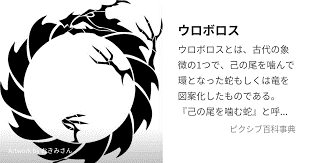
介護業界でも、グローバリゼーション、グローバルノースによるグローバルサウスの収奪と無関係ではいられません。介護現場で目の前にいる外国人労働者は、共食い資本主義の搾取・収奪構造を体現してそこに存在しているのです。
まずは、介護業界でグローバル・ケア・チェーンという言葉、概念をしっかり定着させていく必要があります。
GCCという言葉を知らなければ介護における世界的な収奪構造が見えてきません。問題さえ認識できないことになります。
朱喜哲さんが「人間や社会は受肉したボキャブラリーである」というリチャード・ローティの考え方を、次のように説明しています。
『「人間や社会は具体的な姿形をとったボキャブラリーである。」ということは、どんなことばづかいをするかによって人間は変わる、という帰結をもたらします。
ことばづかいが変われば人間は変わるし、流通することばが変われば社会も変わるのです。ローティが会話や語彙にこだわる背景には、こうした認識があるわけです。』
介護関係者のことばづかいの中に、グローバル・ケア・チェーンという言葉を付け加えたいものです。
3.「われわれ」の拡大
日本の介護人材不足を補うための外国人労働者の増加は、介護現場に排外主義的な非人間的であるレイシズム(racism)を蔓延させ、収奪的なグローバル・ケア・チェーンの末端の介護崩壊を招来させるかもしれません。
朱喜哲さんは、非人間化は「われわれ/やつら」を線引きすること。そして、その線引きが、偶然的な性質ではなく本質的な差異にもとづくもので、改訂不可能なものだとする(本質主義)ことにより、確立すると論じています。
(参照:朱喜哲2024「人類の会話のための哲学」よはく舎 nyx叢書 p222,223)
朱喜哲さんは、この本質主義と「われわれ/やつら」の線引きについて次のように紹介しています。
『本質主義とは定義上、本質を共有する「われわれ」とそこから締め出される外部との境界を固定する。この立場に支えられた倫理では、すべての「人間」に対する倫理的態度と、本質を共有しない「非‐人間」への無慈悲な排斥とが論理的にも倫理的にも両立する。』
『いくらカントを引き合いに「普遍的価値としての人権」や「人間の尊厳」に訴え、私たちの道徳的義務を論じても、そもそも、「私たち」に含まれない存在に対しては、これらの道徳的義務は何の意味も持たない。』
介護現場の人材面での国際化は、介護現場に多様性をもたらしますが、多様性は違いに注目することですので、本質主義に染まりかねません。
「われわれ/やつら」の線引きと本質主義が、外国人労働者を「われわれ」に属さない「やつら」のままに放置することになるのです。
課題は介護現場で働く日本人労働者たちの「われわれ」の範囲を拡大していくということです。
まずは、「われわれ」範囲を一緒に働く外国人労働者にまで拡大すること。そして、「われわれ」の一員である外国人労働者の母国を知り、その国の文化などを味わい、その国の介護についても関心を持てるようになりたいものです。
その際、グローバル・ケア・チェーンという言葉を知っていれば、その国の介護と目の前の介護が構造的に、そして、共感を持って繋がってくるのではないでしょうか?
その時には「われわれ」の範囲が他国の人たちにも及ぶようになるのかもしれません。
GCCはグローバルノースの介護をグローバルサウスが収奪されていることを表す言葉ですが、介護において、グローバルノースとグローバルサウスが何らかのかたちで「支え合う」という意味へと置換されていく可能性に賭けたいと思います。
追記 入居者は「やつら」か?
朱喜哲さんの近著「人類の会話のための哲学」は私のような耄碌爺には難しくて、なかなか歯が立たないのですが、とても刺激的です。
読んでいて?マークが沢山ついてしまうのですが、その?が刺激的なのです。
いま、特に気になった?があります。
それは、『介護施設の労働者たちにとっての「われわれ」には入居者が含まれてるのか』という問いです。
なんか、介護施設の介護労働者たちの「われわれ」には入居者は含まれていないように思うのです。では入居者は「われわれ/やつら」の「やつら」でしょうか?
よく、私たちの施設は、「家庭的雰囲気を大切にしている」という宣伝文句がありますが、そんな施設では入居者も「われわれ」になっているのでしょうか? 家庭的介護いついても考えみる必要がありそうです。
「人類の会話のための哲学」を読んで、いろいろと、考えたいことが増えてしまいました。
[1] ホックシールド(Arlie Russell Hochschild 1940~)アメリカの社会学者
[2] グローバルノース(Global North)は、グローバル化の恩恵を受け経済的な発展を遂げている先進国を指す。
[3] グローバルサウス(Global south)とは、地球規模の権力関係によって生じた格差がうみだした概念。あくまで格差による負の影響や要因に着目するための概念で、グローバル化によってその被害を受ける地域や住民のこと。地理的に南にある地域を指すわけでも、地理的な線引きや国のグルーピングをするものではない。
[4] ウロボロスは、古代の象徴の1つで、己の尾を噛んで環となったヘビもしくは竜を図案化したもの。
以下のnoteもご参照願います。
