
中学受験「憎しみ」がわからない。 その1
みなさん、こんにちは。
今日は、国語指導(中学受験の)において、最近の子どもたちの語彙不足について少し書いてみたいと思います。

物語文の指導の中で、登場人物の心情を問われる問題は必ずといってよいほど出題されます。
また、設問になくとも、気持ちを表すことばというものは多く出てきます。

喜び、悲しみ、怒りなどいろいろな気持ちを表すことばが問題文の中にでてきます。
私たちの普段の生活で、どれくらい使われているかは、各ご家庭様の中での会話の質と量と関係があるのではないかとも思います。
親御様が語彙が豊富で、夫婦間で、わりあい難語といわれるような会話がされていれば、それを聞いている子どもは
「それって、どういう意味」と会話に入っていきます。
また、
親御様は、
「例えばね、それはこれこれ、こういうわけなのよ」
などと具体的な、身近な例を用いて、説明しますので、子どもの語彙が豊富になっていき、難語も自然と身についていくものです。
さらに、親子関係がうまくいっている場合にできることです。
よく、「国語は、どのように教えてよいかわからない」ということをいわれます。
それは、大抵、共働きで、子どもを塾に預け、塾で完結させようという場合が多いです。
集団授業の場合は、問題文の中に出てくる語彙の説明を一つひとつは取り扱いません。
「そこは自分で調べてね」というのが塾の言い分であり、集団授業の限界でもあります。
集団授業でできることは、問題文を解くにあたってのヒントを与えたり、選択肢問題の答え合わせが精一杯です。
記述については、クラスの生徒の出来具合によっては、ある程度は触れることもできたり、個別の添削もできますが、時間に限りがあるので、細かな指導には限界があるのが実情です。

そこで、語彙が絶対的に不足している生徒に対しては、問題を解くことよりも、問題文を読んで、わからない言葉の意味調べから始めます。
辞書引きですね。
辞書は電子辞書でも、紙の辞書でもかまいませんが、中学受験をするなら、大人と同じ辞書じゃないと、そもそもわからない言葉が掲載されていないことはよくあるので、小学5年生くらいになったら大人と同じ辞書を使うようにお勧めしております。
そして、紙の辞書の場合、引いた言葉にマーカーを引いたり、付箋を入れるということや、引いた言葉をノートに書き移すという、自分の言葉ノートを作るようにお勧めしています。
これは、どちらかといえば受験生よりは5年生以下の生徒様にお勧めしています。
辞書引きをするようになると、辞書引きのスピードが上がってきます。
見ていると、(本当は、言葉の意味を覚えて欲しいところですが)辞書引きすることが一つのモチベーションになっていることもあるようです。
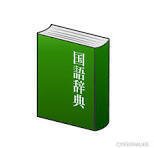
そこで、一言
「辞書引きが早くなったね!」
という褒めてあげることです。
繰り返しになりますが、言葉の意味を覚えて欲しいのですが、まずは行動に移せたこと、そして、それができるようになったことを褒めることが子どもにとっての一つの達成感につながるのです。
言葉ノートを作ってくれている生徒には、時々自分で書いたノートを振り返って、本当にわかったかを確認するように促しています。
まずは、語彙を増やすことが国語には必要なのです。
つづく。

