川崎長太郎「ふっつ・とみうら」
川崎長太郎の、特にこの「ふっつ・とみうら」という短編の中で独特なのは句点の几帳面さである。どこからどこまでが意味のかたまりかわからなくなりそうなとき、割と私も句点を打つことが多いけれども、長太郎はこれでもかというくらい打ってくる。
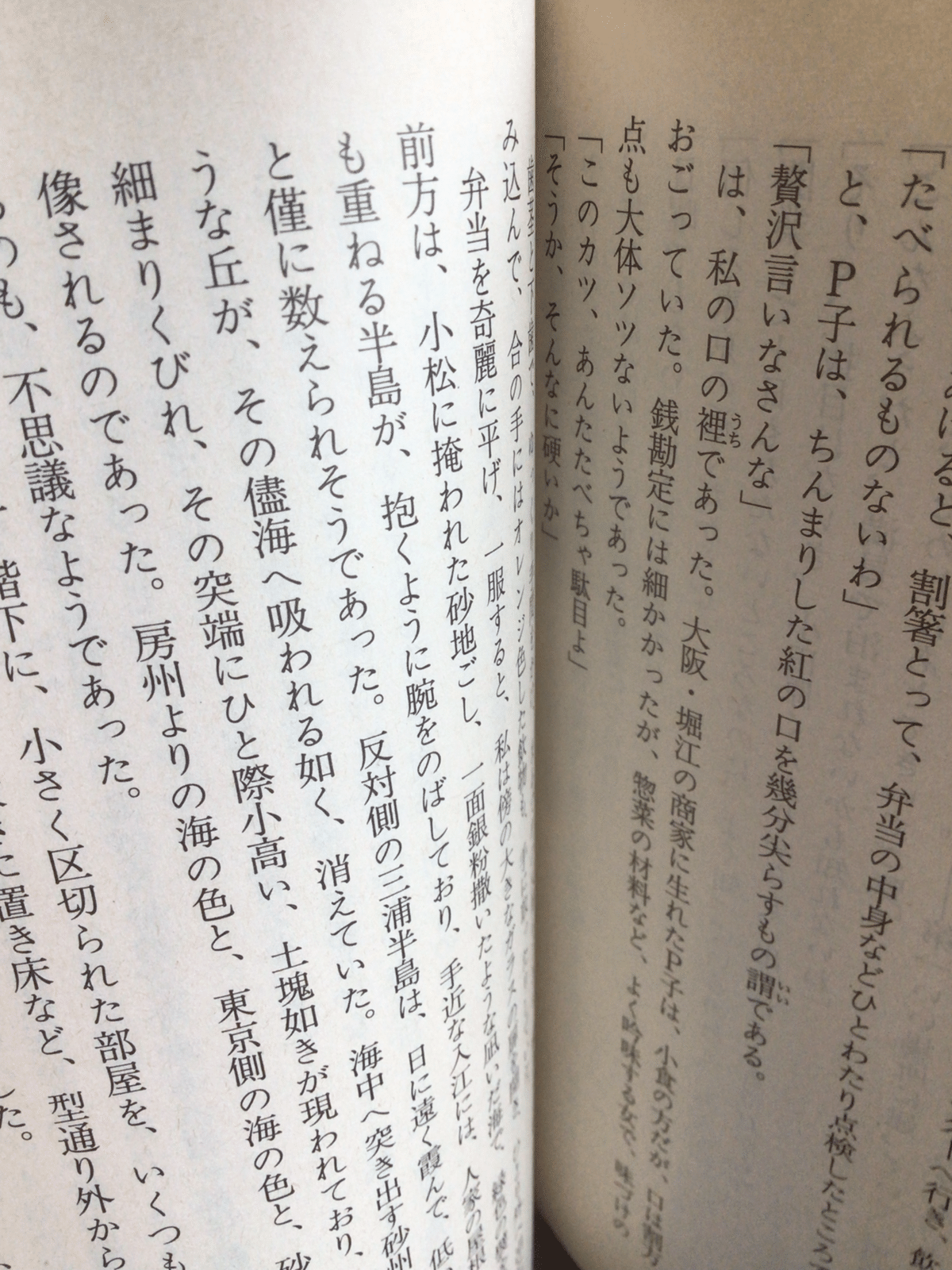
最初の作品「無題」は、段落も句読点もあまりないものなので、おそらくは途中で出会う徳田秋声の影響なのかもしらん、と思った。

川崎長太郎は小田原生まれ。小田原には親戚がいて、何回か、いや、或る年にはかなりの回数いっていたので、割と馴染みがある街だ。そのくせ箱根にはあまり行ったことがない。
*
「ふっつ・とみうら」は、戦後年老いた長太郎が30歳若い女と暮らしだし、その女「P子」と一緒に、横浜から開港した木更津までのフェリーに乗って、木更津から富津にある新しい国民宿舎に行ったら満員だと断られて、南房総の富浦の民宿に泊まって、P子とアレコレと喋る話である。
最後P子が、長太郎が死んだ後、自分はアフリカに行って、そこで結婚するみたいなことを言って、それを長太郎がたしなめて終わる。印象的なラスト・シーンである(笑)
*
横浜木更津間のカーフェリー開業が1965年、国民宿舎は「富津ロッジ」だろう、開業は1965年4月28日。P子と長太郎が行ったのは、ちょうど昭和40年の夏くらいということになる。
私が小学校に入る前に、千葉に旅行に行って泊まった民宿では、なぜか客全員が同じ部屋で膳を並べながら夕食をとる、という形式で、いたく居心地が悪く思ったのに、隣に座ったおっさんが、「坊や何年生か?」と聞いてきたので、「この4月から小学校です」と私が答えたのか親が答えたのか、おっさんは「じゃあ0.5年生だな、アッハッハ」と言われて、たいそう不快に思ったことを今でも覚えている。
そんな民宿ではなく、初めてホテルのようなところに泊まったのは国民宿舎で、旅行に行くと言われて、もう民宿は嫌だ!という私を説得するために、今回は国民宿舎よ、と母親が言い、国民宿舎とはなんぞや、と出かけて行ったら、えらく綺麗なホテルのような建物で、それ以来、国民宿舎は私の中で栄光に包まれていた。
2000年代の中頃、その記憶のまま、どこかの国民宿舎を予約して、妻と旅行に行った。国民宿舎だからまあまあいいよ、なんて言っていたら、ちょっとしたシティホテルよりもボロボロで狭く、自分の記憶の国民宿舎が終わってしまったことを思い出した。
開店当初の富津ロッジはきっと、キラキラとしていたのではなかっただろうか。P子が是が非でも泊まりたいと駄々を捏ねた理由もわかる。
*
川崎長太郎。
私が読んだのは講談社文芸文庫の『抹香町 路傍』所収のもので、解説の秋山駿の解説が、これまた難しい文章じゃないのに、いまいち頭に入って来なくて、それによると宇野浩二や徳田秋声の影響を受けて、アバンギャルドから私小説へと転身、正宗白鳥のような自分の体験したことだけを書くという正直さを貫いた作家であるということだ。
藤枝静男、木山捷平、中薗英助、耕治人、小沼丹…90年代にはかき消えていた作家を、発見できたのは講談社文芸文庫のおかげだけれども、川崎長太郎もその1人で、とはいえ、その文章をいまいち楽しめぬまま、歳を重ねてしまった。
けれども、この間、別件で本を探していたときに、この文庫を見つけて、よけておいた。よけておいたものをめくって、土地について書かれているものとして「ふっつ、とみうら」を読んだ。
「ふっつ・とみうら」に限らず戦後の川崎作品は、身辺雑記が多少なりとも時間軸に配列されており、会話もおそらくは多少脚色含んで提示されているだけの、極めて簡素な作りの小説なんだと思う。しかし、そんなものなのに、なんとも味のあるものとして迫ってくる。それは、今noteの日記作家さんたちの日記を読むのと同じような面白みがあるからなんだと思う。
人の生活が、もちろん編集や自己検閲を経ているとはいえ、表現されたり記録されたりして、外に現れるのは面白い。変に脚色されている物語よりも伝わるものがある。そんな感じ。
*
近所ではないが、巡回する図書館のリサイクル本コーナーに、明治文学全集が放出されていた。
『徳田秋声集』をもらって帰った。
写真の「惰けもの」は、それの冒頭収録作である。
しばらくは秋声を読んでもいいかと思った。
