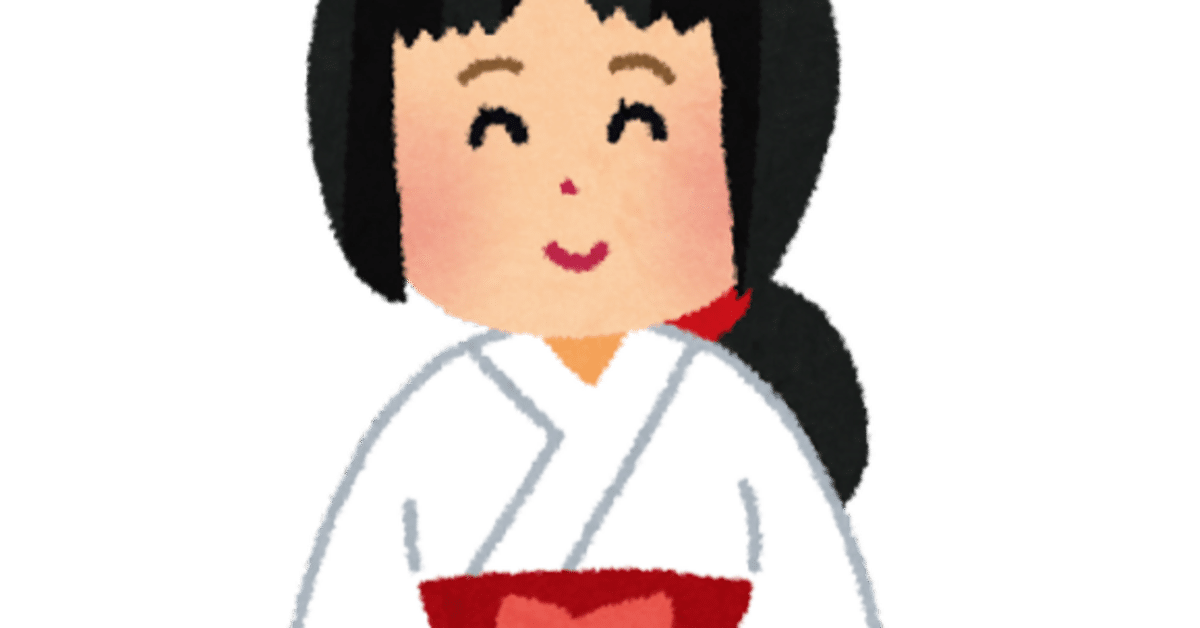
「テレパシーで答えました」
このエピソードは他で書いたことがあるのですが、新マガジン『アノ人の正体』向けにスポットライトのあて方を変えてお送りします。
**********
高校の同級生K君とは、同じクラスだった1年間で会話を交わしたことが10回に満たないはず。けれど、今も彼の風貌をありありと想い出すのは、たった1回きりの、とても印象的なシーンによる。
男子の多くは運動部に属するその高校にあって、K君はおそらく1割ほどしかいないマイノリティーである、文科系サークルのメンバーだった。
長身で、黒縁メガネをかけ、小学生の女児のようなおカッパ髪をした彼の風貌は、今から思えば『オタク』風であり、実際、オタクだったのだろう。
彼はいつも『半笑い』のような表情だった。かといって冗談を言うような人ではない。クラスメイト相手にも、基本的には『必要最小限』の会話を交わすだけだった。
そんな背景から、K君はある日のある授業までは、クラス内の存在感は高くなかった。
その日、数学(数ⅡBだった)の授業前、K君は机の上で『トコトコ人形』を歩かせて遊んでいた ── いや、凡庸なるこの身には遊んでいるように見えたが、実は何か重要な検証実験をしていたのかもしれない。
『トコトコ人形』を知らない人のために:
小柄な数学教師が教室に現れ、授業が始まった。
けれど、一応席についている生徒たちの多くは、彼にあまり関心を示さなかった。
その年に国立の工業大学を出て赴任したその教師は、生徒を叱ったりすることなどなく、自分の授業を職務として淡々と進めていくタイプだった。
授業が始まり、教科書の該当ページを開く生徒はもちろん、一定数いた。その一方、文庫本を広げたままの生徒もいたし、小声で何事か語り合うカップルもいた。早弁に箸をつける体育会系もいたかもしれない。
K君の『トコトコ人形』は、彼の机の上で往復運動を繰り返していた。
教師はそれを少し気にしているようにも見えたが、いつも通り、注意するようなことはなく、マイペースで授業を続けた。
そして、微積分かなにかの問題を黒板に書き、生徒たちに目をやった。
「じゃ、前に出て、この問題を解いてもらおうかな。……解ける人、手を挙げて」
── いつも通り、誰も手を挙げなかった。
「では、こちらから指名します。……K君」
この人に『罰』という概念は無かったはずなので、彼が当てられたのは偶然だろう。
K君は《トコトコ人形》から手を放し、立ち上がった ── いつもの『アルカイック・スマイル』を口もとに浮かべ、無言のまま。
「えーと……」
教師は少し反応をうかがった後、
「この問題、わかりますか?」
と続けた。
K君は沈黙を保ち、教師は困惑し始めた。
「どうしたの。黙っていちゃ、わからないな。……この問題、解けるかな」
教室の雰囲気が険しくなったのを察し、授業に関心を示していなかった生徒も、文庫本から、ひそひそ話から、そして早弁から顔を上げ、両者の『対峙』に目を向けた。
「どうして黙っているの! この問題、解いてみなさい、って言ってるだろ。わからないのか?」
教師が口を荒げた時、K君が口を開いて何か言った。
「え?」
教師も、僕も ── たぶん、教室の誰もが、最初は聞き取れなかった。
聞き取れなかった分、全員が一層彼の方に耳を傾けた。
K君は『アルカイック・スマイル』のまま、今度はゆっくりと、くっきりと、言った。
「今、テレパシーで答えました」
「はあ?」
教師は一瞬、戸惑ったようだった。
いや、彼だけではない。おそらくはクラス全員が戸惑った。なぜなら、K君はジョークを口走るようなキャラでないと、誰でも知っている。
謎の発言をどう解釈していいか、戸惑ったのだ。
教師は戸惑った末に最悪の対応をした。
自分の頭に両手を当て、
「あっ! 来た来た来た、テレパシーが来た!」
と叫び、一目散に黒板に向かうと、自分が出題したばかりの問題を、自分で解いた。
「K君、この答えでいいんだな」
K君は、
「はい。合っています」
《巫女》のように告げて着席し、《トコトコ人形》実験を再開した。
おそらく彼は ── 彼のそれまで、そしてその後の日常から判断しても、『ウケ狙い』でその科白を発したわけではないだろう。
ホントに送ったのかもしれない ── テレパシーで。
