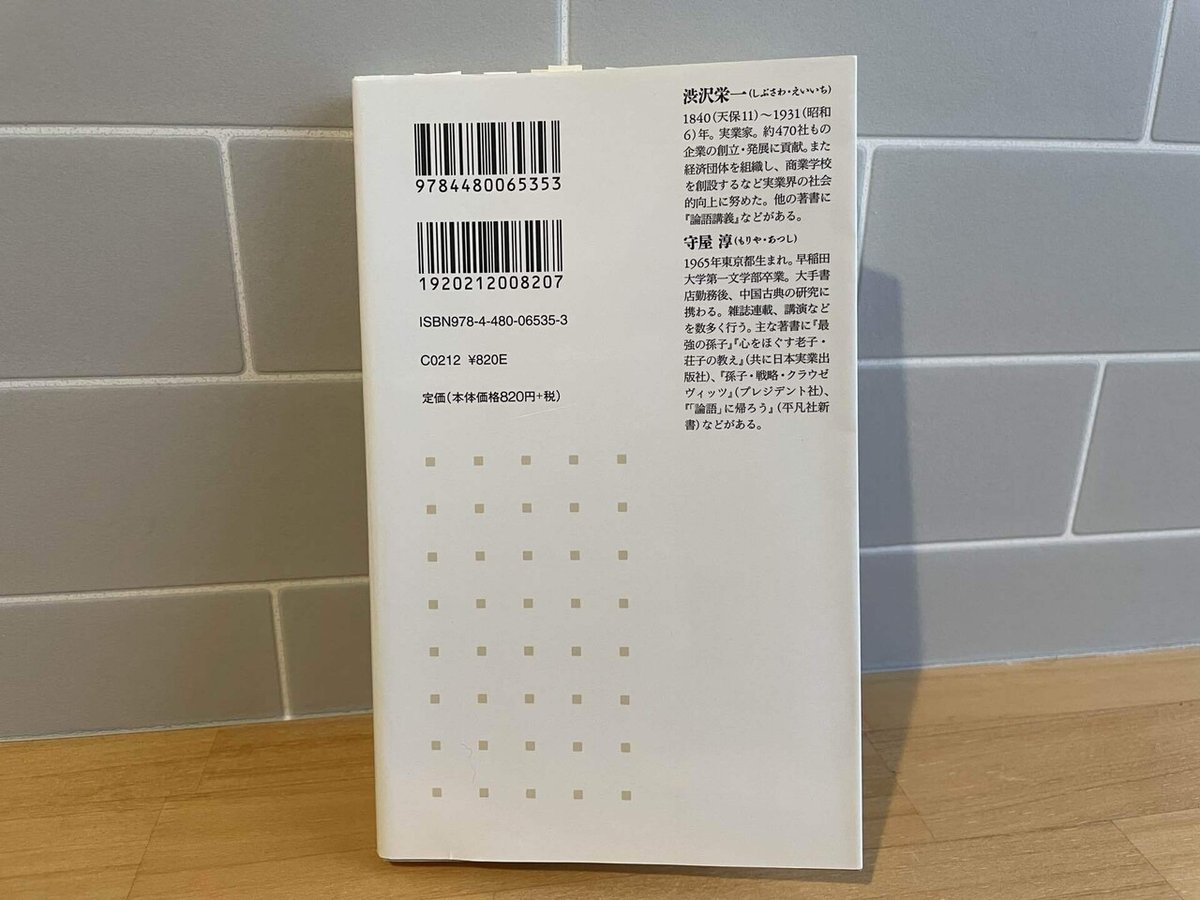論語と算盤 渋沢栄一
『 現代の青年が、いまもっとも切実に必要としているのは、人格を磨くことだ 』
渋沢栄一氏の言葉。
渋沢氏は人格について当時、「 明治維新前よりも衰退したと思う。いや、衰退どころでなない、消滅すらしないかと心配している 」と語られている。まさに現代社会がそうだ。
一体どのくらいの大人が人格を磨くことを語っているだろう?
今こそ、現代人が読むべき一冊であった。
『読書感想』
渋沢さんが語られていることは現代にも当てはまっていた。
商いには論語と算盤の両立が必要である。
当時は論語が蔑ろにされていたそうだ。
しかし、当時よりも深刻な状況かもしれない。
YouTubeやSNSでは提供の隠蔽、情報のリーク、フェイクニュース、アンチが注目を集める。
そうやって注目を浴びて稼いでいる人がいると聞く。
ネットの世界では論語も道徳も忘れ去られて消滅してしまった。
それらは死語であるかのうようで、みんな大量消費に忙しい。
「注目されて、お金を稼げれば、それでいい」
そんなインターネット風土が苦手だ。
渋沢栄一氏の肖像が新紙幣になったのに、こんな皮肉があるだろうか。
せめて本書を読んでから発信するべきではないだろうか。
もはや、そういう方々には届くまい。
『 心に沁みた言葉〜言葉の燈〜 』
商売に学問は不要である、学問があればかえって害がある、という時代だった。
人が世の中を渡っていくためには、成り行きを広く眺めつつ、気長にチャンスが来るのを待つということも、決して忘れてはならない心がけである。
人は平等でなければならない。しかも、その平等は、ケジメや礼儀、譲り合いがなければならない。
わたし自身の意見としては、争いは何があってもすべきものではなく、世の中を渡っていくうえでははなはだ必要なものであると信ずるのである。
このように一見残酷な態度に出る先輩は、往々にして後輩の恨みを買うのもで、後輩たちの人望は極めて乏しいものである。しかし、このような先輩は、本当に後輩の利益にならないのだろうか。この点は、若いみなさんでとくと熟考して然るべきものだろうと思う。
だから人は、得意なときに調子に乗ることもなく、「大きなこと」「些細なこと」に対して考えや判断をもってこれに臨むのがよい。水戸光圀公の壁書の中に
「小さなことは分別せよ。大きなことには驚くな」
とあるのは、まさに知恵あるものの言葉である。
ところが何としたことか、人格は明治維新前よりも衰退したと思う。いや、衰退どころでなない、消滅すらしないかと心配しているのである。どうも物質文明が進んだ結果は、精神の進歩を害したと思うのである。
また誰が仕事を与えるにしても、経験の少ない若い人に、初めから重要な仕事を与えるものではない。藤吉郎ののような大人物であっても、初めて信長に仕えたときは、草履取りという妻っらない仕事をさせられた。
与えられた仕事に不平を鳴らして、口に出してしまうのはもちろんダメだが、「つまらない仕事だ」と軽蔑して、力を入れないのもまたダメだ。およそどんな些細な仕事でも、それは大きな仕事との一部なのだ。(中略)時計の小さな針や、小さな針が怠けて動かなかったら、大きな針も止まらなければならない。
生まれながらの聖人なら、志を立てることに迷いはないかもしれない。しかしわれわれ凡人は、そうはいかないのが常である。
人間はいかに人格が円満であっても、どこかに角がなければならない。古い歌にもあるように、あまり丸いとかえって転びやすくなるのだ。
理解することは、愛好することの深さに及ばない。愛好することは、楽しむの境地の深さに及ばない。
二宮先生は、相馬藩招かれると、まず過去百八十年間における細かい藩の収入統計を作った。そのうえで、百八十年を六十年ずつ三つにわけ、それぞれ「天」「地」「人」と名前をつけた。その三つを比べてちょうど真ん中の平均収入額になった時期を、「平年の藩の収入」とされたのだ。
自分を磨くことは理屈ではなく、実際に行うべきこと。だから、どこまでも現実と密接な関係を保って進まななくてはならない。
もちろん「自分らしさ」や「ありのままの自分」こそ、人のもっとも輝いている部分だというのは、わたしも賛同するところだ。しかし、人の喜び、怒り、哀しさ、楽しさ、愛しさ、憎さといった「ありのまま」の感情の動きが、どんな場合でも問題ないはいえないだろう。理想の人物や立派な人物は、感情が動くときにさえ、ケジメがあるものだ。
現代の青年が、いまもっとも切実に必要としているのは、人格を磨くことだ。
明治維新の前までは、社会における道徳教育が比較的盛んな状態だった。ところが西洋文化を輸入するにつれ、思想界には少なからず変革の波が起こって、今日では、道徳がひどく混沌とする時代状況となってしまった。
もちろん、国民全部がみな富める者になれるのが望ましいのだが、人には賢さや能力という点でどうしても差がある。誰も彼もが一律に豊かになる、というのはちょっと無理な願いなのだ。
「競争」には善意と悪意の二種類があるように思われる。
踏み込んで述べてしまえば、毎朝人よりも早く起きて、よい工夫をして、知恵と勉強とで他人に打ち克っていくというのは、まさしく競争なのだ。
つまり、このわざわいのもとは、重役に適任がつけば自然となくなっていくはずのものなのだ。
福沢諭吉さんの言葉に、
「書物を著したとしても、それを多数の人が読むようなものでなければ効率が薄い。著者は常に自分おことよりも、国家社会を利するという考えで筆をとらなければならない」
「賢者は、貧賤な境遇にいても、自分の道を曲げない」
という孔子の言葉。
いまや武士道はいい換えて、実業道とするのがよい。日本人はあくまで、ヤマト魂生まれ変わりである武士道で世に立っていかなければならない。
孔子はこう答えた。
「父や母に心配をかけるとしたら、自分の病気のことだけにしなさい」
「近頃の親孝行というのは、暮らしの上で不自由ない思いをさせることを指しているらしい。だが、それだけなら、犬や馬を飼うのと同じことである。敬愛の心がこもっていなかったら、区別のつけようがないではないか」
ところが現代の師弟関係は全く乱れてしまって、うるわしい師弟関係の交流があまり見られないのは憂うべきことだ。今の青年は師匠を尊敬しない。学校の生徒など、その教師をまるで落語家か講談師のように見ている。
要するに、青年はよい師匠に接して、自分を磨いていかなければならない。昔の学問と今の学問を比較してみると、昔は心の学問ばかりであった。一方、今は知識を身につけることばかりに力を注いでいる。
順境と逆境の二つに物事が分かれてしまうしまう理由がよくわかる教えになったいる。要するに、悪い人間はいくら教えても聞いてくれないものなのだ。一方、よい人間は教えなくても自分でどうすればよいのかわかっていて、自然に運命をつくりだしていいく。だから厳正な意味からいけば、この世の中に順境も逆境もないということになる。
現代の人の多くは、ただ成功とか失敗ということだけを眼中に置いて、それよりももっと大切な「天地の道理」を見ていない。彼らは物事の本質をイノチとせず、カスのような金銭や財宝を魂としてしまっている。
とにかく人は、誠実にひたすら努力し、自分の運命を開いていくのがよい。
もしそれで失敗したら「自分の智力が及ばなかったため」とあきらめることだ。
人生の道筋はさまざまで、時に善人が悪人に負けてしまったように見えることがある。しかし、長い目で見れば、善悪の差ははっきりと結果になって現れてくるものだ。だから、成功や失敗の良し悪しを議論するよりも、まずは誠実に努力することだ。そうすれば公平無私なお天道さまは、必ずその人に幸福を授け、運命を開いていくよう仕向けてくれるのである。
「いや、独占事業は欲に目のくらんだ利己主義だ。」
栄一は腹を立てて、その席にいた馴染みの芸者といっしょに姿を消した。